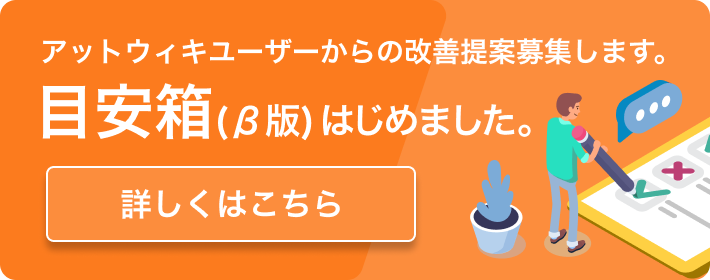ara_arcana @ ウィキ
SS1
最終更新:
ara_arcana
-
view
優しき死神
遙か地平線の彼方へと続く、灼熱の大地。過酷な土地はエリンディルに多く存在するが、此処――無限の砂漠に並ぶ地は少ないだろう。
死と隣り合わせの無限の砂漠だが、東方諸国との交易のためには避けて通れない。また、砂漠に眠る未だ見ぬ遺跡を探そうとする冒険者も多い。それ故に、この過酷な地を行き来する者は少なくない。
だが、生半可な覚悟で砂漠を横断するのは、死に直結する。
まず、吹き荒ぶ風により巻き上げられた砂が視界を覆い、方向感覚を奪う。その結果、迷い続けた挙句、水や食料が尽きて倒れる者が多い。そして、照りつける太陽は体力をジリジリと奪い続け、夜になると気温が低下する。そのような寒暖の差も、大きな負担となる。元々この地に住んでいた遊牧民でさえも、砂漠の気候の前に力尽きることも珍しくないのだ。
そして――
それは、凄惨な光景だった。
数分前までは、東方へと赴く途中の隊商だったのだろう。メアンダールからミースへと向かうルートに、それはあった。だが、そこにあったのはまるでその場所にだけ嵐が起こったかのように、滅茶苦茶になった隊商の残骸だった。
荷車は薙ぎ倒され、それを引いていた駱駝は砂に倒れ伏している。積まれていた荷物もその殆んどがぶちまけられ、護衛と思われる者達も無惨な姿となっていた。
この場を見た者は、盗賊に襲われたかと思うだろう。だが、襲われた彼らからしたら、盗賊の方がまだ可愛く見えるに違いない。
「…………」
そんな無惨な隊商の跡に、一人の少女が佇んでいた。
年齢は十歳前後だろうか。落ち着いたダークブラウンの髪をツインテールに結んでおり、やや東方の血が混ざっているのか、肌の色は少しばかり黄味を帯びている。顔立ちには、子供の快活さを窺わせるようなものが感じられる。
しかし、今の少女の顔は恐怖と絶望に歪んでいた。
無理も無い。一瞬にして、『ヤツ』に全てを奪われたのだから。
死と隣り合わせの無限の砂漠だが、東方諸国との交易のためには避けて通れない。また、砂漠に眠る未だ見ぬ遺跡を探そうとする冒険者も多い。それ故に、この過酷な地を行き来する者は少なくない。
だが、生半可な覚悟で砂漠を横断するのは、死に直結する。
まず、吹き荒ぶ風により巻き上げられた砂が視界を覆い、方向感覚を奪う。その結果、迷い続けた挙句、水や食料が尽きて倒れる者が多い。そして、照りつける太陽は体力をジリジリと奪い続け、夜になると気温が低下する。そのような寒暖の差も、大きな負担となる。元々この地に住んでいた遊牧民でさえも、砂漠の気候の前に力尽きることも珍しくないのだ。
そして――
それは、凄惨な光景だった。
数分前までは、東方へと赴く途中の隊商だったのだろう。メアンダールからミースへと向かうルートに、それはあった。だが、そこにあったのはまるでその場所にだけ嵐が起こったかのように、滅茶苦茶になった隊商の残骸だった。
荷車は薙ぎ倒され、それを引いていた駱駝は砂に倒れ伏している。積まれていた荷物もその殆んどがぶちまけられ、護衛と思われる者達も無惨な姿となっていた。
この場を見た者は、盗賊に襲われたかと思うだろう。だが、襲われた彼らからしたら、盗賊の方がまだ可愛く見えるに違いない。
「…………」
そんな無惨な隊商の跡に、一人の少女が佇んでいた。
年齢は十歳前後だろうか。落ち着いたダークブラウンの髪をツインテールに結んでおり、やや東方の血が混ざっているのか、肌の色は少しばかり黄味を帯びている。顔立ちには、子供の快活さを窺わせるようなものが感じられる。
しかし、今の少女の顔は恐怖と絶望に歪んでいた。
無理も無い。一瞬にして、『ヤツ』に全てを奪われたのだから。
グオオオオオオオオオオッ――
耳を劈くかのような轟音が辺りに響き渡る。それと同時に、少女の前の砂が盛り上がり、一体の巨大なミミズを思わせるかのような魔物が姿を現した。
砂龍 ――
無限の砂漠を徘徊する魔物の一種だ。普段は地中深くに生息しているが、時折地表近くへと這いあがってくる。その際に、隊商や街などがあった場合、それらは悉く砂龍に飲みこまれてしまうこととなる。少女の隊商も、その殆んどを砂龍に呑みこまれてしまったのだ。
そう。砂漠を横断する上で最も恐れるべきなのは、砂塵でも高温でも盗賊でもなく、この巨大な怪物なのだ。
砂龍はちょうど近くにあった天幕や交易品の残骸を、躊躇なく呑みこんでいった。
そして――
「ぃ……いや……」
砂龍が目を付けたのは、今まさに目の前にいる少女だった。
少女はその場から逃げ出そうとするも、足が竦んで動かなかった。恐怖と絶望だけではない。致命傷までには至らないが、彼女の身体は傷だらけであった。荷車から投げ出された時に、全身を打ってできたものだ。そのひとつひとつの傷が、彼女の体力を奪っていたのだ。今、彼女が生きていられるのは、投げ出されたお陰で砂龍の餌食にならずに済んだのだが――
だが、そんな僅かな幸運を嘲笑い、踏みつぶすかのように、砂龍は巨大な口を開けて、ジリジリと彼女へと迫っていく。
「いやぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁっ――!」
もう、終わりだ。
あの巨大なバケモノに呑みこまれて、死ぬのだ――
半ば諦めかけたその時だった。
「伏せろ!」
何処からともなく、若い男の声が響いた。
一閃。まさに、そのような言葉が相応しかった。
少女の前に一つの影が割って入り、身体をうねらせて彼女を捕らえようとした砂龍を真っ二つに引き裂いた。砂龍は断末魔の叫びすら上げずに、砂の上に崩れ落ちた。
「危ないところだったな、大丈夫か」
落ち着いた声と共に、若い男が降り立つ。
少女の危機を救ったのは、一人の天翼族 の青年だった。
外見から察すると、二十代前半だろうか。整った顔立ちで、美麗な銀髪が熱風により揺れている。天翼族の象徴である一対の翼は、左右で異なる色をしていた。
純白と漆黒。光と闇を表すかのような翼は美しいもののお互いがその存在を誇示することなく、潰し合うこともなく、青年の美麗さを引き立てている。
単に美しいだけではない。高尚な職人が作り上げたかのような――いや、彼らでさえも造り出すことのできないような、無駄の無い容姿。あまりにも全てにおいて優れているがゆえに、かえって現実離れしたかのように見える。まるで、人ならざる者のように。
神秘的ではあるが、何処か冷たい雰囲気の男――少女は彼に対して、そんな印象を持った。それは、青年の手に握られている特異な武器も関係しているだろう。
まるで、魂を刈り取る死神を連想させるかのような武器――鎌である。少女は隊商の護衛を幾度となく見てきたが、彼らが装備している武器は剣や槍といったものがほとんどで、鎌を扱う者など見たことが無かった。
「やはり、まだいるようだな」
両手で扱っていた鎌を右手に持ち替え、青年は少女を抱き寄せた。足元から伝わる僅かな震動を、彼は察知していたのだ。
「少し飛ぶぞ」
「……?」
言われるままに、少女は青年の身体にしがみ付いた。ドゥアンにしては、やや華奢とも言える身体つきだが、貧弱さを感じさせない――無駄の無い肉付きが服越しに伝わってくる。
青年は左右の翼を大きく広げると、その場から跳躍して宙へと飛び立った。彼が立っていた場所からは一匹の砂龍が飛び出し、その周辺からも次々と砂龍が姿を現した。本能的なものなのか、あるいはある程度の知恵を持っているのか、新たに獲物が現れたことを察知した砂龍は、青年を取り囲むかのように詰め寄る。
「囲まれちゃった……」
「大丈夫だ、恐れることはない。すぐに済ませる」
恐怖に震える少女をそっと左手で抱き寄せ、青年は優しく言葉をかけた。
「落ちないように、しっかり掴まっていろ」
青年は身の丈ほどある鎌を片手で構え、一匹の砂龍に向けて急降下し、刃をその巨体へと振り下ろした。
鎌の軌道に、純白の光が宿る。刃が砂龍の巨体を一撃で薙ぎ払うと同時に、光に包まれる。砂龍は断末魔の叫びすら上げずに、光の柱に呑みこまれていった。
それだけではない。光は周囲の砂龍をも巻き込み、その身体を一瞬にして粉砕していった。
《ネメシス》――
広い範囲の敵を一瞬にして浄化する、聖騎士 の奥義である。
「凄い……」
少女はただ、その光景を目の当たりにするだけだった。
すべての砂龍を倒し終えたのを確認すると、青年はゆっくりと着地し、片手で抱いていた少女を降ろした。
「怪我をしているな」
青年は、少女の身体の至る所に傷があるのに気付いた。恐らくは、馬車に乗っていたところを、外に放り出されたのだろうか。致命傷というわけではないが、かなりの範囲が擦り切れており、痛々しい。まあ、砂龍とはち合わせてこれだけの傷で済んだのだから、幸運といえば幸運ではあるのだが、年端もいかぬ娘が傷だらけというのは、見る方にとっても痛々しいものだった。
「大丈夫だよ、これくらい」
笑顔を浮かべているが、それが造り出されたものであるのは青年にはすぐに解った。痩せ我慢をしているのは明らかだ。本当はつらいに違いない。肉体的にも、そして、精神的にも――
「無理をするな、俺が手当てしてやる」
青年は少女を優しく抱き寄せると、傷口に向けて静かに《ヒール》の詠唱を始めた。
アコライトの唱える術の中でも最も基本的であり、かつ最も重要な魔術である。傷を治すこの術は、多くの者の命を救ってきたのだ。この魔術が世に存在しなければ、助かる筈の命も助からない。故に、神官となった者はまずこの術から学ぶのである。
少女の傷口が、淡い緑色の光に包まれていく。徐々に痛みが消えていく感覚、そして自分の身体を包みこむ青年の抱擁。少女は暫くの間、青年に己の身を委ねた。
「これで大丈夫だ」
青年は治療を終えると、少女に優しく微笑みかけた。
彼の《ヒール》は、非常に精度の高いものだった。恐らくは、かなりの場数を踏んできた者だろう。身体中の鈍い痛みも気が付いたら完全に消え去っており、傷跡も綺麗に消えている。
「あ、あの」
「なに、気にするな。それより、この場にいては危ない。家まで届けよう」
「あたしにはもう……」
「…………」
青年は辺りを見渡した。
最早、自分達以外に生き残っている者は、そこにはいなかった。何もかもが、今打ち倒したバケモノによって、呑みこまれてしまったのだ。もう、少女には何も残されていないのだろう。家族も、帰る場所も――
この歳で天涯孤独なのは、あまりにも哀れだ。
(仕方あるまい)
何処か自嘲的に独りごちると、青年は少女の頭に手を乗せて、言った。
「お前が望むなら、俺のもとに来い」
青年の言葉に、少女はきょとんとした表情を見せた。
「何と言えばいいのだろう。至らぬことがあるかもしれないが、お前を養おうと思う。家族の代わりになれればいいが」
少女は無言のまま、青年へと寄り添った。それは、青年の誘いに乗ったということだろう。
「俺の名はグレイ。君の名前を聞かせてほしい」
暫くの沈黙の後――
「……リーゼロッテ」
まだ迷いがあるのだろうか、少女は小さな声で名乗った。
「リーゼロッテ……か。至らぬところはあるかもしれないが、君の親代わりとなろう」
少女の名を確認すると、グレイは再び彼女を抱き寄せた。
(俺も変わったものだな。ミラや自警団のこともあるが、少しばかり、人と過ごすのが長すぎたか……。だが、不思議と悪い気はしない)
再び自嘲的な笑みを見せるグレイ。
「よろしく、お兄ちゃん」
「いや、俺は兄では……まあいいか。やるべきことは変わらぬからな」
無限の砂漠を徘徊する魔物の一種だ。普段は地中深くに生息しているが、時折地表近くへと這いあがってくる。その際に、隊商や街などがあった場合、それらは悉く砂龍に飲みこまれてしまうこととなる。少女の隊商も、その殆んどを砂龍に呑みこまれてしまったのだ。
そう。砂漠を横断する上で最も恐れるべきなのは、砂塵でも高温でも盗賊でもなく、この巨大な怪物なのだ。
砂龍はちょうど近くにあった天幕や交易品の残骸を、躊躇なく呑みこんでいった。
そして――
「ぃ……いや……」
砂龍が目を付けたのは、今まさに目の前にいる少女だった。
少女はその場から逃げ出そうとするも、足が竦んで動かなかった。恐怖と絶望だけではない。致命傷までには至らないが、彼女の身体は傷だらけであった。荷車から投げ出された時に、全身を打ってできたものだ。そのひとつひとつの傷が、彼女の体力を奪っていたのだ。今、彼女が生きていられるのは、投げ出されたお陰で砂龍の餌食にならずに済んだのだが――
だが、そんな僅かな幸運を嘲笑い、踏みつぶすかのように、砂龍は巨大な口を開けて、ジリジリと彼女へと迫っていく。
「いやぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁっ――!」
もう、終わりだ。
あの巨大なバケモノに呑みこまれて、死ぬのだ――
半ば諦めかけたその時だった。
「伏せろ!」
何処からともなく、若い男の声が響いた。
一閃。まさに、そのような言葉が相応しかった。
少女の前に一つの影が割って入り、身体をうねらせて彼女を捕らえようとした砂龍を真っ二つに引き裂いた。砂龍は断末魔の叫びすら上げずに、砂の上に崩れ落ちた。
「危ないところだったな、大丈夫か」
落ち着いた声と共に、若い男が降り立つ。
少女の危機を救ったのは、一人の
外見から察すると、二十代前半だろうか。整った顔立ちで、美麗な銀髪が熱風により揺れている。天翼族の象徴である一対の翼は、左右で異なる色をしていた。
純白と漆黒。光と闇を表すかのような翼は美しいもののお互いがその存在を誇示することなく、潰し合うこともなく、青年の美麗さを引き立てている。
単に美しいだけではない。高尚な職人が作り上げたかのような――いや、彼らでさえも造り出すことのできないような、無駄の無い容姿。あまりにも全てにおいて優れているがゆえに、かえって現実離れしたかのように見える。まるで、人ならざる者のように。
神秘的ではあるが、何処か冷たい雰囲気の男――少女は彼に対して、そんな印象を持った。それは、青年の手に握られている特異な武器も関係しているだろう。
まるで、魂を刈り取る死神を連想させるかのような武器――鎌である。少女は隊商の護衛を幾度となく見てきたが、彼らが装備している武器は剣や槍といったものがほとんどで、鎌を扱う者など見たことが無かった。
「やはり、まだいるようだな」
両手で扱っていた鎌を右手に持ち替え、青年は少女を抱き寄せた。足元から伝わる僅かな震動を、彼は察知していたのだ。
「少し飛ぶぞ」
「……?」
言われるままに、少女は青年の身体にしがみ付いた。ドゥアンにしては、やや華奢とも言える身体つきだが、貧弱さを感じさせない――無駄の無い肉付きが服越しに伝わってくる。
青年は左右の翼を大きく広げると、その場から跳躍して宙へと飛び立った。彼が立っていた場所からは一匹の砂龍が飛び出し、その周辺からも次々と砂龍が姿を現した。本能的なものなのか、あるいはある程度の知恵を持っているのか、新たに獲物が現れたことを察知した砂龍は、青年を取り囲むかのように詰め寄る。
「囲まれちゃった……」
「大丈夫だ、恐れることはない。すぐに済ませる」
恐怖に震える少女をそっと左手で抱き寄せ、青年は優しく言葉をかけた。
「落ちないように、しっかり掴まっていろ」
青年は身の丈ほどある鎌を片手で構え、一匹の砂龍に向けて急降下し、刃をその巨体へと振り下ろした。
鎌の軌道に、純白の光が宿る。刃が砂龍の巨体を一撃で薙ぎ払うと同時に、光に包まれる。砂龍は断末魔の叫びすら上げずに、光の柱に呑みこまれていった。
それだけではない。光は周囲の砂龍をも巻き込み、その身体を一瞬にして粉砕していった。
《ネメシス》――
広い範囲の敵を一瞬にして浄化する、
「凄い……」
少女はただ、その光景を目の当たりにするだけだった。
すべての砂龍を倒し終えたのを確認すると、青年はゆっくりと着地し、片手で抱いていた少女を降ろした。
「怪我をしているな」
青年は、少女の身体の至る所に傷があるのに気付いた。恐らくは、馬車に乗っていたところを、外に放り出されたのだろうか。致命傷というわけではないが、かなりの範囲が擦り切れており、痛々しい。まあ、砂龍とはち合わせてこれだけの傷で済んだのだから、幸運といえば幸運ではあるのだが、年端もいかぬ娘が傷だらけというのは、見る方にとっても痛々しいものだった。
「大丈夫だよ、これくらい」
笑顔を浮かべているが、それが造り出されたものであるのは青年にはすぐに解った。痩せ我慢をしているのは明らかだ。本当はつらいに違いない。肉体的にも、そして、精神的にも――
「無理をするな、俺が手当てしてやる」
青年は少女を優しく抱き寄せると、傷口に向けて静かに《ヒール》の詠唱を始めた。
アコライトの唱える術の中でも最も基本的であり、かつ最も重要な魔術である。傷を治すこの術は、多くの者の命を救ってきたのだ。この魔術が世に存在しなければ、助かる筈の命も助からない。故に、神官となった者はまずこの術から学ぶのである。
少女の傷口が、淡い緑色の光に包まれていく。徐々に痛みが消えていく感覚、そして自分の身体を包みこむ青年の抱擁。少女は暫くの間、青年に己の身を委ねた。
「これで大丈夫だ」
青年は治療を終えると、少女に優しく微笑みかけた。
彼の《ヒール》は、非常に精度の高いものだった。恐らくは、かなりの場数を踏んできた者だろう。身体中の鈍い痛みも気が付いたら完全に消え去っており、傷跡も綺麗に消えている。
「あ、あの」
「なに、気にするな。それより、この場にいては危ない。家まで届けよう」
「あたしにはもう……」
「…………」
青年は辺りを見渡した。
最早、自分達以外に生き残っている者は、そこにはいなかった。何もかもが、今打ち倒したバケモノによって、呑みこまれてしまったのだ。もう、少女には何も残されていないのだろう。家族も、帰る場所も――
この歳で天涯孤独なのは、あまりにも哀れだ。
(仕方あるまい)
何処か自嘲的に独りごちると、青年は少女の頭に手を乗せて、言った。
「お前が望むなら、俺のもとに来い」
青年の言葉に、少女はきょとんとした表情を見せた。
「何と言えばいいのだろう。至らぬことがあるかもしれないが、お前を養おうと思う。家族の代わりになれればいいが」
少女は無言のまま、青年へと寄り添った。それは、青年の誘いに乗ったということだろう。
「俺の名はグレイ。君の名前を聞かせてほしい」
暫くの沈黙の後――
「……リーゼロッテ」
まだ迷いがあるのだろうか、少女は小さな声で名乗った。
「リーゼロッテ……か。至らぬところはあるかもしれないが、君の親代わりとなろう」
少女の名を確認すると、グレイは再び彼女を抱き寄せた。
(俺も変わったものだな。ミラや自警団のこともあるが、少しばかり、人と過ごすのが長すぎたか……。だが、不思議と悪い気はしない)
再び自嘲的な笑みを見せるグレイ。
「よろしく、お兄ちゃん」
「いや、俺は兄では……まあいいか。やるべきことは変わらぬからな」
●●●
メアンダール南西部の一角にある、自警団の詰所――
「……ということがあったの」
リーゼロッテは他の団員に、自分の過去について自慢げに話している。
「ははぁ、お前にとってはグレイの奴は恩人……いや、ヒーローみたいなモンなのか」
食卓に置かれているサラダをかきこみながら、カルロスが答える。
「うん。だから、少しでも恩返しのためになれればって思ってるの」
少し顔を赤らめて、リーゼは頬杖をつく。
「なるほどな。ま、お前には結構助けられてるぜ。弓の腕は勿論、街の外へ赴いた時、罠の探知と解除は頼りになるからな」
「えへへ……」
グレイに助けられてから、リーゼロッテは恩を返すために弓の鍛練と罠についての勉強を日々怠らなかった。初めは足を引っ張っていたものの、今では自警団でもトップクラスの実力を持つまでに至っている。
「弓はともかく、罠はアイツがいるからなぁ」
「ああ、ミラ先輩のことでしょ? 大丈夫だよ、あたしは大人だから、別に張り合おうなんて思ってないから」
言って、何処か意地の悪そうな笑みを浮かべるリーゼロッテ。
「……ということがあったの」
リーゼロッテは他の団員に、自分の過去について自慢げに話している。
「ははぁ、お前にとってはグレイの奴は恩人……いや、ヒーローみたいなモンなのか」
食卓に置かれているサラダをかきこみながら、カルロスが答える。
「うん。だから、少しでも恩返しのためになれればって思ってるの」
少し顔を赤らめて、リーゼは頬杖をつく。
「なるほどな。ま、お前には結構助けられてるぜ。弓の腕は勿論、街の外へ赴いた時、罠の探知と解除は頼りになるからな」
「えへへ……」
グレイに助けられてから、リーゼロッテは恩を返すために弓の鍛練と罠についての勉強を日々怠らなかった。初めは足を引っ張っていたものの、今では自警団でもトップクラスの実力を持つまでに至っている。
「弓はともかく、罠はアイツがいるからなぁ」
「ああ、ミラ先輩のことでしょ? 大丈夫だよ、あたしは大人だから、別に張り合おうなんて思ってないから」
言って、何処か意地の悪そうな笑みを浮かべるリーゼロッテ。
その頃――
「ごほっ、ごほっ……、解除出来たわ~」
ミラはトラップを己の身を以て無理矢理解除していた。
「ごほっ、ごほっ……、解除出来たわ~」
ミラはトラップを己の身を以て無理矢理解除していた。