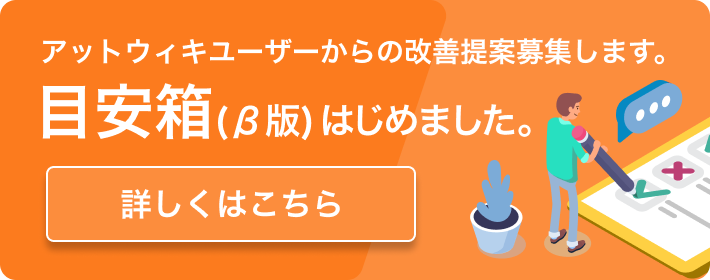「十六夜の月」(2006/10/19 (木) 13:28:28) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
死体だらけだ。
死体。死体。死体。死体。
死体。 死体。
死 体。死体。死体。
死体。死体。
死体。
彼がいない。
誰もいない。
彼とは認めたくない。
私は駆け寄って、彼を抱き起こした。
銃身が焼けて使い物に鳴らなかった銃を
赤子のように大事に抱いて震えている。
「……終わったんだ。」
だが、私の声はまるで届いていない。
「あ……うぅ……。」
銃を私に預け、目を強く閉じ、彼は膝を抱えて丸くなってしまう。
彼は泣いている。
私は彼を強く抱きしめた。
第一章 あれから7年。
極端に暗い照明、そして下品な笑い声とドラックの匂い。
国内であることを感じさせない、難民街独特の空気である。
そして私は、その街の酒場に上手く溶け込んでいる一人の日本人に声をかけた。
「本多昌明だな。」
「ぁん……?ぁんた誰だ?」
大柄の男が振り返る。
反応からしてこの男が本多昌明であることは間違いない。
「んん?、悪い悪い、女だったか。。だがなぁ、あいにく金がねぇくてよ」
場所が場所だが、実におめでたい奴だ。私を娼婦だと思ったらしい。
私は紙封筒から、一枚の紙を取り出し淡々と読み上げる。
「傷害致死、不法入国。並びに麻薬密売、使用。……長いな、後は自分で読め。」
瞬間、男の顔色が面白いように変わる。無理もない、目の前の女が娼婦から死神に変わったのだから。
いい土産話ができたと思い、心の中で私が軽く笑ったとき、男が大きく体を捻った。
上体の捻りでバネをきかせ、体重を十分にかけた一撃が私を叩きつぶそうとしていたのだ。
だが私は素早く顎を引き、流れるような動作で銃を抜いて、相手の顔に突きつける。
M85J。口径は小さいが、別に殺し合いをするわけじゃない。これで十分である。
「どうした?私の顔に何かついていたか?」
私は少し距離を開ける。男は私を親の敵のごとくにらみつけている。
「………」
「なんだ、字が小さくて読みにくかったか?なら署の方でじっくり見せてやる。」
「……あんた、警察違うな。」
「さすがだな、ゴルヴェ。」
「そこまで知っているのか……」
その時だった。一人の客が席を立った。周りの客も立ち上がり、私の周囲を囲み始める。
手には銃、ライフルさえ持っている者さえいる。
「あんたが警察にしろ、場所を考えるんだったな。」
「……ふむ。」
「ここではおれ達がルールだ。ここはあんたたちの国じゃない。」
こうなることは店に入る前からわかっていた。これでいい。……これで。
口の中で大陸から持ち帰った「あの」味が広がる。
暴力を歓喜へと変えるこの味で私は興奮を感じるのだ。
そして、目の前の男に容赦なく銃弾をあびせた私は、
考えることはなく、
感じるがままに、
この時を楽しんだ。
「7人は全治1ヶ月~2ヶ月。全員病院で警察の取り調べを受けている。」
「……」
「明日からは身柄がうちに来て、こっちで取り調べができるんだが……。」
「………」
「一度は取調室を使いたいものだなぁ?㍉子君?」
「……はい」
外務省対外情報調査室調査2部調査2課別室。
通称、捜査2課。……それにしても長い。実に長い名前だ。
「まぁ、別に怒りはしない。むしろよくやった。だが、お前ならもっと上手くやれるだろ?」
「………」
軍を辞めた私がここに拾われてから1年がたつ。
荒事を起こしても咎められないこの職場を私は気に入っている。
「ちゅっ」
「!!!う、うわぁあーーー!!」
「㍉子ちゃん。反応が可愛い。」
「い、いい年して、な、何するんですかぁ!!」
……続けよう。主な仕事は国外からの工作員の捜査だ。
最近は大陸からの難民に混じっていることが多いため、毎日が多忙の日々である。
そんな中、新たに増設された部署の捜査員として私は配属された。
「いい年って、私はまだ20代よ。」
「……(仮に20代だとしても、29だな。」
そして、この永遠の20代と言い張る私の上司。
さながら新ジャンル「BOSS」、「姉御」といったところだろうか……。
「どうかした?」
「い、いえ。ボス。」
「……あんまり年のこと言うと、はねるわよ?」
「す、すみません。(私のせいなのか?」
「まぁいいや、あそこで逃げようとしている男と警察の方に出向いて調書もらってきて。」
そう言ってボスは、飲み終わった缶コーヒーを残業から逃げようとしていた男に投げつける。
「のわ!!!……痛ぅ………別に逃げようとは……、」
「公務員に残業。猫にこたつ、㍉子に拳銃だ。」
「意味わからん……俺は今日は見たいアニメがあるんで帰りまsはっgwわれあwr」
私は缶コーヒーを、昔っから全然変わることがない馬鹿男の口に突っ込む。
「友よ、残業は楽しいよな?」
「はぐらくぁわじゅ(気合い入れていきます」
あたりはもう夕闇でかすかに黒ずみはじめている。
話したいことがあると友がしつこいので、署から出てきた私たちは
近くの公園のベンチに腰掛けた。with缶コーヒー。
私が寒いから早くしろと言うと、友はジャケットを寄こしたが、私はそれを払いのけた。
「早くすませろ。」
「……学園を卒業してからもう7年がたったんだよな。」
「………」
「………7年だぞ?」
「………もうそんなたったのか。」
「楽しかったよな?」
「……否定はしない。」
「あー、文化祭、修学旅行と、色々と修羅場があって面白かったなぁ!」
「……お前は知らないだろうが、体育祭でも色々とあったのだ」
「ぉ、それ知りたいな」
こいつはただの思い出話がしたかったらしい。
だが、思い出してみると、学園祭のこと、修学旅行のこと、学校でサバゲーをやったこと。
武道会のこと。きりがないほどの思い出があの学園にはある。
「まぁ、いいか。話してやろう。もう時効になっているだろうからな。」
「そうそう、卒業式で稲井の姿を初めて見たときといったら」
「私の話を聞け!体育祭の時だなぁ……」
「同窓会いいなぁ!みんな集めてやってみるか?」
それからしばらくの間、私たちは学園の思い出話に花を咲かせた。
「……む、もうこんな時間か。」
午後8時。時計を確認した私はベンチから立ち上がり、襟を正しながらいう。
「明日からはさらに忙しくなるぞ。」
「……㍉子」
「ん、なんだ?」
「……いや、また明日な。」
「あぁ。明日からは新しい仕事だ。さらに気合いを入れていくぞ。」
この時、もう少し日の暮れが遅いか、次の日に仕事がなければ
この男は何かを私に伝えていただろう。まぁ、今となってはどうでもいいことだ。たぶん。
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: