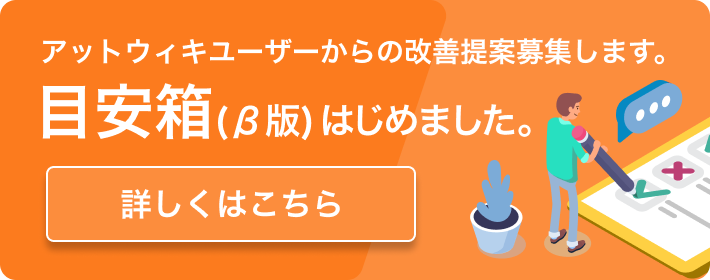「24スレ目」(2006/10/19 (木) 13:42:06) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
彼女は暗闇の中を走っていた。彼女の視覚は、闇の中でも光を捉えていた。それは本能だった。最初から、今まで。
初め、彼女の知覚に戻ってきたのは、パキパキという音だった。その音が、自分が踏みつけるガラス片の音だと気づくまでに数秒かかった。
彼女は走るのを止めた。感覚が徐々に周囲を捉えていく。所々剥げた絨毯……染みになり破れた壁紙……骨だけになった照明……
ふと正面を見ると、目の前に窓があった。窓の外、丁度対角線の中心、満月が彼女と床のガラス片を照らしていた。
いきなり、中身を失い枠だけになったその外から、ヒュッと冷えた風が吹きこんできた。
彼女は驚き、反射的に右手で視界を庇った。冷気が彼女の体温を奪う。彼女は、そこでやっと覚醒した。
―――自分はどうしてここにいるのだろう?
手を除けると、再び月が彼女を捉えた。眩いほどの光が溢れ出していた。女性的な優しい光だった。彼女は思った。月の光は、これほどまでに明るかっただろうか?
彼女は、誘われるように窓に向かって歩き出した。残ったガラス片で手を切らないように気をつけながら、窓枠に手をかけた。
身を乗り出すと、そこから町が一望できた。遠くに高層ビルがかすかだが確認できる。すぐ手前は住宅街。まるで海のようだった。そして、所々に見える赤い光。
―――パトカーだ。
そう思った瞬間また、横風が吹きつけてきた。今度のはさっきよりも強かった。乱れる髪が顔面を覆い隠す。彼女は思わず窓から離れた。
彼女が目を開けると、ぼんやりとした月が、彼女のことを見ていた。彼女をずっと笑っていたように見えた。
ふいに彼女は言いようの無い恐怖感に襲われた。あの満月。あの月は今、私を殺そうとしたのかも知れない。私をおびき寄せて、窓から突き落とそうとしたのかもしれない。
……そうに違いない。
月は、変わらず穏やかな光を放っていた。笑っているようにみえた。しかし、彼女にはもう、獲物を狙う魔女の微笑みにしか見えなかった。
いや違う。獲物なんてものじゃない、そんな生理的な欲望は感じられない。
―――殺すために殺そうとしている。私を。ああ、笑っている。私の血が見たいんだ―――
彼女は、全身の毛が逆立つのを感じた。
―――怖い。
思ったが早いか、彼女はさっき来た道を今度は逆に走り出していた。
息を切らして、右手に階段を見つけると、そのまま駆け上った。ハァハァと呼吸しながら、目には涙を浮かべていた。必死だった。
―――どこか、光の届かないところへ!早く!殺される!
彼女は、しばらく階段を駆け上った後、疲れて、踊り場の床に座り込んでしまった。そこは真っ暗だった。ここなら安心だ、と彼女は思った。
壁に体を預けて、呼吸を整える。自分が信じられなかった。今までこんなに必死になったことはなかった。どうして私、こんな目にあってるの?
そこで………彼女は気付いた。―――自分はなぜここにいるのか?
彼女は、重大な疑問に突き当たった。つまり―――自分が何者であるか。
口に出してみた。ねぇ、ここはどこ?
発された言葉は、空しく壁に当たって消えた。答えは返ってこなかった。
彼女は、しきりに頭を振った。懸命に過去の記憶を引き出そうとした。しかし、思い出せたのは自分の名前、自分が高校生であること、そんな些細なことしか出てこなかった
。
駄目だ。諦めて彼女は立ち上がり、周りを見回してみた。すると、自分がもたれていた壁、その少し上に何か書かれているのを見つけた。
暗かったので目を凝らすと、『11F↑』と書いてあるのがわかった。どうやらこの上は十一階らしかった。
―――どこかの会社のビルか、それとも、ホテルか何か?
ホテル。その言葉で思い出した。……ここはホテルだ。
駅を降りて、待ってるはずの彼は駅にいなかったから、学校に行こうと思ったら、なんかいっぱいパトカーがいたからこりゃマズいと思って、遠回りしたら……。
……ここに来た。
………そんな馬鹿な話があるのか?やっぱり私は何も思い出せていなかったんじゃないか?
彼女はその先を思い出そうとした。
―――ロビーに行ったら、彼がいて、そこで何かを、言われた。そこで、私は逃げてきた。
何を言われたの?彼は何を………。
……いや、違う。間違ってる。いたのは彼じゃなかった。他の誰かだった。
ガシャン、という音が遠くで聞こえた気がした。彼女は、びくっと頭をあげた。確かめようと、恐る恐る階段を登って十一階のフロアに出た。
前後を見回す。物陰は無い。散乱するガラス片や調度品の成れの果て。どこかで照明か何かが落ちたのかも知れない。
彼女はゆっくり、まっすぐ進んだ。さっきのフロアで見た光景と変わりなかった。
………いや、待って。この光景には、見覚えがある。どこで見たんだろう。
…………。
……わからない。なんだろう。物凄く不安だ。いやだ。こんなのはいやだ。
彼女は、そこで諦めてしまった。諦めて座り込んでしまった。ぺたりと腰を落ち着けると、どうしようもなく不安になってしまった。
そのうち、感情を抑えきれなくなった彼女は、涙を流し始めた。
次第に嗚咽が漏れ、しまいには声を上げて泣き出した。わんわんと。えんえんと。
彼女は縋る物が欲しかった。彼女は寂しがり屋だった。それは、自分でも自覚していた。
だが今は、何も縋る物は無かった。自分の記憶すらもあいまいだった。一縷の希望すら見出せなかった。地に足がつかなかった。
このまま自分は死んでいくのだろうか。孤独なままで。何も得られないまま。誰も見つけられないまま。
あの月に。
信じられない。殺すために殺すだなんて。おぞましい………。
そう。さっき殺されかけたように、今度はちゃんと、惨めに殺されて。
そう思うと、一層涙が流れた。もう何も考えられない。彼女は泣き続けた。その姿は、ただの少女のようだった。
母親を見失った幼児のようだった。
彼女は右手にナイフを持っていた。なぜそんなものを持っていたのか、彼女は忘れていた。
刃の部分は綺麗に磨き上げられ、研がれていた。銀色が光を反射した。
彼女は、思いついたかのように涙を拭くと、刃先を左の腕に押し当て、そのまま横に引いた。
痛みが左腕を走った。
彼女は、また泣き出した。いたい、いたいと言いながら。
傷を手で押さえようとしたが、右手はナイフを指先が白くなるほど強く握っていて離れなかったので、仕方なくグーのままで傷に押し当てた。
当然、血がじわじわと彼女の服を赤く染めていった。
赤い一筋となって、左の指先から血が床に吸い込まれていった。
彼女は痛みと悲しみの中で、目を開けた。
世界は彼女の中でクリアになっていった。
これで四十八個目だ。ゆっくり、扉を開ける。一歩進んで、軍師にもらったペンライトで、室内を照らす。ベッドの陰、カーテンの裏。天井。
誰もいない事を確認すると、廊下に出て隣のドアを開ける。さっきからこの繰り返し。
「……やっぱ一人で来るんじゃなかったな」
独りごちても、誰も反応してくれなかった。ちょっと寂しい。
と言うか、本当にしんどい作業だった。軍師が止めたのもこういう事情があったからだったのか。
「…………」
愚痴を言っても始まらない。さっさと済ませてゴハン食べて寝よう。
「………四十九個目…」
扉を開ける。正直さっきの部屋と代わり映えはしなかった。そして、当然のごとく誰もいなかった。俺は深いため息をついて廊下に出た。
「つうか、ここでこっそり下に逃げられてたら、骨折り損ですよねぇ……」
掘った穴を埋め戻す作業を繰り返している気分だった。まさに空役。気が狂いそうだ。
「うがぁぁぁあああああああああ!!!やってられるか!!!!」
狂った。決断するより行動が早かった。体は正直だった。
俺は、床の上に大の字になった。眠かった。疲れで脳液が膨張して破裂しそうだった。畜生。このまま寝てやろうか。
「……しかし、こんな所をあいつに見つかったら、問答無用で内臓ぐちゃぐちゃにされるよなあ……」
内臓ぐちゃぐちゃは嫌だ。こう見えても俺はドナー登録しているんだ。臓器提供意思カードも肌身離さず携帯している。
俺が死んだら俺の腎臓から皮膚から骨髄から爪の先ににいたるまで、日本中の不幸な人間に分配されるんだ。後に残るのは乾いた魂だけ。
そうとも。内臓ぐちゃぐちゃなんかにされてたまるか。目を閉じればほら、俺の心臓や肝臓を心待ちにしている子供たちの輝いた瞳がそこに――――。
「………あほらし」
大体。
いっその事、俺はあいつに殺されたほうがいいんじゃないだろうか。
さっきはみんなに大見得を切ったが、正直、俺はどんな顔をしてあいつを迎えたらいいんだろう。
考えてみても、あんな奴の存在自体がおかしいんだ。本来なら病院送りにしておくべき人材だ。それを放っておいたのは俺たちと、学園だ。
そう。あの学園は異常だ。滅ぼされるべきだ。俺の日常を返して欲しい。全員病院送りにしてくれて構わない。エプロンをして、頭を洗濯しろ。
ありえない。狂みたいなのを放っておくなんて。
でも。
「………あいつを助けたいとは思うんだよなあ」
助ける。
その言葉の意味も、極まって空っぽだ。それは病院送りにするのと何が違うのか。
やっぱり、俺は今まで通りあいつの行動に目をつぶって、今まで通り馬鹿げた日常を貪ることになるのか。
………なんか、これが一番ありそうだった。
ありがちな結末。予定調和。誰もがそれを望んでいる。
―――こうして狂うちゃんを捕まえた男君は、今まで通り、ヘンテコな日常に生き、幸せな日々を送りましたとさ、めでたしめでたし―――。
「………うわ……すっげーありそう」
というか、これが幸せってもんじゃないか?ヘンテコだろうがなんだろうが、それは幸せ。日常は幸せ。平和が一番。
でも。その陰で、たくさん人が死ぬ。俺の知らない人が。
「…………」
げんなりした。
これなら殺されるのが楽だ。何も考えなくて済む。それは、詰まる所逃避だけれども。
考えは結局纏まらなかった。
俺は天井の染みの一点を見つめた。深い、深いため息を一つついた。
そして、確かに語りかけた。心から。
「……狂よ」
か細い声で言う。
「俺さ、何もわからなくなっちゃったよ……お前はどうして欲しい?」
答えは返ってこなかった。
「俺さ、お前のこと、今まであんまり見てこなかったからさ、わかんないんだよ、ごめんな」
割れた窓から冷気がゆっくり流れてきて、頬を撫でていくのがわかった。眠けが徐々に収まっていく。
「俺、お前の声を聞きたいな……だからさ、今から、会いに行くから」
ゆっくり、そっと立ち上がった。
「頑張るわ俺も」
俺は軽く伸びをして、ドアに向かい、再び廊下に出た。左右を照らして、確認をしてから歩き出した。
「……五十」
数字は合ってるだろうか。間違っていないだろうか。
今の俺は?………そんな事知ったこっちゃない。
分からないんだから。分からないことは本人に聞くのが一番だ……まあ、大体は。
俺は、いかなる類の確信も持たずに動いていた。正直何も変わらなかったと言えばそれまでだった。ずっと迷っていた。そして今、それ以上に迷っている。
この先にあるのが天国の扉なのか地獄の門なのか判別がつかない。正直、怖かった。泣き出しそうだった。
だが、俺は彼女に会いたかった。その事実だけが、希望だった。
ドアノブに手をかける。彼女はいるだろうか。彼女は。
俺は彼女に語りかける。お前はどうして欲しい?
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: