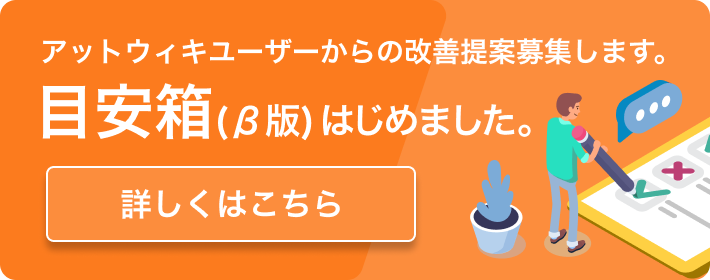空想にふけるのをやめにして、私は瞼をあける。
頭に思い描いていた夜の森の幻影は、痛むほどに冷たい空気もろともに消え去った。
あとに残るのは・・・
◇
帰りのホームルームを終えた教室は、生徒のざわめきで満たされていた。彼等の話し声とともに教室全体を覆っているのは濃厚な人いきれ。
クリームを気体にしたようなその空気は、正午を三時間ほどまわっているということもあって強烈に眠気を誘った。事実何人かは、周りでクラスメイトが帰り支度を始める中、未だ机上に突っ伏して起き上がらない。
彼等は本日最後の授業を、脳の疲労から来る抗しがたいタイプの眠気との格闘に費やしたクチである。
なんとか授業を耐え抜いたはいいが、その後に来た、『授業からの解放感』と『退屈な帰りのホームルーム』のダブルパンチにあえなくノックアウトされた、という訳であった。
彼女が空想にふけったのは、そんな『退屈なホームルーム』をやりすごすためだった。
中身のない半ば形骸化した担任のお言葉と、取り立てて重要でない連絡事項。
無為な時間を、彼女は脳内でお気に入りの風景を呼び起こし、そこに没入することでやりすごそうとしたのだ。
しかし彼女もまた、午後の気だるい空気に意識を半分持っていかれてしまったらしい。気がつくとホームルームはすでに終わっていた。
彼女の考えでは最後の起立と礼のところで現実に帰還するはずだったのが、ものの見事に失敗してしまっていたのだ。
皆が起立する中で、たった一人椅子に座り続けて空を見つめる自分の姿を想像してしまい、思わず赤面する。
因みに彼女、ぼんやりして気が抜けると、口元がひょっとこのようにとがる癖があったりする。
彼女―――友人やクラスメイトからは『通訳』と呼ばれている―――はいそいそと立ち上がると、机の中から教科書とノートを取り出した。
金属製の本体の上に木板を接合した典型的な学生机の上で、取り出した教科書類を両手で持ちトントンと整える。
次にいったんそれらを置いて、脇に下げた茶色い簡素な革製鞄を机の上に乗せる。
最後に鞄を開き、その中に教科書類を詰め込んだ。
両手を揃えて取っ手を持ち、くるりと机に背を向ける。触れば吸い付いてくるような滑らかさで、黒の長髪がさらりと空に踊った。
先程赤面した顔は、すでに平生の色を取り戻して、今ではどことなく虚ろな瞳と感情の読みにくい無表情がくっついている。
そのまま教室内の淀んだ空気を裂きながら、一直線に出口を目指す。
彼女の背後では、胸中の抑えられない愛情を絶叫して表現する女子。
人間だって食べちゃう肉食少女に狙われる、人間に食べられるさだめの食用少女。
一日の退屈な勤めから解放された所為で理由のない悪戯心がふって湧いた友人、
に頭を覆っていた布を取られて慌てるネコミミを生やした男子。
などがいたが、通訳はそれらすべてに無頓着に歩を進めていた。
絶叫も肉食も食用もネコミミも、ツンデレに続く新しいジャンル発見を目的に設立された試立新ジャンル学園では、取り立てて珍しい存在ではないのだ。
と、彼女の耳がクラス内のとある会話を拾う
「なになに?『男』 ―?今日は『男友』 と帰んないの?」
「うるせっ。そんなの俺の勝手だろ。」
「ま、そりゃそーですなっ」
「っつか何の用だよ?『ツン』」
「別に?ちょいとあんたの間抜け面が拝みたくなったってだけよw」
「ああ、そう」
「そうよ」
「ふーん」
「そう」
「で?」
「え?」
「や、だから、で?なに?ツンの方から話しかけてくるの久しぶりだろ?小2で別々のクラスになった時以来じゃね?」
「そ、その・・・」
「あー、悪い。ごめん。」
「へ?」
「俺今日さ、早めに帰ってマルエツまで買い出しにいかないといけないんだわ。親が飲み会で金だけもらって自炊するように言われてんだよ。」
出口の直前で、立ち止まり振りかえった通訳の視線の先には、男と女が一組。
机の脇に立つ女の方は何か言いたそうにしているが、椅子に座ったまま帰り支度を進める男の方は、それに全く気づいていない。
言おうかどうか躊躇っている申し出を、告げられぬまま終わってしまう事への焦燥。
それに気付いてくれない鈍感な男への、軽い失望と憤りが女の胸の内でないまぜになっていた。
――――――――――――そして二人に意識を集中していた通訳の心中にも、『同じ焦燥と同じ憤りが伝わって』くる
(多分・・・このまま過ぎ去っていけば彼女は伝えられないままに終わるんでしょうね)
通訳にとってはどうでもいい他人事だ。見過ごすこともできる。
けれど、彼女はそれをしない。
焦燥と失望と憤り。その背後には素直になれない女の気質があって、さらにその背後には、男に対する異性としての恋愛感情があった。.
そういった、心の中の種種雑多な動きが通訳には『わかる』のだ。
なにかしらの伝達手段を伴わずに、ただ意識を向けるだけで自分の感情の様に理解できた。
だから―――という訳ではないけれど、やはりそういった背景を知ってしまっては、知らぬふりができないのが通訳という人間だった。
それまでは顔だけ二人に向けていたが、回れ右をして体全体でそちらに足を向けた。
「そ、そう。そうなんだ。」
「そう。だから悪いけど帰るな?」
「え、えと・・・」
「ぉっこらせっと。それじゃ・・・」
教科書類は机に入れたままに、男は脇にかけたバッグを手に取る。そのままナイロン製の取っ手を絡ませた右手を机の上につき、掛声一発立ち上がった。
そんな彼に何か言いたそうに、何度も視線を送っては逸らし送っては逸らすを繰返す女。
通訳は男の背後に音もなく立ち、その肩に手をかける。『ホン』という軽い感触がお互いに伝わる。
「彼女は『い、一緒に帰ってあげてもいいわよ?その・・・男が迷惑じゃなきゃ・・・だけど(///)』と言っております」
「ん、通訳?」
男は唐突に現れた人物の名を口にする。通訳は、女の心の声を通訳する。
「え、なに?一緒に帰・・・る?」
通訳の口から告げられた言葉を男は復唱。その表情は、どうにかこうにか言葉の発音を理解して、今現在頭の中で必死に噛み砕いていると言った感じだった。
女の方は、顔をかすかに赤く染め、男に向かって激しく首を縦に振っている。
「あ、そう・・・か。いいよ」
「!!」
いまいち何が起こったか把握できていないのか、気の抜けた表情で、とりあえずの返事をする男に女の顔が輝く。
「・・・・・・・・・・・・」
それを確認した通訳は何も言わずに、踵を返す。
先程教室を出ようとしたときと同じ調子でわき目もふらず出口へ向かう。
その瞳は相変わらず虚ろな印象を与えるものだったが、口もとには何かをやり遂げた者に特有の、満足げな笑みが微かに浮かんでいた。
諸々の理由で、自分の想いを伝える踏ん切りがつかない。そういう人間を見つけるたび、その心を代弁してみる。
外面は無感動に見える彼女であったが、半面、必死になって想いを伝えたがる心を感じると、それを伝えずには居られない直情的なところがあった。
そして、そんな事を繰り返しているうちにいつの間にか「通訳」の通称で呼ばれるようになっていた。
なぜそういう行動を取るのかと問われれば、彼女はしばらく視線を上に向けて思案した後、『暇つぶし・・・でしょうか?』と自信なさげに答えることだろう。
人の心が読める彼女にとっては、『暇つぶし』程度のことなのだろう。
『伝えたくても躊躇われてしまうような想いを伝える』という行為でさえも――――――