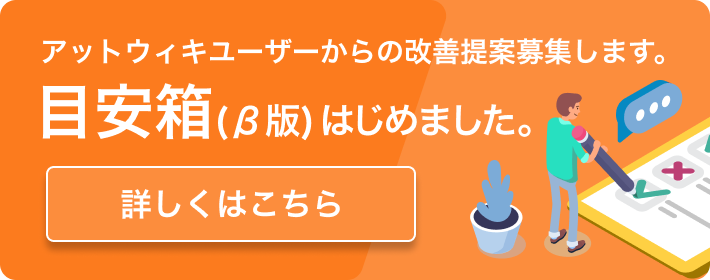市営バスのステップを降り、黒いアスファルトの上に足をつける。背後でお腹に響くようなエンジン音を立てながら、バスは走り去っていった。
ふと空を見上げると、赤く染まった空が見える。私は急に空腹と、それに伴う脱力を感じた。
一日三食、というのは栄養学的にも現代人の生活に合致しているサイクルだ、と家庭科で先生が言っていた。けれどこれには少し問題があるように思う。
このサイクルでいくと、朝には10時頃。午後にはちょうど今―――つまり4時か5時ごろに強い空腹感に襲われるのだ。
さらに午後の方の空腹は、一日の疲労も重なって耐え難いものとなってくる。
その感覚は、空腹と言うよりはむしろ飢餓感と言った方が正しいと思う。
(バナナ・・・バナナが確かに家にあったような・・・ああ、足が震える・・・)
間食はダイエットの大敵かも知れないけど、育ち盛りの私にとっては無くても困るものでもあった。
家には小さい頃から好物だったバナナが、我が家の常として置いてある(日中、空き巣かなにかが侵入して金目の物を盗むついでに食べていった、と言うなら悲しい事に話は別だが)。
一刻も早く帰ってそれを口にしないと、この家から五分と離れていないバス停の上で行き倒れてしまうことだろう。
その光景を頭に思い浮かべてしまう。明らかに恥ずかしい笑い話であることを理解する。
とにもかくにも私は家路を急ぐことにした。
バス停は交通量の多い道路脇の歩道に、標識を立てただけの物だった。そのすぐそばに小道が一本通っている。
私はそこに入って、歩を進める。
小道はしばらく行くと急な坂になり、左手に森が、右手には崖とその下に住宅街が広がっていた。崖側には白いガードレールが転落防止用として連なっている。
もとより幅の狭い道なので、車が来るとどちらか片方によけて、通過するまで待たなければいけない。
自然、どちらかに寄って歩くことになるが、崖側は危ないので大抵の場合が森の方に身をよせて坂を下ることになる。私も例にもれず、落葉した枯れ枝と葉の落ちない針葉樹が入り混じる森の脇を歩いていた。
特になにを考えたわけでもないが、車道の境界線を示す白線だけを踏みながら家を目指す。
頭にあるのは家に帰って早くバナナを食べようという事で、意識して歩いていたわけではない。
幼い頃からこうやって遊びながらここの坂を登ったり降りたりしていて、それが小学校や中学校に上がっても抜けずに習慣となっていたのだ。今では白線以外の黒い部分を歩くと、なんだか妙に居心地が悪くなる。
そうやって右足左足と交互に出しながら昏い木の陰の中を下り続けると、唐突に道が平坦になり森が切れ目の前に十字路が現れる。
左側の森を除けばどちらの方角も家が連なる住宅街であった。因みに、このまま真っすぐ行くと、再び別の森に突き当たる。
住宅街は森の谷間を切り開いて作られていたのだ。
私の家はこの住宅街の一角にある。なので二階にある自室からは、周囲の屋根を通して森が見えたりする。
いつだったかサトリさんを家に招いた際には
『通訳さんって森の傍に暮らしてるんだね?なんかイメージどおりかもw』
と、やや興奮しながら
『でもいいなー。なんか神秘的な感じだよね?森のそばって。憧れちゃうかも。あのね、ほら、あれ。ロードオブザリングのエルフみたい!』
目を輝かせて森の傍の生活に対する彼女の想いを語っていた。
たしかに森と言うのは普通の街中とは雰囲気が違うので、夜に奇麗な色をした月が光輪を半分ほどひきつれて木々の上に佇んだり、雨の夜が過ぎ、大気中に水分が含まれている所を葉の間から差し込む陽光が幾本もの光の柱が浮かび上がらせたりと、幻想的な風景にお目にかかることもある。
しかし、だからと言って浮世離れした場所かと言えばそうでもない。
夏が近づけば虫が大量発生し始めるのだ。気を抜いて網戸をしっかり閉めないでいると、いつの間にか家中が虫だらけ、なんて事がしょっちゅうだった。
私と父は、そのたびに殺虫剤をまき、蚊取り線香を焚いたりと、お世辞にも神秘的とは言えない生活を強いられていた。
その事を話すと、彼女は夢を壊されたような顔で『そっか・・・そうだよね・・・』と先程までとは一転してうつむき暗い声をだしていた。
憧れていたスターや俳優が裏で汚い事をしていたのが暴露された時の様な、落差の激しい失望感が伝わってきた。
彼女には伝える必要のないことだったのかも知れない。
住宅街に入って一ブロック過ぎた所で左に折れる。そこの、右側の一列に道に面した家々の戸。その真ん中が私の家だった。
どこにでもある二階建ての一軒家。屋根は年月を感じさせないツルリとした瓦が並び、隣の家との間の狭い空間には、室外機やポリバケツが見える。
私は、早くバナナにありつこうと、襲い来る空腹感と疲労にせっつかれてスカートのポケットから家の鍵を取り出した。
◇
台所にそびえる食器棚。その隣で壁に掛けられた時計がカチコチと規則的な音をならす。
椅子に座りながらぼんやりとその音に耳を傾ける。
――――カッチ、コッチ、カッチ、コッチ
窓の方に目をやる。
既に日は暮れて、黒一色に染まった引き戸のガラスには椅子に座る私服姿の私と、一斗缶より少し小さいくらいのごみ箱がうつっている。
再び時計の音に注意をむけた
――――コッカ、コッカ、コッカ、コッカ
時計と言うのは不思議なもので、常に変わらず時を刻んでいる筈なのに、秒針の音にいくつかのバリエーションがあるように思える。
現に先程までとは少し音の出方が違う。
恐らくは私のほうの感覚の問題なのだろう。
心理学なんかだと、この時計の音が違って聞こえる現象にも名前がついていそうだ。ゲシュタルト崩壊、みたいな感じの。
そんな風にとりとめもない思考を巡らせながら、ぼんやりと居間と台所の間から伸びる廊下。
その玄関との境界にある扉に目をやる。
扉は完全に閉めきられずに微妙に隙間があいている。
しばらく見つめていると、そこから音もなく一匹の猫が姿を現した。
毛並みは、白と黒が行儀よく住み分けたものだ。
「おいで」
私は椅子から降りてかがみ、猫に向かって呼びかけた。
ジゴ袖で、シンプルなデザインのワンピース。単調な暗色をしたその服の、足元の裾の部分が床と接触して、軽く皺を浮かび上がらせる。
私の言葉に、猫はそれまでの忍び込むようなゆっくりした動作を、少し早めのトコトコと足を動かすものに変えた。
すりよって嬉しそうに体全体をすりつけてくる。
それをひとしきり眺めると、両手で前足の部分を抱えて椅子に戻り、膝の上にのせた。
すると彼は、機嫌よさそうに喉をならし始める。
猫と言うのも時計同様不思議なもので、私が姿を現すと、喜びながらすぐさま駆け寄ってくるのではなく、しばらく時間を置いてやってくる。
現に我が家の猫も、帰ってきた私が手を洗いうがいを済ませ、学校指定の制服―――何故かセーラー服とブレザーの二種類が選べるようになっている。私はセーラー服を選んだが、やはり『試立』と言うだけあってそう言った点での自由度が高いのだろうか―――から私服に着替えて、バナナとホットミルクを用意して台所の机で人心地つくまでの間には、全く気配を示さなかった。
とはいえ、私に対して好意や興味がないのかと言えばそうでもないようであった。
のんびりとくつろぐ彼の心は、お気に入りの飼い主の膝の上へと半日ぶりに舞い戻ったことに、幸せを感じていた。
こういった動物の心も私にはわかる。さらに、本心をうちあけると、人の心より動物の心を読むほうが好きだった。
よく言われるような『人間の心が汚いから』 というのとは少し違う。
確かに汚い部分もあるけど、それは動物も同じだし、奇麗な部分だって人の心にはちゃんとある。
この世界には良い所も悪い所もあるように、人の心も汚いだけじゃなく、心の読める自分が救われるような奇麗な面もあるのだ。
だから、特に人間に絶望しているわけじゃない。
けど、それでも、私は人間より動物の心の方が好きなのだ。
動物の場合、心と行動に矛盾がない。なにか感情が湧きあがると、それが素直に行動や表情にでる。
しかし、人間の場合、そこにズレがある。
雑多な理由で彼等は本心を偽る。
そのあたりの複雑な精神構造が、イマイチ好きになれない。
嫌い、というよりかは、宿題として難しい数学の問題を大量に目の前にしたような、おっくうな気分にさせられるのだ。
もっと皆自分の心に素直になればいいのに。などと良く考えるが、それはそれで社会がうまく立ち行かなくなるのでやめてほしいな。なんて、大抵はすぐに思い直したりする。
「ニャー」
空を見つめてあれこれと考えていると、猫の方から声をかけてきた。
何時もの事だが、私が考え事に没頭して彼の方に注意が向かなくなるのが気に入らないらしい。
「・・・・・」
無言でカリカリとなでてやる。
それで彼は満足したのか、悦に入ったように目をすぼめて口を大きく開く。
至福の表情を披露した後は、私の膝の上から飛び降りて、明りの付いていない玄関のほうへと去っていった。
勝手にやってきて勝手に去っていくあたり、本当にきまぐれな生き物だと思う。
猫から解放されたので、私は考え事を再開することにした。
そろそろ寒くなってきたので、帰ってきてからつけていた電気ストーブのスイッチを「強」にする。
首も降らせていたのを止めて直接私に当たるようにしてから。
◇
いつから他人の心が読めるようになったのか、私にはわからない。
物心ついたころにはすでに人や動物の心が読めるようになっていたし、それに疑問を抱くようなこともなかった。
父親も同じことができる辺り、どうやらそちらの遺伝らしいが、それ以上の事はわからない。
私に母親がいない事と関係があるのかと聞いてみたこともあるが、父は笑ってはぐらかすだけで決して核心に触れようとはしなかった。
心を読んでみても、その部分は固く閉ざされていてわからない。本心が強い情念や意思によって覆われた場合、相手の心を読むのは限りなく難しくなるのだ。
結局、私自身どうしても知りたい事では無かったので、話はそれ以上進展せず終息した。
心が読めないというのは、相手にとって触れられたくない事であるのを意味するし、大して興味のないことを無理に聞いて父との関係がぎくしゃくするのもいただけない。
心を読む力に関する事で軋轢があって二人は別れたのだ、という事にして今のところは自分を納得させている。
それが真実であるかどうか、違うのであれば真相はどうなのか、なんて心底どうでもいい話だった。
私にとっては心が読める理由も母がいない原因も、日々の生活や父との関係と比べれば、無視してもなんら問題のない些事にすぎなかった。
『心が読める』という特殊な、場合によっては深くもある事象に対して、『些事』とは我ながら淡白な反応だと思う。
それもこれも心が読める故なのだろう。
幼い頃から私はひとりが好きだった。
保育園で皆がごっこ遊びやおままごとに興じているのを尻目に、ぼんやりと周囲の人間の心を読んでいた。
あまりよく覚えてはいないが、当時の私にとってはそれが楽しかったのだろう。ともかく日がな一日そうやって過ごしていた。
誰ともその楽しみを共有できない事に苛立ちを感じて、半ば意地になっていた面もあったかもしれないが。
ただ、だからといって孤立して虐められていたかというとそうでもない。
なにしろ心が読めるのだ。相手の思う事を先読みして、それに合わせてふるまえば、トラブルは全て事前に回避できた。
心を読んで要所を的確に押さえて反応しておけば、人間関係で悩まされることも煩わされることもなかったわけである。
そうやって、誰かから迫害されない程度には人付き合いをして、余った時間はたった一人で本を読んだり動物の相手をしたりぼんやりして、今までの人生を過ごしてきた。
誰かに迫害されない代わりになにか大きく得ることもない。
穏やかで平静。プラスとマイナスの差が少ない植物のような生活はしかし、私から熱を奪っていったのかもしれない。
気がつくと私は、なにかにつけて強く思うということが無い人間に育ってしまった。
ただその場の状況に合わせて動き、あとはときたま気紛れを起こして人の心の通訳をしたり空想にふけったりするだけ。
―――そんな私にとっては
たとえ身の周りのことであっても
この世界のことは
どこか別の世界のことのように、ガラスを一枚隔てた所から見ているように
現実味を欠いて感じられたものだった