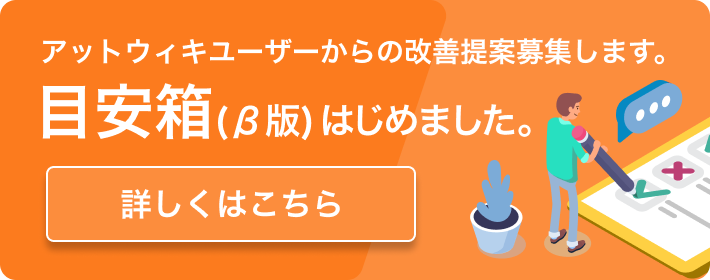女子更衣室の扉を開くと、斜陽に照らしだされた下駄箱の列が目に入った。
ねずみ色の金属でできた下駄箱が10列ほど。緋色を含んだ光を半身に受けて整然と並んでいる。
ガラス戸の入口からから差し込む光は、コンクリートの上に並ぶ踏み板を赤く照らし、リノリウム張りの廊下が伸びる更衣室前まで届いていた。
放課後の飼育当番を終えて更衣室へ向かう時には、まだ昼間と変わらない無色の光だったのが、ジャージから制服に着替えて姿身で乱れを直しているうちに赤く変色したらしい。
冬の日の落ちる速度を実感しながら、私は廊下に足を踏み出す。
ギュッという、上履きのゴム底とリノリウムが摩擦する音が聞こえた。
すでに校舎から人気は無くなり、聞こえてくるものと言えば廊下の曲がり角に設置された、3台の自動販売機の低く唸る様な駆動音。
それから校庭から幻のように響いてくる部活動の掛声だけ。そんな空間では、足音は否が応にも意識された。
ギュッギュッジュッギョッギュッジュッギュッギョ
足を踏み出すたびに、不快と言えば不快な、軽快と言えば軽快な、奇妙な足音が生じる。
それらを引き連れて私は、女子更衣室からは死角になっている自分のクラスの下駄箱へ向かった。
恐らく同僚君はすでに着替え終わって、下駄箱で靴を履き替えていることだろう。
毎週の経験から、ほとんど確信に近い予測ができた。
毎回私が下駄箱に至ると同時に、彼は靴を履き終えて立ち去るのだ。会話を交わすことはないが、私は同僚君の背中を見送ることで飼育委員の仕事の最後としていた。
彼の背中を見送ることは、仕事の中の辛い部分を担う人物との別れ、すなわち仕事の辛さそのものとの決別を象徴していたのだ。
男子である同僚君と女子である私の間には、着替えの時間に大きな開きがある。本来なら私が追い付くことなく、彼の方が先に帰っているはずだった。
しかし、飼育小屋を実質的に管理している用務員さんへの引き継ぎを同僚君がうけ負っているので、私の方が先に着替えを始める形になっていた。
結果着替えの時間差が縮められ、こうして私が追い付くという現象が起こるのだ。
―――ふと、用務員さんのことが頭に浮かぶ。
背の低い、黒い無地のTシャツに短パン姿。常に赤いつばつき帽子を被っている用務員さん。
中性的かつ幼い顔だちをしているため、人によっては年齢的にも性別的にもま逆の判断を下したりすもるが、彼女はれっきとした成人女性だった。
働き者で生徒達からも「裏方さん」「裏方雑用さん」と親しまれているし、トラ吉もわりとなついている。
そんな彼女に同僚君はどう接しているのだろうか?やはり、いつも私に接するように、つっけんどんな態度をとっているのだろうか?
それとも人当たりの良い用務員さんには、それ相応の態度をとっているのだろうか?
そう考えて、飼育小屋や教室での彼とは違う接しやすい同僚君を想像してみようとも思った。が、いつもの眉間にしわを刻んだイメージがどうにも拭えず断念する。
そんな風に考えているうちに、自分のクラスの下駄箱までたどり着いていた。
果たして同僚君はそこにいた。そこにいた、けれど
「おや?」
目の前の光景に、そんな声を出してしまう。
逆光の中、下駄箱前で同僚君は廊下側に向かって立っていた。
その正面には、こちらに背を向ける形で人影が二つ。
「あれ、通訳?」
私の声に人影のうち右側がこちらを向く。
「ツンさん、どうしてここに?」
人影は男さんとツンデレさんだった。
お互いに意外な人物の登場に驚いた声をあげていた。
「あ、そっか。通訳も飼育委員だったんだよな・・・」
私の姿を認めた男さんが頭を掻きながらそんなことを言う。
なんだろう
なぜだか彼の貌、いや、心から何か暗いモノが感じられた。
表情は逆光のせいで読み取れないが、確かに心に流れ込んできたのは暗く沈んだ感覚だった。私がやってきたせい、と言うよりも、もともとそうであったかのような・・・
同僚君と一緒にいた事に関係があるのだろうか、と彼の方に視線を向けてみた。
―――相変わらず心は読めない。表情も、やはり逆光で読み取れなかった。
「男、それで話ってなんだよ?」
そんな、赫い光の中に溶けて行ってしまいそうな同僚君の輪郭が、身じろぎして男さんに呼びかける。
相変わらず、つっけんどんな感じの口調だ。きっと、さっきまで引き継ぎのために相手をしていたであろう裏方さんにも、こんな感じで話しかけていたに違いない。
とにもかくにも、同僚君は、何か用があって二人に呼びとめられていたらしい。
彼の声に、男さんも私に向けていた視線をそらした。
先程の男さんの心の状態も含めて、いろいろと気になった私はそちらに注意を向けようとした。
同僚君の心は読めないが、男さんの方だけでもかなりの事が分かるはずだ。
けど、その行動はツンさんが話しかけてきたことで、未遂に終わってしまった。
「そう言えば通訳、昨日はありがとね。」
「え、と・・・この前、、、というと・・・」
ツンさんは、小声、というほどではないが、声のトーンを落として私にだけ聞こえるように話しかけてくる。
しかしその内容は、どうにも私が失念していることを話題にしているらしかった。というか、流石に『昨日ありがとう』と言われただけだと何のことだか判断しかねる。
彼女はこの学園で、私が最も頻繁に通訳している人物だ。
そうやって何度も付きまとっている内に気がつくと、彼女の幼馴染でいつも行動を共にしている男さんも含めて、いつの間にか『ただの知人』よりも仲が深くなってしまっていた。
サトリさんのような心の読める仲間や、その派生で知り合った誤解殺気さん達とはまた別の系統の人間関係と言える。
そんな訳で日に何度か接している彼女に、『昨日』と言われても、『昨日』のどれであったか迷ってしまう。
恐らくは私が通訳したことに関してなのだろうが、私達の関係は、男さんに対して素直になれないツンさんを(ツンさんは幼馴染の男さんに想いを寄せているが、男さんはその想いに気づかない。私が通訳し続けても決定打にならないあたり、彼は絵に描いたような鈍感さんだと思う)私が通訳する、というパターンがほとんどである。
なので、一日だけでも二人に関しては結構な回数の通訳をしていて、その内容は殆どが頭の中から滑り落ちているのが実際だ。
通訳に関することだとは思いいたってもそこから先は結局、見当がつかなかったりする。
と、言うか、まあ、別に彼女達が相手でなくても、通訳した内容は普通、すぐに忘れ去ってしまうのだけれど・・・
「ほら。昨日の帰りの時よ。あの時通訳がいたおかげで、男と一緒に帰れたんじゃない」
私の反応にほんのちょっと顔をしかめながらも、ツンさんは嬉しそうな表情でそう言う。
「そうでしたか。それはなによりで・・・」
返しながら、我ながら気の抜けた返事をしているな、と思った。
彼女は偽りなく嬉しそうにしているのだから、こちらももうちょっと同調するべきなのに。
しかしおかげで、彼女の言ったことについては、何時の事かはっきりと思い出すことができた。
先程は唐突に話しかけられた上、男さんと同僚君に意識を向けていたせいで、心を読めずそれらしい対応が取れなかった。
けど、今はしっかりとツンさんに意識を向けている。望めば、私が思い出した内容が間違っていないか確認することだって可能なのだ。会話に齟齬が生じたりすることはもう無いだろう。
確かに昨日私は帰り際、ツンさんが男さんと一緒に帰ろうとするのを手助けした。
しかも、心を読む限りその後――――
「でさ、あの後男がどうしても夕飯作ってくれって言うからね。しょうがないからあいつの家まで行ってご飯作ってやったのよ。ホントしょうがない奴ね。感謝してほしいわ。」
「ツンさんの方から誘ったようにも思えますが・・・」
「ば、馬鹿言うんじゃないわよ!なんで私があいつの為にっっ」
どうやら親が飲み会の為に、自炊か外食、もしくは買い食いを迫られていた男さんに家までついていき、夕食を作ってあげたようだ。しかもその後一緒に食べている。
ただ、心を読む限り、言葉とは裏腹に、申し出たのはツンさんのほうであるらしかった。
指摘してみると、顔を真っ赤にして否定する。
想いを寄せているのだから、もっと素直になればいいのに、と思う。男さんも悪くは思っていないから、ツンさんが素直になればすぐにでも恋愛関係に発展するはずだ。
けれど、そうはならない。ここら辺が人間の心理の複雑さ、と言ったところだろうか?
「はあ、そうですか。」
「そ、そうよ」
「と、見せかけて実は、」
「いや、ないから」
「男さんのこと嫌いなんですか?」
「えっ・・・そ、そんなことないけど・・・」
「好きなんですか?」
「あんな奴のどこがっ!」
「じゃあ私が貰ってもいいですか?」
「え、じょ、冗談よね・・?」
「冗談です」(ニコ
「そ、そう・・・よね。そうよね。そ、そんなこと・・・(ちょっ、びっくりさせないでよっ!通訳!)」
唐突に芽生えた悪戯心に任せてちょっとからかってみた。
私が放つ短い言葉にも彼女は一喜一憂する。
その心の動きを感じて、私はなにか、言い知れない気分を覚えた。けど、それが何なのか、良く分からない。
ただ、奇妙な胸の奥が落ち込むようなその感覚は、サトリさんが私の好きな小説を受け入れられないと言ったあの時に感じたものと、何故か似ていた。
その後も二人で他愛もない話を続けていた。
中身は
『去年まで色恋沙汰を一切匂わせなかった誰それが、最近はとある男子と仲がいい』なんて恋愛談議や、
『駅前繁華街のどこそこに、魔性が出るらしい』とかいう訳の分からない怪談(『魔性』が何か尋ねたら『ま、魔性は魔性よっ』と返された。つまり魔性は魔性らしい)に、
『同じ学年の、何組だかは全体的に子供っぽくて困る』などの愚痴だったり・・・
ツンさんは、『これぞ年頃の少女が興味を持つに相応しい』と言った内容の噂話をしていた。
私を相手に語るその貌と口調は、妙に弾んでいる。
いつもツンケンしているのが普通なのだけれど、どうやら今日は機嫌が良いらしい。
彼女の心の中で、昨日男さんと夕食を食べた時の記憶が、折りあるごとに多幸感を伴って蘇っているのが原因であるに違いない。
そして私の中の奇妙な感覚は、彼女がそれを思い出すごとに強まっていった。いつしか私は、その感覚の正体をおぼろげながらも捉えはじめていた。
感覚の正体は、ある種の距離感と、そこから来る寂寥感だった。
楽しそうに語るツンさんは、明らかに昨日の出来事に影響されている。
男さんを想い、恋する。
それに関係するあらゆる結果が、彼女の心に大きな影響を与えているのだ。
今回のことだけではない。ツンさんの通訳をするたび、ある時は悲しみが、ある時は喜びが、またある時は憤りが。私一人のときには決してあり得ない鮮やかさで伝わってくる。
それもこれも男さんに対して想い、執着するゆえなのだ。彼の行動が彼女の心を大きく動かす。
実際彼女の表情や反応にそれらは強く反映している。
そして―――――私にはそれがない。
複雑な心を持つ人間がなんとなく好きになれない私には、なにかしら特別な感情を抱く人間がほとんどいない。
まあ、小さい頃から一緒だった父や、周りの友人なんかは特別と言えば特別だけど、少なくともツンさんのような強い心の動きを起こすほどではないのだ。
そう。私には実感できない。
確かに男さんが好きなツンさんの心の動きは理解できる。その動きの『幅』が、私の物とは比べ物にならない程に多彩であることも。
けれど、特別な感情を抱く人間がいない私には、ツンさんの男さんにだけ感じる恋慕がわからない。
男さんに執着し、彼の動きにことさらに心を動かし、気がつくと相手の事を考えている。
それがどういうことなのか、良く、分からない。
さっき『私が貰ってもいいですか』と聞いた瞬間に、ツンさんから焦燥が伝わってきた。
それは、一人の人間に想いを寄せるがゆえの焦りと戸惑い。
一応、解ってはいる。
なぜそういう反応をするのか、については解ってはいるのだ。
けれど、実感がわかない。
その感覚に同調することが、どうしてもできないのだ。
彼女の心の動きが、鮮やかであればあるほど。大きければ大きいほど。
それが実感できない私は、彼女に対して距離感を感じてしまう。
きっと、他の人にもツンさんのように特別な、大きく心を動かされる特定の人間がいるに違いない。
心を読める人間は(私の知る限り)少数派だし、心が読めるからと言って、誰もが私のように人間全体から距離をとってしまうわけではないのだ。
そう考えると、私のように殊更心を動かす人間がいない人は絶望的に少ない、という話になる。
―――つまり、それが意味するところは
『普通』は、誰にでも想いを寄せる特別な人間はいる。
けれど、そうでない私は『普通』でない。
という事実―――
私はずっと、彼等のそういった側面を『理解』できずに終わるのだろう。ツンさんに感じた距離感を、この先多くの人に感じていかなければならないかもしれない。
そう考えると、たまらなく寂しくなった。
特別な人間のいない私は『普通』ではなくて、多分、この寂しさを分かち合える、『理解』しあえる人間はいない。
そう言う意味で私は孤独だったのだ。
それを今、理解してしまった。
サトリさんに対しても僅かに感じたこの感覚は、同じ作品の面白さを共有できない、違う常識を持つが故に『理解』しあえない。
その事実からくる一種の距離感だったのだろう・・・・・・
「それじゃあ、また明日ね?」
「はい。また明日、教室で」
男さんと同僚君の話が終わったので私達も別れの挨拶を交わす。
ツンさんは男さんのもとに走り寄り、二人並んで下駄箱をあとにしようとする。
結局男さんと同僚君が何を話しているのかわからずじまいだった。それどころか、男さんと同僚君が一体どういう関係なのかも判明していない。
その事に気が付き、ハッとした。
気に掛ったことの答えを明日までお預けにされるのは、なんというか、その、気持ちの良いものではない。せめて男さんと同僚君の間柄は知っておきたいところだ。
私は、二人並んで帰途に就こうとする男さんとツンさんを呼びとめようとした。
呼びとめようとして目にしてしまう。
二つ
踏み板から廊下まで長く伸びる影が
それを映し出す背中も
目にした私の心の中に、例のあの寂しさが湧きあがり溢れ出しそうになった。
◇ ◇ ◇
(多分・・・私はずっとあんな風に誰かと並んでは歩けないんだろう)
なぜなら私はあなた達とは違う『常識』を持っているから。あなた達のように大切な人なんていないから―――
ザワリ、と心がざわめく
そうやって感覚を心の中で言葉の形にしてみると、何故だか妙に落ち着いた。
そうだ。私は私だ。人間が何となく好きになれないのも、友人と違う常識を持っていても。誰か、執着する特別な相手がいなくても。
大丈夫。やっていける。私はうまくやっていける。今までと変わらず。これからもずっと。
彼女から伝わってきたあの鮮やかな感情を私自身が感じることなんて望めない。望めないけれど、それでも良い。
あふれ出しそうになる感覚になんとか対処すべく、そんな風に諦めることを想定してみた。
そうすると意外にもすっきりとして、先程までの寂しさも気にならなくなっていった。
今までの人生と変わらず静かに、周囲にも、私の心にも波風を立てない。ツンさん達のような喜びはないだろうけど、逆に苦しんだりすることもない。
そもそも今までそうやって過ごしてきたのだ。
それをこれからも続けるというだけの話だ。
それに他人と違う常識を持っているというのなら、それはそれで私が周りに流されない確かな私を持っているという証明にもなる。
そう考えると自分が力強くも思えた。自分に自信が持てた。
―――心に浮かんだ寂しさは諦めで薄められ、自身に感じる力強い感覚でかき消される
大丈夫。私は大丈夫だ。何も問題もなく、これからも、きっと、やっていける・・・・・・・
◇ ◇ ◇
「あの、、、」
「ん、なに?通訳」
「なんか忘れもんかあ?」
「いえ、ちょっと気になったんですが・・・」
「なになに?どしたのw男に貸したノートが返ってこないとか?」
「あのなー・・・」
「アンタならあり得る話でしょ。それで、気になることって?通訳?」
「はい。あの、男さんと同僚君ってどういう関係なんでしょう?良かったら教えてもらえると・・・その、意外な取り合わせだったもので」
「ああ、あいつ?幼馴染だよ」
「幼馴染?」
「うん。幼馴染。あいつ、今はあんなんだけど、昔は結構付き合いやすい奴だったんだぜ?」
男さんはいつもと変わらない、気さくな印象を与える笑顔で同僚君との間柄を明らかにした。
彼の容姿を加味して考えた場合、そういう表情で応えるのは大方の女性に殺人的な影響を与えてしまうのだと早く気づくべきだと思う。
見た所無意識のうちにやっているようだが、いずれにせよこのままだといつか彼を巡って女同士の骨肉の戦い――それも史上最大級の――が勃発してしまうことだろう。
と言った所で、この学園の半数近い女子生徒に彼が好かれたり想われたりしてる現状からすると遅すぎて意味のない話でもあるが。
◇
ともかく彼は、人あたりの良さそうな柔らかい表情をしていた。
日没直前の、限界まで紅さを強めた陽光がほとんど垂直に彼とツンさんの顔に当たっていた。
下駄箱前の踏み板の上で、体は昇降口に向けながら、顔は廊下にいる私に向けて捻っているため右半分だけが紅い。
それが、以前に文化辞典で見た、プリミティブな民族が顔を儀式用に赤く塗っている写真と重なった。
写真には、『精霊』の意味を持つペイントを施すことで本来の『人間』としての性質が覆い隠され、儀式において精霊として相応しい意味合いと振舞いを持つことになる、といった趣旨の説明が添え付けられていた。
・・・今の彼は『それ』だった
今彼が顔にしているのは『ペイント』で。
普段と変わらない表情をしているものの、その実心の中はいつもの表情ではなかった。
彼は
『人間』を覆い隠して『精霊』を呼び出すように。
『本心』を覆い隠して『日常』を演出していたのだ。
彼の心には先ほど同僚君と向かい合っていた時に感じた、暗く沈んだ感情が渦巻いている。ついでに何か罪悪感じみたものも。
具体的に言うとそれは、親とはぐれ、どうして良いのか分からず途方に暮れる迷子の心情に似ていた。
暗く沈んで途方に暮れた感覚・・・・・・・そして、そして、
自分でも意外だったけど、私は『それ』に対して特に心を動かしはしなかった。
ただ、感情の変化は起こらなかったけど、それでも『そんな事もあるんだ』という感心は抱いた。
何故って
―――――――同僚君以外で心が読めないなんて、滅多にない事なのだから。
私は男さんの、この沈んだ心の原因を探ろうとした。けれどその部分が、どうしても読めなかった。
すぐに合点がいった。彼にとってそこは、他人に知られたくない部分なのだ。
というよりも、自分でも思い出したくないのだろう。強く鍵をかけて思い出さないようにしている。心に浮かびそうになると別の事を考えて、胸の奥深くに沈めてしまうのだ。
さすがの私も、考えていない事は読めないので原因については知るべくもなかった。
結局その事については探るのをやめた。
相手が思い出したくないと思っている事を無理に思い出させるのはあまり良い趣味とは言えないし、下手をすれば男さんとの仲がぎくしゃくするようになってしまうかもしれない。
それどころか場合によっては険悪な関係に陥る危険性もあるのだ。
昔から、そういった摩擦は起きないように気を付けていた。
そのせいか、この原因の探求の中断は半ば条件反射的に行われた。
普段から心を読んで人間関係の摩擦を避けてきた習性が、私に探求を打ち切らせたのだ。
◇
「はあ、そうですか・・・・・あれ?ということはツンさんとも?」
「あー・・・そーねっ。一応小学校のころからかな?付き合いあったのは男だけで私はあんまりだったけど、三人とも一応顔見知りだよ?」
「俺とツンは幼稚園の頃からだったけどな。物心ついたころから顔見知り」
「あんたと人生のはじまりを共有したなんて消し去りたい過去ねwフフン」
「うわっwwwひでーなwwそんなこと言うかwww」
「今のあんたが不甲斐無いからよ」
「彼女は『昨日だって、ご飯食べてそれで終りってなによ・・・せめて手を握るくらい・・・・・・最後まで行くのだって考えてなくは
「わーわーわー!!!なんでもないっ!!なんでもないからっ!!!(//////////////)」
「ははwww(^^;)顔真っ赤だな。」
「うるさいうるさい!この鈍感!
ともかく通訳!私達は幼馴染!終了!
それから男!旅行っ!どこ行くか決めるんでしょ!?早くしないと遅れるわよ!?」
「あーー、、、そうだった。通訳」
「はい、なんでしょう?」
「俺達さ、男友とかと一緒に春休みどっか行こうかって話になってんだけど、通訳も来る?」
「旅行・・・ですか?」
「うん。」
「考えさせていただいても?」
「ああ、オッケーオッケー。一応さ、3月までにどうするか教えてくれると助かるわ」
「了解しました。」
「うん。それじゃ、またな。通訳」
「また明日ねー」
「はい。また明日、よろしくお願いします。男さん。ツンさん」
男さんとツンさんは、昇降口の外へと出ていった。
下半分に金網が埋め込まれた耐圧設計のガラスの入口。その合間から見える外の空間は、既に群青色の空気に満たされていた。
その中で二人は振り向きざまに手を振って私への別れの挨拶とすると、薄闇の中校門へ向かい、やがて視界から消えた。
いつの間に点いたのか、残された私の頭上では蛍光灯が白々とした明かりを放っている。
時間的にはまだまだ終わらないのだろうけど、部活動の声は止んでいた。恐らく小休止かなにかしているのだろう。
廊下とその前に広がる下駄箱の列。
その中で聞こえる音と言えば、最初から変わらずに響く自動販売機の起動音くらいだ。
いつかテレビでやってた特撮の、超低周波攻撃にも似た鼓膜を震わせるそのリズムは、何故か妙に私のいる空間を広々としたものに感じさせた。
その広漠とした昇降口の空間内で『通訳』はポツンとしている。
―――そう言えば、同僚君はどうしたのだろうか?
ツンさんと話し込んでいるうちにその存在を完全に失念してしまっていたが、今頃になって彼の存在が気になり始めた。
その姿を見出すべく、私は周囲に視線を配った。
廊下の左奥―――蛍光灯に照らされた曲がり角、そこに至るまでに掲示板や会議室の扉が壁に見える。
廊下の右奥―――階段と、誰もいなくなり明かりが消されて黒くなっている一年の教室が見える。
正面――――――下駄箱と、入口。薄闇の広がる昇降口前の広場。
彼の姿はどこにも見当たらない。
残念な、気持ちに、なる
(残・・念・・・?)
今しがた自分の中によぎった感情に、眉をひそめた。
なぜ、私は彼の姿を探したのだろうか?
いたらどうなるという訳でもないし、同僚君の人柄から考えると男さんとの話が済んだ時点で帰ってしまったと判断するのが妥当だ。
冷静に考えればここにはいないと判るはずの人物を探していた私は、冷静ではなかったという事になる。
なら、一体何が私を冷静ではなくしたのか・・・
遠くでは、幻じみた部活動の掛声が再開されている。
いや、違う。
そもそも私が冷静になれないのは今に限ったことではなかったのだ。
私は同僚君を前にすると常に冷静さを失っていた。
心が読めない彼を前にして、どう振舞うべきか判らず恐慌状態になりそうな自分を静めることだけで精いっぱいで。
冷静で論理的な思考はほとんど望めない。
だから私は、数ある人間関係の中で、彼『だけ』が苦手なのだ。
『そう言えば通訳、昨日はありがとね。』
先ほど同僚君に向かう男さんの心を探ろうとした矢先、それを遮ったツンさんの言葉が思い出される。
この時私は、それが何を意味するかすぐには分からなかった。
頻繁に通訳しているツンさんが相手なので、その近辺の話であるのは予測がついた。けれど、そもそも通訳の内容なんて大抵はすぐに忘れてしまうものなのだ。
だからそれ以上の事は分からず、結局相手の心を読むことでやっと『男さんと一緒に帰りたかったツンさんの通訳』を思い出せたという有様だ。
そうだ。本来、通訳した内容は忘れるのが普通なのに―――
「あの、彼は、虎吉も『もうちょっと仲良くしてほしい。二人は似た者同士なんだから・・・』と言っております」
ポツリと呟いた言葉は、反響はせずに寒々とした白い光に照らされる空間に放たれる。
それなのに私の耳と周囲の空間にずっと残留している。
いつまでも消えない。
そらんじようと思えばいくらでも、何度でもできるに違いない今朝の虎吉の通訳。
これが普段とは違い、消えずに残留しているのは、内容が同僚君に関するものだからなのだろう。
心が読める故に、誰とも摩擦を起こすこと無く大した感慨も持たずふわふわと、まるで薄布を通しているような現実感を欠いた空気の中人と接してきた「通訳」
そんな彼女が初めて出会った心の読めない、読まさない人物「同僚」君
自分の行動や言動がもしかしたら相手の怒りを買うかもしれない。次の瞬間には、その合間に険悪な空気が横たわっているかもしれない。
そんな恐怖と緊張は、通訳には体験したこともないような強烈な感覚だった。
いつしか彼女は彼の一挙手一投足に対して、他の人間には決して払わない様な注意を払うようになった。
同僚の言動が、通訳の心に、他の誰にもできない程の大きな影響を与えるようになったのだ。
そういう意味では、私は同僚君に恋していると言えなくもない。
ツンさんが男さんに多くの注意を割き、その言動に普通よりも大きく心を動かされるように。
そんな執着している状況を『恋』と定義するならば、私は紛れもなく同僚君に恋していることになる・・・
「ただし残念ながら、好悪のベクトルは反対ですが、ね♪」
ニヤリとしながら思考の締めくくりを口に出してみた。
私が同僚君に恋をしているなんて、トンデモ本に掲載申請でもしたくなるような結論が出てしまったせいか、胸の底がくすぐられるような感覚がこみあげてきている。
それが顔の方にまで昇ってきて口角から溢れてしまったらしい。
一人笑って呟いたのはその結果だ。
全く・・・我ながら論理の飛躍が甚だしいと思う。
やり方によってこんな変な結果になってしまうなんて、論理的な思考というのも盲目的に信仰するのは止めた方がよさそうだ。
私は思わず笑い出したくなるような気持のままに、下駄箱へと足を運び、靴を履き替え始める。
上履きからローファーに履き替える際に、靴下を通して踏み板のヒヤリとした感触が足に届いた。
それで、さっきまでざわめき浮ついた心が幾分静まる。
冷静になって、さてこれからどうしようと思案しつつ、放課後の冷たい空気を裂いて昇降口のガラス戸のレールをまたぎ、外に出た。
外に出ると、私が降りるバス停周辺の住宅街から夕飯の匂いが漂ってくる。
まだまだ春は遠いんだと思わせる冷たく尖った風に混じっているせいか、物悲しさと郷愁めいたものを強く感じさせる。
旅に出ているわけでも実家から離れて暮らしているわけでもないのに、郷愁もなにもあったものじゃないとは思うけれど。
そんな心持で、ふと空を見上げると、宵の明星が紺の彼方に一つ。
しばしぼんやり見つめていると、父が今朝がた朝食の席で『仕事の都合で今日は帰りが遅くなる』と言っていたのが思い出された。
普段ならば、これくらいの時間に帰らないと夕食が父の帰宅に間に合わない。けれど今日ならば
――――――帰る前に少し、寄り道をしても誰も困らないはず。
私はつい最近見つけた、駅前繁華街の外れにある、古本屋に寄ってみることにした。