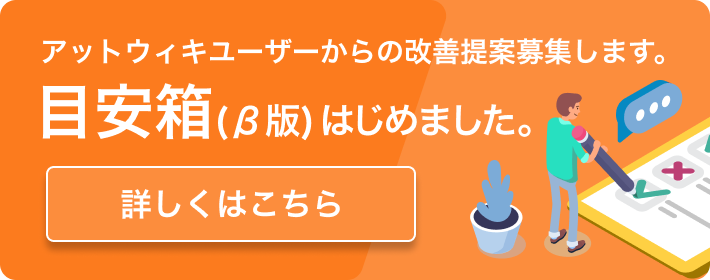窓は黒に染まり外は何も見えない。
駅前から出発したバスは今、駅から離れ交通量の多い公道を進んでいた。
ただ、その周辺は明かるさに乏しく、まばらに現れる森や畑が、連なったヘッドライトや街灯の光を吸い込んでいる。
駅周辺ではネオンやお店の灯りのおかげで、日が落ちても窓から外の様子をうかがい知れた。
けど、ここでは車内を照らす白っぽい照明が、外部の雑多な光に勝ってしまっている。
窓の外を見ようとしても、余程顔を近づけない限りそれは、車内を写す鏡にしかならなかった。
今、鏡となった窓にはコートを着た長髪の少女―――私が写っている。
鏡の中の私は、一人掛けの椅子に深くもたれて虚ろな瞳をこちらに向けていた。
その瞳には、窓のこちら側の私が抱く居心地の悪さなんて微塵も感じられない。
改めて平常時の私は無表情なのだと思い知った。
周りの人間からは、慌てると無表情ではなくなると言われているけど、それはつまり普段は無表情ということなのだろう。
鏡の私は常の表情と何も変わるところがない。
その事実にちょっと残念になる。私は今、こんなに居心地が悪いのだから、出来れば鏡の私も同じ表情をしていてほしかった。
その場の空気に耐えきれず外を見ようとして、鏡の中の私と目が合ってしまった感想がそれだった。
窓ガラスからは椅子に座る私の姿だのみならず、その背後の混雑した車内の様子もうかがえた。
バス内はほぼ満員に近い状態で、傍に立つ人の太ももが座席のひじ掛けに触れてしまう程の混雑であった。
私の傍にも、吊革につかまり窓を向く人たちで壁が出来ている。
と、その内の一人と鏡の中で目が合った。
しばらくお互いに視線を交わした後、どちらからともなく目をそらす。
会話はない。
されど彼とは他人という程、互いに接触がない間柄でもない。
・・・・・・私と同僚君はいつもと変わらない。
飼育小屋で普段感じている、息苦しい居心地の悪さが私の胸から上を覆っていた。
無意識のうちに息が滞っていたのに気が付き、深呼吸を一回。
体内で淀んでいた息を吐き出した後、私は窓の外を見ようとした。今度はしっかりと外の景色が見えるように出来るだけ顔を近づけて。
さきほど結露を拭った窓は、早くも曇り始めていた。私は膝の上に置いていた手袋をはめて、窓の曇りをそっと拭い、そちらに首を伸ばす。
対向車線の車のヘッドライトが幻のように連なっているのが見えた。
その向こう側には広い畑が広がっていて、果てにはゴルフのバッティングセンターを囲むネットが、影の塔のように黒々と佇んでいる。
田舎のような景色はしかし、ふと気がつくと何時の間にか奇麗に整備された住宅街に変わってしまっていた。
そんな風に森や畑と言った田舎っぽい景色の中に、それらを切り拓いてできた新興の住宅地が挟み込まれる。
これがこの辺りの基本的な景観であった。
駅からさほど離れていないのに、ずいぶんと景色は変わるものだと、少し目が開かれるような思いにとらわれる。
そうやって景色に心を移したお陰か、少しだけ息苦しさは和らいでくれていた。
けれどやっぱり左側では息苦しさの大元が、厳然とした存在感を放ち続けている。
お互いに顔見知りの人間が、お互いの存在を認識しあっているにも拘らず、お互いに一言も口を利いていない。
そんな状況から生まれる、或いはそんな状況を生み出してしまう私達の関係が、この場の重く息苦しい空気を醸成している。
同僚君か私がバスを降りるか、もしくは周囲の混雑が解消されて、彼が私の傍から離れる事の出来る状態になるか。
それまで私達二人は、モノを言う事の憚れるこの空気の中で、ただじっと耐え続けなければないのだ。
普段と違うバスを選んだことがこんな結果になるなんて、少し恨めしかった
あの後、古本屋を後にした私は駅前のロータリーまで歩き、このバスに乗った。
普段通学に利用している路線は、新ジャンル学園と家の近くの大通りを結んではいたが、あいにく駅には近寄らなかったのだ。
つまり私は、駅へ行く時も駅から帰る時も、バスを使うならば普段とは別の路線を利用しなければいけなかった。
そんな訳でバスロータリーまで歩き、駅へ訪れる際に帰宅に使う路線を目指していた。
その時、丁度ロータリーに別の路線のバスが入り込んできた。
複数の停留所が示された車体側面の表は、バスが私の家の近くで停まることを示している。
偶然だった。
偶然それまで私は、普段使用している路線以外にも家の付近を通るバスがあるのをを知らず。
偶然その時私は、普段使用している路線以外で家の付近を通るバスがあるのにに気づいたのだ。
奇妙な因縁めいた何かを感じた私は、なんとなくいつもとは違う路線を利用したくなってしまった。
そんな気まぐれを起こさなければ、今みたいに息苦しい思いはしないで済んだのにも関わらず。
まあ、いくら心の読める私でも未来は読めないのだから、今さらそんな風に言ってもしょうがない事ではあるけど。
ともかく私はそちらに乗ることにした。
丁度バスがやってきた所で乗ろうとしたこともあって、停留所には既に何人もの人が長い列を作っていた。
私はバスに乗り込む列の最後尾につく。
当然座ることはできなかったけど、発車してからすぐ次の停留所で、私の目の前の席に座っていた人がバスから降りていった。
運よく席に座ることができたのだ。
自分の選択とはいえ、家に帰るのが遅くなったせいで、気付かないうちに疲れが溜まっていたのかもしれない。
椅子に座ると、自然とため息がこぼれ、安堵した気持ちが体全体に広がっていくのがわかった。
私が座席についてからもしばらくは、新しく乗り込んできた人たちの影響でバス内は蠢いていた。
左側の通路で人の壁が左右に動いたり、後ろの人をこちらに押し出す気配が感じられる。
それもバスが再び発車する頃には終わっていたが、ふと、私は自分の傍に立つ人の姿が気になり視線を上にあげてみた。
――――見知った顔が目に入る・・・
飼育委員の同僚の彼が、私の座る座席の肘あてに足を当てて立っていた。
あの時は、彼も私も驚いた顔をしていた(自分の顔は自分では見えないから、あくまで主観ではあるけど)。
偶然同じバスの、それも非常に接近した位置で私達は鉢合わせたのだ。
けれど、ただそれだけだった。それで終わりだ。
それ以上私達の間に意志の疎通は交わされなかった。ただただ無言で、お互い目を合わせないようにしたにすぎなかった。
当然と言えば当然だ。
私は彼の事が怖かったし、彼も誰かと親しくする性格ではない。
私達の関係は飼育小屋と何一つ変わることがなかった。
摩擦を起こさないように、不必要な接触を避ける。
当然の帰結として温度のある会話はなくなる。
ただただお互いに相手に対して抱く、あまり良くない感情のせいでその場の居心地が悪くなって。
けれども、状況的にはその場を動けなくて。
そう。彼が未だに私の所から離れないのも、車内が満員で移動が難しいだけであって、それ以上の意味や理由は無い。
多分もう少し人が少なくなったら、彼も私の傍から離れるに違いない。
「・・・・・・・・・」
「・・・・・・・・・」
「・・・・・・・・・」
「・・・・・・・・・」
バスは、何番目かの停留所に停まろうとしていた。
停留所の名称や料金を告げるアナウンスが車内に流れている。
私達は相変わらず言葉を交わさない。間には沈黙が横たわっていた。
だけどその沈黙は、お互いに意識している中での沈黙だ。
知り合い同士で無言という異常な状況は、少なからず違和感を生じさせる。
特に私は、苦手な人間を相手にしているという事もあって、より一層居心地の悪さを覚えていた。
そこから少しでも逃れたくて、さっきからずっと私は窓の方ばかり向いている。
外の暗闇に目をやっていると、さまざまな想いが浮かんでは消えていった。外を見ていれば、居心地の悪い空気を意識しなくて済んだ・・・
外側から黒い画用紙を押し付けているような視界の利かない窓を見つめ続けながら、私はとりとめもない考えで頭を満たしていた。
特になんだか今は、今日起こった事ばかりが思い出される。
虎吉の通訳、サトリさんとのお話、ツンさんに感じた距離感や男さんの心が読めなかったこと、そして初めて立ち寄ってみたオフィス街の間を抜けた先にある古本屋・・・
そう言えば古本屋で女店主さんが長々と話をしていた中で、『孤立』とか『攻撃的』とか言っていたような気がする。
確か私はその時、なんだか同僚君の為にあるような単語だな、と思っていたはずだ。
そう。彼はクラスでも、やっぱり孤立していていた。
2年になって間もない頃、修学旅行の班決めが行われたことがあった。
和気あいあいとした雰囲気のなか班が次々と出来ていくその時も、彼はずっと一人でいたのだ。
むしろ、皆が親しい人間の元へ駆け寄って率先してグループを作る中で、彼だけはそれらの行為に逆行するように人の群れから離れていた。
飼育委員で顔合わせをしたばかりのころで、心の読めない彼の行動には今以上に注意を割いていたので、良く覚えている。
結局最後は、たった一人あぶれた同僚君を男さんが一緒のグループにいれる事で落着した。
当の同僚君はあまり嬉しそうな顔はしてなかったけど。
バスが停車する。
結構な数の人がバスから降りようと動き出した。その中の殆どは窓の向こう側に見える、白い塔のような背の高いマンション群に帰る人達だ。
降りていく人たちの心から、それを察することができる。
前方の料金を支払う場所から列が一つ出来上がった。列は、ゆるゆると断続的に進みながら、並びきれなかった人々を次々と組み込んでいく。
私は、その光景から窓へと視線を戻そうとした。
同僚君の脇腹のあたりがちょっとだけ視界の片隅をかすめた。
・・・・・・気になってしまう。
確かに私は彼の事が怖い。
心が読めないからどう接したらいいか判らず、それが同僚君への恐れにつながってしまっている。
けど、やっぱりあれだけ接近した状態で気にするな、というのが無理な話なのだ。
彼への恐れはあるけど、それと同時になんで彼がこんな所にいるのか、という好奇心もしっかりと存在していた。
―――ほんのちょっと。
彼は今どんな服装をしているのか確かめるくらいなら気付かれることはないはず・・・
そんな考えが頭の中で鳴り響いている。
見つかるかもしれない。見つからないかもしれない。
相反する思考が脳内で葛藤していた。
結局私は――――
「奇遇だな・・・こんなところで」
「っ!?」
好奇心に耐えきれず同僚君に目を向けたのと、彼が声をかけてきたのがほぼ同時だった。
予想外の出来事に、思わずビクリと身を弾ませてしまう。
「あ、あう、あ、あうあ、、、あのあのあ、あの、その・・・」
「駅前に来て、何してたんだ?」
さっきからちらほらと目に入ってはいたが、今も制服を着ている私とは反対に彼は私服姿だった。
上着は、いろいろとワッペンがついたカーキ色のジャケットを羽織っている。
色合いやワッペンのデザインから、パイロットのイメージを与えるその上着は、最近街でよく見かけるのと同じモノである。
そしてその下にスキニージーンズをはいていた。
良く分からないけど、流行にのってるあたり、実はお洒落なのだろうか?
そんな彼に突然、本当に突然話しかけられて、私は少なからず慌てていた。
雑多な思考が頭の中を駆け巡るが、うまくまとまらず、すっかりあがってしまう。
その結果、思考と言動両方もろとも完全にフリーズしてしまった。
「―――――」
「・・・・・」
「―――――」
「・・・・・」
さっきとは違う種類の沈黙が間に流れる。
すっかり固まった私を見て、彼は所在無げに頭をかいていた。
そして、それから更に数秒。
「いや・・・その・・・答えたくないなら別に良いけどさ」
「え!?あ、そのっ、はい!えっと、ちょっと古本屋にっ、奥まった所にあるっ、あの、変な女店主さんがやってる」
慌てふためいて余計なことまで言ってしまう。
同僚君は特に感情の変化しない表情で『ふーん』とだけ返してきた。
「・・・・・・・」
「・・・・・・・」
「・・・・・・・」
「・・・・・・・」
再び沈黙。
気まずかった。
本当に、彼を前にするとどうして良いか分からない。
相手の心が読めないからどうしても疑心暗鬼と言うか、地雷原を歩いているというか(歩いたことはないけど)、そんな心に余裕のない状態になってしまう。
まるで猛獣の闊歩するジャングルに放り込まれて、今にもそこの茂みから恐ろしい物が飛び出してくるような、喉がひりつき胃が下に落ち込むよな感覚。
それらが、沈黙が続くせいで、より鮮明に感じられてしまう。
本当に同僚君を前にすると、嫌な気分になる・・・
いつもこうなってしまって何もできない・・・
ただ、それでも今は・・・
今だけは、彼の方から話しかけてきてくれた。
それがどんな思惑であったにせよ、応えた私にも会話を途切れさせないようにする義務があるんじゃないか、という気がしてくる。
私は思い切って、一言だけ聞くことにした。
「あの・・・同僚君はなぜ、このバスに・・・?」
「ん、ああ。ちょっと旅行関係の本を見に駅前まで。」
そう言うと彼は財布を取り出した。
どうやら、ここで降りるつもりだったらしい。
話しかけてきたのも『せっかく知り合いと居合わせたのに、最後まで何も話さないのはいかがなモノか』、という考えからだったのかもしれない。
―――じゃあ・・・ま、そういうことで。
最後にそう言って、同僚君は出口に向かった。
私達の会話の間に、乗客の大部分が吐き出されていた。
ガランとした車内には、空席の目立つ座席と料金を支払う人の列が残されるのみとなっていた。
先程までの混雑が嘘のような、広々と余裕のある空間を、彼は悠然と進んでいく。人いきれだけが以前の混雑を証明する通路を、白い照明にその像を明らかにされながら。
前方で出口から吐き出される人の列は、しんがりに同僚君を加えたかと思うと、一分もしないうちに解消されてしまった。
財布をポケットにしまいながら、最後の乗客はバスステップに足をかける。
そのまま車内の明かりから宵闇に移行するかと思っていたら、彼は、一瞬だけ立ち止まって肩手をあげた。
別れの挨拶だった。
私もつられて、彼には見えないだろうけど、軽く左手をあげて左右に振ってみた。
バスのアナウンスが流れ、扉が閉まる。
座席のシートから伝わるエンジンの振動が強まり、やがて体が後ろに引っ張られる感覚を伴いながらバスは走り出した。
人気の無くなった車内は、さっきとは別の空間みたいだった。
コウコウと強い光に照らされた座席の列と通路。
中央部の乗車口とそこに備え付けられた鈍い銀色の整理券発券機。
窓枠に固定されている降車のためのボタン。
ツルリとした鉄柱からつり下がる、中吊りと吊革。
それらの輪郭が、なんとも言えない非現実めいたモノに感じられる。
フワリと現実らしさを失ってしまった物に囲まれた世界では、今日一日の疲れも手伝ってか意識が曖昧になってくる。
周囲の像が次第にぼやけたり元に戻ったりを繰り返すようになってきた。
斜め前に座るOL風の女の人が静かに頭を揺らしている。
目の前に座るお爺さんの背中も、さっきからずっと壁際に傾いたままだ。
緩慢な思考は、ここが夢か現実か、夢ならばどこからどこまでが夢だったのか、判断することを許さない。
―――――あれは夢だったのでしょうか・・・
先ほどの同僚君とのやりとりの記憶が、境界線を失った夢と覚醒の狭間でゆるりと溶けていく。
―――――同僚君は普段あんな服を着て・・・駅前には旅行の本を探しに来るような人だったんですね・・・・
会話は、いつも彼と交わしているものとは、少し違ったような気がした。
飼育小屋では事務的な会話しかなかったはずなのに・・・ここで話した内容は、お互いのプライベートに踏み入っていた。
半歩にも満たない僅かな領域だけだったけど、確かに私達はお互いが今まで知らなかった部分に踏み込んでいたのだ。
彼は私が辺鄙な所に立つ古本屋に立ち寄るような人間だと知ったし、
私もまた、彼が旅行の本を駅前で探す人間だと知ったのだ。
―――――やっぱり夢なのかもしれません・・・
同僚君と初めて温度のある言葉を交わした。交わしたことで、ほんのちょっとだけどお互いの事を知ることができた。
それは、過ぎ去ってしまえば、本当にあったかどうか信じられない様な出来事だった。
だから意識の定かではない今の私が、夢と判断してしまうのもそれほどおかしな事ではなかった。
だって同僚君の方から話しかけてくるなんて、普段の事を考えれば、まずあり得ないのだから。