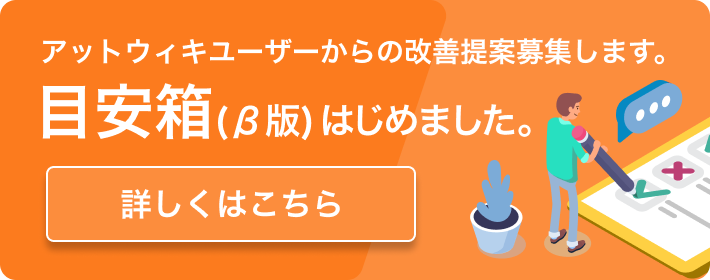奇妙な虎吉の通訳に始まり、帰りのバスにて同僚君と偶然に邂逅して終わった一日から数日。私は平静に日常を過ごしていた。
あれほど心を揺り動かされた一日がまるで夢か何かだったかのように、精神的にも状況的にも凪いだ状態が続いた。
一週間が終わり土日が過ぎ去る中で、特に言及するような事件が起こらなかったことも大きいのだろう。
数日間、私は普段どおりに学校に通い、普段どおりに授業を受け、普段どおりに友人と接して、普段どおりにツンさんや周囲の人間の通訳をして家に帰る、という日常を繰り返していた。
強いて変わった事をあげるならば、2月14日を前日に控えた日曜日。
サトリさんや誤解殺気さん達親しい間柄の女の子で集まり、皆でチョコレートを作ったことくらいだろうか。
読心クールさんが武士デレさんに絡む事で始まった恋愛談議の傍らで、私も父に渡すチョコを作らせてもらっていた。
チョコが焦げたことに悲観して錬炭を焚き始める鬱デレさんを宥めたり、その遠因を作ったほぼ無反応さんは相変わらず無反応だったり、と。
サトリさんの家にて行われたその日のチョコ作りは、割合楽しく進展して終わりを迎えた。
取り立てて何も起こらない数日間は、あの酷く心を揺さぶられた慌ただしい一日から、『起伏の少ない感情』と『現実感を欠いた感覚』で生きる日常への帰還を私に許した。
チョコ作りの最中だって、鬱デレさんの鍋から白い煙があがるのも、未成年の読心クールさんがウィスキーボンボンを作ろうとしていたことも、その挙句に酔っ払ってしまったのも、大した感慨を持たずぼんやり見つめるのみだった。
それは、全くもって非の打ちどころのない、私にとっての『普通』な状態に違いなかった。
けれどその実、完全にいつも通りという訳でもなかった。
心の奥底には未だに例の虎吉の通訳が残留していたのだ。
紅茶のカップの底に残った澱のように、あの日サトリさんやツンさんに感じた距離感や同僚君に対する執着への気付きが、心の奥にしっかりと横たわっていた。
意識的に思い出さずとも、それらの事柄が私の心の穏やかさに影を落としていた。
いつもどおりにサトリさん達と話していても、お腹の底に妙な違和感を感じてしまう。
それは本当に微かだけど確かに存在していて。
あまり経験したことのないような胃が落ち込むような感覚を折につけ意識していた。
あの一日によって私の中で何かが変わってしまったのかもしれない。
心穏やかに緩やかに、毎日を滞りなく流れされるように生きる私。
今は、そこに異物が挟み込まれて、底の方から流れが乱されている。
何も変わらない日常を過ごしながらもその実、何かが起こりそうな変に落ち着かない気分が、静かに胸の中を周回していた。
――――――結果として、予感めいたその感覚は当たることとなる。
後になって思い出して見れば、この後に起こる『事件』によって私は変わってしまったのだろう。
2月14日に、飼育小屋の前から始まった、とある『事件』によって・・・
◇ ◇ ◇
その日は、まるで誰かがカレンダーを一気に2か月分捲ったような暖かさだった。
雲ひとつない青天で朝早くから照りつけていた太陽は、今は南の空高くから地上の気温を上昇させている。
激しい運動を行えば、すぐにでも汗ばみそうな陽気だった。
そんな太陽の下に吹く風は流石にまだ冷たい物を含んではいたが、どことなく胸の奥をくすぐるような香りが混じっている。
風の冷たさも陽光の強さのお陰で相殺されている感じだ。冬の間ずっと感じていた寒さも今は気にならない。
『暦の上では春』なんて言葉は当てにならないと今まで思っていた。
けれど、こんな風に時期にそぐわない暖かい天候から春が始まる、という意味でなら昔の人は正しいのかもしれない。
そんな風に考えながら、昼休みのA棟脇を私は、のんびりと散歩していた。
昼食後で胃が活発に動いているという事もあり、トロトロと溶けてしまいそうな空気が体全体を包んでいる。
そんな色の濃い空気の中、背後から陽光が背中を温めてくれている。
私の小脇には防寒用のベストが挟まれていたが、これは『外でもベストを羽織っていれば十分』という私の予想を、本日の天候が上回った結果だった。
これまでずっと『寒さ』ばかりに晒されていた中で、久しぶりに暖かい、ともすると『暑い』とさえ言えそうな日がやってきたのだ。
校舎から聞こえる、生徒達の賑やかなざわめきと達者な言葉遣いの放送委員が送るお昼の校内放送を背景音楽として、特に目的地のない食後の散歩を楽しんでいた。
現在は、プラタナスやイチョウが並ぶ植込みと校舎の壁に挟まれた幅10mほどの道をプラプラと進んでいる。
頭の中に雑多で形の定かでない思考が次々と流れていく。
もう少し行くと傍らの校舎が途切れて、右側に飼育小屋が見えてくる。
そんな位置までやって来たためか、虎吉の相手をして時間を潰そうか、という気になったその矢先、私の心に強い想いが流れ込んできた。
その内容はこの日、2月14日に特有の、そして私「通訳」が今日になって何度も感じているのと同じモノであった。
◇
北側に面したA棟の壁。
敷地を取り囲む植込み・フェンスのセットと、校舎の直方体の短い辺に当たる壁に挟まれたその一角は、昼時の喧騒から僅かに隔離されていた。
校舎の壁は、どの階も内部から見ると黒板が据え付けられている側なので、他の面にはあるはずの窓が存在しない。
フェンスの向こう側も植込みがあるおかげで殆ど視界は利かない。
仮にはっきりと見渡せたとしても、昼時はほとんど人の通らない住宅街の小道があるのみなので、誰かに見られる心配がない。
壁と植込みの間、その先にある飼育小屋によって、そちらの方の視界も遮られていることも考えれば、密かに覗き見られる可能性はそう高くない場所だった。
つまりそれが意味するのは、
ここは、
他人に知られるのが憚るような行動をするにはうってつけ、
という事である。
そんな空間の入口、学園の敷地の角にあたる、フェンスと植込みがL字を作る地点に、私は立った。
視線の先には―――
「キバッ!キバッ!!!ミギギギギ・・・グギ、ギギギギギイイイイ・・・・シシシシシ」
「うわっ!ちょっ、なん、なんだよ!!突然呼び出し、、、わ、わ、わかった、うわ!!ちょっとやめろ!!やめろって!!」
女の子と言っても通用しそうな顔と体つきをした小柄な男子生徒と、身の丈を4m近くまで膨張させて、全身の至るところから生える触手を管の様になった舌と共に震わせている女子生徒がいた。
女子の方は、体を膨張させつつ背中に生えたコウモリのような翼を、バサバサと神経質に揺り動かしている。
毛細血管が浮き出た頬はどす黒い赤に染まり、カタツムリの様に飛び出た目玉は男子生徒をじっと凝視していた。
私は彼女のカギ爪の生えた手に握られた、財布くらいの大きさの包装された箱に気がつく。
――――これで、何回目でしょうか?
先程心に流れ込んできた想いが、彼女の物であることを確認すると、私はぼんやりとそんな事を思った。
傍らでは、女子生徒の恐ろしい外見に、襲われると勘違いした男子生徒が必死に命乞いをしている。
自分の真意が伝わらずヤキモキしている女子生徒の心を感じながら、今日一日でこの手の通訳を何回行ったか数えてみた。
・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・パーだった両手がグーになった所で数えるのをやめた。
とにかく今日はかなりの人数を通訳した。もう、それ以上の認識を抱くのは煩わしくなったのだ。
そろそろ目の前の通訳をこなさないと、男子生徒の方が恐慌状態に陥って取り返しのつかない事になりそうだったし。
「ほ、、、、ホント、、、なんなんだよぉぉぉ・・・俺、ひっ、俺、、死にたく・・・えっぐ、、や゛た゛よ゛お゛お゛おおおお」
「ミギッ!!ギギギギッ!!ギショ!!ギショオオオッ!!!」
「やああっ!!」
「あの・・・もし・・・彼女は『なんで解ってくれないの!?私はチョコをあげようとしてるだけなのに!!』と言っておりますが・・・」
「ふ・・・ふぇ?」
女子の方のイライラと男子の恐慌。お互いのボルテージが危険水域に達する直前に、私は男の子の方の肩を叩き、女の子の通訳をした。
「え・・・チョ・・コ?」
「はい。チョコです。」
「え・・・ミキ・・・が?」
「はい。こちらのミキさんが。」
「お、俺に?」
「はい。あなたに。」
命の危険、らしい中で、突然謎の人物が現れるという事態に、理解が追い付かなかったのだろう。
心ここにあらずと言った様子で単語に近い質問を彼は繰り返す。私は私で、イチイチそれに応えていく。
次第に、男子生徒も通訳の内容を理解していったようだった。先程までの緊張が徐々に溶けていくのが感じられた。
「ミギイイィィ・・・・」
「彼女は『一生懸命に作ったから・・・食べてくれなきゃやだよ?』と言っております。」
最後にもう一度、補足的に通訳してその場を去る。
とりあえず『恐ろしい外見の女の子にスプラッタ的に捕食されてしまうかもしれない』という男子生徒の誤解は、心を読む限りでは解けたようだった。
あの二人に関してはこれ以上心配はいらないだろう。
結果はどうあれ、女子生徒の『チョコを渡す』という目的は達成されるはずだ。
片方、或いは両方が素直になれないせいで会話を滞らせていた『つっかえ』が、通訳によって取り除かれる。
そんな時、いつも感じている快さを胸の端に認めながら、私は飼育小屋の方に向かっていった。
◇
「見たっすよお?通訳さんはホント通訳さんっすねえw」
飼育小屋に辿りつき金網の前に佇んだ瞬間、背後からそんな言葉がなげ掛けられた。
予期せぬ方向からの声だったので肩が小さく跳ねあがる。
「用務員さん・・・」
A棟とB棟に挟まれた谷間のような中庭。
飼育小屋の金網が面するそんな風景を背にして立っていたのは、黒いTシャツに黄土色のハーフパンツを履いた小柄で童顔の女性。
『裏方雑用』の名前で親しまれている、この学校の用務員さんであった。
彼女は、普段被っている赤いツバ付き帽子を片手に持ちながら、噂好きなおばちゃんのような顔で笑いかけてくる。
「見て・・・いらっしゃったのですか・・・」
「はいっす」
身を捩り振り向いた格好のまま問う私に、彼女ははっきりとした口調で返してきた。
どうも先程の男子生徒と女子生徒を通訳していたところを見られていたようだ。
まあ、別にだからどうという事もないのだけれど。
だけれど、本当のところを言うと、少し、うんざりしていた。
「それでどうっすか?通訳さん自身の方は?」
「・・・・・・・・・・・
いえ・・・・・・特には」
『どうっすか』というのは誰かにチョコを渡したかどうか、もしくはこれから渡すかどうか、という事なのだろう。
彼女の心からは、いや、彼女の心から『も』この日特有の浮ついた気持ちが伝わってくる。
・・・・・・許されるなら、ちょっと、ため息をつきたかった。
今日は2月14日だ。
キリスト教の某聖人の殉教記念日。チョコ屋の陰謀。女の子が想いを寄せる男の子にチョコレートを渡す日。
この学園も例にもれず、今日は一日中こんな感じだったのだ。
こんな感じ、といのはつまり、学園全体がバレンタインムード一色である、という事だ。
『自作のチョコレートを手に真剣に想いを伝えるべくあれこれ手を尽くす女の子』
『数えきれない程のチョコレートを渡されて、周囲から殺意の波動を受けなければならない男の子』
『チョコレートを占有する者に殺意の波動を送りながら、自らは渡されないものかと教室の隅々、下駄箱の裏まで捜してしまう男子』
『バレンタインの雰囲気に便乗して親しい人間に義理チョコを配る女子』
などなどなどなど。
数え上げればきりが無い、いろんな形の恋物語。それらが混じり合い重なり合う事で、普段ではありえない、一種異様な雰囲気に学校が包まれていた。
そう言えば、数日前に古本屋で『隔絶された空間は結界。この本屋はまさに結界といった感じだ』なんて考えていた気がする。
だとすると、今のこの学校も、特殊な雰囲気でもって結界を張られたようなものなのだろう。
私はこれから一日、学校のことを『聖(セント)バレンタインの聖域』と呼ぶことにした。どこかのライトノベルで聞いたような響きが、また良い感じだ。
少し話が逸れてしまったが、ともかく今日は誰も彼もが浮ついていた。
あまりそう言った事を意識していない人でさえも、さすがに学校を覆う雰囲気に抗することはできなかったのだろう。
本当に、ほんのちょっとでも浮ついた心を抱いていない人なんて、一人もいなかったから。
ただ別に、その事についてうんざりしている訳ではない。
かくいう私も、休日にチョコを作ったこともあって一応はその雰囲気を楽しむつもりでいたし、初めのうちは皆の浮ついた気持ちを好意的に見ていた。
そう。好意的に見ていたのだ。――――全く同じケースの通訳をした回数が、両手で数えきれ無くなるまでは。
普段なら色恋沙汰の通訳なんて、ツンさんの想いを伝える時くらいなのだ。それが今日は、全校の半数近くがツンさんになったみたいだった。
通訳する人間のほぼ全てが『想いを伝えたいけれども、伝えられない。』と言う状態だったのだ。
それが数人程度のうちは、まだ私も相手の気持ちに共感していられた。
けれど、教室から出るたびに全く同じ心を通訳しなければならないとなると、流石に何時までも純真な心持ではいられない。
類似した気持ちを感じるたび『ああ、またか』という心の声が次第に大きくなり、大した感動もない筈なのに普段の習性から通訳せずにはいられない自分にもだんだん嫌気がさしてくる。
何時しか、誰かの恋慕を読み取った時に感じる、ほほ笑ましい物を見たような好意的な感情が、マンネリした物に対して抱く、ゴワゴワとした無感動に不快さを孕んだような倦怠感に凌駕されていった。
自然、それに付属するようにしてあった『想いは抱いていないけど、雰囲気に任せて浮つく』人の心も、敬遠したくなってきたという訳である。
特に『学生ではないから流石にないだろう』と思っていた用務員さんまでがバレンタインムードの中にあった、という事実は決定的だったかも知れない。
灼熱の砂漠を歩いている中で、野生の電気ヒーターと遭遇しようなものだった。
「もしかしてアレっすかねえ?叩いて渡る石橋・・・石橋効果
・・・・・・なんか違うっすねえ。ほら、アレっすよ。あの・・・危機的状況から来るドキドキ感を恋愛のドキドキと勘違いするっつー・・・」
私の隣では用務員さんが、金網に手を突っ込んで虎吉の額を力強く撫でながら話している。
虎吉は目を糸の様に細め悦に入ったような表情で、『もっともっと』と金網に体全体を押し付けていた。
「『吊り橋効果』・・・ですか?」
「あー、それそれ。それっすwwww
やっぱなんだかんだで皆さん、虎吉の事が怖いんっすかねえwww」
「ガフガフ」
「虎吉は『みんなが勝手に怖がってるだけ』と言っています。」
「そっすねえw虎吉はこんなおとなしいのに。ねえ虎吉?
――――――そう言えば通訳さんは虎吉、平気なんっすか?」
「いえ、私は・・・・・・・・・もっと怖い人がいるので・・・」
「?」
「す、すみません(///)忘れてください」
怪訝な顔をされてしまい、慌てて前言を撤回する。
毎週この飼育小屋で出会う彼の事を思い出してしまったのは、きっとさっきまで用務委員さんが話していたモノの為に違いない。
用務員さん―――裏方雑用さん。
彼女は、学園内の事務職を除いた雑用全般を任されている。
その仕事は多岐に渡り、飼育小屋の管理もそのうちの一つだったりする。
あまり興味のない人には誤解されがちなのだが、飼育委員会の仕事はあくまで学生活動の一環である。
動物の世話も『学業に支障がない』のを目安としているので、飼育小屋に関する全てを管理運営できるわけではない。
実際の管理は全般的に学園側が行っていて、私達飼育委員がやっているのは、あくまでその『お手伝い』に過ぎないのだ。
裏方さんはそんな飼育小屋の管理を虎吉の世話も含めて任されている。
飼育委員は餌やりや簡単な掃除、小屋の補修の手伝いなんかがせいぜいだけど、彼女はそれ以外の全ての仕事をほとんど一人でこなしていた。
体調を管理するメニュー考案に始まり、必要な業者への連絡や小屋の維持・・・・・・
やるべき仕事は数え上げればきりがない。
どころか、それですら彼女に任された学園全体の雑用からすると、僅かな一部に過ぎないというのだから驚きだ。
どう見てもたった一人でやるような仕事の量ではないのに、ちゃんとこなしてしまう裏方さんは本当に働き者だと思う。
とにもかくにもそういう訳で、私達飼育委員と用務員さんは、仕事の引継ぎなどの関係で一般の生徒よりも顔を合わす機会が多い。
委員会にも2回に1回くらいは、注意事項の確認などのために出席したりする。
自然と私達は普通の生徒以上に彼女と仲が良くなり、裏方さんは裏方さんで、飼育委員会内部の人間模様に明るくなっていった。
飼育小屋の恋愛劇は、そんな飼育委員達と親密な彼女の口からもたらされた。
なんでも、今さっきまで飼育小屋で仕事をしていたという本日の飼育小屋当番の男女二人。
バレンタインたる今日という日に、女子の方からの告白だったようだ。
昼下がり、虎吉以外には誰もいない、学園の喧騒が幻めいて聞こえる飼育小屋の中。
動物がいるために薫る異臭も、お互いに慣れっこになっている。むしろ逆に、臭いに慣れているという共通点が二人の心を盛り上げていた。
仕事が終わる男を、女が引き止める。
ちょっと待って、という言葉とともにポケットから差し出される小さな箱・・・
僅かな間を置いて、男も女の気持ちに気がついて・・・・・・・
「やっぱし男子と女子を一組にすると、そうなっちゃうんっすねえ。」
虎吉の様子を見に来たところで、偶然その現場を目撃してしまった用務員さんは、腕を組んでしかつめらしい顔をしながら、そう一人ごちていた。
「それに未確認情報っすけど、他にも何組か飼育委員同士のカップルが成立してるらしいっすよ?」
「はあ・・・」
「気のない返事っすねえ」
学園全体のバレンタインムードに辟易していた私は、用務員さんの話を聞き流していた。
適当に相槌をうちつつも、件の結ばれた飼育委員に掃除されて、少しだけ奇麗になった小屋の方に目をやっていたのだ。
外の光を取り込んで割と明るくなっている金網の内側。
積み上げられた干草が寄せられている壁に、僅かに白っぽい脂が掃除されずに見逃されている。
それを見ながら『虎吉が食べている生肉は焼いて調理したらおいしいのか否か』なんてくだらない事を考えていた。
が、その中で、横から投げかけられる裏方さんの声の調子にハタとする物が含まれているのを察知した。
思考と視線を飼育小屋から外し、隣に立つ彼女に向ける。
「まあ虎吉はなんだかんだで猛獣っすからねえw
大人しいって皆さん解ってても、どっか緊張してるんじゃないかと自分は睨んでるっす。さっき言った釣り針効果っすよw」
「吊橋効果ですよ?釣り針じゃなくて」
「ああwwそうっすね。うっかりっすw
ともかく皆取り違えちゃうんっすねw緊張と恋愛のドキドキを。で、しかも男女二人で密室っすからwこれで何か起こらない方がおかしいんっすよww」
「・・・・・・・・・・言っておきますが」
「?」
「同僚君と私の間には何もありませんよ?」
「・・・・・・・・・そうっすか・・・・・・」
私の言葉を聞いて、用務員さんは明らかにションボリとした顔に変わった。
呆れたことに―――――彼女は私と同僚君の間にも何かあるんじゃないかと勘ぐっていたのだ。
『気のない返事っすねえ』という先程の言葉にも、いろいろと話を引き出そうとする裏方さんの努力に対して、こちらがそれらしい物をおくびにも出さない事への軽い失望が孕まれていた。
私にとっては傍迷惑な話だった。
同僚君とは飼育委員の同じ曜日を割り振られているだけであって、それ以上の何でもない。
バレンタインムードに浸るのは良いけど、それをこっちまで押しつけてくるのはどうかと思う。
そもそも同僚君に対しては、いい感情よりも悪い感情の方が大きい。
彼は心が読めなくて、それだけでも私にとってはイレギュラーで困る話なのに、さらに無愛想な性格をしているのだ。
彼も私も、お互いに温度のある会話なんてしたこともない。だというのに、どうして恋愛関係に発展しようというのだろうか?
発展するはずもない
発展するはずも
ない・・・・・・・?
そこまで考えて、自分の思考の中に間違いがあることに気がついた。
『温度のある会話』
そんな単語を以前に抱いていたのを思い出したのだ。
あの、古本屋からの帰りのバスの中。
人いきれが未だ残り、車内から降りる乗客の列を背景に、私、通訳と同僚君は言葉を交わした。
いつも飼育小屋で交わしている無機質で事務的なモノではなく、お互いのプライベートに踏み込むような・・・
温度のある会話、とはその時に私が抱いた感想だった。
ほんの少し、飼育小屋の同僚の彼の事を知った会話。あれは彼の方から話しかけてきたのだ。
そんなことがあり得るなんて今まで想像だにしていなかっただけに、バスが動くまどろみの中で、私はそれを夢ではないかと考えていた。
けど、今こうやって覚醒した意識で思い出せば、夢ではなかったのが判断できる。
夢、というのならその後に見た・・・・・・思い出せないが確かにバスの中で私は眠りこけ、その間に夢を見ていたはずだ。
内容は思い出せないのに、見たというのは思い出せる。バスが家の付近まで来たときにタイミング良く目が覚めた、その瞬間には細かい部分まで覚えていて反芻までしたはずだったのだけど・・・
不思議である。
「同僚君って・・・怖い人ですよね」
「はい?」
ポツリ、と口にした。
遠くの校舎から放送委員がやっている、お昼の校内放送の音楽が聞こえてくる。
音楽は、英訳すると変な名前になるスポーツ飲料のCMに、何時だったか流れていた邦楽だった。
青春を感じさせる歌のイメージは、バレンタインを意識しているのだろうか?同時に夏っぽいイメージもあるから、どちらかと言うとただの偶然かも知れないが。
それが昼休みのざわめきに混じり、中庭を通って飼育小屋の方にまで聞こえてくる。
けれどここ、私達が佇む飼育小屋の前は人気がない。
閑散と言うほどではないけれど、青い空の下、太陽に照らされていながらどこか寂寥としている。
校舎の喧騒や明るいBGM、それらが、一枚フィルターを掛けたかのように遠くに聞こえるのが原因なのだろう。
人々の活気が遠い。あちらは皆、ザワザワと五月蠅いけどこちらは静か。
その距離感と対比が、喧しくも活気のある音が聞こえてくる事が、何も聞こえない単なる静寂以上に、寂しさを孤立した感じを引きたててくるのだ。
「用務員さんは・・・どう思いますか?」
先ほどの自分の言葉を追いかけるようにして、言葉を続けた。
耳の中では、例の虎吉の通訳がクルクルと遠ざかったり近づいたりしながら再生されている。
私と同僚君が似ている・・・
あの、心の読めない読まさない彼と、私が。
普通の人なら心が読めない、なんて事はまずない。
人を拒絶して、拒絶して、その果てにやっと心を閉ざすことができるのだ。
そして同僚君はそれをやってのけている。普通ではない。彼はどんな孤独さえも寂しさも耐えてしまうに違いない。
誰も人を寄せ付けない態度はそのためなのだろう。
私にはとても出来ない。サトリさんやツンさんに距離感を感じただけで思い悩んでしまうような私には、彼が全く違う隔絶した理解の及ばない人間に見えた。
ありていに言えば、今口にした通り彼の事が怖かったのだ。
それは同僚君の性格が私を脅かす『不安』ではなく、心を読まさない状態で平気でいられるという、彼の強さに対する『畏怖』からくる怖れだった。
それなのに、そんなとんでもない人間を、虎吉は私と似ていると言ったのだ。
今は、ひとしきり用務員さんに遊んでもらって満足し、小屋の日向になってる部分で寝そべる虎吉。
虎吉自身が抱いたのは『似ている』という実感だけなので、なぜ似ているのかまではその心を読んでも解らない。
だから私は、隣で小屋の中に視線を向けている小柄な女性に聞いてみることにしたのだ。
少し遠まわしに、私が彼と似ているかどうか、のヒントを見つけられたらそれで十分と言った感覚で
「怖い・・・っすか?」
「はい。その・・・なんて言うか、近寄りがたいというか・・・」
「んーーー・・・そうっすねえ・・・でも・・・」
「でも?」
「―――いや、なんでもないっす。ただほら、あの人付き合いが悪いっすからねえ
自分には良く分からないっすよww」
気になる接続助詞を口にしながらも、笑いながら彼女は話をはぐらかした。
「っつーかもう結構な時間っすね。悪いっすけどそろそろ他の仕事もやらんとマズイっす。」
続けて彼女は別れの挨拶をする。
私もその言葉に、ポケットにあった携帯電話のデジタル時計で時間を確認する。
時間は昼休みの終了まであと15分を切っていた。
学生の私はまだまだ大丈夫だけど、用務員さんはそろそろ動かないといけないのだろう。
学園全体の雑用を任されているのだから当然と言えば当然かも知れない。
「はい。いつもお仕事、お疲れ様です」
本当にお疲れ様である。彼女は働き者だ。
――――どもっすw通訳さんも午後の授業頑張ってくださいねー
中庭の方へ向かいながら、振りかえりざまに彼女は手を振ってそう言った。
その姿に、何故か昨日のバスでの同僚君が重なる。
確か、彼も別れ際に手を振っていたはずだ。
裏方さんはやがて中庭にあるA棟とB棟をつなぐトタン屋根の渡り廊下に至る。
そこをA棟側に折れて、校舎の中へ入っていった
◇
用務員さんが去った後もしばらくは、飼育小屋の前に佇んでいた。
裏方さんの言った『でも・・・』という言葉の後に来たモノを考察していたのだ。
あの時彼女は言い淀んで、結果的にその先をはぐらかした。
けど、心の読める私には彼女が何を思っていたのかが分かった。
彼女は、『でも・・・あの人、たまに泣きそうな顔に見える気がするんっすよねえ』と言っていたのだ。
とは言え、裏方さんも確信してそう考えた訳ではなかったようだし、思い違いの可能性が高いと見ていたのだろう。
はっきりと口に出さなかったのは彼女自身もあり得ないという思いが強かったからだ。
むしろ、私同様に気難しい彼を近寄りがたいと考えていたのだろう。
そこまで考えて私は飼育小屋の前から立ち去ることにした。
ポケットから携帯電話を出して開く。待ち受けに表示された時間は昼休み終了が10分後に迫った事を示していた。
時間的にも丁度良い頃合いのようだ。
「じゃあね、虎吉。」
「・・・グゥゥ」
小屋の中で寝そべる虎吉に声をかけて別れの挨拶とする。虎吉は僅かに片目を開けると、お腹が鳴る時のような声で短く返してきた。
今更ながら動物特有の鼻をさす蒸れたような薫りを意識しつつ、私はやってきた方向へと足を向けた。
昼休み終了まであと10分。授業開始まであと600秒。
普段どおりに歩いても、間に合わなくはないだろう。けど教科書やその他もろもろの準備を考えれば、急いで損はないはず。
私はほんの少しだけ足に力をこめて、歩く速度をあげることにした。
日に照らされて暖まった黒いアスファルト。そこからザリッザリッという摩擦音が発生し始める。
地面に対して、掛ける圧力を増やした分だけ音が大きくなっていく。比例して、足に感じる反発もその存在を訴えるようになった。
今まで意識していなかった音や感覚に取り巻かれて、私は先程通過したフェンスとA棟の狭間へと歩を進めていく。
歩きながらも私は思考の続きを考えていた。
泣きそうな顔、というのは面白い見方かもしれない。
確かに同僚君の眉間に皺を寄せる、あの表情は泣いている場合にも当てはまるものだ。
まあ、彼に限って、そんな事はないんだろうな、というのが私の率直な感想だったけど。
同僚君は間違いなく、何か不機嫌なモノに突き動かされてあんな表情をしているのに違いない。きっとそうだ。
足が動く。ジャリっと言う音が反復する。
やがて今現在の歩みのテンポに慣れて、地面からの反発が気にならなくなった頃、私はA棟の影の中へと踏み入っていた。
先程飼育小屋を離れた時からずっと、A棟とフェンスの狭間の道には、二つの人影が見えていた。
初めのうちは距離があり、その二人が誰であるかの判断は覚束なかったが、私自身の早歩きも手伝って、次第にはっきりと認識できるようになっていく。
人影は、同僚君と男さんであった。
丁度自分の頭の中で思考していたのと同じ人物の発見に、私はちょっとだけ目を丸くした。
けれどそれ以上の驚きはない。
別に男さんと同僚君が二人でいたとしても驚くような事ではないからだ。
二人は知り合いで、昔は友達だったという話だし、クラスでも男さんが一番同僚君に親しくしている感じだった。
人によっては、バレンタインデーと言う日にかこつけて、アブノーマルな想像をして一人悶えそうなものだけれど。
生憎私にそんな高尚な趣味はなかったし、なによりバレンタインデーに関連付けてモノを考えるという行為自体に辟易していた。
なので特に感傷は抱かなかった。
ただ『知り合いが二人いるな』なんて取り留めもない、思考とも言えない様な言葉を胸中で発するだけだ。
一応、通りすがりに挨拶くらいはしておくべきかもと考えながらも、それ以上の事には思い至ることはなかった。
普段と変わらず、ぼんやりと、無感動に、ふわふわと・・・
―――その後に受ける衝撃を私は、その時点ではまだ予想も予感もしていなかった。
―――けれど未だ私の中で影すら見えない『その時』は、確実に距離を縮めていたのだ。 私の歩みに倍乗する形で。回転する歯車が、動力源の加速に伴い軋り唸り始めるように ザリザリと、ジャリジャリと、摩擦音をたてながら――――――――――――――――