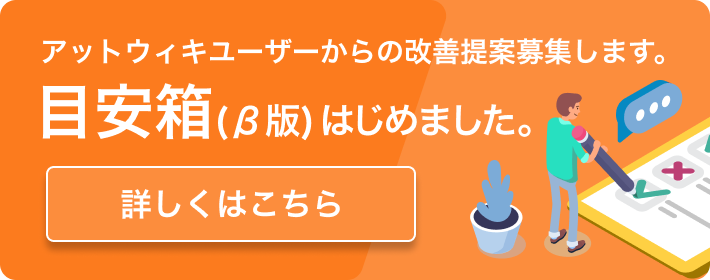◇ ◇ ◇
ほんの少しだけ、昔のことを話そうか。
俺と小学校からトモダチだった奴の話だ。
俺達がまだ中学校に通ってた頃の、つまらない、くだらない類のお話だよ。
「あのさ・・・思うんだけど、やっぱ・・・お前おかしいよ」
ガラス戸の外から強く、赫い光が差し込む夕暮れの保健室で、俺は重く静かに告げた。
赫の光が投げかけれられた部分とそれ以外。
保健室の明暗は斜陽によってはっきりと分たれている。
影になった箇所にいる俺達は、強い光の対比の為にお互いの表情さえも伺い知れない。
すぐ外側が中庭になっている、引き戸式のガラス戸の向こうでは、赤みを帯びた太陽が端っこを輝かせている。
アイツはそれを背にする形で、丸椅子に座って俺と向かい合っていた。
地中から浮かび上がってきた影みたいに黒い輪郭。その頬の部分には、僅かな出っ張りがうかがえる。
出っ張りは先ほど、急用で席を外した保険医の代わりに俺が処置したガーゼだった。
「―――――――」
「・・・・・・・・・・・・・」
俺の言葉にあいつは、小学生の頃からの友人は、何も答えない。
表情が伺えないから、こちらもどんな言葉を続ければいいか判断しかねていた。
結局、無言のまま俺は、保険医に指示された通りの作業を続けることにする。
本当の所を言えば、ただ無言が続くだけの状態になるのを恐れて、『作業をしているから、会話ができない』という口実を作る為に動いたんだった。
正義感が強いけど、無茶で聞かん坊なアイツを説得しようと作業を中断した俺の試みは、一分と持たなかったというわけだ。
ガラス戸側から廊下側の壁に移動して、丁度自分の目線と同じ高さにある棚を開く。
白い木製の扉を開くと中には、絆創膏の箱やピンセットなど応急処置用の道具がゴチャゴチャと置かれていた。
そこに俺は、先ほどまで使用していた消毒液やガーゼ、テープの類を元あった場所に返していく。
全て返し終え、棚を閉じたところで、保険医から指示された作業は完了した。
なんのことはない。
『指示された作業』っていうのは、喧嘩で軽いけがを負ったあいつに、『ガーゼを張ってやれ』というものだった。
赤く腫れた頬に消毒液を塗りガーゼをテープでとめてお終い、という単純作業は、ものの2分とかからなかった。
「それ・・・」
「ん?」
両開きの扉を閉める、『パタン』という軽い音に続いて発せられた声に、俺は後ろを向いた。
相変わらず逆光でどんな貌をしているか判らない状態で、アイツは続けてきた。
「それ・・・・・・さっき先生にも言われた。」
「それ・・・って、今の?」
「ああ、『お前はやりすぎだ。普通じゃない』とか『もうちょっと抑えろ』ってな」
「そ、そうか・・・」
「そうだよ」
「・・・・・・・・・・・・・」
「・・・・・・・・・・・・・」
なんて言ったら良いのかわからなかった。
もっと言うと、アイツが何を意図してそんな事を言っているのか、その見当が皆目つかなかった。
時間経過とともに、沈黙がヒタヒタと心に染み込んできて、気まずい想いを掻き立て始める。
目の前の友人は微動だにしなかった。
逆光で表情が読めないのも手伝って、心の内を推し量る為の材料は皆無に近い。
何故だか大海か、砂漠のど真ん中に取り残されたような。
目の前にアイツという人間がいるのにも関わらず、広漠とした場所に一人置き去りにされたような錯覚を覚えた。
結局、悩んだ末にとったのは、無言で愛想笑いをするという、お世辞にも上手いとは言い難い行動だった。
窓から差し込む赤に照らされた俺の反応は、アイツにはどう映ったんだろうか。
相変わらず表情の読めない状態だったから、高校に上がった今でもその瞬間アイツがどう思ったかは判らない。
ただ言えるのは、こうなった原因を作った事件が俺の友人を変えてしまったに違いない、ということくらいだろうか。
俺がアイツの事を解らなくなってしまったのは、確かこの後からだったから。
・
・
・
・
・
・
愚直なまでに正義感の強い奴だった。
小学校の初年度で同じクラスになって、いつの間にか親しくなって、そのうち一緒に遊ぶような仲になって。
そんなある日、いつも遊んでいる公園で、子犬が上級生にいじめられている場面に遭遇したことがあった。
それをアイツは体を張って止めさせたんだ。数人がかりでよってたかって子犬をなぶる上級生に、たった一人で立ち向かっていった。
ただ、オロオロと何もできない俺を尻目に、殴られ蹴られながらも、とうとう上級生を追い返してのけた。
まるで、年齢の差も人数の差も忘れ去ったかのような奮闘ぶりに俺は、『あんな風にできたら・・・』という憧れと、『何故あんな無茶を?』という不可解を同時に抱いていた。
『愚直』な程『正義感の強い』奴、という評価は、その時からのモノだったように思う。
実際アイツはそうだった。
誰か、いじめられてる奴がいれば率先していじめっ子の前に立ちはだかっていたし、道理に沿わないと感じれば大人でも臆せず対立していた。
周りの俺達はそんなアイツを頼もしく思う反面、俺達なら躊躇して踏み込まないようなところまで行ってしまう性格を、どこか理解できないでもいた。
・・・・普通なら先生に真っ向から逆らったりしない。普通はなかなかはっきりとイジメを悪いとは言えない。
・・・・だから、それができるアイツは普通ではない。
そんな認識が根底にあったのかもしれない。
仲のいい人間は別として、他のクラスメイト達は僅かに半歩、アイツから距離を置いていた。
ただ、それでもアイツのやっている事が『正しい事』なのは、誰も疑う余地がなかった。
寡黙なところもあったけど根はいい奴だったから、中学生に上がるくらいまでは割とクラスに馴染んでいたと思う。
おかしくなったのは、中学の頃からだ。
まず、変わり始めたのは周りの方だった。
反抗期と言うやつだろうか?
そのころからだんだんと、いわゆる『不良』って奴が目につくようになってきた。
他の小学校から上がってきた奴らもいれば、中学になってグレたようなのもいた。
そいつらが学校をサボって外で悪さをしていてくれれば、まだ俺達はうまくやっていられたのかも知れない。
けど、どうにも中途半端なのがこの時期の連中の特徴だった。
溢れ出す反抗心に任せてルールというルールに逆らってみたいけど、殊更に大人に目を付けられたくもない。
そんな心境からか、真っ向から何かに反発する奴はごく稀で、ほとんどは学校にとどまり自分より弱そうな奴を見つけることで、日常のストレスのはけ口としていた、。
授業中も、厳つく怖い先生や扱いが上手い先生なら静かにしているが、そうでなければ大抵は騒いだり教室を歩き回ったりする。
結局のところ、ドロップアウトする勇気さえなく、ただダラダラと欲求に任せて他人に迷惑をかけ続ける中途半端な人種。
そんな奴らが中学になって俺達の周りにポツリポツリと現れ始めた。
アイツは当然のように動いた。
初めはまだ何とかなっていたように思う。
素行不良を咎めたりイジメっ子の側に立って守ろうとするアイツに、連中は煙たそうにしながらも渋々と従っていた。
だけど中学時代ってのは、小学生時代のように生易しくはなかった。
思春期に入って体格も良くなり始める時期だ。
自分達の力に特に自信を持ちはじめた連中にとっては、ただ一人の孤軍にすぎないアイツは、『イジメてもいい人間』に他ならなかった。
すぐに連中の標的は、アイツに移っていった。
机の上に菊の花を置くとか、奴らの手の及ぶ範囲の人間に無視させるとか、靴を隠すとか。
月並みな、というよりむしろ、女の腐った奴らがやるような攻撃が始まった。
手は出さなかった。連中にそんな勇気や根性はなかったし、万一アイツが親や教師に告げた場合に暴力沙汰は面倒だと考えていたのかもしれない。
ともかく、連中はネチネチと執拗に、しかし自分達は傷つかないような方法でアイツをイビるようになっていった。
見方によっては情けない内容ばかりの攻撃だったけれど、それでも持続は効果を生み出し始めた。
次第に周りの人間がアイツを疎んじ始めたんだ。
少しずつ、はじめは連中に近しい奴らから。
次にアイツに親しくして危害が及ぶのを恐れる奴らも。
そのうち関係のないクラスメイトも空気に流されて、それに従って。
俺の小学生からの友人だった少年は、孤立してしまった。
最後のほうではほとんど全員が、『無視』の命令に従っていた。
かくいう俺も、教室ではまともに接することは難しくなっていった。
流れに逆らえば今度は自分が標的になるかもしれない、と言う恐怖に抗えるほど、俺は強くはなかった。
クラスの輪から外されてでも守るべき、確かなモノがあった訳でもなかった。
結局のところ―――――
クラス内の平和や他の友人達の方が、アイツ一人よりも重要だったんだ。
それでも、アイツは何も変わらなかった。
たった一人で、ずっと、身の回りの道理の通らないことに歯向かっていた。
授業中騒いだり校舎内でゴミを捨てるのを咎めたし、自分以外のイジメにも解決しようと努めていた。
俺は、自分の立場が危うくなるのが怖くて何もできないのが苦しかった。
苦しかったけど、心の何処かでは、こんな状況になっても頑なに自分の正義を守り続けるアイツが理解できないでいた。
苦しさと距離感。
それは、幼いころから常にアイツに対して抱き続けていたモノと何一つ変わらない二つの感情だった。
きっと周囲の人間も、どこか自分たちとは違う空気をアイツに感じていたからこそ、最終的に不良達の意向に従ったんだろう。
クラスから孤立させるという、馴れ合い傷を舐めあう連中の価値観において最大級の罰を下したはずなのに、最も疎んじている部分が変わらないことに連中は業を煮やしていた。
事件の引き金は連中のグループ内では、中心から少し外れた位置にいる、イジメが始まってから仲間に加わったような奴が引いた。
そいつは、もとからのメンバーとは纏う雰囲気にも微妙なズレがあった。
もともとのメンバーがいかにも不良然とした乱れた服装をしていたのに対し、そいつ自身は特に問題のない制服の着方をしていた。
教師に歯向かうのではなく積極的に取り入って、自分のワガママを通そうとする、ある意味不良よりも嫌悪感を抱かせるタイプだった。
運動部所属のそいつは腕力にも自信があったし、なにより、クラス全体がアイツと対立しているという状況が、ある種の正当性を与えていたのだろう。
『手を出す』という行動に至ったのは、自然なことだったのかもしれない。
・
・
・
・
・
・
「お前は悪くない・・・悪くないけどさ・・・・・・その・・・何ていうか固執しずぎなんだよ・・・」
「・・・・・・・・・」
「別にいいだろ?・・・連中が校則破っても・・・どこの誰とも知らない奴がさ、イジメられてても―――」
唐突に目の前の友人が顔をあげた。
それまで互いに顔を見合わせにくくて、時折視線を反らしながら話しているうちに、二人とも俯いた状態が常となってしまっていた。
アイツの、それを破るという行動で、自分が言葉の選択を間違えたことに気が付く。
「―――ああ、いや、俺もイジメは良くないと思うよ?うん。イジメ良くない、イジメカコワルイ」
慌てて前言を修正すると、目の前の友人は一瞬間まとっていた緊張感を消して、再び僅かに外れた方向へ視線を戻した。
「でもよ、でもさあ・・・皆に無視されてまでやることじゃないだろ?
終いにゃ喧嘩までして・・・・・・
お前がいくら正しくても、教員連中は『喧嘩両成敗』だったわけだし・・・」
「・・・・・・・・・ああ」
訥々とした俺の説得に、アイツは低い声で返す。
俺が自分で張り付けてやったガーゼに目が行った。
左の頬の半分を覆うほどの大きさのそれに、今更ながら痛々しさを覚える。
アイツが負った主な傷はそれだけで後はほとんど無傷に近かった。
けれど、服のところどころの破れや汚れが、先程までの取っ組み合いの生々しい光景を、頬のガーゼと一緒になって呼び起こしてくる。
・
・
・
・
・
・
運動部の奴が手を出すのが『自然なこと』なら、それにアイツが反撃したのは『当然のこと』だったのだろう。
そもそも、それまで腕力に訴えなかった事の方が、アイツを知る俺には不思議だった。
小学生のころからある意味で喧嘩っ早い性格をしていたはずなのに、今回はじっと耐えていた。
推測ではあるけど、手を出さなかったのはアイツ自身が暴力による攻撃を受けなかったからなのかも知れない。
もともと自分の中で確固としたルールを築いている奴だった。
きっと今回も『相手が手を出してこない以上は、こちらも手を出さない』なんて勝手に決めていたに違いない。
ただ、そんなルールはアイツの中だけでのことだ。
相手側にしてみれば威圧も暴言もない上に腕力にさえ訴えてこないのだから、標的としてはこの上ないはずだ。
手を出されたのも、単純にそうなるような条件が整ったから、というだけの話だったのだろう。
喧嘩は運動部のやつが、アイツにも分るようにして、通りすがりざまに机の脚を蹴ったことから始まった。
それに対してアイツは非難がましい目つきを返す。
それが勘に触ったのか、運動部のやつは、アイツの襟首に手をのばして――――――
久しぶりに見た。
いつも、喧嘩をするときは、突然に火がつくような奴だった。
例えるなら、赤く焼けていないからと言って、安心して触れた金属が、実はまだ百度近いの熱を孕んでいた時のような。
そういう驚きを相手に与えるような奴だった。
襟首をつかもうとする手を払いのけたアイツは、そのまま一発、運動部のやつに入れた。
不意を突いたということもあってか、拳はまるで吸い込まれるように、本当に綺麗に相手の顔にめり込んでいった。
運動部のやつが一発で悶絶してからは、乱闘だった。
状況を察した連中がすぐさまアイツを袋だたきにするべく集まって。
アイツはそれをたった一人で相手にしていた。
乱闘は、6時限目と帰りのHRの狭間の、眠気と人いきれで現実感を欠いた教室の空気を完全に払拭した。
突然に始まった異常事態に、半ば恐慌状態に陥りながら、なるべく教室の遠い位置に離れようとするクラスメイトの環視。
その前で、アイツはたった一人で三人を相手にしていた。
左に一発もらいながらも、それ以上のものをキッチリ相手側全員に返していたのだ。
結局喧嘩が終わったのは、先ほど教室を出て行ったばかりの六時限目の担当を含め、数人の先生がやってきてからだった。
教員がやってきたのに気づいたアイツが、手を引いた事で喧嘩が収まったのは、すでにその時にはアイツが優位に立っていたからこそだった。
その後は連中とアイツ、両方に担任や学年主任による聴取が続いた。
当事者でない俺たちは、教室内での喧嘩というショックから抜けきれないまま、ホームルームを迎えることとなった。
ホームルーム中は、ヒソヒソとした話し声が絶えなかったが、担任はあえてそれを見逃していた。
俺はというと、ホームルーム後にアイツの一番親しい人間として聴取の場に呼び出され、やはり同じ理由から、忙しい保健医に代わって比較的怪我の軽いアイツの応急処置を任されたというわけである。
・
・
・
・
・
・
「じゃあ、俺はこれで帰るけど、お前はどうすんの?一緒に帰る?」
帰ってきた保健医に診察されて、『怪我は全く問題なし』との診断を下されたアイツに、俺はそう問いかけた。
すでに外は暗くなり、保健室は(『電気つけなさい。目、悪くするわよ?』と言いながら)保険医がつけた電気の光に満ちている。
アイツはその下で、まだ丸椅子に腰を下ろしたままで膝に両手をついていた。
俺はその脇で、主のいない保健室のデスクに尻をのせる形でもたれかかり、腕を組んでいる。
「・・・・・・・・いや・・・俺はいいよ」
ややあって、答えが返ってくる。
廊下ではもうすぐ学校を閉めるから帰るように、と言った趣旨のアナウンスが響いている。
遠雷にも似た隔たりを感じさせる音が、保健室にも届いてくる。
そんな中でゆっくりと顔をあげてこちらを見たアイツは、軽く笑っていた。
どこか、困ったような、眉間にシワを寄せた表情で。
―――――それは、妙にツンとくる薬品の匂いが強い、ありきたりな保健室での、ありきたりな日常の会話だった。
◇ ◇ ◇
この一件以来、通訳に同僚と呼ばれている少年へのイジメは、収束していった。
そもそもイジメとは、原則的にイジめる側にリスクがないことが前提となる。
相手が完全に無抵抗であり、その行動も罪に問われない。行う側には一切の痛みや覚悟を伴わないからこそのイジメである。
故に、暴力により、はっきりと相手に、イジメ続ける事への危険性を感じさせた同僚は、最早その対象になり得なかった。
実際にはその後も相手側とは険悪な雰囲気が続いていたものの、その他の人間の態度は、およそイジメが始まる以前の状態へと戻っていた。
それまでクラスメイトが相手側グループの命令や、それによって出来上がった排斥や迫害の空気に従っていたのも、ひとえに自分たちが、『同僚のように』なることへの恐怖からだった。
けれどそこに『同僚に手を出した運動部のクラスメイトのように』なることへの恐怖が新たに生まれてしまった。
以前のように何の気兼ねも抵抗もなく『無視・迫害』の命令に従うのは難しくなっていき、それにつれてクラス全体の雰囲気も、同僚に対して軟化していったという訳である。
喧嘩によって抱いた同僚自身への恐れや、クラス全体の態度の変化によって、相手側の攻撃の程度は目に見えて緩やかになっていった。
せいぜいが仲間内で陰口を言うくらいの、それも同僚に対しては必ず委縮してしまうような中での。
一連の問題の発端となった、彼等の不良行為も同僚の前では行われなくなっていた。
それは誰がどう見ても、問題の解決にして終息であり、正常な日常の再開であった。
帰ってきた代わり映えのない日常の連続は、やがてクラスメイト達の心から、事件の存在を記憶の隅へと押しやっていった。
まったき正常な、事件以前と同様の毎日が続いていた。
同僚と、その親しい間柄の人間達を除いて、ではあったが。
◇
同僚の内心をうかがい知ることは出来ない。
『あの頃』から変わらない、気難しい表情が顔に張り付いているのが見えるだけだ。
それは呼び出されたことに対する不満の表出か、或いは常として変わることのない同僚本来の貌なのか。
男にはうかがい知ることは出来ない。
ただじっと、学ランの黒い袖を組んでこちらに対している同僚の、鋭い視線を受け止めるしかなかった。
右手には、そびえる様なA棟の壁。左手に植え込みとフェンス、その向こうに人通りの少ない道路をはさんで立ち並ぶ家々の玄関。
同僚を人目につかないこの場所に呼び出した明確な理由はなかった。
ただ、奇妙な胸のざわめきが男を知らず突き動かしていた。
ざわめきの正体に男が気づくことはない。
この説得によって、或いは二人の関係は修復不可能になってしまうかもしれない、という懸念を自らのうちに認めることも叶わなかった。
それほど、男の心を覆う、全身が萎え凍りついてしまうような恐怖は強かった。
大切な友人が、自分達から離れていってしまう、という恐怖は。
「―――――ッ…」
唾を飲み込むと、嚥下の音が男の予想していたよりも大きく響いた。
この日の気候は、去年の暮れからこっち、ほとんど毎日続いていた酷寒を忘れたかのような暖かさだった。
天気予報では三月下旬並みと言っていたが、冬の鋭角さが一切失われた、包み込んでくるような柔らかさの空気は、四月と言っても通じたかもしれない。
そんな暖かい日の、気温がもっとも上昇する昼下がりにも、彼らの立つA棟とフェンスの狭間の道には、影が落ちて真冬の空気が保たれていた。
開いた掌を握ろうとしたが、かじかんでうまく動かない。
その事実を認識したことで、体感温度が数度下がった。
体温の低下は、全身の気力を奪ってくる。そうでなくとも目の前にいる相手に関するときは、常に心に暗い影が落ちてしまうというのに。
男は、同僚を呼び出す際に前もってしっかり呼び出す場所を決めず、慌てて場当たり的に決めてしまった過去の自分を恨みつつ、口を開いた。
「―――なあ、やっぱ無理か?旅行・・・」
言葉に同僚が顔をあげる。
その背後のずっと向こう側には飼育小屋の影が。さらにその背景に、形のはっきりとした雲が青地に流れているのが見えた。
「ああ、この前いったろ?俺は行かないって」
「うん、けど・・・」
「別に良いだろ?俺がいなくても。他の友達と楽しんでくればいいじゃないか」
「ぅや、、、そ、そりゃそうだけどさ、それとこれとは別っていうか、なんつーか・・・・・・・・・お前にも来て欲しいんだよっ。俺は」
「・・・・・・・」
「・・・・・・・」
「悪い。いけない」
ごく短く、けれど、これ以上ないほどはっきりと明確に。
呼び出された同僚は、呼び出した男の誘いに答えを返した。
男の喉で再び唾液が嚥下される。
男たちの間で旅行の話が持ち上がったのは、年が明けてからだった。
休み明けに久々に顔を合わせた級友達と、冬休みの思い出談義に花を咲かせる中、誰からともなく旅行の話が挙がっていたのだ。
正月麻雀で、お年玉を従兄や友人からしこたまかっさらわれ、無一文のはずの男友が何故か率先して推した結果、旅行はなし崩し的に実行する運びとなっていった。
「やっぱあれなのか?中学の時のこと・・・まだ引きずって・・・る?」
「―――・・・・・・・・」
男が同僚を旅行に誘ったのは、それによってあわよくば、かつての関係に戻れないかと考えたからだった。
あの一件以来、同僚へのイジメは収束しクラスは元の状態へと戻って行った。
けれど、それは部外者からの視点であって、男や同僚にとっては全く元の鞘、というわけではなかった。
むしろ、決定的に何かが変わってしまった、というのが男の感想に他ならない。
「・・・・・・心配なんだ」
「・・・・・・・」
「・・・・・・お前さ、あの時からずっと俺らのこと、避けてるだろ・・・・・・」
「そうだな・・・」
「わかるだろ?
こんな・・・・・・訳のわからないまま切れるなんて嫌なんだよ。せめて理由は知りたい」
言いながら、男は自分の心がひきつっていくのを感じた。
外側の寒さと内側の寒さが合わさって、泣きたくなるような気分がゾワゾワと広がってくる。
もちろん、涙を押し殺す事は簡単だったし、視線はしっかりと目の前の友人に向けていた。
そうやって意識を集中しているはずなのに、なぜか耳には、校舎のざわめきや敷地の反対側の大通りを通る車の音が入り込んでくる。
それに反抗するような調子で、さらに注視の意識を高めると、目の前の友人の輪郭が次第に揺らいでいくような錯覚を覚えた。
先程からの受け答えの中で、微妙に表情を変化させながらも、眉間の皺だけはずっと消えない同僚が、着ている制服ごと空気に溶け去っていく幻視をしてしまう。
あの一件以来、同僚は男や他の人間と距離を取るようになっていた。
もともと寡黙な質であり、人が大勢いる中ではどうしても浮いてしまうな性格をしていたから、馴染みの薄い者には何も変わったようには見えなかっただろう。
確かに、誰からでも分かるような違いが同僚に生まれたわけではない。
クラスの人間と全く口を利かなくなるとか。学校に来なくなるとか。
そんな分かりやすい変化は無くて、あくまで以前と変わらず、それなりに学校生活に溶け込んでいた。
けれど男のように、同僚と多少なりとでも付き合いのあった人間は誰でも、少なからぬ違和感を覚えていた。
以前なら、遊びに誘えば大抵は付いてきたのが、なにかと理由をつけて断るようになったり。
学校でも、昼食の誘いや班決めの時は一緒になっていたメンバーから、ぽっかりと同僚の姿が消えていたりと。
つまりは誰かと一緒に行動するような事が、極めて少なくなっていったのだ。
それはまるで、自分からそうなるように仕向けているような――――少なくとも男にはそんな風に思えてならなかった。
そうやっているうちに、特に親しくなかった人間は同僚の事を気にかけなくなり忘れていった。
友人と言えるような者達もまた、にべもない同僚の事を持て余しかねてあまり話題にしなくなった。
その事に触れるのがタブーのような雰囲気が仲間内で生まれていたのだ。
そうして同僚はクラスの中で孤立していった。
以前の、クラス全体がイジメの一環としてやっていたモノとは全く別種の、表面上ではうまく付き合っているようでいて、その実、特定の人間との親密な付き合いが全くなくなってしまったタイプの『孤立』だった。
それは彼等の卒業まで続き、高校に上がった今尚、同じ形で同僚は孤立し続けていた。
男にはそれがずっと気がかりだった。
イジメから喧嘩、その一連の事件によって、同僚の中で何かが変わってしまった事は彼にも分かった。
けど、何故、誰もかれも避けようとするのか、男には理解できなかった。
もう事件は解決したはずなのに。
同僚が気にかけるような事はほとんどなくなったし、イジメが行われていた最中だって、学校の外では昔と変わらず親しくしていたはずだったのに。
なのに同僚は、男を含めた周囲の人間を避けるようになっていった。
間に見えない壁が出来て、さらにそれを同僚自身が常に修理・補強しているかのようだった。
時間と比例して、その気難しい友人の周囲から人が消えていく事態に、男は心を痛めていた。
最終的に孤立しても、男だけは何とか傍にいようとしていた。
けれどそんな努力に心を動かされることもなく、今もなお男が近づけば同僚は出来る限り離れようとしている。
それでも男が諦めないのは、古くからの友人としての繋がりだけでなく、ある種の罪悪感も働いての事だった。
結局、自分もまた友人のような顔をしていながら、イジメに加担していたのだ。
攻撃的な行動に移ってはいなくとも、あの状況下ではっきりとクラス全体に異を唱えなかったのは、イジメを容認していた事に他ならない。
本当に友人だと思っていたなら、例え自分もイジメられる側に周っても同僚の味方に付かなければならなかった。
それをしないで同僚自身が自分の身一つで立ち向かうまで、ずっと放置していた。
たった一人で数人を相手にする友人の姿によって、それがとても『かっこ悪い』事だったのだと男は気づいた。いや、気づかされた。
だから、なぜ同僚が誰も彼も拒絶してしまうのかの明確な答えはなくとも、自分には同僚を友人の輪の中に戻す義務があると感じていた。
それが何一つしなかった自分の、罪滅ぼしだと考えてこれまでずっと、どれだけ無碍に拒絶されても友人として接しようとしていたのだ。
未だ同僚ははっきりと人間を拒絶し続けている。
これまでの男の行動も虚しく、ずっと独りのままだった。
――――――きっとこのままでは、帰ってこれなくなってしまう。
そんな男の悲痛な思いも通じないのか、これまでも度々話をして、変わってしまった原因を突き止めようとしても効果はあがらなかった。
どうしても、核心に触れようとすると『別に・・・お前には関係ないだろ。』と言って話をはぐらかすか、立ち去ってしまう。
男も男で、イジメを止めなかったという負い目があるため、それ以上無理に引き止めて追及することもできない。
そんな風にしてズルズルと流れ、時は年単位を数えるようになってしまった。
疲れていた。
男は少しずつであったが、疲れはじめていた。
心を読めない以上、同僚が男や親しかった人間まで拒絶する本当の理由は分からない。
イジメに加担はしてはいなくても、止めようとしなかったのを憎んでいるのか。これはその制裁のつもりなのか。
あまり考えないようにしていたはずの、そんな推測が、最近では特に心に浮かぶようになっていた。
そんな中である日、同僚が人を拒絶するようになって、自分が同僚を何とかしようと考えて、もう何年も経っていることに気づいてしまった。
同時に邪まな推測ばかりが頭に浮かんでしまうのは、自分が疲れているからだとも悟ってしまった。
だから、ここで終わらせたかった。
今までは罪悪感から、なかなか踏み込んだところまで聞けなかった。
けれどここで終わらせるためにも、同僚を旅行に誘い、その先ではっきりと相手を逃がさず自分も逃げずに、真っ向から話し合ってみようと考えていた。
旅行先と言う普段とは違う場所でなら、もしかしたら―――本当にあらゆる意味でもしかしたら何とかなるかもしれないと思っていた。
今回、旅行の話があがった時、男の頭をかすめ、計画が具体的になっていくのに合わせて、はっきりとした物になっていった考えがそれだった。
だから何としてでも男は、同僚を、旅行に連れ出すつもりだった。
多分、いずれ自分も周囲の人間と同様に、同僚から興味を失くして離れて行ってしまうに違いない。
最近の疲れからくる邪推がその証拠だ。
その前になんとしてでも・・・・・・
小学生の頃から、ずっと付き合っていた友人を失くしてしまう。それも、自分から失くしてしまう。
それは、泣きたくなるほどに寂しい、指先が凍えて動かなくなり、手足や体の芯まで凍りついてしまいそうなほどの恐怖だった。
小さい頃から自分の生活の一部にあった人間が離れて、やがて忘れてしまう。それはもしかしたら死ぬよりも怖い事なのかも知れない。
だから、男は、今回の計画は絶対にやり遂げるつもりだった。同僚の心を氷解させるつもりだった。
―――――なのに
―――――その『友人』は
「今日はやけに絡むな。」
『せめて理由はしりたい』という男の言葉に、しばらくの間沈黙した同僚は、やがて視線を外してそう返す。
返事は、先ほどから少しずつ重苦しさを増していた空気を払拭するような、微妙な軽さを含んでいた。
以前からの経験で、男にはそれが何を意味するかが分かっていた。
こうやって軽い感じに持っていき『今日は用事があるから』なんて言って、話をうやむやにしてしまう。それがいつものパターンだった。
呼び出したのが昼休みも終りに近い頃という事もあって、今回は『授業が近い』なんて話を口実に切り抜けようとするに違いない。
そうはさせじと決意をはらんで、男は少し低い声を出す。指や手足は冷えているのに、顔は火照っている奇妙な感覚の中で。
「ああ。今回の旅行は何が何でも来てもらう。それで、話してもらいたい。なんで俺達のこと、避けるのか」
「皆がいる前でか?」
「あ、いや・・・まあ、俺と二人で、どっか人目に付かない所で。」
「気恥しいね」
「そんなことあるかよ。とにかく今回は来てもらうからな」
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・嫌だと言ったら?」
「嫌でもだよ」
「本気なんだな。」
「ああ。本気だ。」
「俺が・・・・・・・お前にどんな態度で当たってるか、解ってんだろ?
クラスの中でどんな風に思われてるのかも。それでも誘うのかよ?」
「ああ。お前がどんなんだろうと、俺には関係ない。
俺はお前と・・・・・・また昔みたいに一緒に遊んだり、どっか行ったりしたい。
その為なら、今、お前にどんな風に思われたって構わない。」
男の様子が普段と違う事に、同僚も気づいたようであった。
話が続く中で、口調から軽さは静かに消えていき、再び重さを取り戻していく。
男の決意は、功を奏したと言ってもいいだろう。
相手の視線もそっぽを向いていたのが――具体的にはフェンスの方に顔を向けて、後ろを見るような感じ――だんだんとこちらを見据える形になっていく。
ついにはお互いの視線は、はっきりと交錯していた。
小型のトラックがフェンスの向こうの道を、エンジンを唸らせて通り過ぎていった。
それによるエンジン音と巻き起こった風で、二人の耳は暫しの騒音に閉ざされ、会話も一瞬止まる。
「俺は・・・・・・・―――――――難しいな。やっぱり・・・・・・・
昔みたいに、なんて難しい。無理だよ。
旅行はお前達だけ行ってこいよ。やっぱ俺はいい。」
ややあって、同僚は少し苦しそうな声で言った。
眉間に皺をよせた表情は相変わらずだったけど、それはどこか困ったような表情にも見える。
けれど同僚の相も変らぬ答えに、気を落としながらも譲るつもりのない男には、その裏にある物はわからなかった。
その後の、触れてはいけない琴線をわきまえない彼の言葉は、ある意味で決定的だった。
「なあ・・・・・・お前の気持ちもわかるよ。わかるけどさ・・・・・・お前のためにも良くないだろ?このまま一人でいいのかよ?」
「 ッ
お前に、俺の何が分かるって言うんだ?」
いつも、突然に火のつくような奴だった。
それを解っていた筈の男だったけど、避けることはできなかった。
目の前の相手は、先程まで見せていた男の決意に対する理解と歩み寄りを、明らかに失っていた。
怒りを顕わにしている、という訳ではなかったが、その口調にはいつも以上の人を拒絶する冷たさが含まれている。
『自分の何がわかるんだ』なんて月並みな子供っぽい表現も、刺すような視線と重苦しい口調で言われると、笑い飛ばすことができない。
男は自分が何かへまをやらかしたことに気づき、『ウッ』ともらす。体中の凍えが一斉にざわめきだしたのを知覚する。
何か良くない事が起こるのを、半ば本能で理解してしまった。
「ゃ、だからさ・・・・・・」
「お前さ、『俺のため』とか言ってるけど、結局お前が連れてきたいだけだろ?俺はいいって言ってんのに。無理矢理連れてって。」
「う・・・・」
「白けんのわかってるだろ?皆に迷惑かけてまでやりたい事なのかよ?」
「あ、あたり前だろっ、、、、そ、、、そんなの決まっ」
「だいたい今やってるのってよ、お前が単に傷つきたくないから俺の事に構ってんだろ?
どうせ『自分がイジメを止めなかったせいでこうなった』とか思って、元に戻そうとしてんだろ。
別にお前の所為じゃねーし。俺は独りになりたくてなってんだよ。」
触れてはいけない場所をわきまえていなかったのは、同僚も同じことであった。
彼が口にした事は正鵠を得ていた。
得てはいたが、ズバリ男の心中を言い当ててしまったのは、この対話においては効果的、どころか逆効果以外の何者でもない。
男の心にまだ僅かに残っていた『余裕』は、この言葉で波に砂がさらわれるがごとく無力なさまで消え去っていった。
「そ、そうだよ!だからどうしたって言うんだよ!!
お前・・・・・・このままだと・・・・・・本当に独りぼっちになるんだぞ!!?」
「いいよ・・・」
「―――――――え?」
「もういいよ。俺の事はさ。気にしなくていい。ほっといていいよ。だから、もう、気にしなくて、いい」
「なに言っ」
「俺は、独りでいいから」
「なんだよ・・・・・それ・・・・」
今までの二人の激しい会話が嘘のように、校舎内のざわめきにかき消されそうなほど、ボソリと放たれた言葉は、男の全身を震わせた。
最後通牒という言葉がある。
仮に当てはめるとすれば、この場が最もふさわしいに違いない。
男にはそう思えた。
何故って――――――
「そうかよ・・・・・・」
この会話は、もう――――同僚と自分の間に交わされる最後の物なんだから。
「じゃあ、いいよ。俺も・・・・・もう、なにもしない」
―――――――泣いているみたいな声で恥ずかしいな。
そんな、どうでも良い思考が何故か湧いてくる。
はっきりと自分も拒絶してみると、意外にも頭が冴えていくような気がした。
まるで、ここで起こっていることが、フィルムの向こう側の世界の様に、現実感を欠いた視線が急速に強まっていく。
ここにいる自分と言葉をしゃべる自分が別々の存在になっていく様な。
そんな感覚が、何故か気に入らなくて、最後に男は怒鳴ることにした。
こんな事になってしまったのも、結局のところ、同僚のせいなのだ。最後に、こうやって怒鳴ることぐらい許されるはずだ。
「このっ――――――――――大馬鹿野郎がっっ!!」
「ああ・・・・」
怒声に同僚は静かに応えた。
その表情は、うかがい知れない。
男は大声を出したことを少し後悔していた。
確かに、大きな声を出すのは自分の本意だったけど、
『予期せず第三者に聞かれる』のは、やっぱり恥しいものだったから。
むしろ、この現場をみられてしまった後悔の方が怒鳴ったことよりも気まずかった。
こんなに人気のないところだからこそ、ここまで込み入った話ができたというのに。
◇
同僚は、怪訝に思った。
さっきまでブルブルと震えながら真剣な表情をしていたはずの男が、今は何故かハトが豆鉄砲を食らったような、奇妙な驚きを顔に浮かべている。
ややあって、彼は自らの背後に誰かが現れたのだという事に思い到った。
振り返った同僚は、ほんの少し眉をひそめる。
「通訳・・・・・」
長髪で、どこか人形めいた顔だちをした彼等の知り合いは、今しがたの男の怒声に明らかに動揺しているように見えた。
普段はどこか無機質さを漂わせているその瞳も、今は予期せぬ修羅場に、若干の熱を帯びていた。