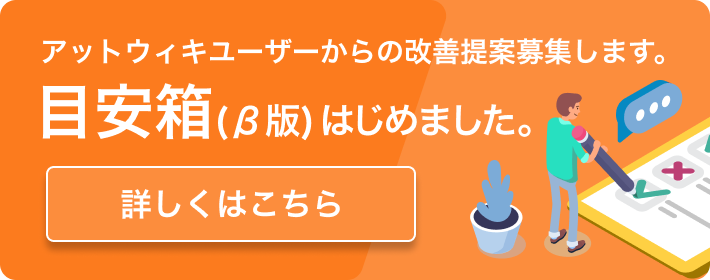昼食として購入した、オシャレな名前のサンドイッチ。私は、その最後の一欠片を口に放り込み咀嚼した。
チーズのまろやかさとトマトの酸味が絡みあった旨みが、口中を満たす。その感覚を充分に楽しんだ末に、それらを嚥下する。
ザラメを加えたラテを少し口に含んで食事の終わりとして、改めて周囲の光景に目をやった。
アメリカの某都市から始まり、世界中に展開しているというそのコーヒーチェーン店には、私と同じくらいの年頃の少年少女が多く見受けられた。
港湾都市発の喫茶店と言う事で、デザイン性の高いもやい綱や羅針盤が描かれた店内の装飾は、茶系の落ち着いた配色となっている。
そこに時折見受けられる、緑のロゴや橙色のほやをかぶせたランプなんかが、丁度良いアクセントとなっていた。
カウンターの向こう側では店員が忙しく動き回り、休日の煩雑な状況をさばいている。
たまにカウンター内部の、ミルクを泡立てる機械から上がるスチームのような音が、店内のざわめきを圧して響いてきた。
某ファーストフード店と同様に『俗悪な資本主義の象徴』なんて批判を時に耳にするこの喫茶店の内部は、コーヒーショップと言う割にクリームの甘い香りの方が強い。
私はそれなりに甘い物も好きなので悪いとは思わないけれど、苦手な人ならば本当に閉口してしまうかもしれない、そんな感じの香りだ。
新ジャンル学園の最寄駅。
その駅前から放射状に広がるメインストリートのうち、特に飲食店やデパートなどが多く並んでいる通り。
休日の昼間には、遊びにきた若者や家族連れが他の通りからやってきて昼食を取るために、ことさらに賑わっている。
そんな通りの一角。両隣りをファミリーレストランとファーストフード店に挟まれている、道路に面したコーヒーショップ。そこに私はいた。
往来を映すガラス張りの傍に席をとり、この場所を指定した相手を待っている。
うつ向けた視線の先では、ガラスの向こう側から差し込む、弱い冬の陽光が机の上にかかっていた。
そこに手をかざして太陽の存在を感じとりながら、忙しく人や車が行き来する往来に目をやる。
手前の歩道には、ひしめくというには些か数が足りないけれど、絶え間ない人の流れがガラス一枚挟んだすぐそこにあった。
その向こう側の車道の方は、今度こそ文字通り車がひしめき合っていて、隙間らしい隙間が見当たらない。
ガラスの端に見える信号は、青になっている筈なのに、まるで全車両がエンジンを切って駐車しているかのようだった。高校生の私でさえも道路行政の不備を疑う程の混雑だ。
さらに車道を挟んで反対側の歩道は、こちらと同様に多くの人が行きかっている。
つまり、休日と言う事で駅前全体が人口過密地になっているのだ。
視界は、歩道に面して並ぶ雑多な飲食店の看板と店舗の入口で終わりを迎える。その先は建造物で遮られていたが、ガラスの上部と店の天井の合間にほんの少しだけ空が見えた。
ガラスに写る僅かな青は、ここ最近と変わる事のない快晴の様相を呈している。休日にはうってつけの空だ。
私はぼんやりと何を思うでもなくそれらの景色を見つめ、やがて視線を机の上に戻す。
十数年間付き合っている自分の細い指が、太陽の光を白く反射していた。
なんで自分がこんな所にいるのか?
じっと手の白さを見つめているうちに、ふっと、脈絡も前触れもなく自分の中の現実感が消え去った。
同時に今まで確かに頭の中にあったはずの、私がここにいる理由が思い出せなくなってしまう。
呆けたような感覚のなか、自分がここにいるのが許されないことのように思えてきて、変に不安な気持ちがわき上がってきた。
まるで間違えて違うクラスに入ってしまい、そのままそこで授業を受けているような。自分がその場に受け入れられていないのに勝手に居座っているような。
子供が親に怒られるのではないかとビクついているのにも似た感覚はけれど、ここで同僚君と待ち合わせる事になった経緯が、脳裏に帰還してくれた事で終わりを迎えた。
◇
『あの・・・・・お話が―――あります。』
数日前、飼育小屋で私は、決意をはらんで声でそう告げた。
小屋の端の方ではトラ吉が小さく喉を鳴らしていたが、それに対して僅かな意識を割くこともせず、彼だけを見つめる。
『・・・・・・なんだよ・・・話って?』
同僚君の方もこちらの真剣なまなざしに気づいたようで、少し緊張した面持ちで返してきた。
ここで彼を説得しなければいけない。
私の心臓は、いよいよ迎えたその時に、料理の達人が千切りをするような速度のリズムを刻んでいた。
男さんと喧嘩別れをしてしまった同僚君。誰とも心を閉ざして、ついに友人だった男さんまでもいなくなってしまった。
親しい人間がいない彼を、男さんと仲直りするように説得できるのは、同じ飼育委員であると同時に二人が決別する場面を目撃してしまった私をおいて他にはいない。
同僚君の心は閉ざされて、心の読める私にもほとんど表面だけしか読み取れないけど、それでも普通の人と比べれば若干条件は優しい筈だ。
問題は、私が、誰かを仲直りさせるために説得する、なんていう重大事に真正面から真剣に向き合った経験が、皆無であるという事。
失敗は怖いけれど、それでも・・・・・・男さんとの関係を、半分は自分の意思で終えた彼の心には、私が抱いているのと同じ寂しさがあった。
わかりあえる人間がいない、孤独な感覚。
それに気付いていながら、そして二人の修羅場を目撃していながら、見なかったふりをして当たり前の日常を送るなんて事は、できなかった。
だから、ここで、失敗する、かもしれないけど、――――彼を説得しないといけない。そう思っていた。
そして彼の胸元に目をやり、ゆっくりと口を開き・・・
『その・・・わかっ』
ガチャリ、と音がした。
『失礼するっす~』
『ってるとは思いますが―――は、あ、・・・裏方さん?』
『どもっす。お二人さんっ。
お取り込み中のところちょっといいっすか?
あ、そんな心配そうな顔しなくてもダイジョブっすwすぐ済むっすよ?』
言葉の途中に割り込んできたドアの開く音。
ある意味絶妙のタイミングで割り込んできたのは、裏方雑用さんだった。
当然の如く私達は、ドキリとした表情でお互いに向けていた視線をそらし、今まで纏っていた真剣な雰囲気を隠そうとした。
幸いと言うべきなのか、日中一杯の仕事で疲れた顔をした彼女は、そんな二人の緊張感などまるで気付かない様子である。
私と同僚君に挨拶をしながらその間を、ヒョコヒョコとした足取りでトラ虎吉の側へ寄っていき話しかけていた。
『トラ吉、急に検査することになったっす。明日一緒にお医者さんの所に行くっすよ?』
『ガ、ガウ!?∑(゜Д゜;)』
『ああ、いや、別にどこも悪いところはないっすよ?
けど市の条例で決まってたんっすよw
【修学旅行で船が遭難した後、流れ着いた無人島から連れてきた虎は市の定めた検査を所定の日までに受けないといけない】
ってwwなんっすかそれwwwwwwどこのトラ吉専門条例wwwwwwwwっうぇwww・・・あ、『っうぇ』とか言っちまったっす。お恥ずかしい。
ま、とにかく今週が期限の最後の日なんっす。うっかり忘れてたっすよ。
こんなこと言ってもトラ吉にはわからんとは思うっすけど・・・・・』
『が、ガウガウ!グガっ!』
『だから悪い所はないっすよ。なんでそんな慌ててるんっすか?』
『ぐう・・・きゅうぅぅ~~~』
『通訳さんの方見てどうしたんっすか?言っとくけど通訳さんに頼んでも検査は無くならないっすよ?』
『ガフン』
『むっ。なんっすか?その態度?あれっすよ?肉食さんとか誤解殺気さんとか呼んじゃうっすよ?ピクル的な意味で』
『ガウっ!?』
不貞腐れた風に腕を組み(腕は・・・虎でも組めるんですね・・・)そっぽを向くトラ吉と、その態度にカチンときて脅かそうと、彼の嫌がる人物の名を挙げる用務員さん。
そんな光景に私は、『彼は「せっかく二人が話し合うところだったのに余計な所で邪魔しないでほしい」と言っております』とよほど通訳してしまおうかと悩んだ。
悩んだが『二人が話し合う』という語に、裏方さんが反応しても困るので、結局通訳は止めにした。
ここで裏方さんを巻き込んでもややこしい事になるだけだという考えが働いたのだ。
私の視線の先では、すっかり機嫌を損ねてしまったトラ吉が、全身を脱力させたようにしてほし草に横たわっている。
用務員さんはそれをなだめすかし、検査のためと思しきタグを前足にはめようとしている。
それはいつもと変わらない、穏やかな日常の光景に思えた。
今ここで同僚君を説得しようとすれば、きっとそんな穏やかな雰囲気は壊れてしまう事だろう。
そうすることでトラ吉や裏方さんに気を遣わせたりするのは、何か違う、と思った。
部外者にいたずらに首を突っ込まれたくないという思いはつまり、私たちが感じる重荷を他人に背負わせたくない、という気持ちから来ていたのだ。
『よう』
トラ吉達に目をやりながらそんな事を考える私に、傍らから声がかかる。
同僚君が、腕を組んでこちらを見ていた。
『ここじゃなんだしさ――――』
その言葉は、彼が私と同じことを考えていた事を示していた。
◇
そして私はここにいる。
場所をどうするかという話の中で、どちらからともなく、休日である今日、この喫茶店で、という話になったのだ。
実際私と同僚君は飼育当番以外では殆ど接点がない。そのため、放課後の小屋掃除の機会を逃してしまえば次のチャンスまで、まるまる一週間待たなければいけない。
さらに用務員さんの突然の乱入が物語るとおり、学校ならばどこであれ、知り合いに目撃される危険があるのだ。
だとすればここは一旦引いて、後日確実に日時と場所を決めた上で、知人を巻き込む心配のない所で話をする方がベターであるように感じられた。
多分、同僚君もそういう意味でここを指定したのだろう。
私は特に疑問を持たずにこの決定に従い、昼食も兼ねて少し早めにこの店にやってきたのだ。
が、すぐにミスを犯した事に気がついた。
別に大きな問題ではないし、ミスと言えるかどうかもわからないつまらない問題なのだけれど。
それでも予想外の事態が、彼を待つ私の周囲で起こっている事だけは疑いようもなかった。
この休日が、いかなる意味を持っているかに思い至る事ができなかった私の、ミスと言えばミスである。
「ごめん。待たせちゃった・・・かな?」
「いや、俺もさっき着いたばっかだか―――ぐああっ!」
「ど、どうしたの?大丈夫!?」
「ち、近づくな!!腕が・・・ぐっ・・・我が投影されし幻想が共鳴しているっ!
『奴』が、、、『奴』が近づいている・・・っっ!」
「ど、どうすればいいの?」
「俺に構うな!死にたいのか!?じき、辺り一体消し飛・・・・・・ぐうぅっ・・・・」
「そんな事言われたらますます放っておけないよっ!私達、もう
・・・・・・その・・・・・・・・――――――恋人なんだから・・・・」
「!!
―――・・・・・・・・・・・・(///)」
「(//////)」
少し離れた席で見知らぬ男女が、そんなやりとりを繰り広げていた。
待ち合わせをしていたらしい二人である。
先に来ていた男の人の方が突然立ち上がったかと思うと腕を押え、それを女の人の方が真剣な表情で構っていた。
正確を期した言い方をすれば、二人とも男女と言うよりかは少年少女と言った方が適当な年格好である。
今は多少落ち着いたのか、先程までのような大げさなアクションはせずに、お互いちゃんと席に着いている。
彼等の会話に耳をそばだてると、『エターナルフォースブリザード』とか『直死の覚醒』とか『カノッサ機関』なんて断片的な単語が、店内の雑多な音の中から拾いだせた。
どうやらさっきのやりとりは単に落ち着いたというだけで、まだまだ継続中のようである。
男の子は女の子に対して、敵がどうだの真の力が目覚めるだの、漫画のような荒唐無稽な話題を真顔で語っている。どうも妄想癖があるらしい。
ただ、そんな二人の様子は、男の子が変に芝居がかった仕草である事を除いても、妙にぎこちなく場慣れしていない感じがした。
男の子のただならぬ雰囲気に驚いて、そちらに目をやっていた他のお客さん達も、今は興味を失くした風に元の方向を向いている。
私はそれに倣いながらも、芳ばしいコーヒーと甘ったるいクリームの香り。それからガラスから射しこむ陽光に包まれつつ、思う。
嗚呼、初々しい。と
ラテに口をつけて改めて周りを見回してみた。
コーヒーショップの端から端まで目をやり終えた時には、眉間にはしわが寄っていた。
同僚君みたいな顔になっているのは、物珍しさにお砂糖ではなくザラメを入れたは良いけれど、何時までも溶けてくれずラテが苦いままだったからではない。
例えばコーヒーを受け渡すカウンター。ホオズキみたいな色をしたランプの装飾の下で、注文した飲み物を待つ少年と少女。
例えば奥の方の席。ガラス側の席の様に明るくはないけれど、長時間座るには丁度いいであろう、居心地の良さそうなソファに腰を下す少年と少女。
例えば入口付近の支払のカウンターでメニューを選ぶ少年と少女。
それから私の目の前の席で光に照らされて幸せそうに談笑する少年少女。
それから背後の席で偶然手と手が触れると同時に、顔が真っ赤に染まった少年少女。
目を交わす少年少女。手を握りあう少年少女。冗談を言い合う少年少女。
つまり仲睦まじい『少年と少女』。
――――――説得はまだ始まってもいないと言うのに、私は早くも帰りたくなっていた。
店内は2月14日に晴れて結ばれた、できたてほやほやの彼氏と彼女であふれかえっていたのだ。
これにはちょっと閉口せざるを得なかった。
今週初めのバレンタインデーに想い人に告白し、それが成った幸福な二人。
日にちを決めてその日まで準備を重ね、遂にその日に計画を実行する。
迫りくる14日のプレッシャーを常に感じる日々をくぐり抜け、ようやく辿りつき告白が成功した人々だ。喜びも一潮なのだろう。
そして、そんな恋人たちが休日に何もしない訳がないのだ。
恐らくこのコーヒーショップは、彼等のデートコースの中で昼食か休憩場所として組み込まれているに違いない。
しかもなんという事だろう。全員初めてなのだ。
ここにいるのは、今回のバレンタインで初めて彼氏彼女ができたという、私と同じ高校生くらいの少年少女ばかりである。
心を読むまでもなく、立ち居振る舞いや反応を見ればわかる。
『イチャイチャしている』のとは違う、どこか適切な距離を計りかねている、ぎこちないやりとり。
けれど赤の他人が傍から見ても、それと分かるほどの幸せなオーラがこれでもかと言う程に発散されているのだ。。
これが一組二組ならば、まだ青春らしくてほほえましいと笑っていられるが、店中に溢れ返っている状況では笑うどころではない。
他のお客さんが男女のカップルであるのに対して、私は一人なのだ。
どうあっても浮いてしまいがちになる。それも見た感じ同じのくらいの年頃であるから、異質性はさらに際立ってしまう。
周囲のカップルはほとんどが自分たちの世界に浸りきって、私と言う異常を認識していないのが唯一の救いと言えば救いだった。
とは言えそれで、私自身が感じる所在ない気分が晴れてくれるわけでもない。
さらに悪い事には『同僚君と話し合う』という事で構えすぎてしまった私は、待ちあわせの一時間も前に来店してしまっていたのだ。
心の準備をする、といった名目で早めに来たのが裏目に出てしまった。
かれこれ一時間近く。
喫茶店そのものが拒絶しているかのような居心地の悪さを感じては、それから逃れるため別のなにかに意識を集中し、集中がきれては居心地の悪さを感じるという繰り返しを味わっていた。
しかもそんな繰り返しの何度目かに気づいたことがあった。
―――これはもしかして、溶け込んでしまうのではないだろうか?
と、いうよりも、誰からも一人きりである私が異質なものとして認識されていないのは、つまり皆それを想定しているからではないのだろうか?
そう。同僚君がやってきたら、私達は周りと同じ『バレンタインに結ばれたカップル』だと認識されてしまうのではないか?
そんな懸念が昼食をとりつつ待ち続ける中、緊張して落ち着かない心に新らしく加わっていた。
当事者である私達にそのつもりが毛頭なくとも、初々しい男女のカップルばかりが目につく中では、どう見てもカップル以外には思われないかもしれない。
しかも私達はぎこちない。私は心の読めない同僚君の事が怖いし、同僚君もそんな私の様子が気に入らないようだ。
なので二人の会話は常にぎこちない。それはこの店の、結ばれたばかりで場慣れしていない客層の雰囲気と、実によく似かよっていた。
これでは溶け込んでしまう。
同僚君がやってくると同時に、私達はそういう事にされてしまう。
このコーヒーショップのに充満する甘酸っぱい空気の発生元でありながら、同時にそれにあてられている人々によって、『初々しいカップル』にされてしまう。
それは、なんというか―――――困る。
明確な理由はないのだけど、なんだか困る気がする。
私と同僚君はそんな関係ではないのだから、そんな目で見られるのは心外だし、それに。
それに・・・これから話し合おうとしているのは、幸せな男女関係からは程遠い、同僚君の内面に踏み込んでいく話題なのだ。
この店の浮ついた空気を受け入れていては、決して解決できない問題だ。
私はあくまで他人の目を無視して、説得に集中しないといけない。
周りの人間がカップルばかりだからと言って・・・
一人でいる自分はこの場に相応しくない気がするからと言って・・・
同僚君が来れば、もしかしたら居心地の悪さは解消されるかもしれないからと言って・・・
今の、この、張りつめて、気分が悪くなるほどに緊張した感覚を放棄することは許されない。
そうでなければ彼の心を動かして、男さんと仲直りさせるなんて事はできないのだから。
「ほいよー、とりあえず抹茶ラテにしといたぜ?これなら抵抗なく飲めるんじゃないか?」
「は!お、おお、おこっ、多分なお心遣い感謝するでありましゅ――ありますっ!!」
「いいっていいってwこっちこそ悪いな。無理言ってこんな所、連れてきちゃって」
「そ、そそそそ、そのようなああああ、、、そのようなっ、そのような事はっっ!!!
じ、自分は今こうやって二人でいるだけで天にも昇る気分でありっ!場所がどこかなど、などは些末な問題なのでありますっっ!!」
「ははは・・・それもそうだなw
でもさ、思いもよらなかったなあ。初めて会った時は、こんな関係になるなんて。」
「あああああああ、、、そ、それ、、っそそそ、そんな、、、じじじじじじじじ自分、自分も、、、自分の方がびっくりしてるでででででででありありありますっ!」
またもや、どこかの席から幸せそうな会話が聞こえてきた。女の子のやけに狼狽した喋り方が印象的である。
私は、ほんの少し眉を動かした。
なんだか、自分の思考に違和感を覚えたのだ。
良く分からないけど・・・・・・・・
今さっきまで私は、このお店の少年少女達と同じ気持ちになることを危惧していた。
そう言った浮ついた気持ちをしていては、同僚君を説得できない、と。
でも、よくよく考えると、どうして私は、浮ついた多幸感を抱くことを心配していたのだろう?
現在コーヒーショップに流れるこの空気は、異性として付き合っている少年少女がお客さんの大半を占めているが故である。
だからそれに同調するというのは、どこかで異性を意識した人間でなければ有り得ない。
一人である私が、この場の雰囲気を受け入れ緊張を解いてしまう、なんていう危惧はおかしいと思う。
誰か、心のどこかに異性がいないと、そうはならないのに・・・・・・
私は自分が感じるはずもない幸せを心配している・・・・・
いや。厳密に言えば、私の心の中にも異性がいない訳ではない。ただ、決してそういう目では見てはいないというだけだ。
好意の対象として見ていないのだから、心配はいらない筈だ。
確かに彼は今の私の思考の大部分を占めているけれど、それはあくまで知り合いとして、もしくは私自身の問題としてのはず。
いくら彼と私が男と女であるとはいえ、ここにいるカップルと同様になるなんて有り得ない。
だからおかしい。とにかくおかしい。良く分からないけどおかしいのだ。
思考しているうちに、理由のわからない反抗心のようなものが湧きあがってきた。
ほとんど論理も何も無く、無理矢理な結論を下して現在の関心事を締めくくる。
締めくくったはいいものの、変にイライラする気持ちまでは一緒に終わってくれなかった。
未だに空虚な頭と胸の中で熱っぽい感覚が渦巻いている。
それを、どうにかして落ち着かせたくて、カップを手に取った。
そろそろ湯気が立たなくなったラテを見つめていると、すぐ側をカップルが通り過ぎていく。
二人は開いた席を見つけ、しばらく何事か言葉を交わした後でそちらへ向かった。
彼等が座った席の周りはやっぱりカップルばかりで。
休憩を終えて、席を立つお客さんもやっぱりカップルばかりで。
自動ドアから外の冷たい空気の中へ出ていく人たちも皆、二人で一組だった。
「まるで・・・二人で一つの生き物みたいです。」
微かに嫌悪感を抱いてそう言った。
私と同僚君がそうであるなんて、考えたくなかった。そんな風に見られてしまうと思っただけでも嫌な気持ちになった。
熱くも冷たくもないカップの中の液体を唇につける。
一口すすった。香ばしさとまろやかさ。それから、今はザラメが溶けたのかほのかな甘みが感じられた。
二口目は、味を感じる余裕なんてなかった。
窓を挟んですぐ側。歩道の中、人の流れに混じって進む同僚君がいたからだ。
私に背を向ける形で、ポケットに手を入れお店の出入口へ向かう彼であったが、不意に途中で立ち止まる。
こちらを振り返り、ガラス越しに小首を傾ぐ動作をしてきた。挨拶らしい動作に、私も類似した動きを返す。
再び出入口へと歩いている彼は、以前バスで出会ったときと同じ、パイロットを連想させるカーキ色のジャケットと細いジーンズ姿だった。
最近街でよく見かけるメーカーのジャケットなので、バスでは流行に敏感でおしゃれなのだろうかと勘ぐったりもした。
けど、もしかしたら反対にあまり興味がないのかもしれない。
偶然出会った以前と待ち合わせた今回とで、同じ服装なのだ。
外用の衣服が乏しい可能性があるし、なによりオシャレでない方が彼のイメージに適う気がした。
私は、外出用に羽織ってきた薄いカーディガンをいじくりながら、ぼんやりとそんな事を思っていた。
彼はガラスの枠の外へ消えた後、ほどなくして自動ドアをくぐり入店した。