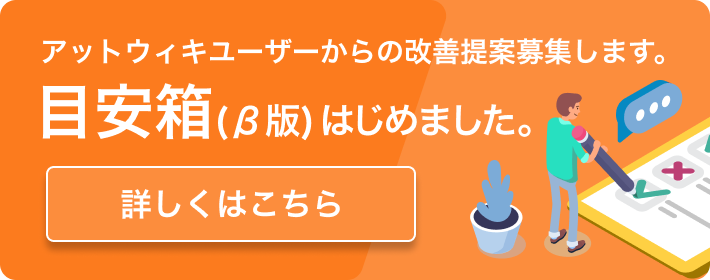◇ ◇ ◇
指先が冷たい。
心臓は早鐘のよう。
全身が、強張る感覚がする。
時折、自分は何をやっているのか、何故自分がこんな所にいるのか判らなくなることがあった。先程昼食を終えた後に陥ったのと同じ現象だ。
まるで丸机の向かいに座る人物に感じる、あまりの緊張から、意識だけが勝手に逃げ出そうとしているみたいだった。
「それで、話ってなんだよ?」
ジャケットを脱いでセーター姿になった同僚君は、左肘を机に乗せ身を乗り出す格好で、開口一番、本題へと入ってきた。
前置きも何もない。一瞬前に私の向かいの席に着席したばかりなのに、これである。
『心の準備』をする暇を全く与えてくれないあたり、相変わらずぞんざいな接し方をする人だった。
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」
私は彼の胸のあたりに目をやりながら、沈黙する。
やがてマグカップがニスで艶やかな机に触れる音が聞こえる。同僚君は、質問と同時にブラックコーヒーを口にしていた。
相手の聞く体勢が整うのを待っていた私は、視線をあげる。
相変わらずの近寄りがたい雰囲気と鋭い目つきが、私を捉えた。
「あの・・・解っているとは思いますが・・・・・・」
私はそこでほんのちょっと躊躇った。
ここから先を切り出せば、本当に後戻りは出来ない。後は彼を説得するか失敗するかの二つに一つである。
同僚君の心は依然変わらず読めないが、意識を集中させると、私が言葉を止めた事を彼がいぶかしんでいるのが、少しだけど読み取れた。
裏返しの試験の問題用紙を、開始の合図と同時にめくる気持ちで、その先を続けることにする。
「2月14日の事。男さんから・・・・・・・・・話は聞きました。全部・・・昔の、その、中学生のころの話も・・・・・・」
同僚君の目が、ほんのちょっと大きくなった。
やはり意外だったのかも知れない。彼は静かにこちらを見やっている。
ガヤガヤという店内の音が、はっきりとした存在感を持ち始める。
沈黙を覆い隠す周囲の人々の話声に晒されていると、嘘をついたのは間違いだった様な気がしてきた。
私は別に男さんから同僚君の話を聞いたわけではない。
それどころか男さんとの間では彼の事を話題にしたことさえないし、今回の行動だって完全に私の独断だ。
けれど、男さんは私が心を読める事を知っている。
フェンスと校舎の間のあの冷たいアスファルトの道で、私がおおよその事情を知ってしまった事にも気付いている筈。
勝手に話を聞いた事にしてしまうのは気が咎めたけど、私の読心能力を知らない同僚君に対しては、これが一番好ましい説明のように思えたのだ。
・・・・・・思えたのだけれど、どうもその判断は間違いだったらしい。
「男が話したのか?」
彼は怖い顔をして聞いてきた。
本当に、低い声色も重苦しく投げかけられた視線も、息ができなくなるのではないかと思うほど圧迫的だっだ。
私は、即座に言葉を選び間違えた事に気が付いた。
サッと血の気が引くなんて、今までは文章上の比喩的な表現技法だと思っていたけど、考えを改めないといけない。
実際に血の気が引いて私の全身が冷たくなっていくのが実感できたのだから。
「もしもさ・・・・・あいつがペラペラと勝手にしゃべったっていうなr」
「あのっ、、、すみませんっ、違います!!」
穏当でない雰囲気を隠しもせずに続ける同僚君を、私は慌てて遮った。
違う?と彼は、もともと皺の寄っている眉間を、さらに深い谷間にしていく。
「えっと、、そのっ、あの、、、、聞いた、というのは別に男さんから話してもらったというのはその間違いで、、、
あの、その、、、えと・・・・・・・・・ともかく男さんは違います・・・別に、彼が話してくれたわけでは・・・ない・・です」
言葉が尻切れトンボになっていくのを自覚しながら、想定外の事態への自身の対応能力の低さを、今更だけど残念に思った。
なんというか、支離滅裂もいい所である。もっとスッキリした言い訳ができたはずなのに。
ただそれ以上に、自分の軽率さが恥ずかしかった。
同僚君にとっては、仲互いをするあの現場を見られたのは、驚いた以上に気まずかったはずである。
そこからさらに、中学生時代にイジメを受けて喧嘩をした、という荒んだ過去まで知られたと解れば、穏やかでいられないのは当然だ。
しかも知らせたのが仲互いをした当の男さんだと言うのだ。
腹いせとして触れられたくない過去を言いふらされた、と取ってしまう可能性持も無くはない。
それに同僚君の事である。単純に関係が切れただけだったのが、これで完全に敵視してしまっても何ら不思議はないのだ。
そうなれば仲直りどころではなくなってしまう。
『男さんから聞いた』なんて台詞は、嘘か真かに関わらず口にしてはいけなかった。
なのに、私は平然とそれを使ってしまった。
人生で初めての説得という行為は、そんな軽率な思いつきで、出だしから躓いてしまった。
「なんだよ。じゃあ話聞いたってのは嘘なのか?」
府に落ちないと言った表情で、同僚君が少し声を大きくして尋ねてくる。
「いえ・・・・・その・・・はい・・・」
「どっちなんだよ?『中学のころの話』って、知ってんのか?やっぱり男から聞いたのか?」
「い、いえっ!男さんからは聞いてませんっ。」
「ってことはあれか?だれか他の奴から聞いたって事か?」
「あ・・・・・い、いえ、その、、、」
「どっちだよ?聞いたの?聞いてないの?」
「その・・・あの・・・――――――――はい。聞きました・・・でも、誰かは言えません」
「言えないのかよ・・・」
「すみません・・・追及しないで頂けると・・・・・・・・その・・・ありがたい、です」
「―――ったく・・・わかったよ。」
そう言うと同僚君は、長めのため息を一つ。額の左半分に手を当てて、うな垂れながら吐き出した。
強く目を瞑ったその姿から、先程までの要領を得ない私の返答に呆れているのが見て取れた。
肘をついた左手で頭を支える彼の向こうで、エターナルフォースブリザードの人がまたもや妙な寸劇を繰り広げている。
今度は目を押えて苦悶の表情を浮かべる彼氏に、彼女の方は真剣に話を聞いてあげている。
同僚君のため息を境に、再び会話の空白が生じていた。
私がカノッサ機関のカップルから視線を戻すと、同僚君は先ほどと同じ姿勢のまま止まっている。
そこに声をかけるべきなのだとは判っていても、何と言って会話を再開したらいいのかが判らなかった。
そう。今のやり取りで私は、はっきりと気付いてしまったのだ。
自分に説得は向かないのだ、と。
相手と摩擦を起こすのを極端に恐れるくせに、心が読める故に自分で考えて相手に接することをしない。
心の起伏を感じた所で半ば機械的に対処してきた私には、相手の気持ちを自分で考えて言葉を発する能力が欠如してしまっていたのだ。
それは相手の気持ちを推し量った上で、意見を変えてもらう『説得』という行動においては致命的であったかもしれない。
なにより心の読めない同僚君が相手なのだから、難易度は格段に上がってしまっている。
強いて言えば、野球をやったことのない人間が、いきなり甲子園の決勝に駆り出されてしまったようなものなのだ。
今更になって私は、自分が無謀な事をしているのだと気付き始めていた。
けれど、だからと言って退くことはしたくなかった。
私は同僚君を説得すると決めたのだ。
たとえ失敗するにしても、私の方から終わりを告げる事はやってはいけない。
多分それは、とても失礼なことなんだと思う。
誰に対して『失礼』なのかは判然としないけど、少なくとも退くことで気が晴れるなんて有り得ない、というくらいは私にもはっきりしていた。
同僚君は相も変わらず額に手を当てた姿勢のままなので、私の方から動くことにする。
「率直に言います」
「あ?」
「あ、いえ。言っても良いでしょうか?」
「ああ。」
「その・・・率直に言います。――――男さんと・・・仲直りはできないでしょうか?」
「嗚呼。―――はぁ・・・」
彼は、二度目のため息をついたかと思うと、頭を動かさず視線だけをこちらに向けてきた。
怒っているのか、戸惑っているのか、悲しんでいるのか。彼の眼差しは、ただ鋭さばかりが際立っていて、肝心の内面をうかがい知ることがほとんどできない。
それにじっと見据えられていると、不意に私の喉がゴクリと鳴る。
そのうち緊張で口の中が乾いてくると、生唾を飲み込まない方が良かったのではないかという後悔を感じた。
彼はやがて顔をあげ、はっきりとこちらを見た。左ひじから先が再び机の上に横たわって、陽光を浴びている。
「あのさ・・・なんで通訳がそんなこと言うんだ?」
「え・・・?」
「だから。なんで通訳は俺と男に仲直りしてほしいんだよ?」
「それは、その、、、、」
投げかけられた質問は、予想の範囲外の物で、私は答えに詰まってしまった。
いや、予想の範囲外という言い方は間違いなのかもしれない。
そもそも私は、彼がどんな反応をしてどんな質問をしてくるかなんて、事前に予想していたわけではなかったからだ。
普通なら多少はシュミレーションを行うのだろうけど、ずっと緊張し通しだった私では思いつくこともなかった。
こんな所でも自分の浅はかさが露見してしまい、気持ちが深く落ち込んでいく。
私は項垂れて、どもりがちに言葉を返す。
「男さんは、私の友人ですし・・・同僚君も同じ飼育委員で・・・・・・その二人の喧嘩別れを目撃して・・・・・・なにもしないのはおかしいです・・・・」
「・・・・・・・・・・・・」
両手を揃えて膝の上に、視線をあらぬ方向に向けて自信無く語る私の姿が、彼を刺激してしまったのかもしれない。
同僚君は再びカップを手に取りコーヒーに口をつけたかと思うと、唐突に立ち上がった。
先ほどから予想の範囲外の事ばかりが起こっていたけど、さすがに今回は訳が分からなかった。
半ば目を白黒させて視線を向ける私に、彼は椅子の背のジャケットを掴みながら、つまらなそうな貌をして一言。
「帰る」
カエル・・・?帰る・・・?
短い単語を理解するのに、数瞬を要した。
やがて非常に緩やかな驚愕が私の中で広がり、臓腑が落ち込む感覚を催し始める。
自分は失敗したのかだろうか?床にこぼれた液体が広がるような勢いで、そんな短文が頭の中を埋め尽くしていった。
「どうして?・・・ですか?」
ほとんどパニック状態でモノが考えられない中、やっとそれだけのことを、咽ぶように吐き出した。
彼はジャケットを着込む作業の途中で手を止めて、こちらを向く。
まだ片腕だけをジャケットに通しただけの状態だった。
彼は、通していないほうの手で首の裏を包むようにして触っていたかと思うと、何度目かのため息をつく。
そしてジャケットを着るのから脱ぐほうに切り替え、椅子にかけ、その椅子を引くと、そこに座った。
私の言葉を折り返し地点として、順序が真逆の同じ動作が目の前で行われる。
机から出来る限り遠くへ引かれた椅子に、浅く腰かけ片腕を背に掛けたおざなりな姿勢で彼は・・・
「だってさ。これは俺達の問題であって、通訳に口を挟まれる筋合いなんてないから。」
「そんな・・・」
冷たい、口調だった。
本当に暖房に効いている店内でさえ、寒さを感じてしまうような。
側の窓からヒタヒタと冷気が忍び寄ってきて、体の奥に入り込んできているような気さえする。
これ以上ない程の拒絶の意を含んだ言葉だった。
思わず、総身が震えた。
外の景色が見たいからと言って、冷たい窓ガラスが側にある席にした自分が恨めしかったけど、それ以上に同僚君の事がこわかった。
体が震えたのも、物理的な寒さというよりは、これほどキッパリと相手を拒絶した態度をとれる彼が信じられなかったからだ。
私ならこれほど相手を傷つけて、自分さえも傷つける言葉はどう頑張っても出てこない。
それを、軽々とした口調で言える同僚君が理解できなかった。
理解できなくて、怖かった。
「そうだろ?
まあ、確かにあんな所を見せられて何とも思わない奴はいないと思うけどさ、丁度いい機会だから言っておく。」
―――通訳とは一応この先もしばらくは一緒に仕事する仲だしな
そう付け加え、同僚君はこちらを見据えて、続けた。
「俺は、良い。男と仲直りするつもりもないし、あいつだって仲直りするつもりはもう無いんだよ。」
「そんなこと・・・」
「ん?」
「彼はそんな事思ってませんよ?」
彼の決め付けたような言い方に、先程までの恐れはどこへ行ったのか、急に私の中で反発心が顔を出した。
実際男さんは、関係を終えるつもりでいるかもしれないけど、心の中は同僚君に対する未練でいっぱいなのだ。
あの日A棟とフェンスの間のアスファルトの上で決裂した時も。その後に教室で顔を合わせた時も。
同僚君を目にした男さんの心からは、やるせない、不安定で未練がましい感情が、確かに伝わってきたのだから。
つまり、本人達が切れたと思っていても、男さんの性格や人柄を考えると、今ならいくらでも修復がきくのが実際だった。
同僚君の方には未練はないかもしれないけど、それを呼び起こすのが今の私のやるべきことなのだろう。
いずれにせよ、彼の言い方にはカチンと来るものがあった。
「思ってるさ。お前だって見てたじゃないか。教室で、あいつが旅行に参加する奴らの中から俺を外すところ」
「それは・・・・・・喧嘩別れをした相手に、今までと変わらない調子で接することの方がおかしいです。」
「けどさ、それでもあいつは俺を外したろ?それは、もう切れた。切れたいって思ってるからなんじゃないのか?」
「確かに・・・それはそうです。
でも、男さんの事はお互い良く知ってるはずです。私も、同僚君も。
今なら、いくらでも彼は思いなおしてくれますよ?」
言いながら、男さんの事を思い出していた。
人当たりがよく、万人に付き合いやすい印象を与える男さん。
温和な性格で皆から好かれていて、通訳するくらいしか他人と関わろうとしない私にも友人として接してくれる。
思えば彼の周囲には、いつも誰かがいるような気がする。
その半分くらいは女の子達とのいざこざによる、というのには苦笑してしまうけど、結局はそれほどに人として魅力的ということなのだろう。
考えているうちに、教室で同僚君を旅行のメンバーから除外していた男さんの姿が脳裏に蘇ってくる。
それまでは積極的に引き入れようとしていた同僚君を、はっきりと『もう参加しない』と男友さんに告げていた。それも、同僚君に聞こえる位置で。
今思えばその時の彼の口調は、先ほど同僚君が席に着いた後の言葉とよく似たモノを孕んでいた。
何かを断ち切ろうとする意思が透いて見えるような、拒絶の意思を前面に押し出した、冷徹で鋭利にして強烈な『言葉』。
普段の男さんで有れば、絶対に口にしないような攻撃性の高い物の言い方だった。
それほどまでに、彼は大きく心を揺さぶられていたのだ。
同僚君と仲互いしてしまったショックから、半ば自棄になっている心境が、男さんの言葉の裏側にあった。
それは、見ていてあまりにも痛々しい光景だった。
説得を決意した本当の理由は他にあるけれど、その場面を目撃したからこそ踏み出した、というのも間違いではない。
私は男さんが、こんな理由で悲しんでいるのを見たくなかった。
彼にはあんな気持は似合わない。何となく、そう思ったのだ。
「だからなんだよ?俺は仲直りするつもりはないっていったろ?」
けど、そんな私の想いも彼には通じないみたいだ。
同僚君は冷たい視線を投げかけながら、そう返してくる。
私は少し焦って会話を続けた。
「寂しくないんですか?それで?」
「別に」
「男さんがいなくなったら、友達が一人もいなくなるんですよ?」
「構わない。」
「男さん・・・・・・可哀そうだとは思わないんですか?」
「言いたい事はそれだけか?」
「・・・・・・・・・・・・・・・」
とうとう私は、次に何を言って良いか分からなくなってしまった。
同僚君はにべもなく、機械的に言葉を返すだけで、何か心境に変化をきたした様にはまるで見えない。
頑なな彼の意思も、心の読めないという状況も、私の言葉では何一つ変わらなかったのだ。
負け戦に臨み、そして奇跡は起こらず城壁は依然として傷一つない。そんな中世ヨーロッパの戦争のイメージが頭の中で浮かんで消える。
打ち負かされた絶望感だけが心を占めていた。城壁の理不尽な堅固さ強大さに、笑いさえこみあげてきそうな絶望だった。
「それだけなら、帰らせてもらうから。」
「・・・・・・・・・」
「じゃあな。」
そう言って彼は席を立とうとする。
何か言わなければいけない。
折れかかった心の中でそんな声ばかりが響いて、具体的な方法がまるで浮かばない。
けれど、逼迫した状況と感覚が私の口を押しあけたみたいだった。半ば無意識に、俯きながら私は言った。
「同僚君は・・・・・仲直りしたくないんですか?」
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別に。なんども言ってるだろ」
「嘘・・・です」
「嘘じゃねえよ。」
「あなたは嘘をついています。」
「しつこいな。もう切れたって言ったろ。」
淡々と。
私達は淡々と中身のない会話を繰返す。お互いの言葉に深い意味はない。
彼は先程までと同じ内容の事を告げるばかりだし、私は私で、ほとんど意識の外側で口が動いていた。
自分でも何を言っているか分からない中で、ふと、ある事を思い出す。
以前、バスで同僚君と出会った時のこと。
不思議な夢を夢を見た、あのバスでの会話。
――――――あの・・・同僚君はなんで、このバスに・・・?
――――――ん、ああ。ちょっと旅行関係の本を見に駅前まで。
偶然同じ車両に乗り合わせ、沈黙が繰り返される中、何故ここにいるのかを問うた私の言葉。それに対する彼の返答。
それは、思いだしたというよりも、どこか遠くから聞こえてきたような追憶だった。
不意に思い出されたその記憶に、私は俯かせていた顔をあげた。
中腰で席から立とうとした格好のまま止まっている同僚君が見える。その向こう側ではラ・ヨダソウ・スティアーナのカップルが二人で、見えない敵と戦っていた。
目の前の風景と頭の中の光景が混ざり合い、絡みあい、相剋しあっている。
――――旅行。 ――――旅行関係の本。
―――――男さんに誘われていた。
――――旅行に。
―――――私達も一緒に行くかもしれない旅行。
脳内で文章の形をなさない思考が、知覚出来ない速度で諸要素を取捨選択し答えを導き出していった。
そう。男さんは同僚君を旅行に誘いたがっていた。
旅行先で、何故同僚君が中学時代の一件以来、男さんや親しい人間を避けるようになったのかを、真正面から問いただそうと思っていた。
イジメを咎め止めさせる事をしなかった負い目からか、気を遣って追及できなかった問題も、旅行と言う特殊な場でなら覚悟を決めて問う事が出来る。
そう、男さんは考えていたのだ。
今まで同僚君は、その誘いに対して表面上はそっけなく断っている。
けれど彼は旅行の本を探していていると、あの時確かに言っていたのだ。
それはつまり、同僚君は男さんの誘いに応じる事を考えている、と捉えても良いのではないのだろうか?
どこまでそう思っているかはわからないけど、少なくとも、
どこかで男さんとの旅行に加わりたいと。
どこかで彼自身、男さんと昔の関係に戻りたがっているのではないのだろうか?
あくまで推測でしかないけど、そこに賭けてみる、縋って拠り所とする価値はある筈だ。
気がつくと、私の心を占めていた絶望が和らぎ溶けはじめていた。
「覚えてますか?」
「あ?」
「以前バスで乗りあわせた時のこと・・・」
「ああ。覚えてる。それがなn」
「あなたは『ちょっと旅行関係の本を見に駅前まで。』と言っていました。」
割り込むように言い放たれた言葉に、同僚君の眉がピクリと動く。
と、今までの席から腰を浮かせていた中途半端な状態から、急にシャンと立ち上がった。
彼は無言で踵を返そうとしている。
「待って下さい。」
「・・・・・・・・・・・」
早口で押しとどめた。彼はこちらに背を向けたまま止まる。
「男さんと仲直りするつもりがないのに、なんで旅行の本を探していたんですか?」
「それは・・・・・あれは、違う。男達のとは関係ない。」
「嘘です。あなたは・・・嘘をついています。」
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・」
「本当はやぱっぱり、仲直りしたいと思っているのではないのですか?」
同僚君がこちらを振り返った。
一瞬。
身の危険を感じた。
振り向いた彼の表情にはそれほどに、何か、尋常ならざるモノの影が落ちていたのだ。
それは恐らくは激情に近い感情なのかもしれない。
貌を見たその瞬間に、自分が絞め殺される想像をしてしまうほど、同僚君は今までのどんな時よりも瞋恚に駆られているように見えた。
ゆっくりと。
彼はゆっくりとした動作で、一つ一つ手順を確認しているみたいに、椅子に近寄り、腰を下ろし、机の方に体を寄せた。
その向こうから『月に廚誠を近いし者』とか『我が固有結界を――』なんて大声が聞こえたかと思うと、(´・ω・`)←こんな顔をした店員さんが私達の側を通り過ぎていく。
と、女の子が謝っている声が切れ切れに聞こえてきて、さっきから時折こちらに届いていた、漫画の設定を並べたような会話が店内の喧騒から消え去った。
目の前では、こちらに詰め寄った姿勢で同僚君が口を開こうとしている。
「お前は、俺の何なんだ?」
―――――――――――・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ゾル。
背筋からそんな音がした。
忘れかけていた、心臓から全身の末端に至るまで針金が入っているような感覚が、その音で呼び覚まされた。
手足が凍りついてしまったのだ。目の前でこちらへ睨むように顔を向けているナニカが、私を凍らせてしまったのだろう。
眉間の皺は、骨に彫りこまれその形に沿っているかのようで、元からある凹凸なのではないかと錯覚する。
真一文字に結ばれた口も、鋭く歪みながらも見開かれた眼差しも。
明らかに、私を威圧するためだけに機能していた。
「友達か?恋人か?家族か?親戚か?
違うだろ?何でもない、ほとんど他人みたいなお前がさ、俺の何を知っててそんな事が言えるんだ?
言ったはずだよな?俺は男に謝るつもりも仲直りするつもりもない、って。」
声は、あくまで静かだった。
それどころか先程までの押し殺したような低い声から一転して、僅かだけど高音でさえあった。
私は何も言えない。彼の瞳は、白熱しているみたいで怖かったから。
怒っているとか、不快に感じているとか。そういう一般的な感情じゃなくて、もっと根源的な『感情の原液』。どちらかと言うと本能に近い『熱』が彼の中で渦巻いている。
恐怖からか、激しく動悸がする。同僚君が来てからずっと心臓は高鳴っていたけど、それよりも一段階上の次元に昇って行ってしまった。
「俺が良いって言ってるのに、なんで通訳は良くないとか言ってんだ?それさ。おかしいだろ?」
――――― っ、、う、、、、
―――いたい。痛いです。
同僚君の突き刺してくるような言葉も。私の心臓が気が狂ったように跳ねまわっているのも。
痛いです。泣いてしまいます。痛い。やめてください。
「俺の言葉を否定するなんてさ、俺の事、知らなきゃできないよな?」
こんなに、痛くて、怖くて、泣いてしまうそうなのに、やめてください。
私はあなたを傷つけるつもりなんてないのに。やめてください。
心が―――体も―――全部、痛いです。
このままだとわたし、泣いてしまいます。泣きたくないけれど、泣いてしまいます。
やめてください。いたいです。傷ついてしまいます。
やめてください。我慢、できません・・・・
・・・・・・・・・・・・・・お父さん。私、彼を傷つけても、、、いいですか?いたい、です。
自分も傷つくかもしれないけど――――私、彼を傷つけます。
「お前は俺の事知らないだろ?他人みたいなモンだr」
「知って―――ますよ。」
目を見開いた。
頭が痛い。手足が痛い。体も心も何かも。
でも何より目が痛かった。
じんわりと、目の中で痛みが溢れだす。やがて、一筋、頬を伝って流れおちた。
同僚君はたじろいでいる。私が口応えしたからかも知れないし、私が涙を流したからかも知れない。
「私はあなたの事を知っています。何もかも知っている訳ではないけれど、知っています。」
今や私は、全神経を彼の心を読むことに割いていた。
同僚君の姿を視界の中に捕らえる。
意識を集中し、余分な情報をカットする。
彼の背後の景色が、午後の白い陽ざしと混ざり合い、やがて一枚の白地となっていく。
周りから聞こえる声が耳鳴りにかき消され始める。
プツ、プツ、。一つ、また一つ、。会話が消える。
『なんだ。この店ガキばっかじゃねえか。死ね。』『お前が死ね。コーヒー飲みすぎて中毒で死ね。』というやりとりを最後に、全てが聴覚検査に用いられる、あの高音の中に没した。
「それに、私は他人じゃありません。」
「他人だろうがっ。彼女でも友達でもなんでもないだろ。」
「違います。」
「は?なにがd」
「あなたは、私の同僚です。
飼育委員の同じ曜日、同じ時間にペアを組まされた、私の同僚です。」
「!
・・・・・・・――――っ、、、」
唐突に聴覚検査の耳鳴りが『ダン!』という音で、かき消された。
見ると、彼の拳が机の上にある。同僚君が丸テーブルに自らの拳を叩きつけたようだった。
その叩きつける音が、私には幾重にも残響を伴っているかのように感じられた。
白い何も無い空間を消去したその音が、何度も何度も私の中で繰り返されているのだ。
実際には拳を叩きつけた最初の音は、聴覚的な痕跡など何一つ残してはいない。
けれどもその、最初の音に、私の心は完全に絡めとられてしまったらしく、脳内で存在するはずのない響きが間をおかずに連続していた。
今や集中は途切れ、意識は普段の散漫な状態にもどってしまった。
白い世界に没したはずの周囲の景色も、網膜に帰還する。
同僚君の背後に広がる店内の様子が、こちらの注意を反らそうと誘惑してくる。
私達の近くに座っている人たちがこちらに視線をやっていた。
ヒソヒソとした会話があちらこちらから聞こえてきた。
『痴話喧嘩かな?』『男の方が怒ってるみたいだな。』『えー?女の子だって怒ってるよー。』『そう?』『だよー』『そうかー』『えへへー』
『と、止め、、止めた方がい、いいいいいいでありましゅかかっか』
『存在不適合者め。計画に支障を及ぼすつもりか?』『存在不適合者ってなに?』『ふんっ、持たぬ者にはわかるまい。』『意地悪しないで教えてよ~』『い、いわゆる超能力者のことだっ。俗な言葉で言うとなっ。』
『おい、見てないで早くしろ。』『あなたみたいな無関心なのが非常識な人を増殖させているんですね。わかります。』『はいはい。人の情事に首突っ込むのはいいことですね。鬱陶しいから死ね。』『お前が死ね。マンションの組合から村八分にされて孤独に死ね。あとさりげに【情事】とかキショイんですけど。万年発情男さん』
『喧ダメ』『いや、でもさ、喧嘩するほど仲が良いって言うし、それに他人の色恋沙汰に勝手に首突っ込むものじゃないって、ばっちゃが言ってたし』『婆言?』『うん。俺もそう思う。』『わかっ』『ひょおおおおおおおおおおおお!!』『五月蠅』『かっかっかっかかかかっかかかかかっかっかっかっかっかっかっかっかっか!?―――止めた方が良いでありますかっ!』『ってまだ言ってたの!?』『は、はい!イエッサー!自分は報告義務をはああああ、、、はたはた、果たさなければならぬのでありましゅしゅ・・・しゅあっ!』『いや、もういいから(^^;)』『あれれ~?あれれ、あれれ~~?ふぇ~、、、ここどこー?佐藤さ~ん(泣)』ブォンp・・・チンポキッキ!
何だか、悲しくなってきた。
ほとんど何も知らない人たちが、私達に関して勝手な推測を立てている。
誰も彼もが好き勝手なことを言っていた。結局彼等にとって、私達の事は他人事に過ぎないのだ。
他人事に過ぎないから、なんとでも言える。仮に推測が間違っていたとしても、他人事なのだから傷はつかない。
何も知らないのに推測する、という行為自体が、安全地帯にいるからこそ可能なのだ。安全地帯から飛び出して心身を削っている私達とは違う。
彼らとは認識が違うのだという事実を、はっきりと突きつけられたような気がして、酷い疎外感を感じてしまう。
同じ店の中にいる筈なのに、はっきりと境界線で隔てられているような疎外感だった。彼等の和気あいあいとした雰囲気も隔たりに一層拍車を加えている。
もともと赤の他人なのだから、それはそれでしょうがないとは思うのだけど、平気なのはあくまで曖昧にされていればこそだった。
これほどはっきり目の前に差し出されてしまえば、やはり悲しくなるのは避けられない。
なんとなく、今の同僚君の私に対する怒りが分かったような気がした。
偶然自分の目に留まったモノに対して、当事者でもないのに勝手に結論を下し、勝手に何事であるかであるかを決めつける。
恐らく私は、こうやって自分自身を危険に晒さなければ、そんな事にだって気付くことはなかったのだろう。
けど、それでも私は、そうやってこちらを遠巻きに環視している人々よりも知っているのだ。
同僚君の過去も、彼が心の中に私と同じ寂しさを抱えている事も。邪推や憶測ではなく、事実として知っている事が確かにあるのだ。
だから、それに賭けている。
やっぱり、知り合いと友人が喧嘩別れはしてほしくないから。それに、彼の寂しさを、自分のものとして、知っているから。
彼が拳で机を叩いて、それが怖くて集中が途切れてしまっても、迷うような事はなかった。
自分が彼を傷つけているのだと知って、彼が自分の所為でどうしようもないくらいに取り乱しているんだと知って、その事実が辛くて酷く私自身泣いているのが分かっても、退こうという気が起こらない。
「黙れよ、頼むから黙れよ・・・・・俺のことなんかどうだって良いだろ!!」
同僚君が吠える。
さっきまでは自分の正当性を主張する形の拒絶だったけど、今はまるで駄々をこねるような言い方をしていた。
「くそっ、、、そうだっ。俺達は同僚だよ・・・・・・だけどそれがどうした!俺達そんな仲良くないだろ!!」
「あなたに仲の良い人がいるの?」
「――――っ!!」
「もう、友達なんていない筈なのに?男さんを突き放したのは、貴方の方でしょう」
「だから・・・・・どうしたっ」
「友人がいなくなったのだから、説得している私が仲の良い人でないのは当たり前の話なのに。」
「知るかよっ!ただ委員会が同じってだけのお前にっ、何が解るんだって俺は言いたいんだよ!!!」
「――――――解らないからこうやってお話をしてるんですっ!!!」
「放っとけよ・・・・・・・・ほっといてくれ・・・・・・・・」
「だけど―――」
「畜生―――」
あなたの、寂しさだけは知っているから!!
俺はもう、独りになるって決めたんだよ!!
私達は、ほぼ同時に叫んでいた。
もう、周囲の視線は気にならない。
ただじっと同僚君の心を読むためだけに、全身を目にして意識を集中していた。
再び返ってきた静かで白い世界の中、机の向かいの人だけが有った。
頭の中で鈍痛が走りまわっている。瞳からは、涙が静かに頬へと伝っていく。
―――彼は、『気分が・・・悪い』と言っています。
―――彼は、『くそ・・・訳・・・わかんねえよ・・・』と言っています。
―――彼は、『その目で見るな。俺を見るな・・・見ないでくれ』と言っています。
―――彼は・・・・
脳細胞が焼き切れるのではないのかと思う程に、強く強く、半ば無理矢理に自らの意識を同僚君へと集中させていた。
頭の鈍痛がますますひどくなり、終にはガンガンと、頭骨を内側から破ろうとしているかのような激しいモノへと変わる。
それでも尚、無視をして心を読もうとしていたけれど、不意に耐えがたい吐き気が混み上がり集中は途切れてしまった。
一瞬前まで確かに聞こえていた同僚君の心の声が、サッと消え去る。
そこで私は、今更ながら、自分が荒く息をしているのに気がついた。
静かな世界の中で、私と、彼のゼエゼエハアハアという押し殺された激しい呼吸が、嗚咽みたいに鳴っている。
やがて同僚君は、崩れるように椅子に座った。
いつの間にかお互いに席から立ち上がっていたのだ。
私も、それを受けて、静かに腰を下す。
彼は・・・・・100kmマラソンを終えた後みたいに疲れきった様子で、深く腰掛け項垂れていた。
まるで、眠っているのではないかと疑うわれる程に、深く深く項垂れて。
私はハンカチを取り出して、頬や目頭や目じりを拭う。
こんなに泣いたのはいつ以来だろうか。
鼻をすすることで、熱を持った鼻腔を空気がスッと冷やしていくのを感じながら、そう、思った。
気分を落ち着かせようと、マグカップを手にとって口をつける。ラテは、その一口で最後だった。
・・・・・沈澱していたザラメの甘さが、カラカラとした口の中へ、ジワリと広がっていくのがわかっった。