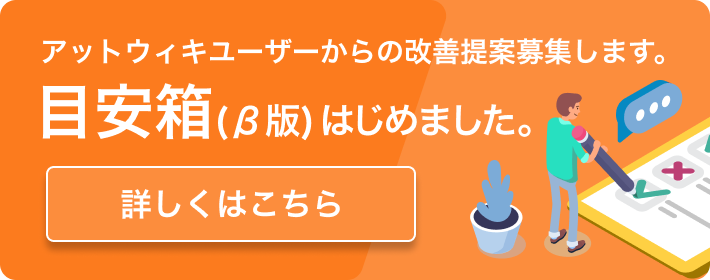――――ゴツゴツと無骨な樹木は醜くく曲がりくねりながらも・・・・・・
鳥のさえずりが一つ。
まだ暗闇があたりを満たしている中、場違いな響きは高らかに高らかに。
空を見上げればそこにあるのは漆黒の帳と、そこに半ば溶けつつある湾曲した裸の枝の輪郭。
冬の月は、何時の間にやら西の空へ沈んでしまったらしい。
私は名残惜しく思いながら、頬に手をやる。
痛いほどの寒さに長らく晒されていたせいだろう。
月が出ていた頃の柔らかさは失われ、そこには固く、冷たい手触りがあるばかりだ。
それを触る指先だって、冷えて半ば感覚を失いかけ、触っているという意識が希薄である。
まるで五感のなかから触覚だけが空気に流れ出して、月と共にこの場から去ってしまったような錯覚を覚えてしまう。
触覚もろとも痛覚を失くした私は、一人ここに置いていかれてしまったのだ。
不意に途方に暮れた気持ちを抱く。
痛覚を失った私は、もう、普通の人とは違う。
痛みを感じないのだから、どんなに酷い傷を負っても何も感じないのだろう。
足を挫いても、内臓に病を抱えても。
それを何とも感じない人間なんて、もう、誰からも理解されないに違いない。
痛みを理解できなくなってしまった私は、痛みを感じる『普通の人』にとっては、もはや得体の知れない存在なのだ。
自覚して酷く胸が痛んだ。けれど。
【痛かったら、痛いって言えばよかったんだ、おまえは】
―――――――なるほど。
『痛み』という言葉の連想から、最近読んだ小説に出てきた台詞が耳元で再生された。
同時に、一歩踏み出す。
足もとから枯草がサクサクと踏みしだかれる軽い感触が伝わってきた。
何と言う事はない。
痛みが無くなってしまっただなんて、ただの妄想に過ぎなかった。
私には、ちゃんと痛みを感じる心があるのだ。
薄い布で目の前を覆ったような暗闇のなか、私は、木が疎になっている広い空間を歩きまわる。
踏み出せば踏み出す程、足もとから伝わる感覚に。
体を動かす事で生じた風が、頬や指先を撫でる感覚に。
私はなんだか無性におかしくなってきた。おかしくて、笑いたくなってきた。
痛みは訴えるものなのだ、と。
あの小説で、彼女は最後にそう言われた。
本当にその通りだと思う。
飼育委員の同僚が怖ければ。怖くて心が痛いのならば
友人との間に、考え方や感じ方の相違があると気付いて寂しければ。寂しくて心が痛いのならば
ただ、その痛みを訴えれば良かったのだ。
そうやって、訴えて、話しあうことで、心の傷は癒される。
私は随分と遠回りをして、やっとその答えを理解できた。
けれど遠回りをしたにしては、実のところ、答えはすぐそこにあったのだ。
しかも『すぐそこの答え』と言うのは、ただの紙とインクで構成された作り話にあったのだから、滑稽だ。
現実に存在する人間である私が、架空の物語に有るのと同じ答えで救われてしまう。
これではどちらが真実なのか分からなくなってしまう。
シンパシーを感じた彼女は、現実の影であり実在しない。本質はただの情報で、さらに突き詰めれば紙とインクという媒体に過ぎない。
対してシンパシーを感じる私は、実在する人間だと言うのに。
その現実の人間が現実の影に遅れて、同じ答えを導き出す。
結局、架空の物語と言えども真実を語るという事なのだろうか?
或いは、現実に存在する人間の生もまた、造られた物語と変わらない胡蝶の夢という事なのだろうか?
そんな哲学的な思考にまで至りながらも、架空の少女が行き着いたのと同じ地点に自分が着地してしまったのが酷くおかしかった。
現実と空想が転倒してしまった事実が、酷く滑稽で、そして愉快で。
実に軽快な足取りで私は、その場を後にした。
森には薄明るい群青の空気が満ちていて、鳥のさえずりは何時の間か絶え間ない物となっている。
つまり森は、遅い朝を迎えようとしているのだ。
森の出口に続く小道にたどりついた私は、ふと、空に目を向けた。
ようよう明るくなりゆく空に、無骨な木の枝が、その輪郭を際立たせている。
ゴツゴツとした樹木は醜く曲がりくねりながらも――――――
その実、紛れもなく天に向かって伸びていた。
◇
どうも夢を見ていたらしい。
なんだか以前にも見たような夢だった気もするし、逆に全く違う夢だった気もする。
いずれにせよ、目覚めた今となっては、何もかもが一睡の幻に過ぎない。
痛いほどの寒さも。曲がりくねった樹木も。想いを馳せた小説・・・・・・・・・だけは現実にも存在するけど。
夢から覚めればそれらはどこにも存在しない。
あとに残るのはただ、、、、、
帰りのホームルームを終えた教室は、生徒のざわめきで満たされていた。
三月に入れば本格的に学年末の試験が始まる。
切れ切れに耳に届く教室内のざわめきもまた、普段とはそこはかとない相違を見せていた。
『サインコサインタンジェント』と歌うように繰り返す少女の声。『アベ公房のアベは安倍か阿部か』という冗談めいた少年達の問い。
そんな個々の構成要素を、川面から飛び上がる魚のように時たま顕わにしながらも、一個の湧き立つ雲としてざわめきは空気中に満ちていた。
二月も後半を迎え、だんだんと季節が暖かくなり始めている。
にも関わらず、それまでと何一つ変わることなく午後もストーブが稼働している教室内は、空気がこもり熱いほどであった。
そんな、人の存在感が空気の成分の大半を占める中で、彼女は机に伏していた頭をあげた。
不思議そうにキョロキョロと周囲を見回す彼女の顔には、数本の細く黒い線がある。線は、彼女の長い髪から延びていた。
机に突っ伏した事で頭髪が若干乱れ、幾本かが彼女の顔にかかってしまったのだ。
無意識に顔にかかった髪を払い、頭髪を整えながら彼女―――友人やクラスメイトや飼育委員の同僚から『通訳』と呼ばれている―――は一人赤面する。
どうやら、ホームルームの間中、机に突っ伏した状態を一貫していたのに気付いたようであった。
周りが皆、立ち上がって挨拶をする中、麻雀の箱から一つだけ牌を抜き去ったみたいな穴の底で、微動だにしない自分の姿を想像したことで、顔に朱がさしてしまったという訳である。
―――どなたか、起こしてくださってもよかったのに・・・
いそいそと立ち上がりながら、そんな風に呟こうとした彼女であった。
が、クラスの大半の顔が厚ぼったくむくんでいるのを見た事で、呟きは喉の奥へと呑み込まれていった。
麻雀の牌が抜けていた箇所は、一つではなかったのだ。
彼女も含めてほとんど皆、テストを控え、連日睡眠時間を削っている真っ最中という事であった。
すぼめた手を口にあてて、欠伸を噛み殺した後、丁寧なしぐさで帰り支度を始める。
教科書やノート類を、端に錆が浮き始めた金属製の机の中から取り出し、毎年使い回されて光沢の無くなった木製の天板の上でトントンと整える。
次に、脇のフックにかかった革製の鞄とジャージの入った袋を机の上に出し、鞄の留め金を外す。
開かれた鞄へ、教科書類を置くようにして緩やかな動作で彼女は入れた。
鞄を閉め、再び留め金を付けると、取っ手を両手で持って彼女は、くるりと机に背を向ける。
その際に、長く伸びた黒髪が、さらりと空に踊る。
そのまま教室を後にしようとテクテクと歩きはじめる彼女であったが、途中で、不意に立ち止まる。
酷く表情の読みにくい、試験前の寝不足を考慮してもなお虚ろと言える彼女の瞳が、教室内のとある席に向けられていた。
そこには彼女、通訳の友人である男女が一組。例によって二人は――――
◇
「おい。」
「・・・・・・・すぅすぅ・・・・・すやすや・・・・・」
「おーい?」(ユサユサ
「―――ハッ」
「起きたか?」
「あにゃ、にゃ、、な、なによ男?何か用?」
「別に用って訳じゃねえよ。たださ、帰りの挨拶終わってるっちゅうのに、ツンがまだ寝てるから」
「あ・・・・・・あ、、(///)
よ、余計なことしないでよ!あんたが起こさなくても自分で起きてたんだからね!?」
「はいはい(^^:)」
「って、わーらーうーなあっ!!ホントにちゃんと起きてたんだから!アンタだってさっきまで寝てたくせに!」
「ははっ、」
「な、なによ・・・その反応。なんか凄い頭にくるんだけど」
「いや、だって寝てるのはいつもの事だし?」
「こっ、」
「ついでに言うと試験勉強もしてません。」
「うわ、、、」
「でもさ、俺もちゃんと寝不足だから安心せい。洋ゲーのやりすぎでなwふはははははははwwww」
「アンタ・・・・・・進級できないわよ?」
「なん・・・だと?
心配?ツンが?俺の?卍解?」
「あああ、あ、あったま来た!!
アンタなんて留年すればいいのよ!留年し続けて留年クール先輩と結婚すればいいんだから!!」
「ちょ、なに不吉なこと―――デュアアアアッシ!
こら!足踏むな!M78星雲出身者みたいな声上げちまったじゃねえか!お恥ずかしい!、、、って行っちまったしよお・・・・」
――――ポンポン
「んお?誰だあ?肩叩くのは、、、通訳か。だよな。」
「はい。私です。
ツンさんは『男の馬鹿ぁ、、、アンタ、前回も成績赤点スレスレだったじゃない、、、
折角勉強手伝ってあげようと思ったのに・・・・い、一緒に・・・・・うっ、、、一緒に進級したく、、、ないの?
私と一緒に卒業したく、、、ないの?やだ、、、私は、、、やだよお、、、、
男が留年するなんて・・・・・ひっぐ、、、、男のバカァッ!なんで・・・・わかってくれないの?』と言っておりました。」
「は?え?」
「・・・・・・」
「ツン・・・・が?」
「はい。」
「心配・・・・してんだな。ツン。俺のこと・・・・・」
「あの・・・・・・・・追いかけた方が、よろしいのでは・・・・」
「ん・・・・・・・だな。そうするか。」
「お気をつけて。階段など転んで怪我などなさらないように。」
「お、おう。・・・・・・・・・・・あれ?」
「?」
「あのさ、通訳、なんか・・・・・・・・雰囲気変わった?」
「はあ・・・」
「ああ、―――いや、何でもね。忘れてくれ。変なこと言って悪かった。んじゃ、また明日なっ。」
「はい。また、明日も。」
かくて男は走りだす。クリームを気体にしたような濃厚な空気を裂いて、裂いて、廊下に飛び出る。
急な温度差に身を震わせながらも、素直になれない、あの幼馴染のもとへとひた走る。
―――なるほどなるほど
一人、そう口にして。
【→新ジャンル「通訳」】
更衣室はは普段どおりのよそよそしさで私を迎えた。
側面の壁に並ぶロッカーの半分以上は、鍵がかかっていて開かない。
中には半開きになっている所もあるのだけれど、その隙間からだらしなく衣服がはみ出していたり、雑誌やラケットケースなどの私物が覗いているあたり、私に使用可能なロッカーは存在しないようであった。
奥の擦りガラスからは午後の明るさが流れ込み、電気の点いていない更衣室に濃い陰影を生み出している。
窓は東に向いているため、放課後の、この時間に直射日光が差し込む事はないけど、それでも一切の文明の利器を必要としない明るさをもたらしている。
輝く擦りガラスとそれに照らされる影のような更衣室。
暦の上では春であり実際にも寒さが和らぎつつある昼下がり、とはいえ、さすがに無人の室内ではその恩恵にもあずかれないらしい。
キンと引き締まった空気が、十数分前までここを使用していたであろう人たちの、微かに残った諸々の匂いを織り込んで、鼻を刺激してくる。
物悲しくなるような匂いの中に人の気配を嗅ぎ取れる。
私はそんな更衣室の空気に体を震わせつつ、着替えの出来るスペースを探し始める。
半開きのロッカーからはみ出した衣服や私物は、奥の窓からしみ込むような光が覆う床の、大半を侵食していた。
私達飼育委員は、飼育小屋の掃除という仕事内容の関係上、基本的にジャージに着替える事になっている。
なので更衣室の使用が認められているのだけれど、印象的には、運動系の部活が所有する更衣室を『使わせてもらっている』と言った方が正しいように思う。
事実、更衣室は男女両方共に、運動系の部活が主要な使用者であった。
持ち帰らなければならない筈の彼等の私物も常時置かれていて、それが学校側にも半ば黙認されているのが現状である。
ただ別に、その事について不満や反感があるわけではない。
それはもはや、昔からの慣習になっていて、今更正そうとしても学校や生徒会に余計な仕事を増やすだけなのだ。
それに、毎日使っているのに、その度ごとに持ちかえらなければならないというのも、激しい運動で体を疲労させいる部員達には酷な話だろう。
だから少なくとも私自身には、それに私の見る限り飼育委員会自体にも、この『間借りさせてもらっている』現状をどうこうしようという意識は無かった。
更衣室に入って一分ほどして、奥の壁とロッカーの列が直角に交わる地点に、若干の空きを見つける。
背後の出入口の鍵を閉めると、泥棒が抜き足差し足をするように、床を彩る雑誌や脱ぎ散らかされた制服なんかを避けて、慎重に移動を開始した。
やがてどうにかして、部屋の隅っこの貴重な床の露出部へとたどり着き、着替えを始める。
制服を脱ぎつつ、器用にも立ったままそれらを畳み、床におろした袋へジャージと入れ替わりに詰め込みながら、私は酷く落ち着かない気分だった。
飼育委員は仕事の時間の都合上、昼の時間を除けば、朝も放課後も、運動系の部活の人たちが着替えた後に更衣室を使用している。
しかも飼育小屋の仕事は男女二人一組であるため、一日で最も散らかった状態の更衣室で、たった一人で着替えなければいけないのだ。
それはまるで、無許可でこっそりと忍び込んでいるような錯覚を覚える行動であった。
別に悪い事をしている訳でもないのに、なんだか自分が場違いな存在に思えて、更衣室そのものがこちらを拒否している気がしてくる。
着替えの時間はそんな気分にさせられるのだ。
とはいえそんな事にも既に慣れっこになっている私にとっては、そんな感傷も今や通過儀礼の一種に過ぎなかった。
むしろ仕事を始めるにあたって、気持ちを切り替える上では好都合とも言えた。
何よりあの同僚君と顔を合わせる前には、そうやって気持ちを切り替えなければ、やっていけなかったのだろう。
そんな風に思考しつつ、私は下着の上に体操服を着て、次にジャージに腕を通した。
上半身の着替えが終わると今度は、スカートを履いたままの足にジャージを通す。
少し長めのジャージの足もとを整えた後、スカートのホックを外して脱ぎ、上と同様に畳んで袋に入れた。
思考は、飼育委員の同僚の少年に至った事で、ここ最近に起こった一連の出来事の記憶を呼び覚まし始めた。
あの日。あのコーヒーショップでの説得の翌日。
同僚君と男さんの関係は、私達の懸念や緊張をよそに、意外なほどにあっさりと回復した。
自分が全面的に悪いという同僚君の態度に、男さんの中にあったわだかまりが、ほとんど瞬間的に解消されたのが大きかったに違いない。
表面上は『お前の方から切っといて、ずいぶん勝手だな』なんて言いながらも、男さんにの心には仲直り以外の選択肢が存在していなかった。
結局、ほとんど何の障害もなく、同僚君は男さんに受け入れられるに到った。
やはり私の睨んだ通り、どんな風になろうとも男さんは、同僚君と元の関係に戻りたい、というのが本音だったようだ。
お互いに理解しあえない、という気持ちから距離をとっていた同僚君が、これからどうなるかは解らないけど。
あの男さんが相手なのだから多分、なんとかやっていけるに違いない。
それに―――
?
『それに』と言うのはどういう事だろう?
今確かに私の中で、この先の彼等の関係を保証する要因を、男さん以外にも見出していた。
けれど、それが何なのか、判然としない。一体何なんだろう?
バッグから貴重品を取り出して、ポケットに入れながら、私は首をかしげた。
考えても一向にはっきりしてこないので、諦めて着替えを続けることにする。
あらかじめポケットに入れておいたゴム紐を、貴重品と入れ替わりに取り出して、髪を結い始める。
長髪を束ね、それを後ろの方で髷に結う。最後にヘアピンで留めて完了である。
私は来たときと同じ経路をたどって、散らかった更衣室を出入り口へ向かった。
最後に、しっかりとした金属性の造りの扉に添え付けられた鏡で、全身をチェックする。
鏡の中で、十数年付き合ってきた自分の姿が、頭に手をやり髪を整えていた。
ふと、手を止めて見つめてみる。
以前と何一つ変わらない、虚ろな瞳がこちらを見返してきた。
男さんと同僚君が仲直りしてから、五日ほど経過していた。
いろいろあって、大切な事も学んだけれども、だからと言って私の生活に何か劇的な変化が起こったわけでもなかった。
自分が心の底で人を拒んできたと気付いても、原因は生まれた時からの読心能力と幼い頃から無意識のうちに続けてきた行動にあるのだ。
フワフワと現実感のない感覚は性根に染み付いてしまっていて、そう簡単に変えることができない。
結局、相も変わらず私は、たまに強い感情が流れ込んでくればそれを通訳し、その他は心を読んで行動を選択するだけの日々を続けていた。
それがあまり健全ではないと解ってしまった今でも、特に何かをしようとは思えない。
心が読める私には、同僚君のように決定的な問題が生じたりもしないから、危機感も感じない。
現状に対する『このままじゃいけない』という意思が、どうにも薄弱であった。
けれど、そんな自分を、ちょっと悲しく思う自分もいるにはいた。
今までは何ともなかった事を考えた時に、ほんの少しだけ、胸が痛むような気がする。
或いは、そういう意味で、私は変わってしまったのかもしれない。
大きな変化は無くとも、今度の出来事で、確かに変わった部分もあるのかもしれない。
飼育委員の仕事で飼育小屋に向かう度に感じていた、お腹が締め付けられるような不快感が、今日はない事に気がついて、そう思った。
変化、というのならば、これが一番大きな変化に違いない。
どうもあれから私には、妙に飼育委員の仕事を待ち遠しく思っている節があった。
確かに虎吉に会うのは楽しみなのだけど、今までは心の読めない同僚君の存在がそれを阻害していた。
恐らく、同僚君を説得する中で、彼の事を知ることができ、彼もまたほんの少し私に気を許してくれたからなのだろう。
お互いの間にあった壁が消えた事が、きっと一番の理由なのだと思う。
彼に対する畏れも怖れもなくなった今、なるほど飼育小屋へ行き渋る理由もない。単純に、気兼ねなく虎吉と触れ合う喜びに浸れるのだ。
だけど、どうも奇妙な所があった。
純粋な虎吉と触れ合う喜びにしては、説得の日から初めての飼育委員の仕事になるこの日を、待ち遠しく思うと言うのは奇妙な話だ。
触れ合いたければ、飼育委員の知り合いに頼んで、彼等の仕事のついでに飼育小屋の中に入れてもらえば良いだけである。
しかもただ単に会うだけなら、それも必要ない。
何にせよ、心が浮ついているにしては訝しい気持ちが拭えなかった。
ドアノブに手をかけ、少し力を込めて扉を開ける。
金色の、夕暮れを控えた午後の光が差し込む昇降口が、少しずつその姿を顕わにし始めた。
それにしても、同僚君を怖くなくなる、というのは、事件以前には思いもよらなかった事である。
なるほど確かに、私は変わってしまったのだろう。あの、2月14日の日を境にして。
そう、心の中で一人ごちながら、私は廊下に出る。
低い段差になっている更衣室と廊下の境界を踏みこえ、自分のクラスの下駄箱へ向かい、そこで運動靴に履き替えた。
昇降口から外の広場に出ると、校舎内の影が消え去った明るい光に包まれる。
私はそこに、同僚君がいるのに気がついた。
広場の中心にある、花で造られた半ば芸術的なオブジェが立つ花壇の周りを、ブラブラと歩いている。
「ん・・・・・・よう。」
こちらに気付いた彼が軽く手をあげて、挨拶する。
「どうも・・・」
私もそれに返すが、ふと、ある事に気がついた。
いつもなら彼は、私より先に着替え終わって、そのまま飼育小屋へ向かっている筈なのだ。
たまに私の方が先んじる事はあるけど、いずれにしろ、二人が出会う場所は飼育小屋以外には存在しない。
それが今は広場で顔を合わせていた。つまり、それが意味するのは・・・・・・・
「待って・・・いらしたのですか・・・」
意外な彼の行動に、意図が掴めずちょっと動揺しながら、そう尋ねる。
彼は、『ん』と短い肯定の返事をしたのち、『行くか』と花壇から離れて歩き始めた。
私もそれを受けて彼と歩調を合わせる。
並んで歩く彼の心からは、何故だか、妙な緊張が伝わってきた。
・
・
・
・
・
・
私達は歩く。
横に並んで、歩調を合わせて。
隣からは彼の存在と心の半分が伝わってくる。
普通の人の半分くらいしか心が読めない、というのは、やっぱりまだまだ、彼の問題の全てが解決されていない事を物語っているのだろう。
私と同じく、彼が抱える問題も、根が深いのだ。
数年間。中学生の頃から想い続けてきた事。
ずっと独りで有り続けてきた彼の心は、すぐに昔のような状態に戻る事はないのだろう。
読心のほとんどを拒む程の物だったのだから、それが自然な現実なのかもしれない。
むしろ、半分とはいえ、彼が私に対して気を許してくれた事の方を喜ばなければいけない。
まだ、周りの全てに心を開いたわけではない彼の、橋渡し、それこそ通訳をするのが、信用された私の義務なんだと思う。
私達は校舎の角を折れ曲がり、植込みと壁に挟まれた、狭いアスファルトの上を行く。
あの日、同僚君の心を垣間見たその道は、今は背後からの輝く陽光で照らされていた。
運動系の部活動の掛け声や、吹奏楽部の合奏。それから未だ校舎に残る生徒達のざわめき。
こんな世界の端のような道にさえ、それらは音を届けてくれるみたいだった。
人気のないさびしい筈の道が、そう思わせない程に暖かい。
私は隣を歩く同僚君を見た。
男の子だけあって私より二つほど目線が高いので、ちょっと頭を傾けなければいけない。
こんな近くで歩かなければ、きっとそんな事実にも気付かなかったのだろう。
私の視線に彼もこちらを向いた。
柔らかい表情をしていたけど、やっぱり眉見に皺の跡が見られる。それどころか、額にまで一本縦に線が通っていた。
きっと、これが同僚君の顔なのだろう。
人を拒んできた彼の、寂しさと張りつめた心を反映した表情。
たった一度、訪れた問題を解決した程度では氷解できない頑なさ・・・
結局、彼を説得できた本当の理由は、そこに同じ寂しさがあったから、なんて単純なモノじゃなかったんだ。
実際にはそれも含めて、いろんなモノに突き動かされた結果だったから、同じ寂しさ、というのも無くはないのだけど。
でも、あれほど恐れていた同僚君を、放っておかなかったのは。
怖いと思う相手を、会いたくないと思う相手を、強制されたわけでもないのに、説得しようと思ったのは。
怒鳴られ衝突して涙まで流すほどに激するなんて、普段の私からは考えられないような行動をとったのは。
あなたが私にとって―――――――ただ一人の心の読めない人間だったから。
人間に興味のない私が、こんなにもあなたに執心していたのは。
あなただけが、私に、心の読めない『普通の人の世界』を見せてくれていたから。
同じ寂しさがあるとか、男さんが苦しんでいたから、なんて、全て後付けに過ぎない。
誰も彼もを薄い膜の向こう側に追いやっていた私の世界に、ただ一人、その膜を突き破って現れたあなたが。
どうでもいい人だなんて、その先がどうでなっても構わない他人だなんて。
私には思えなかったから。
あなたが居なければ、私は自分が人を拒んでいたなんて気付く事もなかった。
こうやって、ほんの少しだけでも変わることなんてできなかった。
気付かなければ平和だったかも知れない。
ずっと薄い皮膜の内側にいれば、傷は付かなかったかも知れない。
けど、後悔はしていない。
それはきっと、いつかは気付くべき事だったのだから。
それに―――私と似ているあなたがいると気付いたのだから。
やがて私達は飼育小屋に至る。
黒っぽい木材で建てられた壁を周り、植込みと接する裏側の入口を開けて中へ。
見慣れた細長い通路。
いくつかの扉が並ぶ汚れのこびりついた壁を左側に。
私達は、虎吉のいる部屋へと進む。
裸電球に照らされた道の中、不意に、同僚君が口を開いた。
「――――あのさ」
「は、はい」
「その―――ありがとうな」
「え?」
「いや、そのさ・・・・なんていうか・・・・・」
言葉を交わしながら私達は扉を開く。
奥にある金網に、渡り廊下や連絡通路を通して、学校の向こう側の端が僅かに垣間見える中庭が映っていた。
虎吉は、退屈そうにほし草の上に横たわっていたけど、私達が入ってくると嬉しそうに視線を向けてきた。
「なんていうか・・・・・まさか仲直りできるとは思ってなかった。」
「・・・・・・・・・・・」
「俺はさ。もう、ずっと一人だと思ってた。
男だけが、俺を本気で心配してくれたけど、あとはもう誰も味方になんてなってくれないと思ってた。
だから・・・つい、カッとなって、男まで切っちまったあの時は、もう駄目だと思ったんだ。
本格的に俺は一人になったんだって思った・・・特に、あいつが俺を旅行のメンバーから外したのを見た時はさ。」
「それは・・・・・・」
「うん。だから・・・実は、嬉しかった。
通訳が本気で俺を説得してくれた時は。
なんか今まで甘く見てたよ。最後には仲直りまで持ってけるんだから。すごいと思う。」
「は、はあ。それは、その、、、どう、いたしまして・・・」
「それにその、、、、さ、、、、あれ・・・・・・だったから、、、、、、」
「―――――――――――っ」
その瞬間、私は、自分の鈍さ加減を呪った。
本当に、心を読む、というのは解る事も解らなくさせるのだ、と。瞬間的かつ痛切に理解した。
けどそんな事は
そんな事はやっぱり一瞬で、あとはただ、ただただ顔が熱く鼓動が激しくなるばかりであった。
(そんな―――っ、、、、嘘、、、この人、、、心が読めないから・・・っ)
思い返せば、隠されていたモノが露わになってしまえば、成程それは、心あたりだらけだった。
いつか、彼とバスの中で乗りあわせた事があったけれど。あの時は確か、彼の方から話しかけてきたはず。
本当に私の事が嫌いなら、そんな事はしない筈だし、それ以前に近づく事もしなかったろう。
説得の時だって、何故あんなにも簡単に私の呼び出しに応じてくれたのか?
普段の関係からすれば、『なんで俺が行かなきゃいけないんだ』くらいは言いそうなのに、二つ返事で承諾していた。
そして、そして用務員さんが、裏方雑用さんがいつか言っていた・・・・
『ほら、アレっすよ。あの・・・危機的状況から来るドキドキ感を恋愛のドキドキと勘違いするっつー・・・』
虎吉は、いくら大人しくとも猛獣で、そこでの仕事はやはり緊張するものだという。
私は動物の心も読めるから全く怖くはないけど、同僚君は違う。
今までは畏れていたから、そんなこと考えもしなかったけど、やっぱりドキドキとしてはいたのかもしれない。
そしてそれを、その、、、、勘違いする、、という、、、別のドキドキ、、、と、、、
「その、、、なんだ、、、特に用はないけど、また、どっか喫茶店でも、、、さ、、、」
今まではイロイロとお互いに溝があったから、彼も私に冷たく当たるしかなかったのだろう。
どの時点で、気持ちが芽生えたのかは解らないけど、それをずっとひた隠しにしていたに違いない。
いや、答えを知ってしまえば、あの態度はむしろ、自分を誤魔化すための物だったのではないかとさえ思えてくる。
彼の心から伝わってくる感情を総合すると、そう言えなくもなかった。
けど、ここ最近、確かに私達の距離は急激に縮まっていた。
用務員さんの言っていた吊橋効果じゃないけど、一緒に緊張する状況を乗り越えもした。
しかも手を繋いだりしちゃったりも・・・・・・ああっ(/////)
(それに、俺達は似てるんだろ?文字通り、お似合い・・・だと思って、、ってなに馬鹿なこと言ってるんだよ俺は、、、)
口には出さなかったけど、同僚君は心のなかでそう言っていた。
それは、あの、虎吉の通訳。
ずっと私の耳に張り付いていたけど、いつの間にかどこかへ行ってしまった、あの『二人は似ている』というトラ吉の印象の通訳。
どうも、それは私の耳だけじゃなく、思わぬ所にも残留していたみたいだった。
「ガウ」
愉快そうなトラ吉の唸りが傍らから耳に届く。
『ともかく皆取り違えちゃうんっすねw緊張と恋愛のドキドキを。で、しかも男女二人で密室っすからwこれで何か起こらない方がおかしいんっすよww』
愉快そうな裏方さんの言葉、その記憶が頭に蘇る。
思わぬ事実は、私を大いに動揺させたけど。
なぜか心が跳ね上がった挙句に浮つき軽く。
なぜか『とても嬉しいです。私も実は―――キャッ(////)』などとおかしなことを私の心は言っておりました(///)
ええっと、つまり、ですね(////)
――――――残留した通訳は、もうずっと、消えてくれそうにありませんでした。はい(//////)
2008年2月
天気は快晴。
オシマイ。いやごめん、やっぱ続く。というのは我が邪気眼の見せる幻で本当は続かない。とか思ってると知らない内に続けられてるから油断できない。というのが出任せであって続くとも言い切れない。
あー、だから、その、なんだ?
→新ジャンル「通訳」スレのレス番92あたりに続くんじゃねえのっ?
ははんw若いっていいねえw
ってことよwだからここでお終いっつう話。そいじゃお休みっ。また明日っノシ◇◇◇
――空の境界第三章「痛覚残留」読書感想文――
【新ジャンル「通訳」残留】 (了)