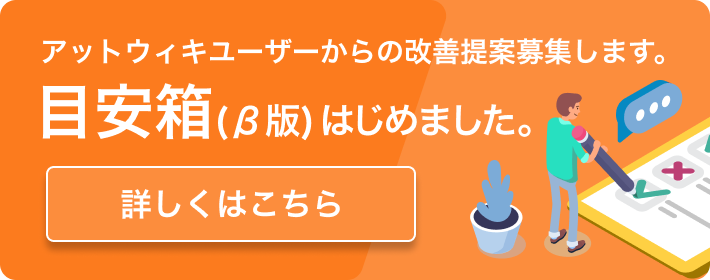それは当たっていた。ウィルは竜舎のいつもの房へハイビーを入れると、轡と鞍をはずした。その二つは、使い古されてはいるが、十二年前、ウィルが竜騎士を辞めたときのままだった。もちろんハイビーも。ウィルは、城で一番の竜を下賜されて、辞めた。
轡を見つめたまま、しばらくウィルは動かなかった。
「ゥルルルルル」
ハイビーが優しく鳴いた。朱い肌の竜がウィルの顔を覗き込む。
ウィルはその様子に気づいて顔を上げ、打ち消すように横に振った。
「はは、思い出に浸ってる場合じゃないな。餌やらなきゃな」
ウィルは、轡と鞍の手入れを済ませて、鞍は棚に置き、轡は自分の腰にぶら下げて、駅事務所へ向かった。
ポゥーン。ポゥーン。
柔らかい光の差す外廊下を歩いていると、祝砲が聞えてきた。きっと、お姫様の一行が近づいているのだろう。
気持ち悪いほど青い空を見上げて、ウィルは懐かしい名前を呼んだ。
「ミスト……」
もう十年も昔、ウィルは竜騎士だった。いまは、竜乗りと呼ばれている。竜騎士はまさしく竜を駆る騎士のことであり、各国の貴重な戦力であり、戦の代理人であった。
竜と人間が共存する世界であれ、国家は領土から成っている。大きな浮陸を分け合っている国家もあれば、たくさんの浮島から成る国家もある。浮陸は人類の帰る場所であり、竜の背に乗って一生を過ごすわけではない。
であればこそ、豊かな土地をなるべく多く所有することが、当然国家としての欲望だった。飛龍、浮竜、火竜、電竜、さまざまな竜を纏め上げた軍隊が動くとき は、他国との戦が常だった。国は軍を持ち、竜乗りを抱えた。その中で、特に飛竜の扱いに長け、自身も超人的な身体の能力を有するものが竜騎士と呼ばれる人 間だった。
ウィルは竜騎士だったころの思い出に浸り始めていた。ゆっくり、腰を落着けるところが必要だった。まだ開いていないバーの扉を押した。カウンターの中のオヤジが、広がった額の下からジロリとウィルを見る。
「まだだ」
「わかってるよ」
短いやり取りにかまう風もなく、ウィルはカウンターに腰掛けた。ここまでは外の喧騒が入ってこない。
グラスに注がれる透き通った茶色が、ウィルの心を慰めた。
いつしか、グラスの表面に過去が浮かぶ。
白銀に輝いていたはずの鎧が敵の返り血で赤く染まっている。普段はなんてことのない肩当がやけに重く感じる。血の匂いが鼻を突く。目を周りに転じれば、そこは王宮で、火こそ出ていなかったが、窓は砕け、そこかしこに死体が転がる、修羅場と化していた。
カチャリ。コツ。カチャリ。カチャリ。コツ。カチャリ。
玉座へ続く間の高い天井に踵と戦槍のマーチが響いた。
暗い色の両開きの扉を、篭手のついた両腕が押し開ける。
白い柱、白い壁に黄金の装飾。
謁見の儀の折には神々しいまでの雰囲気をかもし出す玉座の間は、今、朱に濡れていた。
玉座には一人の男が座っているのが見えた。さながら、幽鬼のように、やつれ果てた表情だった。
「遅かったじゃないか」
黒いマントを胸の前で合わせて玉座についていた男が言った。
「途中でしつこく誘われちゃってね」
白銀鎧の男が酒場で友人に謝るときのように言った。だが、槍を持つ手は疲労で震えていた。
玉座の黒い男が唇の橋を歪めて訊く。
「ハイビーは一緒じゃないのか?」
「置いてきた。疲れてるんだ。それに……」
白銀の男は深く息を吸い、長くはいた。震えが止まった。
黒い男は、白銀の男を昏い目で見た。
何かを言いよどんだ白銀の男は、槍を持ち替え、とうとう吐き捨てるように言った。
「見られたくないんだ」
玉座の男は頷いて、立ち上がった。
「はじめようか」
黒いマントの裾を割るようにして、血に汚れた刃が覗いた。黒い男はゆっくりとした動作で剣を顔の正面に掲げた。マントはまだ、身を守るかのように体を覆ったままだった。それはまるで、男の背中から闇がとりついているかのようだった。
槍の男が構えた。剣と槍。間合いの差は明らかだった。踏み込みさえ速ければ剣のほうが有利だが、お互いにそんな力は残っていなかった。
どうやれば、傷つけずに終わらせられるのか、白銀の男がそう考え始めた心を読んだように、黒い男が唇の端を笑みの形に変えた。
フワア。
黒いマントの前が開いた。黒い鎧の胸に抱かれた幼子がいた。白銀の男はその娘をよく知っていた。夢を見ているのだろうか、目を閉じている。黒い男の娘だ。
「おまえ……その子を盾にする気か!」
白かった男が叫ぶと、黒い男が間を詰めた。
「この娘は殺せまい。あいつの子だからな」
挑発するような台詞が逆に白銀の男を冷静にさせた。
人は変わる。
一瞬そう思った時、白銀の男は黒い男を敵と認識した。そう、介錯のために訪ねた親友ではなく一人の忌むべき敵として。
黒い男が槍の間合いの外から飛び込む。闇の疾風、かつての異名は衰えがなかった。音速よりも速いかもしれない突きが繰り出された。白銀の男は何も考えることができずに、ただ、突きを出した。
血と脂で彩られた白刃が交差する。
黒い男の剣が、白銀の男にまっすぐ向いて止まった。
白銀の男の槍の穂先が、黒い鎧の隙間、腕の付け根から差し込まれていた。
二人は数瞬、動かなかった。白銀の男の手には槍を伝わって、黒い男の鼓動が感じられる。突然、それは痙攣に代わった。
黒い男がむせ返り、端正な唇から血の塊が逆流した。
すると、黒い男は左腕に抱えた子供が自分の血を浴びないよう、避けたのだった。
「……!」
白銀の男が槍を放し、倒れる男から子供を抱き取った。
「血を、ガフ、浴びさせるわけには、いかん。絶対に」
黒い男は親友の顔に戻っていた。
その時、子供の目が開いた。地に倒れて見上げる男の瞳と幼い女の子の目は、やはり同じすみれ色の目をしていた。
轡を見つめたまま、しばらくウィルは動かなかった。
「ゥルルルルル」
ハイビーが優しく鳴いた。朱い肌の竜がウィルの顔を覗き込む。
ウィルはその様子に気づいて顔を上げ、打ち消すように横に振った。
「はは、思い出に浸ってる場合じゃないな。餌やらなきゃな」
ウィルは、轡と鞍の手入れを済ませて、鞍は棚に置き、轡は自分の腰にぶら下げて、駅事務所へ向かった。
ポゥーン。ポゥーン。
柔らかい光の差す外廊下を歩いていると、祝砲が聞えてきた。きっと、お姫様の一行が近づいているのだろう。
気持ち悪いほど青い空を見上げて、ウィルは懐かしい名前を呼んだ。
「ミスト……」
もう十年も昔、ウィルは竜騎士だった。いまは、竜乗りと呼ばれている。竜騎士はまさしく竜を駆る騎士のことであり、各国の貴重な戦力であり、戦の代理人であった。
竜と人間が共存する世界であれ、国家は領土から成っている。大きな浮陸を分け合っている国家もあれば、たくさんの浮島から成る国家もある。浮陸は人類の帰る場所であり、竜の背に乗って一生を過ごすわけではない。
であればこそ、豊かな土地をなるべく多く所有することが、当然国家としての欲望だった。飛龍、浮竜、火竜、電竜、さまざまな竜を纏め上げた軍隊が動くとき は、他国との戦が常だった。国は軍を持ち、竜乗りを抱えた。その中で、特に飛竜の扱いに長け、自身も超人的な身体の能力を有するものが竜騎士と呼ばれる人 間だった。
ウィルは竜騎士だったころの思い出に浸り始めていた。ゆっくり、腰を落着けるところが必要だった。まだ開いていないバーの扉を押した。カウンターの中のオヤジが、広がった額の下からジロリとウィルを見る。
「まだだ」
「わかってるよ」
短いやり取りにかまう風もなく、ウィルはカウンターに腰掛けた。ここまでは外の喧騒が入ってこない。
グラスに注がれる透き通った茶色が、ウィルの心を慰めた。
いつしか、グラスの表面に過去が浮かぶ。
白銀に輝いていたはずの鎧が敵の返り血で赤く染まっている。普段はなんてことのない肩当がやけに重く感じる。血の匂いが鼻を突く。目を周りに転じれば、そこは王宮で、火こそ出ていなかったが、窓は砕け、そこかしこに死体が転がる、修羅場と化していた。
カチャリ。コツ。カチャリ。カチャリ。コツ。カチャリ。
玉座へ続く間の高い天井に踵と戦槍のマーチが響いた。
暗い色の両開きの扉を、篭手のついた両腕が押し開ける。
白い柱、白い壁に黄金の装飾。
謁見の儀の折には神々しいまでの雰囲気をかもし出す玉座の間は、今、朱に濡れていた。
玉座には一人の男が座っているのが見えた。さながら、幽鬼のように、やつれ果てた表情だった。
「遅かったじゃないか」
黒いマントを胸の前で合わせて玉座についていた男が言った。
「途中でしつこく誘われちゃってね」
白銀鎧の男が酒場で友人に謝るときのように言った。だが、槍を持つ手は疲労で震えていた。
玉座の黒い男が唇の橋を歪めて訊く。
「ハイビーは一緒じゃないのか?」
「置いてきた。疲れてるんだ。それに……」
白銀の男は深く息を吸い、長くはいた。震えが止まった。
黒い男は、白銀の男を昏い目で見た。
何かを言いよどんだ白銀の男は、槍を持ち替え、とうとう吐き捨てるように言った。
「見られたくないんだ」
玉座の男は頷いて、立ち上がった。
「はじめようか」
黒いマントの裾を割るようにして、血に汚れた刃が覗いた。黒い男はゆっくりとした動作で剣を顔の正面に掲げた。マントはまだ、身を守るかのように体を覆ったままだった。それはまるで、男の背中から闇がとりついているかのようだった。
槍の男が構えた。剣と槍。間合いの差は明らかだった。踏み込みさえ速ければ剣のほうが有利だが、お互いにそんな力は残っていなかった。
どうやれば、傷つけずに終わらせられるのか、白銀の男がそう考え始めた心を読んだように、黒い男が唇の端を笑みの形に変えた。
フワア。
黒いマントの前が開いた。黒い鎧の胸に抱かれた幼子がいた。白銀の男はその娘をよく知っていた。夢を見ているのだろうか、目を閉じている。黒い男の娘だ。
「おまえ……その子を盾にする気か!」
白かった男が叫ぶと、黒い男が間を詰めた。
「この娘は殺せまい。あいつの子だからな」
挑発するような台詞が逆に白銀の男を冷静にさせた。
人は変わる。
一瞬そう思った時、白銀の男は黒い男を敵と認識した。そう、介錯のために訪ねた親友ではなく一人の忌むべき敵として。
黒い男が槍の間合いの外から飛び込む。闇の疾風、かつての異名は衰えがなかった。音速よりも速いかもしれない突きが繰り出された。白銀の男は何も考えることができずに、ただ、突きを出した。
血と脂で彩られた白刃が交差する。
黒い男の剣が、白銀の男にまっすぐ向いて止まった。
白銀の男の槍の穂先が、黒い鎧の隙間、腕の付け根から差し込まれていた。
二人は数瞬、動かなかった。白銀の男の手には槍を伝わって、黒い男の鼓動が感じられる。突然、それは痙攣に代わった。
黒い男がむせ返り、端正な唇から血の塊が逆流した。
すると、黒い男は左腕に抱えた子供が自分の血を浴びないよう、避けたのだった。
「……!」
白銀の男が槍を放し、倒れる男から子供を抱き取った。
「血を、ガフ、浴びさせるわけには、いかん。絶対に」
黒い男は親友の顔に戻っていた。
その時、子供の目が開いた。地に倒れて見上げる男の瞳と幼い女の子の目は、やはり同じすみれ色の目をしていた。