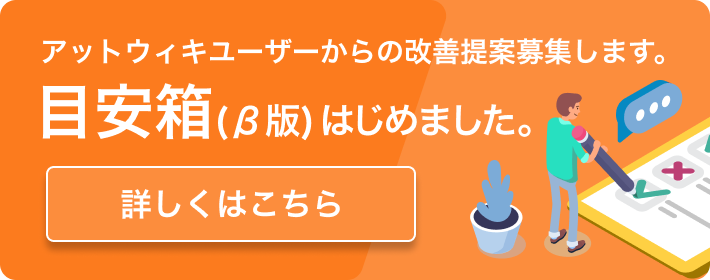「えー? 男が出来た? どうやって知り合ったわけ?」
髪を背後で無造作に束ねたエプロン姿の蘭は、菜箸を握り締めたまま電話の向こうの紗月に、とげとげしい声を浴びせた。
「そんな言い方しなくても。まだ、お付き合いしてるわけじゃないし」
「いいから、質問に答えなさい」
「え、ええ。えっと、最初は、その、趣味でよく覗いているドラマのサイトで、話が合うなって思ったの。そのうち、個人的にメールをやり取りするようになって」
紗月は小さな声で、嬉しそうな、それでいて困ったような声で答えていた。
「へー、あの電子機器オンチの紗月の口からサイトだのメールだのなんて言葉が出るようになるとはね。さすが21世紀ね」
「あなたが、連絡するのにメールくらい覚えろって言ったんじゃないの」
「ネット上で男引っ掛けるなんて高等な使い方を教えた覚えは無いです」
「ひ、ひっかけるなんて……そんなこと、思ってなかったんだけど」
いつもどおり紗月に怒鳴られると思っていた蘭は、そのトーンダウンの仕方に拍子抜けした。
……あらら、これは本物みたいねぇ……
「わかった。冗談よ。で、その相手の方とは会った事あるの?」
「うん。実はもう結構。最初はオフ会、っていうのかしら。みんなで会って」
「個人的には?」
「その後、その、彼から誘いが会って……」
「デートか?」
「デート、になるのかしら。最初はそのドラマに関係した歌手のコンサートに行って。それが1年位前かしら?」
「1年もか! それで?」
「その後も、月に一回くらい、その、コンサート行ったり、イベントに行ったりしていて」
ここで蘭は、必死で、「どこまで進んでるのよ?」という言葉を飲み込んだ。紗月のしゃべり方の雰囲気から、今回ばかりはそれを言ったらしゃれで済まないと踏んだのだ。
「紗月、それは、まごうことなき立派なデートです」
「やっぱり、そうよね? そうなるわよね……」
蘭は、電話のタイミング、紗月の様子から、この電話の意図が読めてきた。そして、紗月の態度に腹が立ってきた。
「で、紗月、あんたはそれがデートがどうかあたしに判定してほしくて電話をかけてきたわけ? じゃ、そういうのは全部デートです。以上。切るわよ。」
蘭はわざと突き放すように言ってみた。受話器の向こうからは予想以上に弱々しい、今にも泣きそうな紗月の声が帰ってきた。
「ま、待ってよ。切らないでよ。ごめんなさい、話が回りくどくて。でも、相談できる相手はあなたしかいないの……」
……やれやれ。こりゃそうとういかれちゃってるわね。小学生かっつーの。少なくとも35歳の相談じゃないわね……
蘭は、紗月の事がちょっとかわいそうになってきた。
「あーもう、わかった、わかった。切らないから。話を続けて」
「う、うん。それで、この間の日曜日も彼からお誘いがあって、それで彼が行きたいという水族館に行って、帰りにお食事をしたの。ここまではいつもどおりだったんだけど……」
紗月がモジモジしている様子は受話器のこちら側でも手に取るようにわかった。蘭は喉もとを2,3回強く掻いた。
「で、いつもと違うってことだから、なんかあったわけね。突然告白でもされちゃった?」
蘭はあきれ返ったような声で言った。
「う、うん……」
紗月は蚊の泣くような声で返事をしたまま黙ってしまった。予想できた反応ではあったが、蘭は背中が猛烈にかゆくなり、近くにあったおたまを取ると背中を掻き始めた。
「あーあー、そーっすかー、そりゃよかったわねー。幸せそうでなによりだわー」
蘭は口ではそう答えたが、ちょっと気を引き締めていた。
……ま、ここからが本題なんでしょうけど……
「あ、ありがとう。でも、私、どう答えれば良いかわからなくて」
……やっぱり……
蘭はため息をついて、イライラしたような口調で言った。
「そんな事だろうと思った。大体、予想はついてたわよ。そんなの、自分の気持ちに素直に答えればいいじゃない。紗月はどう答えたのよ? まさか何にも言わなかったわけじゃないでしょ?」
「えっと、彼には、そんなこと言われるとは夢にも思ってなかったから、全然考えられないし、今すぐお答えする事は出来ない。って、言ったんだけど」
紗月の曖昧な言葉を聞いて、蘭のイライラは沸点を越えた。
「紗月……あんた、本当にバッカじゃないの?」
「蘭、そんな」
「いい、あんたね、それは遠まわしに交際を断ってることになるのよ」
「わ、私、そんなつもりじゃ」
「紗月がそう思わなくても、相手はそう取るの! いい、相手はあんたと昨日今日会ったわけじゃないわよね? あんたと十分仲良くなってから告白するんだって1年間デートを重ねて、そろそろ大丈夫だろうと思ったから告白したんでしょうが。いまどき珍しい紳士じゃない。まぁ、気が小さいだけかもしれないけど」
「彼は、優しいのよ!」
「うっさい。んじゃ、その優しさに答えてやんなよ! やっとの思いで告白したのに、そんなこと夢にも思わなかった、考えられない、なんて言われたら、自分は男性として見て貰えてなかった、この1年は無駄だったって思うんじゃないの?」
「あ……」
「あ、じゃないでしょ。ったく、あんたそれでも国語教師?」
そう言ってから、それは関係ないかと蘭は思った。しかし、あえて訂正はしなかった。
「でも、私、あの時は彼の気持ちに応えられる自信がなかったから」
紗月の声はもう消え入りそうなほど弱々しくなっていた。蘭も少しかわいそうに思えてきたが、紗月の気持ちをはっきりさせるためにあえて心を鬼にした。
「だから、自信がどうとかじゃなくて、あんたの気持ちはどうなのよ? 彼氏の事を好きだと思ってるか、それとも、全然好みじゃないからパスなのか」
「えっと……」
「はっきりしなさい、はっきり!」
「う、うん。その、私、彼の事、好きなんだと思う。多分」
紗月が初めて自分の気持ちについて口にした。蘭はしてやったりと思ったが、まだ不満だった。
「多分ってのが弱いわね。じゃ、ちょっと検証しましょう。普通、好きじゃない男の誘いに、月1回とは言え、1年ものこのこついてく?」
「それは、どうなのかしら?」
「彼からのお誘いが全部あんたの好みにぴったりだったら、そういうこともあるかもね」
「う、ううん。そういうわけじゃ。正直、私にはよく分からなかったところも行ってるし」
「じゃ、何でついて行ったの?」
「んー、誘われてうれしいって言うのもあったし、彼が一緒なら大丈夫かなっていうのもあったかしら」
「で、実際行ってみた感想は?」
「彼といると、楽しいから、あんまり場所の良し悪しは気にならなかったわね」
「要するに、誘われた場所よりも彼とどこかに行くのが目当てってことじゃないの?」
「う、そうなるかしら?」
「少なくとも、好きでもない男ってわけじゃないでしょうね」
「でも、彼といると楽しいけど、あんまりドキドキはしない……それは好きって言うの?」
「うんうん。それはリラックスしてる証拠よ。会うたびドキドキしてたら死んじゃうって」
「でも、けっこう緊張はしてるのよ? 彼に格好悪いところをみられたくないって」
「なお良い状態じゃない。それこそ紗月が彼氏の事を異性として見てるってこと。男性から少しでも良く見られたいってのは女性として当然の心理よ。だいたい、夫婦でもない男女が一緒にいて緊張感がまるで無かったら、そりゃ最初からダメだわ」
……本当は夫婦でも必要なんだけどね、緊張感……
蘭は軽く首を振って気を取り直した。
「それから、告白された時はどう思った?」
「びっくりして……それからドキドキした」
「嬉しくはなかった?」
「その時はおどろいちゃって。でも、家に帰ってから、その時のことを思い出すと……自然に顔が緩んじゃって。治らなくなっちゃう。あ、やだ、また……」
「ふざけてんじゃないわよ。そこまで行ったら決まりじゃないの。あんたは彼氏が好きだ。告白されて、はぁ? とか思ったってんなら、迷わず断りなさいと奨めるとこだけど」
「そう。私は、彼のことが好き……」
「じゃぁ、善は急げということで、さ、彼氏に電話を」
「ちょ、ちょっと待って!」
紗月が急に大きな声を出したので蘭は受話器から耳を離した。
「く、くぉおお。いきなりバカ声ださないでよ」
「わ、私の気持ちははっきりしたかもしれないけど、でも、お付き合いするってなったらまた色々考えなきゃいけないでしょ? 簡単に答えていいものか……」
「あーん? なによ? まだなにか問題あるっての?」
「だって、彼……8歳も歳下なんだもの……」
「あんだって? もう一回、ちょっと大きな声で言ってみそ」
紗月の弱々しい声に、蘭は自分の耳を疑った。蘭は本当に聞き取れなかっただけなのだが、紗月はからかわれたと思ったらしく、怒ったように叫んだ。
「ええ? も、もう、蘭のイジワル。うーっ、だから、彼は私よりも8つ歳下の、27歳なの!」
次のページへ