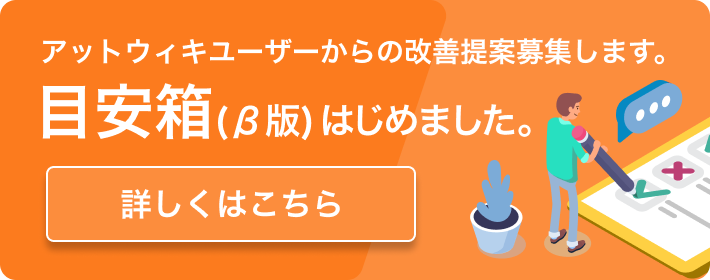バスカードで料金を払い終え、ステップから路上に降り立った私の体を、朝の冷たい空気が包み込む。
暖房のきいた車内で火照った体が、急激に冷やされて引き締まる。引き締められた勢い余って、震えが走ってしまう。
目の前には民家と道を隔てるザラザラした質感のブロック塀と、1m30cmくらいの高さのバス停を示す標識がある。
そこから顔を背けると、両脇に民家が立ち並ぶ道が、有るかないかの朝もやの中続いているのが見えた。
民家は瓦の屋根ありタイル張りの屋根あり四角い屋根あり、ブロック塀あり垣根ありでバラエティーに富んではいたが、どこにでもあるような民家、という点では共通していた。
道は、民家の中を突き進んで、50mもしないうちに塀に突き当たりT字路となっていた。
突き当りの塀の向こうには民家の屋根が立ち並び、さらにその先には新ジャンル学園の校舎がわずかに頭をのぞかせている。
このバス停から、歩いて数分程の所に新ジャンル学園があるのだ。
私はテクテクと無頓着に新ジャンル学園を目指した。
近づくにつれ学園から朝連をする部活の声が聞こえてくる。
まだ時間が早いという事もあってか、私の周囲にはほとんど人がいない。
朝連をする生徒はもっと早く登校するし、一般の生徒はもう少し遅く登校してくる。必然的に今の時間、学校周辺は過疎化する。
T字路を左に曲がり、次の十字路を右に曲がると、僅かにかすんだ空気の向こう側に、試立新ジャンル学園の校門と背後の校舎がそびえているのが見えた。
結局、辿りつくまでに私が出会ったのは、犬の散歩をするお爺さんと校舎周りをランニングする野球部の一群だけだった。
いつもなら私同様、早くに登校してきた一般の生徒がチラホラ見受けられるのに。今日は特に人が少ないような気がする。
・・・・・・やはり朝から冷えるのが原因だろうか?
・・・・・・それとも単なる偶然なのだろうか?
―――いや、偶然というのもあるだろうけど、やっぱり今日はいつも以上に寒い朝なので、
全体的に家を出る決意を鈍らされてしまった、というのはどうだろうか?
などと、とりとめのないことを考えながら、私は校門を過ぎ、昇降口に入り下駄箱で靴を履き替えた。そのまま教室には行かず、下駄箱のすぐ近くの女子更衣室へと足を踏み入れる。
更衣室は主に、運動部系の生徒達の着替え用として使用されている。
毎週私が着替えに入るころには、ロッカーに入りきらない、或いは初めからロッカーを使用することを拒否した各部員達の私物や制服で、足の踏み場もない。
その光景を見ると、なんだか更衣室が、私に使用されるのを拒否しているような気分になってしまう。
更衣室自身が、足の踏み場をなくすことでこれ以上の使用を拒んでいる。そんな感じだ。
なので許可は得ているのに、忍び込んで勝手に使っているような、変に落ち着かない気分で毎回着替えを済ませなければならなかった。
この日も私はすごすごと、なんとか床の露出している所を見つけて革製カバンとジャージの入った袋をおろし、着替えを始めた。
ジャージに着替え終わったあとは、髪の毛を汚れないように短く結う。最後に備え付けの姿身で軽くチェックをして、着替えを終わりとする。
私は荷物を持って更衣室をあとにした。
◇
昇降口で再び靴に履き替えた私は、右に折れてA棟とフェンスの間の狭い道を通り抜ける。路地の先には古びた飼育小屋の壁が見えた。
飼育小屋はトタンの屋根と背後の中庭に面した金網、他は木造の黒っぽい壁で構成されていた。私は、その前で立ち止まる。
―――飼育委員である私の仕事は、割り振られた日の三度の動物の餌やりと内部の簡単な掃除であった。
本来飼育小屋の管理は、学園内の諸事雑用と一緒に用務員さんが担っている。
飼育委員は活動の一環として、一部その仕事を手伝っているのだ。
だいたい二人から三人組で、週一程度のローテーションで当番が回ってくる。
動物のフンを掃除したり餌やりもするので、仕事は制服ではなくジャージで行う決まりになっていた。
私は飼育小屋の裏側に回り、バッグから前日の当番から渡された飼育小屋の鍵を取りだした。小屋の端に取り付けられたドアノブに鍵を差し込み、そのまま回そうとする、
・・・・・・・・・・鍵は、僅かな反発を受けながら少し進んだ後、そこで止まる。
このまま左に回せば鍵がかかってしまうだろう。
鍵は、開いていた。
私は、躊躇いがちに鍵をしまい扉を開いた。
中は、薄暗く細長い空間を黄色っぽい電球の光が照らしていた。
入口の正面には掃除道具やらなにやらが雑然と積まれている。ここは中庭から見ると、一番端の、一か所だけ金網ではなく木の壁になっている場所だ。
入口から右を見ると、細長く続く通路の片側に扉が三つ。どれも反対側の壁同様、黄土色の汚れがまだらにこびりついている。
扉は、一番奥の一つが細く開いていた。
「やっぱり・・・もう、来ていらっしゃるんですね・・・」
ため息とも呟きともとれる声を吐き出して、私は飼育小屋の中に足を踏み入れる。通路は外と変わらず冷え冷えとしていた。
◇
一番奥の扉を開くと、一人の男子生徒が黙々と作業をしているのが見てとれた。
脇にはバケツが二つ置かれ、片方には濁った水が半分ほど入っている。
もう片方はバケツというより樽に近い大きさで中は空っぽであった。空っぽのバケツには内側全体になにか白っぽいものが付着している。
彼は手に持ったデッキブラシをバケツに突っ込むと、床をこする。コンクリートの灰白色をした小屋の床は、3分の2が濡れて黒っぽくなっていた。どうやら、仕事は終わりが近いらしい。
「あの・・・」
声をかける。
「・・・・来てたのか」
彼はまず始めに開かれた扉、次に傍へやってきた私に目をやって、それだけ言うとすぐまた黙々と掃除を再開した。
束の間見えた顔は、鋭い目と皺のあとが消えていない眉間が、ただただ印象的だ。
その顔も今は、ブラシをこする反復運動を繰返す背中に遮られて見えない。
「あの・・・」
「なんだよ?」
遠慮がちに再びかけられた声に、彼の背中はとげとげしく返した。
私は、しばらく言いよどむ。デッキブラシのシャカシャカジャカジャカという音だけが、小屋の中に響いている。
10秒か、30秒か、或いはもっと長かったかも知れないし、その逆もあるかもしれない。ともかく、飼育小屋を覆う重苦しい空気のなか、私はやっと口を開いた。
「あの・・・もう餌はやり終えたみたいなので、バケツの方はかたしておきます」
「・・・・・・・・」
彼は何も言わない。いちいちつまらない事で煩わせるな。憮然とした彼の背中が、そう告げていた。
私のほうも、それ以上何も言わずに空の方のバケツを抱えて、出口へ足を運んだ。
去り際に、この小屋のたった一匹の住人が目に入った。
「おはよう。トラ吉」
小屋の金網と壁の境目の草を敷き詰めた場所で、行儀よく足を揃えて掃除の終わりを待つ一匹の虎。
黄色と黒の毛並みが織りなす顔は、私達二人の会話のぎこちなさにどうして良いかわからず困っているように見えた。
私は、安心させようと軽く微笑みかけながら、彼、虎吉の部屋をあとにする。餌である大量の牛肉が入っていたであろう、巨大なバケツを抱えて。
◇
ジャボボボボボボボボボボボボボボ………
ホースから出る水が、バケツの内側にあたり、くぐもった音をたてている。
私は道具置き場からホースと亀の子タワシを拝借して、飼育小屋脇の水道でバケツを洗っていた。
さすがにこの季節に温水の出ない水道を扱うのは辛い物で、何度も途中で作業を中断し、濡れた指先を持参したタオルで拭かなければならなかった。
途切れがちで遅々として進まない作業のなか、冷たい冬の空気と水のせいで私の手は真っ赤に染まってしまっていた。
それでもなんとかバケツの内側にこびりついた脂の大部分を落として、後は水で流すだけの所までこぎつける。
水気を多量に吸い取ったせいで湿り、本来の用をなさなくなったタオルを力の限り絞る。
ボタボタと多量の水滴がタオルから滴り、私の指の間を濡らした。
冷たさが体の芯まで伝わってきて、普段とは違う奇妙な震えが走った。急いでタオルをほどき、私の手についた水気をぬぐう。
それで目に見える水分はぬぐえたものの、まだ私の掌と十指は湿った感覚を訴えてくる。
その感覚をなんとかしようと、両手をこすりあわせた。しばらくやっていると落ち着いてきたので、仕上げとしてバケツの内側を水で洗い流す作業を開始した。
バケツの内側に反響する音を聞きながら、私は先に来ていた男子生徒――飼育委員で同じ仕事を同じ曜日に割り振られた、つまり同僚――の彼の事を思い出していた。
私は彼のことが苦手だった。
複雑な心を持った人間全体を『なんとなく』好きになれないのとは違い、同僚である彼は『はっきり』と苦手であった。
未だに名前を教えあっていないのもそのせいだろう。
彼が私を呼ぶ時は他の皆に倣って『通訳』のあだ名で。
私から彼を呼ぶ時は『同僚君』と。
つまりは、私と同僚君の関係はそれで支障のない程度のものという話だった。
―――初めて彼と出会ったとき、軽い眩暈を感じたのを今でも覚えている。
飼育委員は同じクラスの者同士で仕事を割り振られる。なので、彼とは同じクラスであった。
とは言っても、初めての委員会で顔を合わせるまで、話したことは一度もなかった。それでも、遠目から明らかに彼は近寄りがたいモノを持っているのがわかった。クラスの誰も近づけまいとする、誰とも溶け合おうとしない、そんな態度を前面に押し出しているのが感じられた。
それ以上の事は分からなかったけど、少なくとも彼がクラスから浮いていて孤立しているのは確かだった。
初めて彼と顔を合わせた委員会での席。毎月飼育委員会が開かれる一年五組の教室。
担当の曜日と仕事の内容が割り振られて、これから仕事をともにする相手として同僚君の方から私の席の隣にやってきた。
そこで初めてまともに彼を見た私は、愕然とした。
そんな人がいるなんて、それまで一度も、考えたことさえなかった。
けど実際に、どうしようもないほどの存在感を伴って、『そんな人』は私の前に現れてしまったのだ。
彼の心は、表層の僅かな部分を除いて全く読めなかった
普通、私が意識を向けると、人によって多寡の違いはあるけど、相手の心が流れ込んでくる。
また私自身が強く思えば、ある程度心の深い所までは読むこともできる(ただし、人間の心は沢山の要素が幾層にも分かれて複雑な構造となっているので、そうするのは非常な疲れを伴う。当然、そこまで覗くことはまずない)。
こちらから読もうと働きかけなくとも、強い感情や思いは自然とこちらに流れ込んでくる。
私が通訳をしている理由は基本そこにあったし、人の心の有り方はそれが標準、というより原則である、というのが私の認識だった。
なのに、それに反して彼の心は、全力で意識を集中させても表層の部分をおぼろげに感じるくらいだったのだ。
その事実に、私は軽く眩暈を覚えた。
確かに単純に忘れていたり意識していない事柄や、誰にも悟られたくない、と強く思った事柄はそう簡単に読むことはできない。
彼の場合、後者の部類に入るものだったが、それにしても普通ではなかった。
いったいどれほど強く思えばここまで壁を作れるのだろう?
私の読心に気がついてもいないのに。ただ、有るだけで、ほとんど心を読ませない。
ひょっとしたら彼は、世界中の人間が全員敵に回ったとしても、その鋭い目と眉間のシワの跡が張り付いた顔で平然としていられるのかもしれない。
そう思えるほどに強く強く、他人を拒絶していたのだ。
自分の心の壁の内側に誰ひとりとして入れないという覚悟。ただただそれだけが私に伝わってきた。
私には彼が、なにか人間とは違う別の存在のように思えた。
自分にも心を読む、という普通ではない力がある。けどその程度では、彼と比べらば普通の人と大して変わらないような。
それほどに尋常ならざるモノを彼から受け取っていた。
正直に打ち明けると、私は彼が怖かった。彼に恐れを抱いていたのだ
出来れば一緒にいたくは無かった。一緒にいれば何をされるという訳でもなかったけど、心が読めないという事実。その一点だけでも私が彼を恐れる理由は十二分に過ぎた。
そう。今まで、特に頓着することなく人と接してきた。けれど、初めて苦手な人間というものが現れたのだ。
そんな私の感情を彼は感じ取っていたのだろう。いや、そもそも人に対しては誰でもああいう接し方をするのかも知れない。
ともかく私に対する彼の態度も、あまり好ましいものではなかった。ほとんど口をきくことはなく、たまに交わす言葉は大抵が刺の生えた物か事務的な内容の物だった。
初めて心の読めない相手と出会い、私自身どうして良いか分からない苛立ちを抱えていたのも、状況を悪化させていたのかもしれない。
動物が好きでこの委員に立候補したけど、彼の存在が仕事に苦痛を与えていた。
毎週、彼が風邪か何かで休まないものかと淡い願望を胸にしていた。
そうすれば、虎吉と思う存分触れ合えるのに、と。
そこまで考えてふと足元に目をやると、一抱えもあるバケツに水が半分近くまで溜まっていた。
遠くの方では登校してくる一般生徒達のざわめきが響いている。
どうやらぼんやりとし過ぎてしまったらしい。
◇
「あの・・・・っ、すみませんっ。ついぼんやりと考え事を――」
そう言いながら、慌てて飼育小屋のトラ吉の部屋の扉を開く。
道具はすでにかたされて、小屋は普段通りの様相を呈していた。
トラ吉が突然開いた扉に驚き、びくりと身を震わせてこちらを見る。
同僚君はというと、すでに学ラン姿に着替えて虎吉を挟んだ金網の向こう側にいた。仕事を終えて虎吉相手に戯れていたらしい。
「別に構わない。もう帰るつもりだったし」
それだけ言うと彼はトラ吉から視線をそらし、こちらからは死角の部分へ身をかがめる。
地面に置いた荷物に手を伸ばしているのだろう。
トラ吉は名残惜しそうにその姿を目で追っていた。
私は心が読めるので虎が相手でも危険を敏感に察知できる。なので、ここでの掃除や餌やりも別にどうという事はない。
ほんのちょっとでもトラ吉に恐ろしい考えが浮かんだら、一目散に逃げればいいだけの話だ。
それに、トラ吉は虎とは思えないほど大人しく、こうやって全く隔てる物がない状態でも人を襲おうという気を起こしたことがなかった。
しかし、同僚君や他の飼育委員はよくここでの掃除が務まると思う。怖くはないのかとたまに不思議になる。
けど、校長が幼稚園児と同年齢にしか見えなかったり、虎を飼育することも許してしまうような学園なのだ。深く考えたら負け、という奴なのだろう。
同僚君や他のみんなは動物好きだから、心が読めなくてもトラ吉が安全だと直感的にわかるのだ、という事にして今のところは自分を納得させている。
「それじゃ。また昼に」
短く挨拶をして、同僚君は踵を返すが、
「あの――その事なんですが……」
私は、この場から立ち去ろうとするその背中に向かって声をかけた。
「ん、」
「その、朝は同僚君の方が早く来てほとんど全部やってくださったので、昼は私一人に任せていただけないでしょうか?
えと・・・・・・放課後の方はいつもどおりでいいので」
言いながら私は奥に足を進め金網に近づく。彼の方もこちらを振り返り、視線を向けている。
私が近づいた結果、二人の距離は間に金網を挟んだ状態で1メートル程となった。
「いや、いいから。」
私の申し出をつっけんどんに彼は返し、再び飼育小屋から離れようとする。
「いえ。でも、私、今朝は遅れてしまってほとんど何もやってないですし。なんだか悪いです」
「いいよ別に、気ぃ遣わなくったって。そもそも通訳が遅れたんじゃなくて、俺が早く来すぎただけだから。」
「けど、それじゃあ私の気が済みません。」
彼は譲らなかったが、私も引くつもりはなかった。
これが普通の人が相手だったら、私もここまで我を通そうとは思わなかっただろう。
何かを主張するのは相手の反感を買いやすい。
心を読んで雰囲気が悪くなりそうならば、すぐに自分の方から道を譲るのが普段の私だ。
誰かの敵意や反感を買って酷い目にあった人間はごまんと見てきたし、そんなことで心を煩わせたくはない。
心を読んだ上で、誰かの意見と対立しない領域で自由にすればいいのだし、それ以上を望むのはわがままというものだ。
けれど、同僚君の場合はそうはいかない。彼の心はガードが堅いから、こと普段から心を読んで対処している私には引き際が分からない。
特に今回は彼に対する苦手意識がそれに拍車をかけていた。
『彼と一緒に仕事をしたくない』
毎週、飼育小屋へ向かうたびに湧き上がるその想いが、今の私を突き動かしていた。
そもそも良く考えれば、大したメリットはなく、むしろ同僚君との関係をさらに悪化させる恐れもあるのだ。
けれど私は絶対に、昼休みに来て欲しくはなかった。
ここまで拘る明確な理由はなかった。ただ単純に、彼の反発に対して生来の意固地な性分が鎌首をもたげていたのだ。
「あのさ!!」
彼が、いつもの低く静かな語調を突然荒げたのは、『来るな』『行く』の問答が堂々巡りを始めた矢先だった。
大声に、反射的に身をすくませてしまう。肩が跳ね上がった所為で金網から手が離れる。
そこで初めて私は、自分が金網を掴んでいたのに気がついた。知らず熱くなっていたのだ。
「あのさあ、通訳はさ、遅れて悪いと思ってんだろ?」
「…………」
「………………聞いてる?」
「あの、その、えの、、、じゃなくて、えっと……はい」
「俺に対してすまないと思ってんだろ?
だったらなんで俺が良いって言ってんのに反対してんだよ?それさ、おかしいだろ?」
彼は、明らかに怒気をはらんだ口調と射るような視線をこちらに向けている。
私は、ただただ怒鳴られたショックで、半分放心したように受け答えをしていた。
―――今なら、簡単に催眠術にかかってしまうかも知れない。
体中の力が抜けて筋肉がこわばるような感覚の中、そんな無意味な思考が脳裏に浮かんで瞬時に消える。
「だいたい飼育委員は最初に決まったメンバーで作業しろって決まりじゃねーか。勝手に破っていいのかよ?」
「………いえ」
「俺も一人でやりたいけど我慢してるんだよ。お前さ、勝手なこと言うなよ?」
「………すみません」
ほとんどなじるようにして言う同僚君に、私はうつむきながら必要最低限の返答だけをボソボソと口にしていた。
こちらが譲歩するべきところをわきまえず、相手の神経を逆なでし、怒りの分水嶺を越えてしまったという事実が、私の心を酷く陰鬱で沈痛なものにしていた。
目の前ではっきりと非友好の態度を表す彼を見て、自分が相手に嫌われているのをまざまざと実感する。
そのたびに心が一段、また一段と落ち込み暗くなっていくのがわかった。
彼の言葉、いや、それ以上に自分を拒絶する彼の存在そのものが、私の心に対する重しになっていたのだ。
私が同僚君を苦手な理由がこれだった。
彼を前にすると、言葉を発したく無くなってしまう。
普通の人は心が読めるから、私がその心の通りに動けば摩擦は起きなかった。まあ時には、運悪く私の言動が裏目に出てしまい、相手が気分を害してしまう事もあったけれど。
でもそういう場合だって、私はそれを察知できたのだ。
だから相手が私に抱いた悪感情はその心中にとどまって終わり、それ以上悪化したり表出したりなんてしなかった。
物心ついた頃から、そうやって人と付き合ってきた。
つまり人との関係に悩む、という事自体が私にとっては理解の外側の出来事だったのだ。
それはちょうど、戦争や飢餓が蔓延する地域に対して抱く感情に似ていた。
知識として知ってはいても、自分の事としては未体験。いくら想像をめぐらして見ても、当事者の気持ちに辿り着いているかどうかは結局わからない。
けれど、長らく他人事だった対人関係の悩みは、同僚君が現れたことで私自身の物ともなってしまった。
心が読めない彼には、今まで私がとってきたやり方が通じないのだ。
それでも私達は飼育小屋で一緒に仕事をしないといけない。当然、私達の間には摩擦が起こった。
―――今日はどちらが餌をやるか、とか、
―――鍵はどちらが預かるか、とか、
―――会話中の何気ない一言で、とか
すれ違いの火種は、後になって思えば本当に下らない些末な事柄ばかりだった。
大抵はどんなに酷くとも、今回のように私が同僚君になじられて終わりなので、喧嘩や対立といった物騒な状況に陥ることはなかった。
だけど、今まで人と付き合って感じた事のないような息苦しさが、二人の間に横たわっているのも事実だった。
まるで飼育小屋の中だけ空気が薄くなっているような、しかもその中に気持ちを落ち込ませる成分も混入しているような。
普通は誰だって嫌いな人間はいるのだから、こんな経験は、数え上げたらきりが無いだろう。いちいち気にしていたら身が持たないだろう。
でも、誰かと衝突した事のない私にとってそれは、とても辛いものだった。
自分の何気ない一言で彼の怒りを買ってしまうかもしれない。
どうでも良いような事で、嫌な思いをしなくてはいけないかもしれない。
会話の中で引き際がわからない
どんな言動を取るべきかがわからない
それが――――――こんなにも息苦しくて気持ちを萎えさせる物だなんて、知らなかった
極力余計な事は喋らない。
心が読めない相手を前にして摩擦を起こさない為に私は、自然とそういう風に反応するようになった。
彼を前にすると、全身が萎えるような感覚と共に、今まで当たり前のように使っていた『言葉』を発したく無くなってくるのだ。
それは、本当に辛くて嫌な気分がすることで――
だから私は、飼育委員の同僚である彼が、苦手だった。
「………………すみ……ません」
同僚君くんの言葉に対する何度目かの相槌。
それが、変に涙ぐんでいるように聞こえて、ハッとした。
謝罪というよりは、早くこの状況が過ぎ去るのを願う祈りの言葉。
いろいろな想いを心に渦巻かせつつ、それを繰り返しているうちに、知らず鼻孔から目にかけて熱い物が溜まっていたらしい。
それがまた、不意を突くように唐突に声に出たので、私自身吃驚していた。
同僚くんの方はというと、明らかに気まずそうな顔で視線をそらしている。
さしもの彼も、女の子を泣かせる趣味はなかったようだ。
「いや、あの…俺もついカッとなって怒鳴ったりして………悪い……」
同僚くんは申し訳なさそうな顔をして、困惑気味に頭をかいていた。
涙声を出すまで追いつめてしまった自分自身を、恥じているような表情をしている。
先程までの調子が嘘のような、しおらしい、とさえ言えそうな姿を見ていると、ムクムクと申し訳ない気持ちが湧きあがってきた。
なんというか、涙腺が緩すぎるのは女性の欠点だと思う。
『涙は女の武器』なんて言ったりするけど、なんだか卑怯な感じがして私は嫌だし、今みたいに自分の意思に反して相手を翻弄してしまうのは望ましくないとも思う。
「いえ、その…私も無理にわがまま言って………すみません……」
私も、相槌のように言っていた先程までの言葉とは違う、本心からの『すみません』を口にする。
「ああ。じゃあ、また昼に。」
「はい。それではお昼に、また。」
お互い、なんとか落ち着いてやっと別れの挨拶を交わす。
飼育小屋の金網を通して見えるA棟とB棟が作る渓谷のような風景。
ふと眼をやると、私が来た時にかかっていた朝もやは既に消え去っていた。代わりに今では登校してきた生徒達の活気に満ちた話し声が、到る所で反響している。
そんな風景を背後に抱え、同僚くんは今度こそ踵を返して去ろうとした。が、その中途で動作をやめて、こちらを振り向く
「その……………もう一回言うけど、さっきは悪い。もうちょっと言い方があったかも知れない」
「は、はい。あ、いえ、私のほうこそ・・・すみません。」
「ガウ………」
彼は、心底済まなそうにこちらに謝罪する。
私も、その言葉に相応しい反応を返す。
隣で虎吉が、呟くような感じで喉をならす。
動物特有の、簡単な単語の羅列と、普段私達二人が醸し出す険悪な空気に対する不満の感情が私の心に流れ込んできた。
私はそれを
通訳と呼ばれるその名の通り
誰かの強い感情を感じ取ると通訳せずにはいられない
その習慣に突き動かされるまま
普段と何一つ変わらぬ調子で、何一つ感慨や感情を持たず条件反射的に
羅列を文章に、感情を言葉として、人間が言うように意訳して――――――――――――――
「あの、彼は、虎吉も『もうちょっと仲良くしてほしい。二人は似た者同士なんだから・・・』と言っております。」
すでに飼育小屋から離れてA棟とB棟の間を進んでいた同僚くんに、通訳の内容がはっきりと聞こえたかどうかは定かではない。
ただ、彼は背中を向けたまま軽く右手をあげて、反応した。
同時に、一時限目が10分前に迫ったことを知らせるチャイムの音が響き渡る。
―――けれど、私の耳には
―――今しがた自分の口からこぼれるようにして放たれた『通訳』と、
―――最近読んだ小説に出てくる、『痛みが残留する』という話のイメージが、
予鈴を圧倒して響いていた。