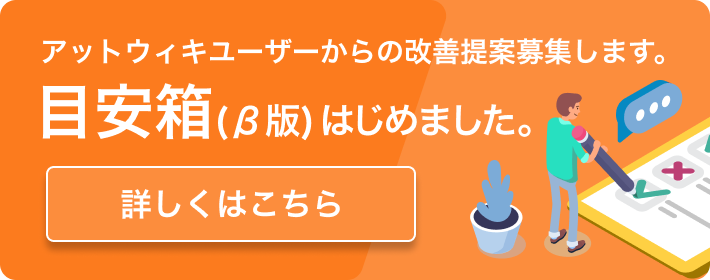3.自分自身/PAST
「私は・・・、ほら、大丈夫だから」
――あれ?アイツ・・・。
夢の中で俺は“目を覚ました”。
目の前に広がるのは幻想的なものでも何でも無い、とても現実的な風景と、その中に一人たたずむ金髪の女の子。
「本当はいけないんだけど、今日だけちょっとルール違反ね」
女の子は冗談っぽく笑って、肩をすくめた。
そしてその笑顔に気付く。
――嗚呼、俺、御前の笑顔を良く知ってる気がする・・・。
こうやって夢の中で女の子に話しかけると、聞こえたのか、反応して苦笑してくれた。
なんでこんなに知ってるのに、思い出せないんだろう。
――なぁ、御前、俺の・・・なんだ?
問いかけに彼女は表情から今までの笑みをなくして、悲しそうに言う。
「ごめんね、まだ思い出しちゃいけないんだよ、秋」
現実的な風景、沢山の建物がならんだ街中の流れる人込みの中に一人立ち尽くす彼女と俺の間の距離は、こんなにも近いのに何故かとても遠く感じられた。
「でも、嬉しいんだよ?微かでも覚えていてくれて・・・」
女の子の表情が明るくなり、風が吹いた。
ショートカットの金髪の髪が風に乗り、なびいて何かに気づいたように彼女は続けて言う。
「あ、そろそろ行かないと」
――また会えるよな?
まだ話していたい、この懐かしい感覚を続けていたい。そう思った俺は思わず聞いてみた。―――彼女は俺の好きな笑顔で答えてくれた。
「うん!何時になるかは解らないけど、また会えるから!」
彼女は嬉しそうに手を振って叫んだ。
それを見て距離が離れていくのに気付く。でも俺の体は前には進まない。
そして俺が無意識に口にした。
――愛里、それは現実世界での話しか?それとも夢の中の話か?
この問いに、彼女は驚いた反応を見せて、そして俺の意識は夢から離れた。
――あれ?アイツ・・・。
夢の中で俺は“目を覚ました”。
目の前に広がるのは幻想的なものでも何でも無い、とても現実的な風景と、その中に一人たたずむ金髪の女の子。
「本当はいけないんだけど、今日だけちょっとルール違反ね」
女の子は冗談っぽく笑って、肩をすくめた。
そしてその笑顔に気付く。
――嗚呼、俺、御前の笑顔を良く知ってる気がする・・・。
こうやって夢の中で女の子に話しかけると、聞こえたのか、反応して苦笑してくれた。
なんでこんなに知ってるのに、思い出せないんだろう。
――なぁ、御前、俺の・・・なんだ?
問いかけに彼女は表情から今までの笑みをなくして、悲しそうに言う。
「ごめんね、まだ思い出しちゃいけないんだよ、秋」
現実的な風景、沢山の建物がならんだ街中の流れる人込みの中に一人立ち尽くす彼女と俺の間の距離は、こんなにも近いのに何故かとても遠く感じられた。
「でも、嬉しいんだよ?微かでも覚えていてくれて・・・」
女の子の表情が明るくなり、風が吹いた。
ショートカットの金髪の髪が風に乗り、なびいて何かに気づいたように彼女は続けて言う。
「あ、そろそろ行かないと」
――また会えるよな?
まだ話していたい、この懐かしい感覚を続けていたい。そう思った俺は思わず聞いてみた。―――彼女は俺の好きな笑顔で答えてくれた。
「うん!何時になるかは解らないけど、また会えるから!」
彼女は嬉しそうに手を振って叫んだ。
それを見て距離が離れていくのに気付く。でも俺の体は前には進まない。
そして俺が無意識に口にした。
――愛里、それは現実世界での話しか?それとも夢の中の話か?
この問いに、彼女は驚いた反応を見せて、そして俺の意識は夢から離れた。
/
目を覚ます。
自分の部屋でないのに直ぐ気付いて、此処が榊原の家の中だということを思い出した。
そして、俺は何となくだが彼女を覚えていた。
水城愛里――。
俺の中で、一番親しかった存在。
「恐らくは親友か恋人関係・・・」
そんな事を口にして、ハッとした。
「あああああああ!」
思い出したように叫んで、
「しまった、コンビニから買ってきた俺のプリン冷やすの忘れてたああああ!」
急いで食卓に突撃するのだ、無謀な格好で。
そしてその後に食卓で遭遇する榊原から変体呼ばわりされ、嫌な場所に蹴りが入るのは言うまでも無い。
ちなみにプリンは榊原に食われていたというオチ。
自分の部屋でないのに直ぐ気付いて、此処が榊原の家の中だということを思い出した。
そして、俺は何となくだが彼女を覚えていた。
水城愛里――。
俺の中で、一番親しかった存在。
「恐らくは親友か恋人関係・・・」
そんな事を口にして、ハッとした。
「あああああああ!」
思い出したように叫んで、
「しまった、コンビニから買ってきた俺のプリン冷やすの忘れてたああああ!」
急いで食卓に突撃するのだ、無謀な格好で。
そしてその後に食卓で遭遇する榊原から変体呼ばわりされ、嫌な場所に蹴りが入るのは言うまでも無い。
ちなみにプリンは榊原に食われていたというオチ。
「カザマくん」
朝の食卓で、命さん、榊原、アレックスと俺の4人で囲んだちゃぶ台に並ぶ朝食を挟んでアレックスが唐突に声をかけてきた。
朝食にしては豪華で味も間違いなく店を出せる程の美味さ。
和風式にご飯と味噌汁に沢庵、そして焼き鮭。普段、朝は食欲が無い俺も流石にこの料理を目の前にしてよだれを垂らさずには居られなかった。
これを作った本人ことアレックスはエプロンを着用したまま食卓のちゃぶ台についている。
「昨日、カエデちゃんから聞いたんだけど、支援武器を持っているんだって?」
聞かれて、俺は昨日の鍵を思い出した。
榊原は、常に持っていなさい!というので今もポケットにある。
それを俺は取り出して向かい側に座るアレックスに見せた。
「これの事だろ?」
「ちょっと見せてくれないかな?」
別に拒否する理由もないので俺はその鍵をアレックスへと手渡した。
受け取るなり食事中なのに片手にお箸を握ったまま鍵と睨めっこをはじめだしたアレックスを榊原はあからさまに嫌そうに見た。
この支援武器と呼ばれる言術者なら誰もが持つという武器が俺の家の倉にあった事、それが導き出す一つの真実は、昔の倉の所有者が言術者だった事である。
榊原の話では言術者の人口は以外と多いらしく、世界人口の1割3分は言術者だと言う。
1割3分というのは少ない数字に聞こえるが、これが以外と多い方らしい。
もし世界が1億人だったとしたら少なくとも1千3百万人が言述者といえば確かに多く聞こえる。
言術者達は基本的に表の社会に彼らの力を出す事は無い。さらに言術者は、他の言術者を見てもその人が言術者だという事を証明する方法が無いらしい。
つまり、実は近所のおばさんが言術者でしたー、なんて事は良くあるらしい。おばさん限定でなくても良いのだけど・・・。
「はい、ありがとう」
「ん?ああ、もう良いのか?」
睨めっこが終わったらしく、アレックスはこの支援武器について何も言わぬまま俺に返してくれた。
そして俺が鍵をポケットにしまう頃には榊原は朝食を終えちゃぶ台の側から離れていった。
朝の食卓で、命さん、榊原、アレックスと俺の4人で囲んだちゃぶ台に並ぶ朝食を挟んでアレックスが唐突に声をかけてきた。
朝食にしては豪華で味も間違いなく店を出せる程の美味さ。
和風式にご飯と味噌汁に沢庵、そして焼き鮭。普段、朝は食欲が無い俺も流石にこの料理を目の前にしてよだれを垂らさずには居られなかった。
これを作った本人ことアレックスはエプロンを着用したまま食卓のちゃぶ台についている。
「昨日、カエデちゃんから聞いたんだけど、支援武器を持っているんだって?」
聞かれて、俺は昨日の鍵を思い出した。
榊原は、常に持っていなさい!というので今もポケットにある。
それを俺は取り出して向かい側に座るアレックスに見せた。
「これの事だろ?」
「ちょっと見せてくれないかな?」
別に拒否する理由もないので俺はその鍵をアレックスへと手渡した。
受け取るなり食事中なのに片手にお箸を握ったまま鍵と睨めっこをはじめだしたアレックスを榊原はあからさまに嫌そうに見た。
この支援武器と呼ばれる言術者なら誰もが持つという武器が俺の家の倉にあった事、それが導き出す一つの真実は、昔の倉の所有者が言術者だった事である。
榊原の話では言術者の人口は以外と多いらしく、世界人口の1割3分は言術者だと言う。
1割3分というのは少ない数字に聞こえるが、これが以外と多い方らしい。
もし世界が1億人だったとしたら少なくとも1千3百万人が言述者といえば確かに多く聞こえる。
言術者達は基本的に表の社会に彼らの力を出す事は無い。さらに言術者は、他の言術者を見てもその人が言術者だという事を証明する方法が無いらしい。
つまり、実は近所のおばさんが言術者でしたー、なんて事は良くあるらしい。おばさん限定でなくても良いのだけど・・・。
「はい、ありがとう」
「ん?ああ、もう良いのか?」
睨めっこが終わったらしく、アレックスはこの支援武器について何も言わぬまま俺に返してくれた。
そして俺が鍵をポケットにしまう頃には榊原は朝食を終えちゃぶ台の側から離れていった。
「やっぱり、“草薙の剣”だった?」
風間秋が食卓を出て、部屋に七原とアレックスだけが残った頃、七原が切り出した。
「ああ、まさか再び目にするとは思わなかったよ・・・最後に見たのは何時だったかな・・・。今の“草薙の剣”は時代に合わせて姿、形を変えているみたいだけどね」
話に持ち出された“草薙の剣”。それは神話の中で登場する三種の神器の一つとされていて、それは秋が持っている鍵の事である。
アレックスは真剣な表情で腕を組んで何かを考えていた。
一方、七原は少し懐かしそうな表情で、
「あの剣が再び現れたと言う事は、やはり風間君は無関係でただ巻き込まれた、って事にはなりそうには無いのね」
「やはり彼の魂はヤマトタケルの生まれ変わりかな、彼が月蝕を見つけたのは偶然ではなく運命なんだろうね」
七原命は食後の緑茶をゆっくりと口にして開いたままも襖から空を見上げた。
「私達は何をしてあげられるかしら・・・」
「草薙の剣があるなら、伊邪那岐(イザナギ)もいるはず。僕等に出来る事は伊邪那岐の企みを阻止する事だけさ」
ふっと力を抜いて組んでた腕を下ろすとアレックスは立ち上がり襖に手をかけ七原と同じように空を見上げた。
「今日も天気が良い。外にでかけようかな」
晴れた空に向かい微笑んだアレックスは七原に微笑みをうつして言った。
風間秋が食卓を出て、部屋に七原とアレックスだけが残った頃、七原が切り出した。
「ああ、まさか再び目にするとは思わなかったよ・・・最後に見たのは何時だったかな・・・。今の“草薙の剣”は時代に合わせて姿、形を変えているみたいだけどね」
話に持ち出された“草薙の剣”。それは神話の中で登場する三種の神器の一つとされていて、それは秋が持っている鍵の事である。
アレックスは真剣な表情で腕を組んで何かを考えていた。
一方、七原は少し懐かしそうな表情で、
「あの剣が再び現れたと言う事は、やはり風間君は無関係でただ巻き込まれた、って事にはなりそうには無いのね」
「やはり彼の魂はヤマトタケルの生まれ変わりかな、彼が月蝕を見つけたのは偶然ではなく運命なんだろうね」
七原命は食後の緑茶をゆっくりと口にして開いたままも襖から空を見上げた。
「私達は何をしてあげられるかしら・・・」
「草薙の剣があるなら、伊邪那岐(イザナギ)もいるはず。僕等に出来る事は伊邪那岐の企みを阻止する事だけさ」
ふっと力を抜いて組んでた腕を下ろすとアレックスは立ち上がり襖に手をかけ七原と同じように空を見上げた。
「今日も天気が良い。外にでかけようかな」
晴れた空に向かい微笑んだアレックスは七原に微笑みをうつして言った。
/
俺は街中を歩いていた。
空唄市にある数少ない繁華街の通りを人ごみに紛れながらただ単にふらふらと歩き回っていた。
空唄市、紅葉区の繁華街と言ったら空唄市の住民で知らない人は居ないだろう。
というか、田舎だし空唄市は狭いからなー。
別に何か様があった訳では無い。未だに脳裏に残った夢の内容が忘れられず考え事をしていたら気づけば紅葉区に居たと行った所だろう。
繁華街は相変わらず賑わっていて多くの男性や女性、年齢は子供からお爺さんお婆さんまで限りなく歩き回っていた。
左右に並ぶ店はファーストフードのチェーン店、カラオケ、電化製品、八百屋、本屋、スーパーマーケットやら何でもござれだ。
此処の繁華街は田舎なのに歩けば何でも揃っているという事で住民の間でも人気があるのだ。
歩く人の表情を伺うと誰もが笑っている様に見えた。
一瞬、言術の事や怨霊の事などが嘘の話に思える。
しかし右ポケットにある通常の鍵とは違って少し大きめのその鍵がやはり裏の世界では信じられない化け物やまるで正義の味方の様に戦う戦士達がいるのだと教えてくれる。
榊原は俺があまりにも冷静な所が変だ、と言っていたが正直かなり混乱していた。
突然、今までの一部の記憶は嘘でした、なんて言われても一体何処から何処までの記憶が偽りで、思い出す記憶が本当記憶なのか偽者の記憶なのか判断が付かないのだ。
足が勝手に紅葉区へと向かったのはきっとそのせいだろう。
この繁華街にはちょっとした思い入れがあるのだ。正確には気がするだけなのだが。
っというのはついさっき思いだしたのだが、ただ確かなのは記憶にかすかに残る金髪のショートカットで活気的な女の子は本当の記憶に存在していて、偽りの記憶に存在していないという事だ。
そして俺はこの繁華街で金髪の女の子との思い出がある気がしたのだ。
確信は無いが今はなるべく混乱した記憶を整理したかったから、とにかく屋敷でじってしているより外を出歩いた方がきっとプラスになるだろうと信じて・・・。
それに怨霊は日が沈んだ時にしか出ないらしいからお昼に外に出歩いても問題は無いだろう。
ふと、隣を金髪の女の子が通り抜けて俺はとっさに振り返った。
だが知らない人だった。容姿が記憶に残っている顔とは全然違ったのだ。
彼氏であろう男の子と腕を組んで楽しそうに歩いてるその女の子の後姿を見送り、その様子が何か記憶のパズルに当てはまった気がした。
あのカップルがゲーセンの前を通り抜けると、誰もいなくなったゲーセンの前にとある記憶の光景が重なった。
空唄市にある数少ない繁華街の通りを人ごみに紛れながらただ単にふらふらと歩き回っていた。
空唄市、紅葉区の繁華街と言ったら空唄市の住民で知らない人は居ないだろう。
というか、田舎だし空唄市は狭いからなー。
別に何か様があった訳では無い。未だに脳裏に残った夢の内容が忘れられず考え事をしていたら気づけば紅葉区に居たと行った所だろう。
繁華街は相変わらず賑わっていて多くの男性や女性、年齢は子供からお爺さんお婆さんまで限りなく歩き回っていた。
左右に並ぶ店はファーストフードのチェーン店、カラオケ、電化製品、八百屋、本屋、スーパーマーケットやら何でもござれだ。
此処の繁華街は田舎なのに歩けば何でも揃っているという事で住民の間でも人気があるのだ。
歩く人の表情を伺うと誰もが笑っている様に見えた。
一瞬、言術の事や怨霊の事などが嘘の話に思える。
しかし右ポケットにある通常の鍵とは違って少し大きめのその鍵がやはり裏の世界では信じられない化け物やまるで正義の味方の様に戦う戦士達がいるのだと教えてくれる。
榊原は俺があまりにも冷静な所が変だ、と言っていたが正直かなり混乱していた。
突然、今までの一部の記憶は嘘でした、なんて言われても一体何処から何処までの記憶が偽りで、思い出す記憶が本当記憶なのか偽者の記憶なのか判断が付かないのだ。
足が勝手に紅葉区へと向かったのはきっとそのせいだろう。
この繁華街にはちょっとした思い入れがあるのだ。正確には気がするだけなのだが。
っというのはついさっき思いだしたのだが、ただ確かなのは記憶にかすかに残る金髪のショートカットで活気的な女の子は本当の記憶に存在していて、偽りの記憶に存在していないという事だ。
そして俺はこの繁華街で金髪の女の子との思い出がある気がしたのだ。
確信は無いが今はなるべく混乱した記憶を整理したかったから、とにかく屋敷でじってしているより外を出歩いた方がきっとプラスになるだろうと信じて・・・。
それに怨霊は日が沈んだ時にしか出ないらしいからお昼に外に出歩いても問題は無いだろう。
ふと、隣を金髪の女の子が通り抜けて俺はとっさに振り返った。
だが知らない人だった。容姿が記憶に残っている顔とは全然違ったのだ。
彼氏であろう男の子と腕を組んで楽しそうに歩いてるその女の子の後姿を見送り、その様子が何か記憶のパズルに当てはまった気がした。
あのカップルがゲーセンの前を通り抜けると、誰もいなくなったゲーセンの前にとある記憶の光景が重なった。
「あー!もう、なんで取れないんだろー!」
ゲーセン前で苛立ってる制服姿の金髪の女の子が一人でブツクサ愚痴っていた。
その姿に気づいた俺はその場所から手を挙げて彼女の名前を呼んだ。
「あっ、秋じゃーん。良いとこに来たよホント!さっすがチームの救世主!もちろん私の救世主にもなってくれるよね?」
偶然ばったり出会うなり駆け寄ってきて何か訳のわからない話しを持ちかけられて俺は戸惑っていた。
答えを返す間もなく金髪の少女は腕を絡めてきた。
「ねぇ、お金貸してよー。どーしてもぬいぐるみが取れなくて、お財布の中身全滅しちゃったのよ。ね、いいでしょ?」
ゲーセン前で苛立ってる制服姿の金髪の女の子が一人でブツクサ愚痴っていた。
その姿に気づいた俺はその場所から手を挙げて彼女の名前を呼んだ。
「あっ、秋じゃーん。良いとこに来たよホント!さっすがチームの救世主!もちろん私の救世主にもなってくれるよね?」
偶然ばったり出会うなり駆け寄ってきて何か訳のわからない話しを持ちかけられて俺は戸惑っていた。
答えを返す間もなく金髪の少女は腕を絡めてきた。
「ねぇ、お金貸してよー。どーしてもぬいぐるみが取れなくて、お財布の中身全滅しちゃったのよ。ね、いいでしょ?」
そして、っは、と記憶から現実に引き戻される。
「あー、そういえばアイツ俺の財布抜き取ってUFOキャッチャー続けたんだっけな。結局一個も取れず二人揃って金欠になったんだけどな。借りた分の金返してもらってないし」
一つの記憶を思い出して俺はゲーセンの入り口を眺めながら一人苦笑した。
小さな記憶だけど、それが確かな事実である事が解かる。それがとても嬉しかった。
「おっ、風間じゃねーか」
唐突に後ろから声をかけられて俺は振り返った。
「どーしたんだ?こんなとこでボケっと突っ立ってさぁ」
そこにはあからさまに悪の企みを持った悪のある笑顔でまさにその悪意ある計画を実行せんとする悪友、坂本英二が居た。
「却下だ」
話しを持ちかけられる前に俺は制止する。
「ちょっとまてよ、俺まだ何もいってねぇのに」
「御前の事だ。どうせこれからゲーセン行こうと思ってたけど財布忘れたから金かしてくれ、とでも言うんだろ?本当は財布持ってるくせに」
「っう、なんでわかったんだよ・・・テレパシー?」
図星かよ、この野郎。
「まぁ分かってるなら話は早い、っつーわけで、金かっしてー!」
「帰れボケ。貴様なんぞに貸してやる金はない」
「んだとゴルァ。大人しく金貸せって言ってんだよ!」
「カツアゲしても駄目」
「ねぇ、いいでしょ?かしてよ風間くん・・・」
「気色悪い裏声出して無理な色気と流し目されても駄目」
「あ、もしもし?風間さんのお宅ですか?実は娘さんが事故にあって大怪我されて、2時までに・・・」
「俺俺詐欺も駄目、ちなみに娘はおらん」
「ぶー、なんだよ良いじゃんか、金かしてかしてかしてぇー!!」
「だ だ こ ね て も 駄 目」
「昨日夜、榊原さんの家に入った事、明日の学校で言いふらしてやっちゃおうかなー」
「だから駄目なもんは・・・って、はぁ?!」
「そっか、駄目か、なら仕方ないよな!まぁ俺も無理に親友の財布から金を抜き取るほどの悪いヤツじゃないし、無理なら諦めるよ!」
と言って背を向けて去らんとする英二。
「ちょっ、まて坂本――・・・!」
「じゃぁな裏切り者!明日の学校、皆の前で脱チェリーボーイの話し聞かせてくれよ!」
「脱チェリーボーイって・・・じゃなくて、おい!!英二ぃーーーーー!!」
妙にさわやかな顔してスキップしながら輝き去って行く悪友の後ろ姿は追いかける間もなく人ごみに消えていってしまった。
ヤツが去った戦場には妙な脱力感と敗北感、そして毎度の事ながら疲れが残ったのであった・・・。
明日の学校は修羅場と化しそうだが、どうやって誤解を解くか・・・。
榊原の家に行った事が事実だと知られている以上、何をしに行ったのか言い訳を考えなくては・・・。
うーん、と唸る俺の横を再び同年代の金髪少女が通り抜けて行く。
それについ振り返ってしまうのだが、その横顔は―――・・・。
「――愛里?」
一瞬だけ見たその横顔は記憶にある本人とそっくりだった。
「あー、そういえばアイツ俺の財布抜き取ってUFOキャッチャー続けたんだっけな。結局一個も取れず二人揃って金欠になったんだけどな。借りた分の金返してもらってないし」
一つの記憶を思い出して俺はゲーセンの入り口を眺めながら一人苦笑した。
小さな記憶だけど、それが確かな事実である事が解かる。それがとても嬉しかった。
「おっ、風間じゃねーか」
唐突に後ろから声をかけられて俺は振り返った。
「どーしたんだ?こんなとこでボケっと突っ立ってさぁ」
そこにはあからさまに悪の企みを持った悪のある笑顔でまさにその悪意ある計画を実行せんとする悪友、坂本英二が居た。
「却下だ」
話しを持ちかけられる前に俺は制止する。
「ちょっとまてよ、俺まだ何もいってねぇのに」
「御前の事だ。どうせこれからゲーセン行こうと思ってたけど財布忘れたから金かしてくれ、とでも言うんだろ?本当は財布持ってるくせに」
「っう、なんでわかったんだよ・・・テレパシー?」
図星かよ、この野郎。
「まぁ分かってるなら話は早い、っつーわけで、金かっしてー!」
「帰れボケ。貴様なんぞに貸してやる金はない」
「んだとゴルァ。大人しく金貸せって言ってんだよ!」
「カツアゲしても駄目」
「ねぇ、いいでしょ?かしてよ風間くん・・・」
「気色悪い裏声出して無理な色気と流し目されても駄目」
「あ、もしもし?風間さんのお宅ですか?実は娘さんが事故にあって大怪我されて、2時までに・・・」
「俺俺詐欺も駄目、ちなみに娘はおらん」
「ぶー、なんだよ良いじゃんか、金かしてかしてかしてぇー!!」
「だ だ こ ね て も 駄 目」
「昨日夜、榊原さんの家に入った事、明日の学校で言いふらしてやっちゃおうかなー」
「だから駄目なもんは・・・って、はぁ?!」
「そっか、駄目か、なら仕方ないよな!まぁ俺も無理に親友の財布から金を抜き取るほどの悪いヤツじゃないし、無理なら諦めるよ!」
と言って背を向けて去らんとする英二。
「ちょっ、まて坂本――・・・!」
「じゃぁな裏切り者!明日の学校、皆の前で脱チェリーボーイの話し聞かせてくれよ!」
「脱チェリーボーイって・・・じゃなくて、おい!!英二ぃーーーーー!!」
妙にさわやかな顔してスキップしながら輝き去って行く悪友の後ろ姿は追いかける間もなく人ごみに消えていってしまった。
ヤツが去った戦場には妙な脱力感と敗北感、そして毎度の事ながら疲れが残ったのであった・・・。
明日の学校は修羅場と化しそうだが、どうやって誤解を解くか・・・。
榊原の家に行った事が事実だと知られている以上、何をしに行ったのか言い訳を考えなくては・・・。
うーん、と唸る俺の横を再び同年代の金髪少女が通り抜けて行く。
それについ振り返ってしまうのだが、その横顔は―――・・・。
「――愛里?」
一瞬だけ見たその横顔は記憶にある本人とそっくりだった。
- 人違いかも知れない。
だが振り返らないその金髪少女を俺は思わず追いかけていた――。
/
紅葉区の繁華街のとあるファンシーショップから私は結局何も買わずに出た。
自動ドアのガラス扉から一歩踏み出すと相変わらず暑い夏の熱気が肌に触れて店から出るのを少しばかり惜しんだ。
「んー、あの服良かったのだけど・・・他の店も見てから決めるしか・・・」
服選びはなるべく安めで慎重に、というのが私流なのだが、友人は気に入った服があったら値段なんか気にするな!と言っていた。
とは言っても、生活資金は命とアレックスから貰っているとは言え、流石に服類や趣味の物はその生活資金から出す訳には行かないので、自給自足のお小遣いで購入するしかないのだ。
自給自足の方法は偶に臨時バイトしたりして貯めたりしている。
今では言術者として働けるわけだから少しは収入が多くなるが、言術者の仕事の給料というのはそれ程高いものでも無いのであった。
少なくとも、言術者業だけで生きていくのは難しい。
アレックスは成功報酬制の仕事を幾つかやっているらしく、株にも手を出しているらしい。
命は実は大手洋服会社のファッションデザイナーだったりする。
つまり、生きる中で言術者というのは副業みたいなものだ。
言術者業をメインで生きている人は恐らく殆ど居ないだろう。
生活費は今の所はフォローされているけど、何時か保護者の二人から独立しなければならないその日までに何か考えておかなくてはならない。そう思うとやはり貯金を貯める事も考えるのだけど、実際は貯まらないでつい消費してしまうのが女性なのだろうか・・・。
「やっぱ洋服買うのはやめておこうかしら・・・」
悩んでいるのに足は向かい側のファンシーショップへと向かっていく――。
「・・・!?」
一瞬、妙な胸騒ぎと悪寒に襲われた。
慌てて後ろを振り返るが、そこには何事も無く歩く人々の姿のみ。
「今のは一体・・・・・・ッ?!」
そして今度は源の流れが大きく乱れた。
何処かで言術者が力を開放したらしい、とは言えこの乱れ方は普通じゃない。
「・・・・・・」
妙な胸騒ぎがして、私は源の流れを感じながら、その開放源へと駆け出した!
自動ドアのガラス扉から一歩踏み出すと相変わらず暑い夏の熱気が肌に触れて店から出るのを少しばかり惜しんだ。
「んー、あの服良かったのだけど・・・他の店も見てから決めるしか・・・」
服選びはなるべく安めで慎重に、というのが私流なのだが、友人は気に入った服があったら値段なんか気にするな!と言っていた。
とは言っても、生活資金は命とアレックスから貰っているとは言え、流石に服類や趣味の物はその生活資金から出す訳には行かないので、自給自足のお小遣いで購入するしかないのだ。
自給自足の方法は偶に臨時バイトしたりして貯めたりしている。
今では言術者として働けるわけだから少しは収入が多くなるが、言術者の仕事の給料というのはそれ程高いものでも無いのであった。
少なくとも、言術者業だけで生きていくのは難しい。
アレックスは成功報酬制の仕事を幾つかやっているらしく、株にも手を出しているらしい。
命は実は大手洋服会社のファッションデザイナーだったりする。
つまり、生きる中で言術者というのは副業みたいなものだ。
言術者業をメインで生きている人は恐らく殆ど居ないだろう。
生活費は今の所はフォローされているけど、何時か保護者の二人から独立しなければならないその日までに何か考えておかなくてはならない。そう思うとやはり貯金を貯める事も考えるのだけど、実際は貯まらないでつい消費してしまうのが女性なのだろうか・・・。
「やっぱ洋服買うのはやめておこうかしら・・・」
悩んでいるのに足は向かい側のファンシーショップへと向かっていく――。
「・・・!?」
一瞬、妙な胸騒ぎと悪寒に襲われた。
慌てて後ろを振り返るが、そこには何事も無く歩く人々の姿のみ。
「今のは一体・・・・・・ッ?!」
そして今度は源の流れが大きく乱れた。
何処かで言術者が力を開放したらしい、とは言えこの乱れ方は普通じゃない。
「・・・・・・」
妙な胸騒ぎがして、私は源の流れを感じながら、その開放源へと駆け出した!
/
金髪の少女を追いかけていると、彼女は突然横に曲がって狭い路地裏へと入っていった。
此処で見失う訳にはいかない、と俺も路地裏へと入り後を追う。
狭い路地裏は薄汚れていたが、しかし肩幅以上のスペースがあったので楽に通り抜ける事ができた。
金髪少女を追ってやがて路地裏の小道から出ると妙な空間に出た。
――赤い。
目の前に広がるのは、真っ赤な景色。
天も地も無く、その空間だけが赤くなっていた――。
赤、それはまるで誰かの血を吸ったかのように・・・。
そして急に体が冷えた。今までの夏の暑さが嘘のようにひいていく。
気づけば追っていたはずの金髪の少女が赤い空間の中でこちらを向いていた。
前髪が長くて彼女の顔が見えない。愛里じゃないのか?
「ひさしぶりね、草薙」
そして愛里かと思ったその姿は赤色に溶け、形を変えていき・・・、少女から大人びた黒髪の女性へと姿を変えた。
「まさかまんまと引っかかってくれるとは思わなかったわぁ」
やっと気が付いた頃には既に遅かった。
俺は罠にはまったと気づいて後ろを振り向くが、・・・そこには元々あった路地裏が無くなっていた。
四方八方が赤く、自分が立っているその場所が地面なのかすら分からない。
そう、この赤の次元はまるで二次元の様に影も光も無く、赤だけに包まれていた――。
俺は黙って前方に立つ黒髪の女性を見据えた。
「あらあら、そんなに警戒しなくても良いわよ。せっかく久しぶりに会えたんだから喜んで欲しいわ、草薙。・・・でも、邪魔者は排除して欲しいわねぇ」
先程から呼ばれている草薙の名前、誰だか知らないけど、人違いならそうであって欲しい。
とにかく一刻も早くこの空間から出たかった。
赤い色を見ていると、血を見ている気分になって――。
――血?
目の前が過去のフラッシュバックに潰れる。
そこには大量の血を流して俺に微笑みを向ける少女が・・・。
――血が、血が。
出欠が止まらない。俺は我武者羅に走り続けていた。
その少女を抱えて・・・。
少女、水城愛里?
彼女は必死に駆ける俺に精一杯の笑顔を向けて、唇を動かした。
――ぁ・・・、ぁぁ・・・。
ぁ・・・。
――ぁ、やめ・・・ろ。
思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無いっ!!!
――ぁ、ぁぁ、あああああああああああああああああああああッッ!!!!!?
「うあああああああああああ?!」
無我無心に手に握りしめた鍵が刀へと姿を変える!
俺は頭の中で切れる何かが分からないまま奇声を挙げて黒髪の女へと飛び掛った!
「アイスブレイカー!!目を覚まして!!!」
そして、知った女性の声に俺は目を覚ました。
気づけば黒髪の女の姿は無く俺は刀の切先を榊原に向けられていて――!!
「・・・ッ!」
「キャ――」
ズドン!
刀に何かが刺さる感触と音が聞こえた。
――俺は一体何をしていた?
しばらくの静寂が訪れる・・・。恐る恐る顔を上げると刀は紙一重で榊原の頬をかすめて壁に突き刺さっていた。
「あ、アイス・・・ブレイカー?」
「ぁ・・・榊原、俺は・・・、俺は――」
何もかもが混乱していた。
気が付けば辺りの赤い空間は無くなっていて、路地裏に有る小さな空間で俺は榊原に刀を向けていて、俺は榊原を殺そうと・・・?
「だ、大丈夫!アイスブレイカー?混乱してるのは分かるわ。貴方は幻を見せられていたのよ!」
「でも、俺、もう少しで榊原を殺そうと・・・!」
それでも刀から手が離れない。刀身はザックリと壁に突き刺さったままで、体が動かなかった。
榊原は壁に背を預けたまま地面に腰を落としていた。
「落ち着いてアイスブレイカー!深呼吸して・・・、それからゆっくりと体から力を抜いて・・・」
俺は何か言いたい事が有ったのか、口ごもってから出来る限り落ち着こうと息を吸って吐いた。
何度かそれを続けてからゆっくりて力を抜くと刀から手が自然と離れて、急に襲われた疲労感で腰を落とした。
「どう?大丈夫?」
榊原は横顔の直ぐ傍にある刀から離れて、腰を落として何も言えない俺に問いかけた。
口は開くのに言葉が出てこない。
俺は大丈夫だと言いたくて二回ほど頷いた。
「状況を説明すると、貴方は何処かの言術者に幻を見せられていて、それで私を敵だと思い込んだのよ」
榊原は腰を上げて膝をついて俺の瞳を覗き込んだ。
「言術による幻は解けたけど、また掛かるかも知れないから覚えておいて。・・・自分を信じ続けるの・・・。絶対に疑っちゃ駄目、現実から目を背けても駄目、・・・わかった?」
ようやく少し落ち着いて来て俺は相変わらず声が出ないものの何度か頷いた。
未だに信じられないほど心臓が跳ね続けている。
榊原は、よし、と言って立ち上がってから刀を壁から引き抜いた。
すると刀は音も無く鍵へと形を戻していく・・・。
「立てる?一度私の家に戻りましょう」
言うと鍵を左手に、空いた右手を俺に差し伸べてきたので、その手を握り俺は何も言えないまま立ち上がった。
しかし足がふらついていて、何故か真っ直ぐ立てない。
それに気付いた榊原は黙って俺に肩を貸してくれた。
「・・・さ・・・さかき、ばら・・・」
「?」
「ごめん・・・」
ようやく声が出るようになると、俺はそれしか言えなかった。
そして俺の記憶は戻りつつあった――・・・。
此処で見失う訳にはいかない、と俺も路地裏へと入り後を追う。
狭い路地裏は薄汚れていたが、しかし肩幅以上のスペースがあったので楽に通り抜ける事ができた。
金髪少女を追ってやがて路地裏の小道から出ると妙な空間に出た。
――赤い。
目の前に広がるのは、真っ赤な景色。
天も地も無く、その空間だけが赤くなっていた――。
赤、それはまるで誰かの血を吸ったかのように・・・。
そして急に体が冷えた。今までの夏の暑さが嘘のようにひいていく。
気づけば追っていたはずの金髪の少女が赤い空間の中でこちらを向いていた。
前髪が長くて彼女の顔が見えない。愛里じゃないのか?
「ひさしぶりね、草薙」
そして愛里かと思ったその姿は赤色に溶け、形を変えていき・・・、少女から大人びた黒髪の女性へと姿を変えた。
「まさかまんまと引っかかってくれるとは思わなかったわぁ」
やっと気が付いた頃には既に遅かった。
俺は罠にはまったと気づいて後ろを振り向くが、・・・そこには元々あった路地裏が無くなっていた。
四方八方が赤く、自分が立っているその場所が地面なのかすら分からない。
そう、この赤の次元はまるで二次元の様に影も光も無く、赤だけに包まれていた――。
俺は黙って前方に立つ黒髪の女性を見据えた。
「あらあら、そんなに警戒しなくても良いわよ。せっかく久しぶりに会えたんだから喜んで欲しいわ、草薙。・・・でも、邪魔者は排除して欲しいわねぇ」
先程から呼ばれている草薙の名前、誰だか知らないけど、人違いならそうであって欲しい。
とにかく一刻も早くこの空間から出たかった。
赤い色を見ていると、血を見ている気分になって――。
――血?
目の前が過去のフラッシュバックに潰れる。
そこには大量の血を流して俺に微笑みを向ける少女が・・・。
――血が、血が。
出欠が止まらない。俺は我武者羅に走り続けていた。
その少女を抱えて・・・。
少女、水城愛里?
彼女は必死に駆ける俺に精一杯の笑顔を向けて、唇を動かした。
――ぁ・・・、ぁぁ・・・。
ぁ・・・。
――ぁ、やめ・・・ろ。
思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無い思い出したく無いっ!!!
――ぁ、ぁぁ、あああああああああああああああああああああッッ!!!!!?
「うあああああああああああ?!」
無我無心に手に握りしめた鍵が刀へと姿を変える!
俺は頭の中で切れる何かが分からないまま奇声を挙げて黒髪の女へと飛び掛った!
「アイスブレイカー!!目を覚まして!!!」
そして、知った女性の声に俺は目を覚ました。
気づけば黒髪の女の姿は無く俺は刀の切先を榊原に向けられていて――!!
「・・・ッ!」
「キャ――」
ズドン!
刀に何かが刺さる感触と音が聞こえた。
――俺は一体何をしていた?
しばらくの静寂が訪れる・・・。恐る恐る顔を上げると刀は紙一重で榊原の頬をかすめて壁に突き刺さっていた。
「あ、アイス・・・ブレイカー?」
「ぁ・・・榊原、俺は・・・、俺は――」
何もかもが混乱していた。
気が付けば辺りの赤い空間は無くなっていて、路地裏に有る小さな空間で俺は榊原に刀を向けていて、俺は榊原を殺そうと・・・?
「だ、大丈夫!アイスブレイカー?混乱してるのは分かるわ。貴方は幻を見せられていたのよ!」
「でも、俺、もう少しで榊原を殺そうと・・・!」
それでも刀から手が離れない。刀身はザックリと壁に突き刺さったままで、体が動かなかった。
榊原は壁に背を預けたまま地面に腰を落としていた。
「落ち着いてアイスブレイカー!深呼吸して・・・、それからゆっくりと体から力を抜いて・・・」
俺は何か言いたい事が有ったのか、口ごもってから出来る限り落ち着こうと息を吸って吐いた。
何度かそれを続けてからゆっくりて力を抜くと刀から手が自然と離れて、急に襲われた疲労感で腰を落とした。
「どう?大丈夫?」
榊原は横顔の直ぐ傍にある刀から離れて、腰を落として何も言えない俺に問いかけた。
口は開くのに言葉が出てこない。
俺は大丈夫だと言いたくて二回ほど頷いた。
「状況を説明すると、貴方は何処かの言術者に幻を見せられていて、それで私を敵だと思い込んだのよ」
榊原は腰を上げて膝をついて俺の瞳を覗き込んだ。
「言術による幻は解けたけど、また掛かるかも知れないから覚えておいて。・・・自分を信じ続けるの・・・。絶対に疑っちゃ駄目、現実から目を背けても駄目、・・・わかった?」
ようやく少し落ち着いて来て俺は相変わらず声が出ないものの何度か頷いた。
未だに信じられないほど心臓が跳ね続けている。
榊原は、よし、と言って立ち上がってから刀を壁から引き抜いた。
すると刀は音も無く鍵へと形を戻していく・・・。
「立てる?一度私の家に戻りましょう」
言うと鍵を左手に、空いた右手を俺に差し伸べてきたので、その手を握り俺は何も言えないまま立ち上がった。
しかし足がふらついていて、何故か真っ直ぐ立てない。
それに気付いた榊原は黙って俺に肩を貸してくれた。
「・・・さ・・・さかき、ばら・・・」
「?」
「ごめん・・・」
ようやく声が出るようになると、俺はそれしか言えなかった。
そして俺の記憶は戻りつつあった――・・・。
/
夢を見た、夢の中で俺は笑っていた。
何時もの様に、何も知らなくて、愛里と一緒に笑っていた。
思い出せばアイツと初めて会ったのは幼稚園の頃――・・・。
「ねぇ、なんでみんなとあそばないの?」
幼稚園に初めて入った俺は既に友達を3人くらい作っていた。
母さんは、俺は人から好かれるタイプだと誇らしげだった。
でも、この幼稚園には入学してからずっと気になる姿があったのだ。
その頃はまだ恋とかそんな意識は無かったから、俺はその女の子を見て、なんで何時も泣いているんだろう?としか思わなかった。
だから俺は膝を抱えて座り込んでいる少女を後ろから声をかけた。
なんでみんなとあそばないの?
「わたし・・・ひっく、みんなとちがくて、くろくないからだれもあそんでくれないのぉ・・・ぅう」
そして初めてその女の子が泣いている事に気付いた。
なんで泣いてるんだろう?
俺には訳が分からなかった。彼女が何を言ってるのかすら分からなかった・・・。
みんなとあそべばたのしいのに、あそばないからないてるんだ・・・。
そう思って俺は女の子に右手を差し出して言った。
「ね、いっしょにあそぼーよ!いっしょにいればなかないよ?」
俺は笑顔で彼女が右手を握ってくれるのを待った。
彼女はきょとんとした顔で何がなんだか分からない様な表情だったが、暫くして恐る恐る俺の右手に彼女の右手が差し出された。
俺はその右手を掴み引っ張りあげて、手を繋いだまま皆と遊んでいる砂場まで一緒に走った。
最初、彼女は何時も驚いていたが、やがて同じように笑う様になって――。
「ねぇ、わたしすいじょうあいりっていうの。あなたは・・・?」
「ぼく、かざましゅーだよ!」
それが俺と愛里が初めて出会った日だ。
幼稚園だけでなく、気付けば小学校も同じだった。
腐れ縁か何かなのか、教室は毎年同じ教室になった。
当時の俺と愛里には、まだ恋愛というのがよく分からなくて、何かを意識しはじめたのは小6くらいからだったか・・・。
それから中学生になり、俺はずっと憧れていた学校のバスケチームに入った。
愛里はもともと剣道が得意で、そのまま剣道クラブに入った。
偶に俺のバスケチームが他校と試合することになると、例え俺がプレイしてなくても愛里は毎回必ず見に来てくれた。だから俺も愛里の剣道の試合は全て見に行った。
流石に同じ時間に自分の試合がある場合はできなかったが、俺たちは親友の様な関係だった。
そして中学2年の頃、唐突に友人にこんな事を聞かれた事がある。
「御前さ、水城と付き合ってるのか?」
「・・・――は?」
意識した事は無かった、と言えば嘘になる。
確かに愛里は女の子で、中学に入ってから時折胸の鼓動が早くなるような仕草も見せてくれた。
それでも俺はただの親友だ、と友人に言い張ったのは恥ずかしいからでもあったし、同時に愛里にはそんな気はきっと無いだろうと思っていたからだ。
もし俺から告白して、愛里がそれを拒絶した場合、そのまま親友の関係を続けるのが難しくなる。
俺は愛里との関係が無くなるのを恐れていた。
だが、それは唐突に起こった・・・。
ある日、俺はバスケの試合で大きなミスをしてしまった。
時間切れまであと1分で、2点差で負けていたチームは慌てていた。
俺も慌ててパスを回したのだが、それがミスを犯してしまったのだ。
――相手のチームにパスを出した。
1分という時間は直ぐに潰れて、残り時間あと僅かなところで反撃も返せなかった。
俺は更衣室で先輩の人達に殴られていた。
「――御前のせいだ!!御前のせいで・・・っ!!!」
分かってる。
先輩の人たちは今年で中学を卒業して、全員それぞれの希望高校へと向かう。
つまりこの試合は、先輩達3年生の皆が揃ってやる最後のゲームになってしまったのだ。
そう、俺のせいで。
更衣室でロッカーに叩き付けられ、顔面を3、4発殴られてから地面に座り込んだ俺の腹を5、6回蹴った。
俺は全く抵抗しなかった。
無抵抗なのが余計に気に食わなかったのか、俺の襟元を掴み無理やり立ち上がらせると頭を掴んでロッカーに叩きつけられた。
「ちょっとやめなさいよ!!!」
と、突然男子更衣室の扉が開かれて愛里が現れた。
「んだよ?ああ、風間の彼女か」
彼女呼ばわりされて、彼女は顔を赤く染めたが怒りで混乱しているのか知らないが殴られて血だらけになってる俺の姿を見るなり、駆け寄って先輩達を突き飛ばし、俺に指一本触れさせんとするかの様に仁王立ちをした。
「風間は悪くない!大体あんた達、虫がよすぎるのよ!!」
「なんだとっ?!」
力強い愛里の声が更衣室に響き渡る。
「風間は今日休み無しで走り続けていたわ!それにチームの点数の7割が風間が取った点数じゃない!風間がいなければ今日の試合以上にボロ負けだったのが分からないの?!」
反論できない事実を突き付けられて先輩は怒り、口より手を出した。
愛里の制服の胸倉が掴まれて、
「このアマぁ!犯し殺してやる!!」
だがその瞬間俺の口は勝手に動いていた。
「水城に手を出すなぁあ!!」
先輩達や愛里以上に激しい怒鳴り声、たった一言で辺りが沈黙した。
胸倉から手を離されて愛里は地面に膝を付いて震えた。
――泣いていた。
アイツが泣いた所を見たのは幼稚園の頃だけだった。
俺は愛里にかける言葉が見つからなくて黙った。先輩達も黙り続けて、更衣室には愛里の流す小さい嗚咽が残った。
「悪かったな風間・・・」
暫くの沈黙の後、先輩達は俺に言葉を残して更衣室を出て行った。
俺はその場に座り込んだまま泣きじゃくる愛里の背中を見続けていた。
後輩達も引き上げていって、更衣室には俺と愛里だけが残された。
愛里は自分自身の肩を抱いて泣き続けている。
俺は掛ける言葉も見つからず、初めて自分が愛里に何もしてあげられない事が悲しかった。
「水城・・・、ごめんな」
愛里はゆっくりと泣き崩れた顔で振り返って、座り込む俺の胸の中に飛び込んで先程以上に泣いた。
怖かった、怖かった、と泣き続けて、何時の間にか俺も涙を流していた。
「ごめんな・・・っ」
暫く一緒に泣き続けた愛里は、泣くのをやめて立ち上がると俺に右手を差し出してくれた。
俺がその右手を握り返すと引っ張りあげて立たせてくれる。
更衣室の窓から差し込む赤い夕日の光が目の前の愛里を照らしていて、愛里はとても綺麗だった。
「水城、俺、御前の事好きみたいだ・・・」
自然に口から漏れたその言葉を、愛里は驚いた顔を一瞬見せて、それから微笑んで言った。
「ふふ、知ってるよ?私もだもん」
楽しげに笑って――・・・。
「さっきまで泣いてたのにな」
俺たちはお互いの泣いた後の顔に写った笑顔に笑っていた。
そして愛里はあの時俺が言った言葉を言い直した。
「――いっしょにいれば・・・」
――なかないよ。
―ね、いっしょにあそぼーよ!いっしょにいればなかないよ?
何時もの様に、何も知らなくて、愛里と一緒に笑っていた。
思い出せばアイツと初めて会ったのは幼稚園の頃――・・・。
「ねぇ、なんでみんなとあそばないの?」
幼稚園に初めて入った俺は既に友達を3人くらい作っていた。
母さんは、俺は人から好かれるタイプだと誇らしげだった。
でも、この幼稚園には入学してからずっと気になる姿があったのだ。
その頃はまだ恋とかそんな意識は無かったから、俺はその女の子を見て、なんで何時も泣いているんだろう?としか思わなかった。
だから俺は膝を抱えて座り込んでいる少女を後ろから声をかけた。
なんでみんなとあそばないの?
「わたし・・・ひっく、みんなとちがくて、くろくないからだれもあそんでくれないのぉ・・・ぅう」
そして初めてその女の子が泣いている事に気付いた。
なんで泣いてるんだろう?
俺には訳が分からなかった。彼女が何を言ってるのかすら分からなかった・・・。
みんなとあそべばたのしいのに、あそばないからないてるんだ・・・。
そう思って俺は女の子に右手を差し出して言った。
「ね、いっしょにあそぼーよ!いっしょにいればなかないよ?」
俺は笑顔で彼女が右手を握ってくれるのを待った。
彼女はきょとんとした顔で何がなんだか分からない様な表情だったが、暫くして恐る恐る俺の右手に彼女の右手が差し出された。
俺はその右手を掴み引っ張りあげて、手を繋いだまま皆と遊んでいる砂場まで一緒に走った。
最初、彼女は何時も驚いていたが、やがて同じように笑う様になって――。
「ねぇ、わたしすいじょうあいりっていうの。あなたは・・・?」
「ぼく、かざましゅーだよ!」
それが俺と愛里が初めて出会った日だ。
幼稚園だけでなく、気付けば小学校も同じだった。
腐れ縁か何かなのか、教室は毎年同じ教室になった。
当時の俺と愛里には、まだ恋愛というのがよく分からなくて、何かを意識しはじめたのは小6くらいからだったか・・・。
それから中学生になり、俺はずっと憧れていた学校のバスケチームに入った。
愛里はもともと剣道が得意で、そのまま剣道クラブに入った。
偶に俺のバスケチームが他校と試合することになると、例え俺がプレイしてなくても愛里は毎回必ず見に来てくれた。だから俺も愛里の剣道の試合は全て見に行った。
流石に同じ時間に自分の試合がある場合はできなかったが、俺たちは親友の様な関係だった。
そして中学2年の頃、唐突に友人にこんな事を聞かれた事がある。
「御前さ、水城と付き合ってるのか?」
「・・・――は?」
意識した事は無かった、と言えば嘘になる。
確かに愛里は女の子で、中学に入ってから時折胸の鼓動が早くなるような仕草も見せてくれた。
それでも俺はただの親友だ、と友人に言い張ったのは恥ずかしいからでもあったし、同時に愛里にはそんな気はきっと無いだろうと思っていたからだ。
もし俺から告白して、愛里がそれを拒絶した場合、そのまま親友の関係を続けるのが難しくなる。
俺は愛里との関係が無くなるのを恐れていた。
だが、それは唐突に起こった・・・。
ある日、俺はバスケの試合で大きなミスをしてしまった。
時間切れまであと1分で、2点差で負けていたチームは慌てていた。
俺も慌ててパスを回したのだが、それがミスを犯してしまったのだ。
――相手のチームにパスを出した。
1分という時間は直ぐに潰れて、残り時間あと僅かなところで反撃も返せなかった。
俺は更衣室で先輩の人達に殴られていた。
「――御前のせいだ!!御前のせいで・・・っ!!!」
分かってる。
先輩の人たちは今年で中学を卒業して、全員それぞれの希望高校へと向かう。
つまりこの試合は、先輩達3年生の皆が揃ってやる最後のゲームになってしまったのだ。
そう、俺のせいで。
更衣室でロッカーに叩き付けられ、顔面を3、4発殴られてから地面に座り込んだ俺の腹を5、6回蹴った。
俺は全く抵抗しなかった。
無抵抗なのが余計に気に食わなかったのか、俺の襟元を掴み無理やり立ち上がらせると頭を掴んでロッカーに叩きつけられた。
「ちょっとやめなさいよ!!!」
と、突然男子更衣室の扉が開かれて愛里が現れた。
「んだよ?ああ、風間の彼女か」
彼女呼ばわりされて、彼女は顔を赤く染めたが怒りで混乱しているのか知らないが殴られて血だらけになってる俺の姿を見るなり、駆け寄って先輩達を突き飛ばし、俺に指一本触れさせんとするかの様に仁王立ちをした。
「風間は悪くない!大体あんた達、虫がよすぎるのよ!!」
「なんだとっ?!」
力強い愛里の声が更衣室に響き渡る。
「風間は今日休み無しで走り続けていたわ!それにチームの点数の7割が風間が取った点数じゃない!風間がいなければ今日の試合以上にボロ負けだったのが分からないの?!」
反論できない事実を突き付けられて先輩は怒り、口より手を出した。
愛里の制服の胸倉が掴まれて、
「このアマぁ!犯し殺してやる!!」
だがその瞬間俺の口は勝手に動いていた。
「水城に手を出すなぁあ!!」
先輩達や愛里以上に激しい怒鳴り声、たった一言で辺りが沈黙した。
胸倉から手を離されて愛里は地面に膝を付いて震えた。
――泣いていた。
アイツが泣いた所を見たのは幼稚園の頃だけだった。
俺は愛里にかける言葉が見つからなくて黙った。先輩達も黙り続けて、更衣室には愛里の流す小さい嗚咽が残った。
「悪かったな風間・・・」
暫くの沈黙の後、先輩達は俺に言葉を残して更衣室を出て行った。
俺はその場に座り込んだまま泣きじゃくる愛里の背中を見続けていた。
後輩達も引き上げていって、更衣室には俺と愛里だけが残された。
愛里は自分自身の肩を抱いて泣き続けている。
俺は掛ける言葉も見つからず、初めて自分が愛里に何もしてあげられない事が悲しかった。
「水城・・・、ごめんな」
愛里はゆっくりと泣き崩れた顔で振り返って、座り込む俺の胸の中に飛び込んで先程以上に泣いた。
怖かった、怖かった、と泣き続けて、何時の間にか俺も涙を流していた。
「ごめんな・・・っ」
暫く一緒に泣き続けた愛里は、泣くのをやめて立ち上がると俺に右手を差し出してくれた。
俺がその右手を握り返すと引っ張りあげて立たせてくれる。
更衣室の窓から差し込む赤い夕日の光が目の前の愛里を照らしていて、愛里はとても綺麗だった。
「水城、俺、御前の事好きみたいだ・・・」
自然に口から漏れたその言葉を、愛里は驚いた顔を一瞬見せて、それから微笑んで言った。
「ふふ、知ってるよ?私もだもん」
楽しげに笑って――・・・。
「さっきまで泣いてたのにな」
俺たちはお互いの泣いた後の顔に写った笑顔に笑っていた。
そして愛里はあの時俺が言った言葉を言い直した。
「――いっしょにいれば・・・」
――なかないよ。
―ね、いっしょにあそぼーよ!いっしょにいればなかないよ?
/
「いっしょにいれば・・・か」
「え?何か言ったかしら?」
肩を貸してくれていた榊原は帰路の途中つぶやいた俺の言葉をうまく聞き取れずに聞いた。
「いや・・・、なんでもない。もう大丈夫だ」
そう言って借りていた肩を返して自力で地面に立つ。
そして夕焼けに染まった空を見上げた。
あの時と同じ夕焼け同じ空。
愛里は何処かに居るんだろうか?それとも俺の記憶にあるあの血は愛里の・・・。
「榊原」
「ん?」
「腹減ったな」
「・・・はぁ」
「え?何か言ったかしら?」
肩を貸してくれていた榊原は帰路の途中つぶやいた俺の言葉をうまく聞き取れずに聞いた。
「いや・・・、なんでもない。もう大丈夫だ」
そう言って借りていた肩を返して自力で地面に立つ。
そして夕焼けに染まった空を見上げた。
あの時と同じ夕焼け同じ空。
愛里は何処かに居るんだろうか?それとも俺の記憶にあるあの血は愛里の・・・。
「榊原」
「ん?」
「腹減ったな」
「・・・はぁ」
/
「やぁ久しぶりじゃないか、伊邪那美(イザナミ)」
闇夜に沈んだ街のある一角でアレックスと七原命は黒髪の女と対峙していた。
「・・・誰?」
「忘れたのかい?三貴子を」
「あら、素戔嗚(スサノオ)と月讀(ツクヨミ)なの?貴方達にも呪いが掛かっていたとはねぇ」
「あの儀式の場に居た者の殆どが呪いに掛かっているよ、卑弥呼の呪いにね」
月の無い夜に七原は黙り続けて様子を伺っていた。
「僕らが君の前に姿を現した理由、知っているよね?」
黒髪の女、伊邪那美の魂をこの世から排除するためにアレックスと七原は現れたのだ。
伊邪那美という女はくすりと笑ってから得物を構えた。
それは鞭、言術者の支援武器だ。
「せっかくタケルと会えたんだから、此処で消滅される訳にはいかないのよ」
七原とアレックスも得物を取り出した。
七原の持つ支援武器は両腕にくっついた巨大な円形の盾。
彼女の服装は今までのコスプレとは違い、アレックスと同じ、スーツ姿だった。
アレックスが取り出した支援武器は一丁の拳銃。
「伊邪那岐が居るんだろう、何処に居るか教えてくれないかな?今回草薙を襲った怨霊も彼が操っていた事くらいは想像が付く」
「へぇ、流石草薙の右腕ってことかしら?2千年経ってもまだその頭脳は健在ね。でも・・・残念だけど教えてる事は出来ないわ・・・!」
黒髪、赤いドレスを着た女は鞭を振るった!うねる鞭は不規則な動きでアレックスの肩へと落下していく。
それを七原が右腕の盾で防いで、防御、途端に盾が八等分に分解した!
盾が崩れたのかと思えばその分解した盾の欠片は三角の形となり空中に浮遊する。
「伊邪那美・・・!」
初めて対峙する相手に口を聞いた七原は、腕を伊邪那美に向けると八個の浮遊する七原の支援武器がそれぞれ違う動きで高速で水無月に迫る。
「くっ・・・!」
それを避けんと後方に飛ぶが不規則に動く八つの支援武器を完全に避けきれず幾つかの武器が伊邪那美の体を切り裂いた。
一度の反撃に更に反撃を返そうと鞭を握り直す伊邪那美だが気付けばアレックスの拳銃の銃口が額に当てられていた。
「伊邪那岐は何処だい?」
一見決着が着いたかの様にみえるが、しかし、伊邪那美の表情はむしろ笑みが増すばかり・・・。その不気味な表情に疑問を抱いた途端、一閃の黒い太刀筋が銃口を伊邪那美へ突き付け押さえ込んでいるアレックスの首元へと迫ってくる――!
「――っくぅ!?」
唐突に迫ってきた太刀筋に気付きアレックスは伊邪那美を押さえつけるのを放棄して後方に跳躍、間も無く命の隣に着地した。
そして、アレックスはその太刀筋を振るった者の姿を見た・・・。
「な――、」
アレックス、そして命も同時にその姿を見て驚きの表情を隠せずにいた。
目の前に居るのは一人の少年。栗色の長髪で、長い髪を後頭部で結び吊るしている。
そして闇夜に溶け込む漆黒のロングコートを夜風になびかせ、片手には一振りの刀剣が握られていた。
月明かりが刀剣を怪しく照らす。
「天叢雲(あめのむらくも)――・・・!!・・・なるほど、ね」
しかしアレックスは自分の目の前に対峙する者が持つ剣がかつての愛刀であるにも関わらず、ニヤリと苦笑にも似た笑みを浮かべるのだった。
「・・・天叢雲と草薙を揃える気か。力の象徴を集めて何を企んでいるかは知らないが、伊邪那岐の企みに必要な物さえ解かってしまえば――・・・」
「ふふ、でもこちらには天叢雲が既にあるのよ? 草薙だって、もうすぐ・・・」
天叢雲と草薙・・・、それぞれの剣は一説には同一とされている。しかし此処に存在しているのは二つ、それぞれ別々の剣・・・。
「嗚呼、それと紹介しておくわね、新しい天叢雲剣のマスターを・・・」
伊邪那美が刀を持つ者の後方に立つと闇の中で笑みを浮かべた。
「彼の名前は、ウ ィ リ ア ム ・ ウ ェ ー ル ズ」
そしてアレックスと命の表情が再び驚愕なものとなる。
「ぁあ、そういえば、今の貴方も同じウェールズって名前があるらしいわねぇ?何か関係でもあるのかしら・・・?」
伊邪那美は同姓の理由を知っているにも関わらずわざとらしくアレックス・ウェールズへと問い掛けた、クスリクスリと笑いながら。
「・・・・・・・・・・」
一丁の銃を構えていたアレックスの手が軽く振るえ始めた。彼の目は恐れを映し出していて、そして銃のトリガーにかけた指が夏だというのに酷く冷えていた。
アレックスの頭の中で古い記憶が蘇る・・・、それはイギリスのある家を映し、赤く燃えて、全てを失い消えていく光景・・・、手元に残ったのは一人の愛する女性が持っていた小さい十字架のネックレス。
無意識の内に空いている左手が胸の中心辺りを服の上から掴んだ。
その服の下には小さい銀の十字架のネックレスがある。
肌に触れた十字架が一瞬チクリと痛みを作った。
「――ッレックス!アレックス!!」
命の声にッハっと我に帰り、目の前に対峙する者達を見直した。
しかし自分が自ら作ってしまった気の迷いと隙が相手の姿を見逃し、相手の二人は既にこの場から気配を消し去っていた。
「くっそ・・・っ!」
その場に残ったのは何も無い闇だけ・・・。
アレックスは拳銃の踵を傍に立つ一本の電灯にぶつけると空しい金属音が小さく響いた。
闇夜に沈んだ街のある一角でアレックスと七原命は黒髪の女と対峙していた。
「・・・誰?」
「忘れたのかい?三貴子を」
「あら、素戔嗚(スサノオ)と月讀(ツクヨミ)なの?貴方達にも呪いが掛かっていたとはねぇ」
「あの儀式の場に居た者の殆どが呪いに掛かっているよ、卑弥呼の呪いにね」
月の無い夜に七原は黙り続けて様子を伺っていた。
「僕らが君の前に姿を現した理由、知っているよね?」
黒髪の女、伊邪那美の魂をこの世から排除するためにアレックスと七原は現れたのだ。
伊邪那美という女はくすりと笑ってから得物を構えた。
それは鞭、言術者の支援武器だ。
「せっかくタケルと会えたんだから、此処で消滅される訳にはいかないのよ」
七原とアレックスも得物を取り出した。
七原の持つ支援武器は両腕にくっついた巨大な円形の盾。
彼女の服装は今までのコスプレとは違い、アレックスと同じ、スーツ姿だった。
アレックスが取り出した支援武器は一丁の拳銃。
「伊邪那岐が居るんだろう、何処に居るか教えてくれないかな?今回草薙を襲った怨霊も彼が操っていた事くらいは想像が付く」
「へぇ、流石草薙の右腕ってことかしら?2千年経ってもまだその頭脳は健在ね。でも・・・残念だけど教えてる事は出来ないわ・・・!」
黒髪、赤いドレスを着た女は鞭を振るった!うねる鞭は不規則な動きでアレックスの肩へと落下していく。
それを七原が右腕の盾で防いで、防御、途端に盾が八等分に分解した!
盾が崩れたのかと思えばその分解した盾の欠片は三角の形となり空中に浮遊する。
「伊邪那美・・・!」
初めて対峙する相手に口を聞いた七原は、腕を伊邪那美に向けると八個の浮遊する七原の支援武器がそれぞれ違う動きで高速で水無月に迫る。
「くっ・・・!」
それを避けんと後方に飛ぶが不規則に動く八つの支援武器を完全に避けきれず幾つかの武器が伊邪那美の体を切り裂いた。
一度の反撃に更に反撃を返そうと鞭を握り直す伊邪那美だが気付けばアレックスの拳銃の銃口が額に当てられていた。
「伊邪那岐は何処だい?」
一見決着が着いたかの様にみえるが、しかし、伊邪那美の表情はむしろ笑みが増すばかり・・・。その不気味な表情に疑問を抱いた途端、一閃の黒い太刀筋が銃口を伊邪那美へ突き付け押さえ込んでいるアレックスの首元へと迫ってくる――!
「――っくぅ!?」
唐突に迫ってきた太刀筋に気付きアレックスは伊邪那美を押さえつけるのを放棄して後方に跳躍、間も無く命の隣に着地した。
そして、アレックスはその太刀筋を振るった者の姿を見た・・・。
「な――、」
アレックス、そして命も同時にその姿を見て驚きの表情を隠せずにいた。
目の前に居るのは一人の少年。栗色の長髪で、長い髪を後頭部で結び吊るしている。
そして闇夜に溶け込む漆黒のロングコートを夜風になびかせ、片手には一振りの刀剣が握られていた。
月明かりが刀剣を怪しく照らす。
「天叢雲(あめのむらくも)――・・・!!・・・なるほど、ね」
しかしアレックスは自分の目の前に対峙する者が持つ剣がかつての愛刀であるにも関わらず、ニヤリと苦笑にも似た笑みを浮かべるのだった。
「・・・天叢雲と草薙を揃える気か。力の象徴を集めて何を企んでいるかは知らないが、伊邪那岐の企みに必要な物さえ解かってしまえば――・・・」
「ふふ、でもこちらには天叢雲が既にあるのよ? 草薙だって、もうすぐ・・・」
天叢雲と草薙・・・、それぞれの剣は一説には同一とされている。しかし此処に存在しているのは二つ、それぞれ別々の剣・・・。
「嗚呼、それと紹介しておくわね、新しい天叢雲剣のマスターを・・・」
伊邪那美が刀を持つ者の後方に立つと闇の中で笑みを浮かべた。
「彼の名前は、ウ ィ リ ア ム ・ ウ ェ ー ル ズ」
そしてアレックスと命の表情が再び驚愕なものとなる。
「ぁあ、そういえば、今の貴方も同じウェールズって名前があるらしいわねぇ?何か関係でもあるのかしら・・・?」
伊邪那美は同姓の理由を知っているにも関わらずわざとらしくアレックス・ウェールズへと問い掛けた、クスリクスリと笑いながら。
「・・・・・・・・・・」
一丁の銃を構えていたアレックスの手が軽く振るえ始めた。彼の目は恐れを映し出していて、そして銃のトリガーにかけた指が夏だというのに酷く冷えていた。
アレックスの頭の中で古い記憶が蘇る・・・、それはイギリスのある家を映し、赤く燃えて、全てを失い消えていく光景・・・、手元に残ったのは一人の愛する女性が持っていた小さい十字架のネックレス。
無意識の内に空いている左手が胸の中心辺りを服の上から掴んだ。
その服の下には小さい銀の十字架のネックレスがある。
肌に触れた十字架が一瞬チクリと痛みを作った。
「――ッレックス!アレックス!!」
命の声にッハっと我に帰り、目の前に対峙する者達を見直した。
しかし自分が自ら作ってしまった気の迷いと隙が相手の姿を見逃し、相手の二人は既にこの場から気配を消し去っていた。
「くっそ・・・っ!」
その場に残ったのは何も無い闇だけ・・・。
アレックスは拳銃の踵を傍に立つ一本の電灯にぶつけると空しい金属音が小さく響いた。
/
思い出し始めてる・・・。
そんな感覚が確かに俺にはあった。
しかし、思い出す内容は明るい物ばかりではない。
まだハッキリとは思い出せないが断片的に見える真っ赤な視界とドロドロの世界。
これは――、誰の記憶だ?
――俺の?
俺なのか?
それとも、別の何かなのか?
・・・できればそうで有って欲しい。
榊原の屋敷の客室で敷かれた布団がとても暑く感じた。
何度もその場で寝返りを打ちながら頭から離れない赤色と未だに手に残っている刀の柄の
触が少しずつ俺自身の存在を潰していっている様な気がした・・・。
愛里は何か知っているのだろうか?
―何処に居るんだよ・・・・?
・・・・・・。
・・・・。
そんな感覚が確かに俺にはあった。
しかし、思い出す内容は明るい物ばかりではない。
まだハッキリとは思い出せないが断片的に見える真っ赤な視界とドロドロの世界。
これは――、誰の記憶だ?
――俺の?
俺なのか?
それとも、別の何かなのか?
・・・できればそうで有って欲しい。
榊原の屋敷の客室で敷かれた布団がとても暑く感じた。
何度もその場で寝返りを打ちながら頭から離れない赤色と未だに手に残っている刀の柄の
触が少しずつ俺自身の存在を潰していっている様な気がした・・・。
愛里は何か知っているのだろうか?
―何処に居るんだよ・・・・?
・・・・・・。
・・・・。
/
誰もがもつ記憶。
そして記憶が示すのはその者の視点からの、過去――。
過去があってからこその現在、そして自分という存在。
過去がなければ、人はその存在を失ってしまう。
・・・ただ真っ暗な闇の中で自分が誰だか分からないというのは、一体どういう気持ちなのだろうか?
きっと苦しい筈。だから私は彼に過去を与えた・・・。
でも、それは同時に私が彼の存在を作ってしまったという事になる。
私はあの時、彼が目に浮かべていた涙を見て、助けてしまった。
でも、結局私のやっている事はナギと同じ・・・。
――ごめんね、秋。もう、ちょっと・・・だけ、ね。 もうちょっとだけ、貴方の過去に居る私を信じて・・・? 本当の貴方の存在の理由は、まだ思い出さないで――・・・ね?
秋――。
そして記憶が示すのはその者の視点からの、過去――。
過去があってからこその現在、そして自分という存在。
過去がなければ、人はその存在を失ってしまう。
・・・ただ真っ暗な闇の中で自分が誰だか分からないというのは、一体どういう気持ちなのだろうか?
きっと苦しい筈。だから私は彼に過去を与えた・・・。
でも、それは同時に私が彼の存在を作ってしまったという事になる。
私はあの時、彼が目に浮かべていた涙を見て、助けてしまった。
でも、結局私のやっている事はナギと同じ・・・。
――ごめんね、秋。もう、ちょっと・・・だけ、ね。 もうちょっとだけ、貴方の過去に居る私を信じて・・・? 本当の貴方の存在の理由は、まだ思い出さないで――・・・ね?
秋――。
そして時は止まらぬまま進んでいく・・・。
この世界の過去に隠されたモノはゆっくりとその姿を現し、そして黒いカーテンで覆い尽くして行くのだ。
過去からの現在。
PAST。それは過去。
PRESENT。それは現在。
本当に現在は過去からのPRESENTなのだろうか?
この世界の過去に隠されたモノはゆっくりとその姿を現し、そして黒いカーテンで覆い尽くして行くのだ。
過去からの現在。
PAST。それは過去。
PRESENT。それは現在。
本当に現在は過去からのPRESENTなのだろうか?
一人の男が祭壇に立ち、差し込む光に両腕を掲げて微笑む。
「さぁそのプレゼントの中身を、変えてしまおう。代わりのプレゼントはより良い物を――」
差し込む白い光が赤いモノとなり、祭壇を真っ赤に染めてしまう。
その中心に眠る金髪の少女の体を巻き込んで・・・。
「――《言語製作》、」
現在は崩れ始めていた。過去という名の大黒柱から・・・。
「さぁそのプレゼントの中身を、変えてしまおう。代わりのプレゼントはより良い物を――」
差し込む白い光が赤いモノとなり、祭壇を真っ赤に染めてしまう。
その中心に眠る金髪の少女の体を巻き込んで・・・。
「――《言語製作》、」
現在は崩れ始めていた。過去という名の大黒柱から・・・。
第三章 PAST END