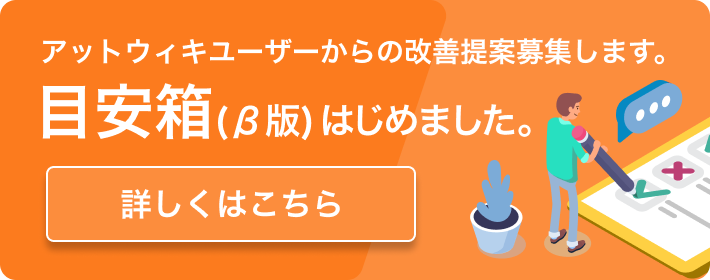「ベア・司 純愛物②」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
「ベア・司 純愛物②」(2005/07/17 (日) 01:25:56) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
自動ドアを通るとちょうど一階にエレベーターが到着したところだった。<br>
次々と人が乗り込んでいくのを見て司は慌ててベアの手を引っ張った。<br>
「ベア、早く早く! いっちゃうよ!」<br>
「その呼び方はやめてくれって」<br>
「だって呼びやすいんだもん」<br>
司は頬を膨らませた。<br>
「あーあ、もたもたしてるから行っちゃった」<br>
「すまん」<br>
「それにベアだってぼ……私のことよく司って呼ぶじゃない」<br>
「すまん」<br>
なかなかこないエレベーターを待ちながら司は言った。<br>
「なんか、さ」<br>
「ん?」<br>
「実感わかないんだ」<br>
「ここが、The Worldの中じゃないってことか?」<br>
「それもちょっとあるけど……こんなに幸せでいいのかなって。<br>
夢だったり、それこそゲームの続きなんじゃないかって」<br>
うつむく寂しそうな横顔にかつての『司』の孤独が垣間見えて、ベアは司にどう声をかけたものか考えた。<br>
「司」<br>
結局うまい言葉が見つからず、仕方なしに彼は司の髪をくしゃりと乱した。<br>
語る言葉のない小説家はただのしがない40男でしかなく、ベアは己の未熟を再認識した。<br>
司はなおもうつむいたまま、黙ってベアの手を受け入れていた。<br>
その頬がうっすらと色を変えていく。<br>
二人の間にいつもとわずかに密度の違う空気が流れたそのとき、ようやくエレベーターの到着を示す電子音がなった。<br>
降りる人の波が去るのを待って乗り込む。<br>
同乗者数人のために「開」ボタンを押してやりながら、ベアは司にたずねた。<br>
「何階だ?」<br>
「えーっと……3階」<br>
全員乗り込んだのを確認して離した指を3階のボタンにのばす。<br>
3階……何売り場だったかな。<br>
そんなことを考えながら周囲に目をやる。<br>
ベビーカーを押している夫婦。<br>
友人同士であろう、中学生くらいの少女三人組み。<br>
腕を組んだ若いカップル。<br>
<br>
じゃあ、自分たちは?<br>
どうなのだろう。どういう風に見えるのだろう。<br>
休日に一緒に買い物に来た仲のよい父親と娘?<br>
『父親』か。<br>
その単語は少しの苦味をベアの心にもたらした。<br>
自分は父親としても夫としても失格したのだ。<br>
<br>
「何ぼうっとしてるの? 着いたよベア」<br>
司に袖を引かれてベアはわれに返った。<br>
またしても司が彼をゲーム内の名で呼んだために、一緒に乗っていた人間たちの怪訝そうな顔が横目に見えた。<br>
「あ、ああ」<br>
だが彼はそのことで司をとがめたりはせず、促されるまま鉄の箱から降りた。<br>
<br>
「何考えてたの?」<br>
「ン――たいしたことじゃない」<br>
「たいしたことじゃないなら教えてくれたっていいじゃない?」<br>
司は頬を膨らませた。<br>
その子供っぽい仕草に、ベアは苦笑しながらも素直に告白する。<br>
「そうだな……俺たちは親子に見えるのかなと考えてたのさ」<br>
その言葉で司の頬は急速にしぼんだ。<br>
「どうした? 何か気に障ることでも言ったか?」<br>
「なんでもない」<br>
そう言って司は笑顔をベアに向けた。<br>
「なら、いいが」<br>
立ち並ぶマネキンの群れをぬって二人は歩いた。<br>
そしてベアは気づいたのだ、前方に見える売り場の名称が何なのか。<br>
ピンクのリボンやら純白のフリルやらが主張するそこは、『下着売り場』だった。<br>
<br>
胴体だけのほの白く光るマネキンが形状記憶合金ワイヤー入りのブラジャーの宣伝のために燦然と自己主張している。<br>
いや、ここはデパートであり、その物を売るという目的上商品のディスプレイに力を入れるのは至極当然で、その軽くて硬い無機物の群像がひときわ目に付くのも当然だ、当然なのだが……<br>
なぜこんなにも自分はうろたえているのだろう。<br>
齢40も越えた、それなりに人生の経験値も稼いできた、それなりに感情のコントロールもできる自分が。<br>
下着売り場自体が恥ずかしいのではない、と思う。<br>
溢れる色の洪水が目に痛いのは認めるし、自分の容貌があまりにもこの場所にそぐわないことも認める。<br>
だがそれは今抱えているどこかいたたまれない気持ちの理由ではない。<br>
「うわー、すごいビラビラしてる」<br>
そんなベアの葛藤をよそに、司は白いワゴンに山と積まれた上下ペアで1000円セールの真っ赤なやつを手にとって眺めている。<br>
「派手すぎ。誰が買うんだろこんなの」<br>
しげしげと見てからワゴンに戻すと、司は今度は黒いレースのパンティーに興味を持ったらしく細かい模様を数え始めた。<br>
「もっとふつーのないのかな」<br>
ね? と無邪気に見上げてくる顔にどう返せばいいのか。<br>
ベアは頬の筋肉に力を入れた。<br>
レジの女性のなんてことのない視線が、今の彼には酷く突き刺さって痛い。<br>
売り子担当であろう清楚なロングヘアーの女性がにこにこと営業スマイルで近寄ってくる。<br>
流石に手馴れたもので、彼女は早速司にいくつかブラジャーを見立てている。<br>
<br>
―― サイズはいくつ?<br>
測ったこと無い……<br>
あら、そう? じゃあ測ってみますか?<br>
え、ここで?<br>
はい。今できますよ。――<br>
<br>
こんな会話を目の前でされた。<br>
……どうしろというのだ。<br>
ベアは完全に蚊帳の外に追いやられた男の身である自分を持て余していた。<br>
そうして視線をその辺にさまよわせているうちに、いつのまにか話はまとまったらしい。<br>
司はベアをちらりと見ると、「待っててね」と言い残して店員と試着室に行ってしまった。<br>
ベアは再び思った。<br>
どうしろというのだ。<br>
この位置ではときおり試着室の中の会話の断片が聞こえてくるではないか。<br>
スポーツブラをもっぱら愛用していたとか、ワイヤーが気持ち悪くて慣れるまで苦手だったとか。<br>
ベアは行き場の無い気持ちのままにそれとなく視線を移すと、レジの女性と目が合ってしまった。<br>
あわてて顔を元の位置に戻す。<br>
やはり彼女も俺を司の父親だと思っているのだろうか。<br>
その場合、彼女の想像はおそらく離婚家庭にたどり着くのだろう。<br>
普通はこういったところへは母親とくるものであり、男親とふたりでくる客は滅多にいないだろうから。<br>
カーテンのジャッと開く音でベアはそちらを向いた。<br>
「B65だって」<br>
「……」<br>
彼は沈黙で返すことしかできない。<br>
「あのね、トップとアンダーの差が13ぐらいだとBなんだって」<br>
「……そうか」<br>
今度ははっきりと店員のくすくす笑う声が聞こえた。<br>
司はなおもベアに話しかけようとして気づいた。<br>
……ひょっとして、照れてる?<br>
「15だとCなんだけど。2センチしか違わないのに」<br>
「……ああ」<br>
「はやくおっきくなんないかなぁ。今度から家で定期的に測ってみようかな」<br>
「……」<br>
「ねえ、メジャーって置いてある?」<br>
「確かあったと思うが」<br>
「こう、下から少し持ち上げて測るのが正しい測り方なんだって、店員さんが教えてくれたんだ。<br>
ベアは知ってた?」<br>
「……いや」<br>
「そうだよね、だいたいの男の人は知らないよね。<br>
でね、二人で測るんだって。だからベア、測るときは手伝ってくれる?」<br>
<br>
絶句。<br>
<br>
そうする以外に彼に何ができただろう?<br>
硬直しているベアの耳に届いた麻痺治しの呪文は、司の噴出す音だった。<br>
「あはは! ベアってば顔固まってるよー」<br>
司はそういってぺろりと舌を出した。<br>
それでようやくベアも思い至った。<br>
「……からかったな」<br>
「えー、なんのこと?」<br>
こいつめ。<br>
ベアはらしくもなく狼狽した自分を恥じ……、というよりは呆れ、同時に司の微妙な変化を好ましくも思った。<br>
それはおそらく昴やミミルといった同年代の少女たちに与えられた力のおかげ。<br>
そういった意味では、THE WORLDをプレイしたことは司にとって良かったのかもしれない。<br>
司は屈託無く笑う。<br>
その姿には、かつてゲームの中で見せたなにもかもをあきらめたような、なげやりな暗い影はない。<br>
ベアは気づかなかった。<br>
その影に光を投じ、司の目に輝きを取り戻させた出会いの中に、自分も含まれているということを。<br>
だからこそ司は、嬉しいと感じるのと同じスピードで、実は傷ついているのだ。<br>
それは司が、彼にしてみれば自分を引き取ったのは『父親』としての贖罪の意味しかないと知っているから。<br>
自分の役割は『娘』でなければいけない。彼の『子供』でなければ。<br>
気づかれてはいけないのだ。<br>
彼が自分を引き取るといってくれてからほのかに芽生え始め、しかし確実にふくらみ続けてきたこの胸の花に。<br>
けれど同時に――――いっそ、気づいてくれたら良いのに――――とも、思ってしまうのも事実だった。<br>
そうすればわずかにでも、このつらさも払拭されるような気がするのだ。<br>
もちろん本心では、そんなことはないのもちゃんとわかっている。<br>
きっとそんなことになればもう今のような関係ではいられない、<br>
あの家にある微妙な雰囲気は崩壊し、ただ気まずさだけを残して司はまたひとつの痛みを得るのみだ。<br>
……言えないよ。<br>
やっと手に入れた居場所を失うということは、たった一言に対して負うにしては大きすぎるリスクだった。<br>
<br>
司は水色のブラジャーとショーツを手に取ると、<br>
「色がきれいだし、これがいいなぁ。どう思う?」<br>
などと、ベアがまた面食らうだろうことを予想したうえで意見を求めてみる。<br>
小首をかしげた上目遣いのおまけ付。<br>
「こういうの好き? 嫌い?」<br>
私のこと好き? それとも――嫌い?<br>
はっきりそうとは問えないから。<br>
「…………」<br>
一方ベアはそんなふうなことを訊かれても返答に窮するわけで。<br>
だってそうだろう。<br>
そりゃあ自分も男だ。<br>
40を過ぎ、妻とは別れたとはいえ枯れるにはまだ早い年齢だ。<br>
女性の下着を好きか嫌いかと問われれば、まあ嫌いではない。<br>
しかし。<br>
しかしだ。<br>
<br>
自分は男でしかも少女とは30ほども歳が離れていて、<br>
先ほどから挙動不審気味に少女に翻弄されていて、<br>
今の状況は『休日に買い物に来た父と娘』ではなく、『援助交際のパパと女学生』に見えるのではないかと。<br>
思い至ってしまった彼は体に余計な力が入って硬直した。<br>
「……」<br>
「……?」<br>
あれ? ベアの様子、へん。<br>
石になってしまった小説家を救うべく、司は小悪魔な追及をぴたと止めた。<br>
<br>
司が突然ベアをからかうのをやめたのも。<br>
ベアがいらぬ心配をして少々普段の彼らしくなかったのも。<br>
そんな二人がどういうふうに販売員の目に映っていたのかということも。<br>
それら全てが偶然絡まりあってその事態は生まれてしまった。<br>
いってみればタイミングが悪かった。悪すぎた。<br>
悪すぎて、だから……、――――後悔しても遅かったけれど。<br>
「娘さんと仲がよろしいんですね」と笑顔で言った店のお姉さんには悪気なんてこれっぽっちもなくて、なかったのに、<br>
それなのに司の胸が痛んだのは、続くベアの一言のせいだった。<br>
「あ……はは、そうなんですよ」<br>
なんで。<br>
……なんで?<br>
(僕、ベアの娘じゃないよ!!)<br>
そう叫んで泣き出して、その場から走り去ってしまえたらどんなにか良かっただろうに。<br>
つらいよ。<br>
どうしてこんなにつらいんだろ。<br>
ああ、そっか。<br>
僕、やっぱり、ベアのこと……。<br>
司は『僕』であったころの『司』に戻ったかのように、傷ついた身体を小さく丸めてうずくまってしまっていた。<br>
「司?」<br>
「……」<br>
きゅうにしゃがんでしまった司を気遣うようにベアが声をかける。<br>
「疲れたのか?」<br>
「……うん」<br>
「そうか。じゃあ今日はもうやめにして帰ろう……家で休め」<br>
「……うん」<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
次の休み。<br>
司はファーストキッチン、通称ファッキン(なんとも物騒な略語だ)にいた。<br>
テーブルの上には季節限定デザートのイチゴミルフィーユパフェが載ったトレーがふたつ。<br>
その向かいには制服の女子高生。<br>
ミミルはスプーンで上のアイスクリームをすくうとぱくりと一口食べた。<br>
「くぅ~、おいし」<br>
司は彼女があんまりおいしそうに食べるのでつられて笑顔になり、自分もスプーンを口に運んだ。<br>
「でぇ、どうよ司」<br>
「どうって何が?」<br>
興味津々、といったふうに目をきらきらさせて身を乗り出してくるミミルに司は若干たじろいで言葉を返した。<br>
「決まってんじゃん。新しい生活よ、ベアとの。もう慣れた? あのおっさんに変なことされたりしてない?」<br>
「……ああ」<br>
いっそ変なことでもしてくれればこっちは嬉しいのに。<br>
「よくしてくれるよ、すごく……」<br>
父親として。<br>
「へえ、そっかぁ。安心した」<br>
「ありがとミミル、心配、してくれて」<br>
「いえいえ」<br>
ミミルのパフェはもうほとんどなくなってしまっていた。<br>
司はふと、思いついたようにミミルにたずねた。<br>
「ねぇ、ミミル」<br>
「ん?」<br>
「ミミルってさあ、彼氏……いる?」<br>
「な、なに言ってんのよー! い、いないよそんなの」<br>
「そうなんだ、じゃあ、好きな人は?」<br>
「う? うー、う~ん……ちょっちいいかなぁって思ってる人は、まぁ」<br>
「ふーん……」<br>
司のパフェもだいぶ食べ終わってきた。<br>
下のほうのコーンフレークがスプーンに触れてさくさくと音を立てる。<br>
「あたしのことより、司のほうこそどうなの?」<br>
「え?」<br>
「好きなヒト。いないの?」<br>
「うん……いる、と思う」<br>
さくり。<br>
「えっ! どんな人!?」<br>
先ほどより身をずずずいっと乗り出してミミルは司に迫った。<br>
「かっこいい? どんなタイプ? 誰に似てるの?」<br>
「ベア」<br>
「……へ?」<br>
ミミルの目が点になった。<br>
「へ、へー。ベアに似てるんだ。渋好みなんだねぇ司……」<br>
「ううん、そうじゃなくて。ベアに似てるんじゃなくて、ベアなの」<br>
そう言うと司は最後の一口を口に入れると席を立った。<br>
「ごめんミミル、僕もうそろそろいかないと」<br>
「あ、うん」<br>
「じゃあまたね、今日はありがと」<br>
司が階段を降りていってしまっても、ミミルはまだ夢でも見ているかのようにぼーっとしていた。<br>
「え?」<br>
今司はなんて言った。<br>
「……え?」<br>
司が。<br>
ベアを。<br>
「…………え?」<br>
<br>
――好き。<br>
<br>
「なんですとぉ~っ!?」<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
階段を上りながら、司はあのゲームの中を思い出す。<br>
<br>
さわさわ、さわさわ。<br>
髪が風になぶられて。<br>
二人は肩を寄せ合って座っていた。<br>
風の清々しさも、ぶつかる肩の温かさも、ゲームの中のことなのに、自分にとっては現実で。<br>
でも、彼女の体温を感じていられるなら、この特殊な状況はそんなに悪いことばかりでもなかったと、ちらり思った。<br>
<br>
(必要なのは、“勇気”です)<br>
――勇気?<br>
(人からの受け売りなのですが……)<br>
――ああ、クリム? いかにも言いそうだね、そういうこと。<br>
(けれど、私はその言葉のおかげで自分が為すべき事を為せたのだと思います)<br>
――昴。<br>
(一歩踏み出せる勇気さえあれば、さっきとは少し違った景色を見ることができる。<br>
リアルでは自分の足で踏み出すことの出来なかった私が言うのもなんですが……)<br>
――違った景色……。<br>
(司。あなたは強い。ただ、自分の中にある勇気に気づいていないだけ――)<br>
――僕の中にあるかな。こんな僕の中にも、勇気が。<br>
(あります。だって、私には見えるから。あなたの心に触れたとき、私にはわかったんです)<br>
<br>
ありがとう、昴。<br>
必要なのは勇気。<br>
今のままじゃだめなんだ。<br>
玄関を開けて、今の景色を変えるために、一歩。<br>
心臓がものすごくばくばくいっていたけれど、司はためらったりしなかった。<br>
「ああ、司。おかえり」<br>
「ただいま。あ、そうだベア、ミミルがよろしくって」<br>
「ミミルか。元気だったか?」<br>
「うん、『ちょー元気』だって」<br>
「ははは、そうか」<br>
「でね、僕」<br>
息を吸って、精一杯踏み出す告白を、した。<br>
「ベアが好きだって、ミミルに言っちゃった」<br>
「……なんだって?」<br>
ベアは信じられないものを聞いた、といった顔をした。<br>
「僕、ベアが好きなの。もう遠慮しないから、覚悟してね」<br>
ご丁寧に指まで突きつけて、宣戦布告をする。<br>
勝負はこれからだった。
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: