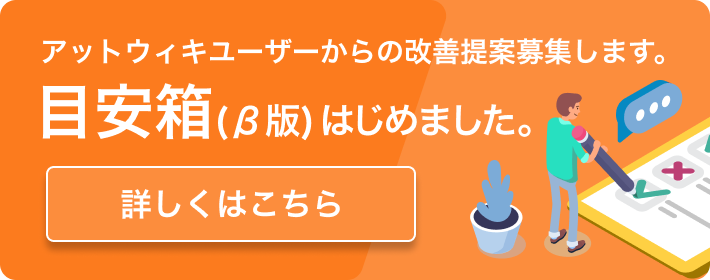◇ ◇ ◇
読んで・・・・・・しまった。
男さんの心―――同僚君がこんな風になってしまったきっかけも、それに対する男さんの気持ちも・・・
心の読める私には、男さんから否応なしに流れ込んでくる。
以前、放課後の昇降口で、飼育委員の仕事を終えた同僚君を引き止め、話をしていた男さん。
その時に感じた彼の、暗く沈んだ感情と罪悪感めいたモノ。そして、私を少しだけ驚かせた、男さんにも心の中に読めない部分があるという事実。
心が読めないのは本人が誰にも知られたくない、と強く思っているからだ。
同僚君の場合は、その想いが極端に強いからほとんど読めないけど、人付き合いが良く誰とでも分け隔てなく接する男さんなんかは、実にクリアに心の中を覗ける。
そんな彼が唯一ひた隠しに、誰にも知られないよう心の底に沈めていたはずの記憶は、偶然にも私の知るところとなってしまった。
それは、
たまたま私がこの時間にこの場所を通りがかったが為に
たまたま男さんがこの時間この場所に同僚さんを呼び出したが故に
本当に、誰も意図していない、泣きたいほどの『偶然』が重なった結果として男さんが知られたくない事を、私は知ってしまったのだった。
「通訳・・・・・」
私が現れたことで男さんが少し動揺し、その変化を感じ取った同僚君もこちらを振り向いてきた。
同僚君は少し眉をひそめながら、私の通称を口にする。
先ほどまで殺伐とした会話をしていた為か、さしもの彼も、私の読心を拒絶しきれないみたいだった。
確かに中学時代の二人に起こった出来事や、それ以降の変化といった細かい出来事は男さん側の視点でしかわからなかった。
同僚君の心はそういった部分に関しては相変わらず、鉄壁といえるほどの頑なさである。
けど、それでも同僚君からは、『先ほどまでの顛末』と『思いがけない人物の登場』による動揺が確かに伝わってきた。
それは、彼の向こう側で立ちすくむ男さんと比べれば、空気の澄んだ冬の空と夏場の霧の夜ほどの違いはあったけど。
「・・・・・・・・じゃあな。」
「あ・・・」
そうやって、私達、飼育委員どうしが視線を交わしたまま静止していると、不意に声がかかる。
――――男さんは、踵を返してその場を去ろうとしていた。
予期せず彼がとった行動に私は短く声を漏らす。
男さんはそれに、一瞬こちらを見たが、すぐまた背を向けて歩みだした。
彼の行動は本当に突然で、今まで私達に目をやっているのが嘘のような無関心さだった。
私と同僚君は、お互いに向けていた視線を同時に男さんへと移していた。
校内のバレンタインデー熱を冷まして余りあるような、冷たい冬の空気に満たされたA棟の影。
その先にある日の当たる校舎の角へ向かって、ビロードの様に真っ直ぐ伸びていくアスファルトの道を男さんはスタスタと進んでいく。
途中にあるマンホールを頓着なく踏み越えて、やがて光がさして明るくなっている場所へ出るとこちらを一瞥することもなく曲がって消えていった。
私達は、彼が消えた後も視線の向きを変えずに、今まで男さんが歩いていた道を見ていた。
見つめることも、睨むこともせず、ただ意味もなくそこにある空間を『見て』いた。
立ち位置の都合上、私の視界には同僚君の背中が入っている。
彼の心は、既にほとんど読めなくなっていて、何を思ってずっとそちらを見ているのかはわからない。
私の目には、冷えきってガランと空虚に映るA棟脇の空間が、彼にはどう見えているのだろう?
先程、飼育小屋へ向かう前に一度通った際、ここで通訳をしたけれど、その時とは全く印象を変えてしまったこの空間を見て、彼は何を思っているのだろう?
さっきまでの男さんの記憶と感情は、ほんの一瞬で私がすべてを理解してしまうほど強かった。
事実、実際に聞いたのは男さんが『大馬鹿野郎』と叫ぶ所だけだ。
たまたま通りがかったに過ぎない私が、事の顛末を理解して、且つその際の男さんの心の動きまでも見えてしまった。
それ程、あの怒号には多くのモノが含まれていた。
あれほど強く複雑な感情はそうそう感じられるモノではない。
中学時代の忌まわしい記憶に始まり、
理由も定かではない同僚君の変化に対する戸惑いと苦しみ、
イジメを止めようともしなかった自分への罪悪感。
どれほど時が経っても修復されない関係への疲労。
それを跳ね除けてでも何とかしたい想い。
何としてでも旅行に連れて行く。そこですべて終わらせるという決意。
そして、そんな彼の決意さえも無意味に終わらせてしまう現実の理不尽さ。
それに対する深い深い絶望と憤り。
人間の心が複雑な理由の一つに、本心を直接伝えると摩擦が生じてしまう、といったことがある。
だから、そうそう人間の言動は本心と一致したりしない。
私も含めて、誰だって意味もなく人とぶつかり合うのは嫌なのだ。
男さんもその例に漏れない。漏れないどころか彼は、人一倍その傾向が強いように思う。
割とクラスの中で親しまれているのは、そういう所があるからなのだろう。彼が自分の意見をはっきり言ってる所は、あまり見たことがない。
そんな男さんが今回だけは、自分の意見を無理にでも押し通そうとしていた。
傷つくのも摩擦が起きるのも、ほとんど気にしていないようだった。
それは・・・どれほどの決意だったんだろう?
私に同じ事ができるかと聞かれれば・・・・・・・・・・・・・・難しいに違いない。
それなのに、同僚君は、そんなことはお構いなしに、まるで何時もと変わらない調子で跳ね除けてしまった。
男さんの心には耐え難いほどの、胸を焼くような、臓腑を無理矢理下に引っ張られるような苦しみが満ちていた。
ぶつかり合うことも覚悟で、傷だらけになることも覚悟で、勝負に出たはずなのに、現実は戦うことさえ許してくれない。
最後の最後、去り際の彼から感じたのは、紛れもない『諦め』だった。
友を助けるために走って、走って、走り続けて。
襲い来る障害を半ば命を賭して乗り越えはしたけれど、総身萎え精も根も尽き果て、そして道半ばで全て投げ出してしまう。
吐き出すことも吸うことも許されなかった呼吸を、深々と行った瞬間にも似た、重荷から解き離れた開放感。
それと、胸の奥をかすかにチクチクと刺激し続ける幻のような罪悪感。
私はそんな男さんの強い心の動きを認識しながら、現代文の授業でやった太宰治の小説の事を思い出していた。
確か二学期の半ば、文化祭に前後してやった所だ。
男さんの心の動きが走れメロスのとある一説に似ていて、そこから連想したためだった。
・・・・・・・・・・・・・私は、通訳は、男さんがあんなにもがき苦しんでいる事を知りながら、なんの感慨も抱いてはいなかった。
彼の想いも苦悩も決意も放棄もなにもかも。
何もかも私の中を素通りするだけの心理的反応に過ぎない。それ以上の事は何もなかった。
『通訳』にとっては、それが普通だった。
心を読めるから、人のいろいろな感情が伝わってくる。
それにいちいち同調していると、気が狂ってしまう。
そうしなけらばきっと、感情の波に翻弄され続けて、今現在まともな人生を送れていたかも怪しい。
あくまで一歩置いた距離から。
なるべくその気持ちに染まらないように。
そう心がけてきた積み重ねが今の私だった。
誰かの強い心の動きを『読む』ことはできても、『共感』はできない。
男さんの悲痛な叫びだってどこか遠い国、もっと言うならフィクションを見るみたいに現実味を感じない。
それで良いはずだった。
―――なのに今、私はこう考えている・・・・・・
『男さんがこれほど苦しんでいるのに私は・・・・・・
友人が苦しんでいれば、人は誰でも心を動かすものなのに・・・・・・
私は心を動かせない・・・・・・・
動かせないから私は・・・心の動く普通の人と解り合うことなんて出来ない。』
そんな事、昔から気にもしたことなんてなかったはずなのに・・・
私が人と違う、なんて自明すぎて疑問にすらならなかったのに・・・
今はその事実が心臓をつかんでくる。
人とは違うという事。
男さんの苦しみを見て、何とも思わない自分を異常だと、おかしいと思っている自分が確かにいる・・・
教室でサトリさんと貸した本について話したときに感じた
ツンさんと話している最中に気づいてしまった
目の前が暗くなって動きたくなくなってしまうような、寒気を伴う寂寥感がこれ以上ないほど強く感じられた。
なんでこんなに私は思い悩んでいるんだろう?
こんな事で、私が心を動かすのはおかしいのに。嫌なのに。感情があることがこんなに辛いなんて。
事実を拒絶しようとすればするほど、反対に自分の体の内が冷えていく感覚は強まっていく。
それが嫌でたまらなくて、体全体を両腕で抱いてみる。
ここに来るまでは確かに熱を帯びていたはずの両手が、冷たい氷のようになっていた。
ヒヤリとした感触をセーラー服を通して二の腕に感じながら、私は両手に力をこめる。
なのに私を覆う寂しさは、その行動をあざ笑うかのように内部にとどまり続けている。
「この気持ちは―――――なんなんだろう?」
知らず、口にしていた。
そこで初めて自分が酷くイライラしているのに気がつく。
こんな、カッとするような気持ちは滅多に抱かないはずなのに・・・・・口に出してしまうなんて・・・・・・まだ、同僚君がここにいるというのに。
そう思って、彼の方に目をやった。
なんだかそれが、ずいぶん久しぶりの行動のような気がした。
ついさっきも、そうやって視線を交わしていたはずなのに。
「・・・・・・・・・・・・」
同僚君は、私が苛立たしげに呟いた事に少し驚いてるみたいだった。
眉間のしわが少しだけ薄くなっている。
相変わらず無言だったけど、それでも表情の変化くらいは読み取れた。
左右に揺れ動く視線は、急ぎながらも何かを待ち続けている為に、そこから動けないかのように見えた。
「あの―――・・・・・そろそろ時間ですので、私はこれで」
「ん?―――あ、ああ、、そうだな」
どうも急いでいたのは、もうすぐ授業が始まるのからのようだった。
ただ、あまりに気まずい現場を、あまり見られたくない人物に見られた、という事実にまるで無頓着でもいられなかったという訳だ。
男さんが去った事で一応は用事が終わったからといって、それで「はいさようなら」と言える気分にはなれず、なにかしら上手くその場を去る口実を探していたらしい。
そんな事が察せられたので、私は彼にきっかけを与えてみた。
案の定、同僚君はあまり変化しない表情の裏側でホッとしていた。
「それじゃ、」
彼はそう言って、男さんが辿ったのと同じ、A棟のクリーム色にコーティングされたコンクリート壁の脇を、一歩一歩確かな足取りで踏み出していた。
けれど、それは、どこか影を感じさせる歩き方でもあり。
なぜだか今にも折れてしまいそうな茎のような弱さを連想させる。
そうやって、じっと見つめていると、ふと彼が立ち止まってチラリとこちらを見た。
彼はいつもやっているように手を上げて別れの挨拶とした。
私はそれにぼんやりと返しながら、彼の心から何かが流れ込んでくるのを感じて――――――
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
――――――――――・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・
嘘・・・・・・・・です。
こんな事・・・・・・・嘘・・・・です。
こんな・・・・・・・・・
私は、いつの間にか、自分でも知らないうちに同僚君の心を読んでいた。
信じられない話だけど、いつも、どれだけ意識を集中してみても、ほんの上辺だけしか読めない彼の心が。
寝起きのぼんやりとした頭にかかる靄のように、定かでないはずの彼の感情が今は、コーヒーか栄養ドリンクを飲んだ後のように冴え渡って理解できた。
けど、そんな事、今の私にはたいした問題じゃない。
なんで同僚君の心が読めたかなんて、本当にどうでもいい話だった。
『彼が私と同じ気持ちだった』という事実に比べれば。そんな事は些事に他ならない。
同僚君の心にあったのは、凍りつくような寂しさと『普通』の人への距離感だった。
彼は、世界全体を敵に回しても何も変わらないと私が思っていた、飼育委員の同僚の彼は。
私がさっきまで感じていたのと、全く同じ感情を抱えていたのだ。
『あの、彼は、虎吉も『もうちょっと仲良くしてほしい。二人は似た者同士なんだから・・・』と言っております』
どこか、恐らくは世界の果てに程近いところで、五時限目の開始を知らせるチャイムが鳴り響いていた。
けれど私は焦りをほとんど感じない。
背中にはじっとりと汗がにじんでいて、小春日和の風にさらされながら急速に冷気を強めていった・・・・・・