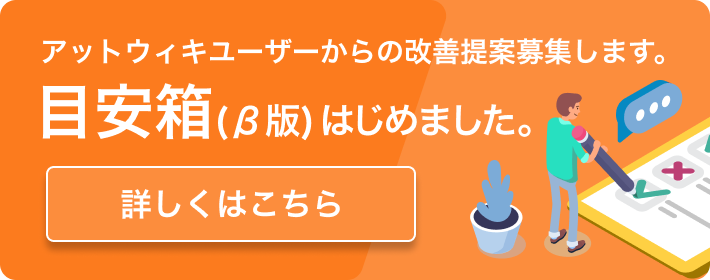『彼』がその古本屋の常連客になってから、随分と長い時間が経っていた。
その店を見つけたのがいつの頃だったかは、彼自信にもよく思い出せない。
気がつくとギリギリで『駅前繁華街に在る』と言えるその店の常連となっていた。そんな感覚だ。
けれど、カンカンに日が照りつける熱い盛りにも足しげく通っていたのは確かだし、さらにそれ以前。今みたいに寒い季節の頃には、既に常連客になっていた記憶がある。
だから少なくとも、彼がそこに通うようになって一年以上は経つ計算になるはずだ。
古本屋の立地は一応『駅前』と言う事になるのだろうか。
彼の卒業校でもある試立新ジャンル学園の最寄駅。
そこから放射状に広がる数本のメインストリートには、遊興施設や飲食店、或いはスーパーや商店街、生活雑貨屋に服飾店などといった、地方都市に必要なおおよその店舗が備わっていた。
学生の帰宅や主婦の買い出しが重なる時間帯には一部の通りで交通制限がしかれ、歩行者天国が姿を現したりもする。
一般に駅前繁華街の通称で呼ばれるそれらの通りの一つ。
メインストリートの中ではあまり賑わっていない部類に入るその通りを、途中で左折して右折してまた左折して右折して。
駅前の賑わいから遠ざかる形で、数限りない曲がり角を辿った先にその店はあった。
良く言えばその道の通だけが通っていそうな、悪く言えば小汚くて入ることが躊躇われそうな、ラーメン屋や喫茶店、それから似たような書店や古本屋を両隣りに。
道を挟んだ向い側には、寒色系をした色気のない、それでいて圧倒するようにそびえたち影を生むオフィスビルが建ち並んでいる。
ビル群と古本屋の間の道は、日が西に沈みかける僅かな時間を除いては、ほとんど影の中にあった。
オフィスビルの列が終ると道にも日が射すようになるのだが、同時にそこは『繁華街』ではなくなっている。
つまり、古本屋の界隈は住宅街と接していた。
どのくらい接しているかというと、木枠にガラスをはめた入口を出て店の前に立つと、50mほど先に一般家屋が並んでいるのが視認できるくらいだった。
◇ ◇ ◇
そんな繁華街の辺境も辺境。生存限界ギリギリといった位置に建つ、古本屋の内部。時刻は午後6:00より少し前。
「ここに一冊のベストセラーがある」
「ありますねえ」
客寄せのつもりなのか、店内の本棚には最近話題のベストセラーがちらほらと見受けられる。
けれどむしろ目につくのは、ベストセラーの数と同じくらいある本棚の空白。それと、店全体を占拠しかねない勢いで床に積み上げられた本の山。
今現在の店内の客は、常連の彼を除けば、ダッフルコートを羽織った高校生くらいの少年と少女がそれぞれ一人ずつ。そのどちらも、彼が以前何度かこの店で見た顔ぶれである。
二人とも空白の目立つ本棚の前に立ちながらも、そこから本を取るようなことはせず、床に積み上げられた方から選び出して吟味していた。
1メートル近くまで積み上がった本の塔。そこから、器用にもど真ん中の一冊を抜き出し読んでいる少女の姿が、常連の彼の目に入る。
―――いい加減・・・
ここの店主はお客さんの為に一度本を整理するべきだ。少なくとももう少し快適に店内を歩けるようにするべきだ、という思いが彼の頭をよぎる。
が、同時に、ここの店主の性格を考えるとそんな事はまずあり得ないというのも解っていた。
「こいつがなかなかの売れ行きなんだ。まあマスコミや携帯会社の猛プッシュ、というのもあるだろうけどね」
「はあ。まあ俺は読んでませんけどね。」
「私も読んでないよ。」
「そうですか」
「そうね」
「……………」
「…………・・・・・・・ワッ!」
「……………」
「・・・・・・・・・―――微動だにしないのはどうかと思うんだけどな?お姉さん」
「なんか言いました?」
「(-Αー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
いや?なんでも?」
「そうですか」
「まあともかく、これがなかなかの売れ行きでさ・・・・・・」
彼は、店内の自分以外の客に注目してみた。
彼が今立っている奥のカウンターから、今一度背後に視線を向ける。
開店から今まで店内を照らし続ける蛍光灯の白い光は、あたりが暗くなり外部からの明かりが無くなったため、その存在感を増していた。
壁や本棚など、店内にある物すべてが日の昇っている時間とは違った輪郭を浮かべている。
そんな中で、少年と少女が同じ本棚の列の比較的近い位置で立ち読みしているのが見えた。
こうやって書くとなんだか、二人の間に特別な関係でもあるかのように錯覚しそうなものだが、少なくとも常連の彼が知る限り彼等は赤の他人である。
というより、接点なんてこの古本屋以外には恐らくあり得ないであろう、全く違うタイプの人間であった。
少女の方は切れ長の瞳と肩まで伸びた髪が印象的だった。透き通るような白い肌も相まって、間違いなく美人の部類に入るだろう。
ただ、その立ち居振る舞いや言動は、全体的に淡白だった。
何度かこの店で買い物をしているのを彼は見ているが、その時の様子も淡白だった。
客に絡むのが三度の飯より好きなここの店主につかまっても淡白だった。
ともかく淡白だった。誰がなんと言おうと淡白だった。新ジャンル(嗤)。
少年の方は一見すると普通だった。髪を染めているわけでも、過度に乱れた服装をしている訳でもない。かと言って、オタクっぽさやガリ勉じみた感じもない。
強いて特徴を挙げるならば、全体的に均整のとれた体型をしていると言った程度で、取り立てて目立つところのないごくごく普通の外見をしていた。
ただ、その立ち居振る舞いや言動は、明らかにタダモノではなかった。
何度かこの店で立ち読みをしているのを彼は見ているが、一緒に見てしまったのだ。
本棚から伸びる、生きている人間ではありえない蝋のように白い腕を、蚊を殺すのと同じ要領で彼が『グシャッ』としてしまったのを。
客に絡むのが『うしおととら』より好きなここの店主も、『グシャッ』とするのを見てしまったらしい。
少年が本をカウンターに持ってきた際には、普段では決して拝めない大手チェーン店流の対応をしていた。
得体のしれない白い手を『グシャッ』とするなんて、都市伝説にでもなりそうな場面を目撃して以来、常連の彼は少年を密かにこう呼ぶことにしていた。
『都市伝説の男』と。裏新ジャンル(怖)。
「――――と、言う理由で、ネットでは――まあ、ぶっちゃけちゃっちゃっちゃうと、2chを中心にさ。叩かれてるわけ。この本は。
・・・・・・・・・あんたさ、聞いてる?」
「聞いてますよー」
「そう?てっきりそっぽ向いてるからさ、聞いてないのかと。あっちのお客さんの方を見てるのかと?」
「!!
い、いえ?そんな筈、ないじゃ?ないですか?
で、それで?あれですか?2chで叩かれて、なんですか?」
「うん。でもさ、こいつは売れてるのよ。売上の大部分は書籍化されてからだから、流行に神経質な大衆がマスコミに煽られてってのも無くはない。
けど、ほら、火のない所に煙は立たないでしょ?聞いてる?うん?聞いてるか。ならいいや。
ともかくマスコミや携帯会社が飛びつくにしてもさ、持ちあげるにしてもさ、それに足るだけのモノがないと持ちあげられないでしょ?
つまり実際に人気はあったってこと。ケータイ小説はサイトで人気のある順に書籍化してるって言う話だし。
結局のところ『イマドキのジョシコーセー』が求める物がこの本にはあった。けれども、我らが親愛なるネットの向こうのお友達が求める物はなかったのね。
この本のメインの客層が求めていたのは、自分達が良く使う単語や言い回しで構成された、平易で馴染み深い文章。
それから、漠然とした憧れを具現化し、日常生活の中で鬱積した退屈を適度に解消してくれる刺激的なストーリーってところか。
ただ、そういった願望は割と全時代的に共通していてさ。単純に要望に応えるだけだと、既成のものと非常によく似た物語が出来上がってしまうのよ。
で、そこにこれを読む少女達とは違う価値観、常識、悩みを持つ人間がやってくる。
彼等はこれを読む田舎の女子高生のように、日常に退屈してるわけでもドラマのような恋がしたいわけでもない。
まあ中にはそういう人もいるかも知れないけど、それが一番だって言うのは少ないはず。
当然小説に対するスタンスも違ってくるし求める物も変わってくる。
彼らはさ、女子高生がイケメンの彼氏と巡り合い悲劇の末に相手の子供を身ごもるなんて話じゃ心は動かされない。人生においてそういう展開を願望してないから。
むしろ逆に、そういった物語のありきたりさ、文章の拙さにばかり目が言ってしまう。
で、結局、売れている現状にも関わらず、それに対して『駄作』の判断を下しちゃうのよね。
ま、売れる背景には今時の女の子が本を読まなくて、凡庸な展開を凡庸として受け取れなくなって言うのもあるから。彼等の判断も間違いっちゃあ間違いじゃないけどね。」
いい加減見る物が無くなってきたので、彼の目はふらふらと無秩序に空を彷徨い始めた。
やがて視線は、天井の蛍光灯に行きつく。
どこにでもある細長い白色灯が二本。くすんだ灰色をしたコンクリート製の天井で輝いている。
二本の蛍光灯の間、半分くらいの所には短い紐が垂れている。あの紐は何のためにあるのか、―――スイッチだとすると、高すぎて手が届かない―――彼は昔から疑問だった。
前方からは興に乗った話相手の声が聞こえていたが、肝心の内容が頭に届くことはない。ただ、ダラダラと右から左に流れていくだけだった。
天井の蛍光灯の一本がチカチカと明滅している。
―――やばいな・・・
何とはなしに彼は思った。
本来蛍光灯は人間には知覚出来ないスピードで明滅するものだ。なのでこういった知覚できる明滅、というのは普通の状態ではない。
事実、以前にもこういった輝き方をする蛍光灯を彼は見たことがあった。その蛍光灯はそれから数日のうちに使い物にならなくなってしまった。
「つまり、この本は――――」
「……………」
「つまりだね、私が言いたかったのは――――」
「……………」
「あのさ、あんた、やっぱ聞いてなかったでしょ?」
「それより蛍光灯、代えた方がいいんじゃないですか?あれ、もうすぐ消えますよ?」
目の前のカウンターの内側に座る人物の話がようやく終わったのを悟ると、彼は視線を天井から下におろした。
白いカッターシャツの上に店名の書かれたエプロンをかけた妙齢の女性が視界に入る。
髪をを束ね丸い眼鏡をかけているのが、端正な顔立ちに良く映えていた。
―――これでずぼらが治って怠け癖がなくなれば、引く手数多なんだろうな・・・
「やる気のない古本屋の女店主」を目の前にして、常連客の彼が頻繁に抱く感想がそれだった。
「あー!絶望した!久々に勝負服着てみたのに、みごとにスルーされる現実に絶望したっっ」
ボリュームを上げた声を出しながら、女店主はカウンターの上に突っ伏した。
カウンターの上の煙草の箱と灰皿。及び彼女が出しっぱなしにしたまま雑然と散らばっている小物類が、突っ伏した衝撃で軽く跳ねる。
彼女が突っ伏したことで、その背後にあるカレンダーや黒電話が常連の彼にも見えた。
カレンダーに書かれた赤や黒の印や、黒電話脇のボードに張られた幾枚ものメモ用紙からすると一応仕事はまじめにこなしているらしい。
「勝負服?それって勝負服なんですか?だったらもうちょっと・・・」
「ア・ホ・か。言い回しだよ。言い回し。これが勝負服のわけねーだろお。もうちょっとさー、読めよな?行間とか、人の心の裏側とかー」
「はあ・・・」
突っ伏したせいでくぐもって聞こえる女店主の声に、彼は適当に相槌を打った。
『勝負服』という意外な語が出てきたせいで反射的に疑問の声をあげてしまった彼であるが、何故『勝負服』と言ったのかは察しがついた。
この古本屋をきりもりする女店主の性格は、一言で表すなら『面倒くさがり屋』だった。
ともかく古本屋という仕事に対する情熱が全くない。
店が開いている時間のほとんどは入口脇のカウンターでぼんやりしているか、客(主に常連客の彼の事をさす)を巻き込んで下らない遊びに興じるかのどちらかであった。
因みに店の奥には座敷があって、テレビと各種ゲーム機のハードとソフトが揃っている。
本自体も、たまに思い出したように入れ替えるだけで基本的に床の上に山積みであり、全くこんな状態でよく店がつぶれないなと通い始めの頃は疑問に思っていたものだった。
結局、近くの小学校の生徒に本の読み聞かせをしているという話を店主から聞いて、副業の存在を確認したことで疑問は解消されるにいたったが。
そんな本業には不真面目な彼女であるが、それではいけないと思う事も(本当に稀にだが)あるらしい。
普段の彼女はニットのセーターを着て髪をおろした状態だが、たまに今日のようにカッターシャツに着替えて髪もまとめることがあった。
本人いわく『やる気を出したい日は、気を引き締めるためにシャキっとした格好をする』のだそうだ。
実際、髪をおろしている時の女店主はべらんめえ口調で一人称も『俺』だったりするが、カッターシャツを着て髪をまとめると、一人称が『私』になり口調も割と穏やかな女性らしいものに変化する。
そういう訳で、彼女のカッターシャツ姿というのは、仕事に対しての『勝負服』とも言えなくはなかった。
ただ、それで本当に仕事の能率が上がるかと言えばそうでもなく、むしろ逆効果なのではないか。と言うのが常連の彼の率直な感想だった。
張り切るのはいいのだがその所為で、普段はやる気と一緒に鈍っている頭の活動が中途半端に活性化されてしまうらしい。
普段の彼女は女性としてはあまりおしゃべりな方ではないのだが、『勝負服』を着ると途端におしゃべりになるのだ。
しかも救われないのが、ただおしゃべりなのではなく、その話の殆どがコメントのしづらい小難しい話ばかりだったりする。
大抵はほとんど彼女一人で自己満足的に垂れ流し他人の話を聞かないので、ただ仕事をしないだけの普段よりも質が悪いと言えた。
しかも、まともに聞かないと見るやいなや今のように拗ねたりするオマケ付きだ。
常連の彼は、常連なだけあって、そんな『勝負服』の彼女の一番の被害者であった。
もっともカッターシャツを着てなくても、このやる気のない女店主が厄介なことに変わりはなかったが。
彼自身、全く良く付き合っていると思っていた。
普通の人なら常連になんてならないような、辺鄙な場所にある変な店主がやっている古本屋。
それでも彼が常連客を続けているのは、そんなどこか世界から外れたような、つまりは『普通じゃない』ところに魅入られたからだった。
まあ、女店主さんが奇麗な容姿をしているから、というのもなくはなかった、が。
「だいたい店主さん」
「…………………」
「店主さーん?」
「…………………なによ?」
彼の呼びかけに女店主がむくりと起き上がる。
腕から持ち上げられた顔は、前髪が微かに乱れていているのが妙な色っぽさを感じさせる。
「ああいう小難しい長話って、本人は良く出来てると思っても聞く側からしたらなんのこっちゃって感じで面白くもなんともないですよ?」
「うるさいなーっ!じゃあ面白い話ってな」
「あ」
「んだ・・・なんだよ?どしたの?」
現在、二人は向かい合っている状態にある。
カウンターに座る女店主は、自宅につながる店の奥を向いているので、自然と常連の彼はカウンター脇の出入口に向かう形になっている。
女店主からは死角になって見えない出入り口。十字の木枠にはめこまれたガラスの向こう側は、宵闇と店内の明るさの所為でほとんど何も見えない。
よほど近づく物がない限り、ガラスは店内の様子を反射する鏡としてしか機能しないだろう。
そして、出入口の方を向く常連の彼は、見た。
―――ガラスの入口に、『よほど近づく』者を。
「お客さんですよ?店主さん」
「そう。じゃああんたはあっち行ってなさい。私は相手しないといけないから」
「ちょwww何いきなりやる気出してるんですかw」
「いやさ、きっとね―――」
女店主は体をよじって出入口の方を向く。
ガラス戸の向こう側には、奇麗な長髪をした虚ろな瞳の少女が立っているのが見えた。羽織ったコートの隙間から、新ジャンル学園の制服がのぞいている。
「あっちのほうが私の『小難しい長話』聞いてくれるだろうからさw」
常連客の『こらこらwww』という声と、扉に取り付けられたベルの、来店者を告げる音が重なった。