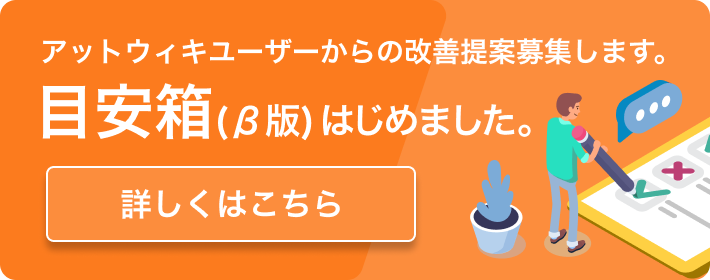◇ ◇ ◇
ンンンンンンンンンンンンン―――――――・・・・・・・・・…………
扉を押して店の中に入った途端、オフィス街の向こうの大通りから響く喧騒が、一段階ボリュームを下げる。
大通りを途中で左折すると現れる、オフィスビルの群れが織り成す渓谷。
その谷底を流れる川にも似た、曲がりくねった道を私が行く間にも始終付きまとっていた音が、瞬間的に収縮したのだ。
駅から延びる複数のメインストリート。
そこを行き交う車の騒音。そこに並ぶ種種雑多な店舗の雑音。
そして、毎日様々な悲劇や喜劇を繰返す、或いは繰り返すこと無く別の場所へと向かう、人々のざわめき。
それらが混然一体となりゴォォォォ・・・というくぐもった遠雷のように、街を歩く人間の鼓膜を絶え間のない震動に晒している。
けれども大抵の人間は、その、多様な音が混ざり合った結果として起伏を失くしフラットになった音を、意識の外側に追いやっている。
高低大小の変化と途切れることを忘れた音は、その中にいる人間にとっては存在しないに等しいのだ。
学校と駅を結ぶバスから降りて20分足らずの私も例外ではなかったらしい。
店に入った時に抱いた感想は、『音が小さくなった』ではなく『耳の周りに見えない壁ができた』と言った物だった。
意識していた音が小さくなったのではなく、それまで『あって当然』と思っていたものが剥奪された感覚。
もっと言うと、自動車に乗って高所へ行った際に、気圧で耳の聞こえが悪くなるのと似ている。
こういった古本屋に限らず、新書店や図書館でもこういった現象は良く起こる。
きっと立ち並ぶ本(を構成する紙)が音を吸収しているのだろう。
そんな風にある程度は原理の推測はできているのだけれど、やっぱり扉をくぐると瞬間的に静かになるのは不思議な感じがする。
もしかすると本屋というものにはすべからく、魔法の結界が張られているのではないか、なんてことを本屋に入るたび、良く考えたりもした。
「いらっしゃい」
右側からハスキーな女性の声が掛けられる。
予期せぬ方向からの言葉に変にドキっとしながらそちらを向いた。
円いノンフレームのメガネをかけ白のカッターシャツを着た女性が、仕事用の道具以外にも様々な物が散らばるカウンターに頬杖をついて、こちらに笑いかけている。
シャツの上に紺のエプロンをかけた店員と思しきその女性は、髪を後ろで束ねていた。
(橙子さんだ・・・)
掌の上に顎を乗せ、営業スマイルを浮かべる目の前の人物は、『空の境界』に出てくる『蒼崎橙子』に瓜二つだった。
まさに『小説から飛び出してきた』かのように、身にまとう雰囲気まで似ている。
この古本屋もメインストリートの中では最も人通りの少ない通りを、さらに人気のない方向へ人気のない方向へと進むことで辿りつけるような所に立地している。
余程モノ好きでなければ見つけられないような店だが、作中で橙子さんが構える事務所の『結界による暗示で、普通は認識できず見つけられない』という設定にも通じるところがある。
これだけ路地裏の奥まった場所に、それも本屋とは無関係なオフィスビルが続いた矢先に、不意打ち的に建っているのだから。
普通の人には、それこそ『認識できていない』だろう。
そう考えてみると、目の前の店員が『小説から飛び出してきた』というよりも、私が『作品の中に迷い込んでしまった』ような気分になる。
さっきまでの『本屋には魔法の結界が張ってあるのではないか』という思考もその錯覚に拍車をかけていた。
そう。
『結界』と言うのは今でこそ漫画やアニメの影響で、『魔法の力で作るバリアー』というイメージが先行しているが実際は違う。
本来『結界』とは、仏教僧が修行のために外界と遮断した領域のことをいうのだ。
だから結界を生み出すのに、そもそも霊力だとか魔力だとか言ったオカルトじみたものは不必要。
単純に、物理的に、何らかの形で外界とは違う環境、即ち『異界』を生み出せば――仏道修行なら集中しやすい静かな環境なんかが特にいいに違いない――それで結界は完成される。はず。
そういう意味で言えば、本を並べることで余計な音を吸収させて、外界よりもずっと静かな空間を生み出す、というのも立派な結界になるのだろう。
少なくとも本屋の入口の、あの瞬間的に音が小さくなる感覚は『結界の中に足を踏み入れた』と言う表現が多分一番しっくりくる。
などと小説で得た知識を持ちだして、何ともヒロイックな思考をしてしまったものだが、とりあえず私の中で目の前の女性のあだ名は『橙子さん』に決定した。
むしろ『橙子さん』以外のあだ名はあり得ない。
折りあるごとに心の中で『橙子さん』と呼ばせてもらうとしよう。
もちろんキョトンとされるのは恥ずかしいので絶対に面と向かって言ったりはしないけど。
「あの、と―――っ、、、
・・・・・・(//////)」
「ふあ?」
さっそく面と向かって『橙子さん』と呼んでしまいそうになった。
怪訝な顔をされてしまい、赤くなった顔がさらに過熱する。
初対面の人に、勝手にあだ名をつけるのは良くないことなのだと強く実感した。もう誰かに勝手に変なあだ名をつけるのは止めようと思う。
「あの、もし良かったら何かオススメの本など紹介していただけると・・・初めて立ち寄った店なので・・・」
「ん、そう?じゃあ、ちょいとお待ちを―――っと」
私の依頼に彼女は掌から顎を離して姿勢を正すと、カウンターの下に手を伸ばした。
しばらくガサゴソやっていたかと思うと、おもむろに一冊の本を取り出す。
「ほい。今話題のケータイ小説『恋空―RENKU-』おまちっ」
彼女はハードカバーの本を二冊。両手で揃えて表紙がこちらに向く形で、ダンっとカウンターの上にたてた。
その際の所作が、表紙がこちら側に来るようにクルリと回すのも。立てた瞬間の衝撃で、前髪とカウンター上のガラクタが踊る様子も。
イチイチ洗練されていてカッコいい。
「モテカワ体質の女子高生エーコは、ある日イケメンの真島と出会う。自分とよく似た感性を持つ相手にスピリチュアルな感覚を覚えるエーコ。
やがて二人は恋に落ちる・・・だが幸せは長くは続かなかった!
嫉妬に狂う真島の元カノ、真島を襲う不治の病『樹熱』、進むインフレ、湧きあがるトレス疑惑・・・」
「あの」
「樹熱によって余命1ヶ月となった真島のため、不屈の象徴『ドクロ』のマークの花を無菌室にかざるエーコ!しかし『ドクロ』は世間一般には死を意味すr」
「あのっ、、、」
「ん?なにかしら?」
「そういうのは・・・あまり、なんというか・・・」
彼女が出した本については私も一応知っている。
確か携帯電話で書いた小説を書籍化したものだったと思う。
女子高生の間で人気の恋愛小説と言う話で、実際に私が通う学園でも、他の女の子が話題にしているのを耳に挟んだことがあった。
ただ露骨な性描写が多いとも聞いているので、そう言った趣向のない私は未だ目を通していない。
どうせ恋愛モノであるのなら性描写無しの爛れていない方が読了感は良い筈なのだけれど・・・これが価値観の違いと言う奴なのだろうか・・・
「あら、好みじゃなかった?じゃあ――――っと」
私の反応に、そう言って橙子さん似の店員さんは再びカウンターの下でガサゴソ手を動かし始めた。
私は黙ってその様子を見つめている。
―――話題のケータイ小説を紹介したこの店員さんは、今度は何を紹介してくれるのだろう?
彼女が探している間の手持無沙汰も相まってそんな考えが浮かんだ。
答えを知るべく、彼女に意識を集中して心を読んでみる。
が、別段何の本を探しているという訳でもなかった。適当に近くにある本を取って、それに相手が興味を持つよう面白おかしく語ってやろう、というスタンスらしい。
なんというか、それこそ小説や漫画なんかで良くある、何でも見通し主人公に助言をしたり導いてくれるキャラクターみたいに、私の本質や内面をズバリと見抜いて『これ』という本を選び出してくれるのではないか。
なんて冗談半分に期待していただけに拍子抜けな気もする。
まあ、つまらない本でも面白おかしく紹介して興味を抱かせるというのは、それはそれですごいのかもしれない。
やる気は伝わらないが才能はあると言ったところだろうか。
心を読んだ際、彼女がここの店主であるというのが一緒に判明したが、見た目二十代程でありながらこんな辺鄙な場所に建つ古本屋を経営できるのも、恐らくは才能のなせる技に違いない。
「っかしいな・・・・――――ああっと、、ちょっとお待ちくださいねー?」
どうも、カウンターの中にあったのは例のケータイ小説一組だけだったらしい。
女店主さんはこちらに笑顔を向けた後、椅子から離れてカウンターの裏側にしゃがみ込んだ。
彼女の笑顔は一目でわかる営業スマイルでありながら、こちらが『ほぅ』と感心してしまうほど整い完成されたものでもあった。
こちらからは死角になっているカウンター裏からは、ビリビリと言った音が聞こえてくる。推測するに段ボールの箱を開けているのだろう。
それからまた先程同様のガサゴソという雑音が再開された。
私はぼんやりと女店主さんが本を見つけるのを待っている。
店の壁に掛けられた振り子時計のカッカッカという音。私の他のお客さん――入った時に目にした限りでは三人いた――が立ち読みしている本のページをめくるサラリ、パラリという音。
それらを背景に、女店主さんが本を探して立てる物音は続く。
「―――ん、」
こめかみから顎にかけて一筋、冷たい何かが這う感触。
反射的に頬に手をやると、指先が僅かに濡れる。這い落ちたのは汗だった。
今更ながら自分が汗をかいていることに気がつく。先程まで二月の冷たい空気の中を進んでいた所から、暖房のきいた店内に入ったのだ。
しかも今私が立っている場所は、カウンターのま上に備え付けられた暖房から温風が直接当たっている。
上着を着たままであれば汗をかかない方がおかしいのだろう。
背中の肌からも、いつの間にかいたのか、湿っぽい汗ばんだ感覚が伝わってきた。
私はコートを脱ぐと軽く畳んで小脇に抱える。すると、途端に背中の湿っぽさが冷やりとしたものを帯びた。
そんな現象も外であれば風邪を心配していただろうけど、暖房が直接当たっているこの状況では却って心地良い。
そうやって特に何を考えるでもなく立ち続けること数分。
ふと。
背後に人の立つ気配を感じた。
◇
(・・・・・・おおっ。何も無い、なんも無い、なんもねーっていうか何も無いっ
あれか?やっぱ店の本棚からとってこようか知らん?しかしまあそれにしても何も無い。なんかあったっけ・・・・
ああ、そういや昨日処分したんだっけwwwwだから何も無いのかーwwwwwはははははははは
って笑ってる場合じゃないわね・・・・OTL)
カウンター裏は店内同様、足の踏み場のない異空間であった。
店主の座る丸椅子とその周辺半径50cm程度の空間だけが確保されていて、あとは何に使うかもわからないガラクタが蟻地獄の外壁のようにすり鉢状に積み上がっている。
その中からめぼしい物はないかと漁り続ける店主の傍らには、段ボール箱が一つ。
クルリと丸まったガムテープが脇にひっつく箱の中には、以前に彼女が特売セールで買い込んだカップラーメンが並んでいる。
普通の本屋なら、入荷した本が詰まっていそうなものだし、彼女もそれを期待して箱を開いたのだが、いかんせん、彼女はやる気のない古本屋の女店主と言う訳であった。
紛らわしい真似をした過去の自分へ、濡れっちまいそうな罵詈雑言を浴びせた後、探せばどっかしらあるだろと彼女は周囲のガラクタを探り始める。
が、見つからない。
なんで集めたのか当の本人にも分からない、
―――リトルグレイと金髪美女が一丁のベレッタを巡って繰り広げる熱い恋愛劇をおさめたDVDや
―――特殊機関モサドが使用していたとかいう触れ込みで、チョンブリ県サッタヒープの土産屋に売られていたスペツナズナイフ
―――あと、炎多留の一作目
は出てくるのに
肝心の本の方は、雑誌はおろかパンフレットの類にいたるまで一切出てこなかった。
さしもの店主も、お客を待たせてはいけないという当たり前の商業道徳は、なんとか持ち合わせていたらしい。
平野●太が江○達也を強制収容所でアレコレするガチホモアニメーション(グロ注意)を手にしたあたりから、彼女は焦燥に襲われ出した。
『これだけイロイロ積まれてるんだから、どこかしらにあるだろう』という想いを捨てきれず、ガラクタを漁るうちに悪戯に時間が過ぎていく。
素直に本棚に収まっている方を紹介すれば早いのだろうが、その一歩が踏み出せず、ただただ焦りばかりが募ってくる。
結局、彼女が本棚から持ってくるのを決意したのは、以前にカウンター周辺の本全てを処分したのを思い出してからだった。
なるべく焦りと自らの失態を悟らせないように、余裕を孕んだ営業スマイルを浮かべてカウンター裏から立ち上がる。
「ちょっといいかしら?あっちの方に―――」
『あなたにピッタリの本があったから、それ持ってくるわね?』と続けようとした店主の口が中途で途切れた。
カウンター越し、白色灯に照らされた本棚が続く細長い店内を背景に、少女が二人。
片方はさっきのお客さん。そこに、切れ長の瞳をした端正なのが追加されている。
追加された少女は以前にも何度か来店している見知った顔であった。
「あの、彼女は『お会計と本の買い取りお願いします』と言っています。」
「はあ・・・・・ああ、じゃあ、ちょいとお待ちを」
何故だか切れ長の瞳の少女本人ではなく本の紹介を待っていた方が店主に要望を伝えてきた。
が、予期せず現れたお得意さんに面食らった店主は、そこに疑問を抱くことも無く、呆けたように反応するのみであった。
◇
「おっと、これはなかなか良いわね。ちょいとお客さん、あんたコレ、どこで手に入れたの?」
「知り合いの本棚に」
「ちょw盗品はお断りだよ?」
「盗品ならもっとマシな嘘つくから。正月に麻雀で勝って、金は無いから好きなの持ってけって」
「麻雀wwww意外ねw麻雀やるの?」
「一応できる。あんまやんない」
「うち、麻雀あるよ?」
「ふうん。そう」
「今度一緒にやらない?」
「いやよ」
「冷たいわね」
「ならやるわ」
「相変わらず淡白な子ねwwこっちまで淡白になるわこれww」
「査定」(カウンターを指でトントン
「ん、ああ。そうね。
まあ、その、なんだね?あんた、その知り合いの本棚から無作為に選んだっぽいけど運がいいよ。
なんせこの『秒速6000センチメートル』はこの店じゃ高値で買い取ることにしてるからねw」
「プレミアでもついてるの?」
「んーん。特に大した価値はないわよ?っていうか新書でも簡単に手に入るし」
「じゃあなんで?」
「そりゃあ私がこいつをひいきにしてるからさ!」(エッヘン
「ふうん。そう」
「・・・・・・・・・・・・(って普通ここは『なんで威張ってるんですか!!』とかなんとか言うところでしょうが!!ってなんで私がツッコんでるんだ!
嗚呼・・・・・ツッコミってのは貴重な才能ね・・・常連客だし、あいつにはもうちょっと優しくしとこうかしら?)」
パイプ椅子に座る私の傍らでは、店主と先程私が通訳した少女との間で、そんなやり取りが繰り広げられていた。
そっけない淡白な反応しかしない少女と、その対比で感情の起伏が目立つ店主さんの会話を背景音楽に、私はカウンターの壁際で熱いほうじ茶を一口すする。
熱い液体が口腔を満たした後、喉から胸、お腹の順に熱が広がっていく。
淹れたてのお茶はことさらに熱く、体内に広がる熱は僅かに刺すような感覚を引き起こす。暖房のきいた店内に入ってなお平熱に戻らなかった末端が、それによって温度を得ていく。
そこに便乗する形でほうじ茶独特の香ばしい焦げた香りが、気分を落ち着かせてくれた。本当に寒い日はほうじ茶に限る。
私はゆっくりと長い息を静かに吐き、湯呑を黒く滑らかなカウンターの上に置いた。
ゴトリと言う重い音が、まだまだほうじ茶で体を温めることができると告げている。
さっきまで私が立っていた入口近くに視線をやると、店主さんによる買い取り査定はまだまだ続いていた。
(こういうのを『お茶を濁す』というのでしょうか?)
先程までのことを顧みながら心中でそう呟くと、ほうじ茶を出された状況と『お茶』という単語の合致に気がついて思わずニヤリとしてしまう。
背後に立った少女の通訳をした、あの後。
私達はお互いの同意の上で、先に買い取りと会計の方を済ませようという話になった。
実際私にはまだまだ時間はあったので、後回しは何の問題もなかった。適当に店内の本を読んで時間をつぶしておこうか、程度の感覚である。
けれど店主さんにとって待たせた上に後回しにする、というのはやはりバツが悪かったのか、椅子とお茶を用意してくれた。
しかも熱いお茶には茶菓子までついていた。
ただしこちらは、『後回し』に対する『謝罪のお茶』とは違い、どちらかと言えば彼女の中の罪悪感を解消する意味合いが強かった。
本屋としての微かな矜持が抱える矛盾を、茶菓子で誤魔化したというわけだ。
やはり彼女の判断の結果としてのこの状況だから、『お茶を濁す』と言う言葉は、一番はまった表現だと感じる。
「これが最後の一冊・・・いや、上下巻セットだから二冊か。これも売るの?」
「ええ。」
そんな声が私のすぐ側。1~2mほどのところでしている。
カウンターはL字に曲がっていて、店の壁とで四角形の空間を作り出している。
レジはカウンターの入り口側の一辺にあって、店主さんと少女はそこで買い取り査定のために向かい合っている。
因みに私はもう一方の辺の端、店の壁を背にして座っていた。右を向けば細長い店内の様子が見渡せる位置だ。
ただ、本で出来た幅50cmかそこいらの通路が奥の壁まではっきり見通せる右とは対照的に、左の視界はあまりよくなかった。
ここからだと店主さんの半身に遮られて、カウンターで少女が何を売っているか、というやり取りは半分ほどしか分からない。
時たま店主さんが動かす腕と脇の隙間から、チラリホラリと本の表紙が見える程度だ。
「これさ、今映画化してるらしいね」
「ふうん。そう」
ふとそれまで店内の奥に向けていた視線を――痩身長駆であることを除けば取り立てて特徴のない、私と同い年くらいの男の人が、なにかを『クシャッ』としていた。まだ寒い季節だけれど、暖かい店内には蚊でもいたのだろうか?――気紛れに二人の方向へ向けて見た。
その途端、私は『ウッ』となる。
「でもこれ、全七章映画化とか無茶苦茶ねwあいつら調子乗りすぎwwww」
「あいつら?」
「え?型月よwwwあいつらってwww」
「馴れ馴れしい」
「やっぱ馴れ馴れしいかwww場末の古本屋の店主だもんねwwwwww」
私の視界に入ったのは、厚めの本が二冊。こちらに背表紙を向けて重なっている光景だった。
背表紙には白地に挟まれた黒地の上に金文字でタイトルが刻まれている。
少女が最後に売り払おうとしているのは『空の境界』上下巻であった。
―――これは、ちょっとショックだった。
彼女は、私が特に気に入っている作品と同じモノを古本屋に売ろうとしているのだ。
つまりそれは、彼女にとって『空の境界』は手放してもなんら問題のない小説であるという事になる。
もちろん『読んでみて、つまらなかったから売った』と考えるのは短絡的な発想だとは思う。
何かどうしても欲しい物があって、充分な吟味の末に苦渋の決断を下した、という好意的解釈も成り立たなくはない。
けれど仮にそうだとしても、彼女が手放そうとしている事実に変わりはないのだ。
結局のところ『空の境界』は彼女の所有物の中ではそれほど重要ではないに違いない。
苦渋の決断の末であろうとなかろうと、『手放しても問題がない』と彼女が判断したのは確かだ。私は少なくとも向こう5年は手放すつもりのない小説を。
「でもこれ売っちゃうの?なんだかんだで映画も人気みたいだしさ。持っててもいいんじゃない?
ま、こっちとしては流行に乗り遅れまいとするヌルヲタにわかヲタの良い客寄せになるから、歓迎ではあるかしら?」
「この本、先が読めちゃってつまらないから。ミステリーっぽくしてる所もあるけど、なんかイマイチすっきりしなくて無理があるし」
―――ああっ、ああっ!やっぱりそうだったんだ………っ!やっぱりつまらなかったんだ………っっ!!
少女がはっきりと『つまらない』と言い切ったのを見て、私の気持ちはズシリと落ち込んだ。
『何か事情があったのかもしれない』という薄い望みで急降下を免れていたのが、当たり前と言えば当たり前の現実に直面して、一気に浮力を失ったのだ。
真っ暗な蔽いを目の前にかぶされたような、暗い穴のそこに落とされたような、自分に自信が無くなっていくような。
変に不安な気持ちが、落ち込んだ気持ちの上に充満していくのが分かった。
単純に『見ず知らずの少女が私の好きな本を売っている』という今の状況だけならここまで気持ちが落ち込むこともなかっただろう。
けれど今日は二度目なのだ。
私の好きな作品を否定されたのが、今日だけで二度目なのだ。
一度目は今日のお昼。
サトリさんが私の貸した「空の境界」を『変に気取って格好をつけている感じが、生理的に受け入れられなくて』まだ未読である、と判明したこと。
そして二度目は言うまでもなく、今目の前で繰り広げられている。
作品の登場人物とよく似た雰囲気の店主さんを巻き込んでの買い取り劇(?)であった。
別に私は彼女達の趣味をとやかく言いたいわけではない。
私が面白いと思った物をつまらないと、受け入れられないというあなた達はおかしい、なんて嬌慢な想いは毛ほども抱いていない。
むしろ、どちらかと言えばその逆だ。
皆がつまらないと言う物を、私は面白いと感じてしまっている。
一日に二度もつまらないと言われる作品を、嬉々として、あまつさえ宝物のように思い、向こう5年は何があっても売り払わない、なんて思ってしまっている。
・・・それはどう考えても普通じゃない
・・・・・・・誰もがつまらないと思う物を、面白いと思うのは普通ではない。
『誰もが』と言うのは言い過ぎかもしれないけど。実際この作者はある程度の人気を博している筈だし、出版社の方も見込みがあるからこそ出版したのだろう。
けれどそれでもやっぱり、日に二度も拒否されている光景を見せつけられて動揺しない程、確かな証拠や強固な論理があるわけでもなかった。
結局面白いというのはあくまで唯の感覚に過ぎず、『作者の人気』も『出版社の見込み』も全ては私がそう思いたいが故の材料に過ぎないのだ。
「空の境界」が駄作であるという証拠も論理の材料も、私が目をつぶって見ていないだけで、見つけようとすればいくらでも見つかるだろう。
そして駄作の根拠を『見ようとしない人間』と『見えてしまう人間』のどちらが多いか、なんて私にはわからない。
或いはあの小説の至らない部分に、目をつぶってくれる人間の方が多いかもしれない。
反対に気に入らなくて、率先してあらを探す人間が思っている以上に多いかもしれない。
いや、もしかしたら、ほとんどの人間がつまらないと思っていて、私くらいしか面白いと感じていない可能性だってあるのだ。
そんな思考が『私はおかしいのかも知れない』という胸の不安を、絶えず煽り続けている。
不安が消えそうになると、すぐまたその思考が頭をあげて私の心を上から抑えつけてくるのだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・そもそも、、
そもそも今日の私はちょっとおかしい。
こんなに動揺するなんて、何にせよ、ちょっとおかしい。
『私はおかしいのかも知れない』なんて事で悩んだことなんて、今まで一度なかったのに・・・
だって私は心が読めるのだ。
普通もなにもあったものじゃない。
他人と違うかと問われれば、普通か否かと問われれば、考える間もなく首を縦に振って、それで終りだ。
というよりも、私は心が読めて他の人は心が読めないのが私にとっての『普通』だったのだ。
だから他人との差異に悩んだり疑問を抱けというのが、まず無理な話だった。
なのに何故。
私はそんな事で動揺してしまっているんだろう?
サトリさんと淡白な少女に自分の好きな作品が拒絶されて、『私はおかしな趣味を持っているのではないか』と不安になったから?
違う。
それはさっきまでの記憶の蒸し返しにすぎない。原因はもっと前にあると思う。
・・・ツンさんに距離感を感じたから?
近い。
ツンさんには特別な人間がいて、私にはいないという事実。
その事実故に毎日を彩り鮮やかな感情で過ごせるツンさん。その事実故にそう言った状態には決してなれない、実感できない私。
そう理解した瞬間、私は、『自分は普通ではない』と強く意識したのだった。
けど・・・けど、それが大元ではない。
なんの摩擦もなく生活し、心は常に凪いで荒れない筈の私が、今日に限ってこれほど穏やかではない、その根本的な理由は・・・
『あの、彼は、虎吉も『もうちょっと仲良くしてほしい。二人は似た者同士なんだから・・・』と言っております』
残留した通訳が、また耳元で鳴り響いた。
そうだ。思いだした。
いや、嘘をついた。思いだしてなんていない。
何故って彼の事は、ずっと私の心の片隅にひっかかり、忘れることなんて到底できないのだから・・・
「同僚君・・・ですか」
知らず呟いていた。ポロリと口からこぼれおちた感じだ。
虎吉の通訳を忘れずに覚えているのは、内容が彼に関することだったから。
結局、ツンさんへの距離感も、『空の境界』の人気がないことに対する不安も。
全ては同僚君の心が読めない事から始まったのだ。
彼の心が読めなくて、私はどうしていいか分からなくて・・・それまで人を相手にして、どうしていいか分からないなんて思った事はなかったのに・・・
同僚君に関しては普通の人には抱かないほどの、強い不安と怖さを感じていた。
今日一日の感情のブレは、多分、いや、間違いなく、同僚君が原因なのだ。
彼と言う石が私の心と言う水面に投げかけられて、一気に波紋が広がり波が立った。
なんていうのは気取りすぎた言い方だけど、『同僚君と私が似ている』という言葉にとらわれているうちに、彼以外の事柄にも心が動いてしまうようになったのは確かな筈だ。
だけど、私と彼が似ているというのはやっぱり分からない。
私は彼みたいにクラスの中で浮いたりしてないし、ましてや自分から周囲を拒絶するなんて絶対にあり得ない。
なのに虎吉は「似ている」なんて勝手な事を言う。私と彼の一体どこが似ているというのだろう?
「お客さん」
そもそも私は心が読める分、虎吉のことは他の人より解っている筈なのに。
虎吉はそんな私と、他人の心を読む力がない『普通の』同僚君が一緒だというのだ。
実際彼は、虎吉が嫌がっているのに無理矢理エサを食べさせようとするし、じゃらし方もなっていない。
虎吉は背中を触られた方が喜ぶのだ。なのに彼はそちらではなく顎の方を触っている。
大して嬉しくもない部分を触ってくる同僚君の方が、虎吉は良いというだろうか?
「お客さ~ん?」
大体同僚君は飼育委員には向いてないと思う。
エサをやり終わって、白っぽい脂にまみれた自分の手を眺めながら不快そうな顔をしていたし、手を洗う時も念入りに二回石鹸で洗っている。
それもどんなに寒い盛りであろうと、肘のあたりまでしっかりと。
動物を飼育する以上汚れはつき物なのだから、潔癖な人間に飼育委員の仕事は辛いだけだと思う。
「ちょい、とお客さん―――」
あとは手持無沙汰になると掌で首の後ろを覆う癖もやめた方がいいかもしれない。
奇麗な時は良いけど、手が汚れている時もお構いなしで触るのだ。
首筋に汚れがついてしまう。さすがに私もそれは
―――脇腹に、固い物を押し付けられる感触が走る
「ひゃ・・・」
「―――よっと。査定と会計終わったよ?」
店主さんが脇腹の敏感な部位に本を押しあててきたのだ。
そのせいで、素っ頓狂な声を上げてしまった。
彼女はニヤニヤしながら私の番が回ってきたことを告げてくる。
「え、あ、あれ、あ、、、いません・・・・・・そ、そうですか・・・」
彼女の言葉に辺りを見回すと、確かに淡白な少女はいなくなっていた。
どうも考えに没頭しているあまり、少女が用を済ませ店を出ていったことにも気付かなかったようだ。
「―――にしてもあれねw
なんか深刻そうな顔でブツブツ呟いたり、顔を顰めてみたりしちゃってまあwww
どうだい?このモノ好きなお姉さんに話してくれたら嬉しいな?悩みごとなら打ち明けるとスッキリするわよ?」
―――あなたに合った本も用意できるだろうし、ね。
そう付け足しながら彼女は、頬杖をつきながらニヤリとした不敵な笑みをこちらに向けてきた。